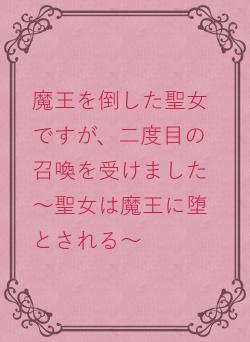「何にもすることがないわね」
私は、誰もいない部屋で、テーブルの椅子に腰掛けて、私は肘をつきながらぼうっとしていた。
ある意味、前の家ではやることは侍女の如く山のように合った。それとはうって変わって妃となって、何もすることがなくなって、正直、時を持て余していた。
衣食住にも事欠かない。
衣装は、前の家では考えられないような美しい衣を、体裁上、困らない程度に与えられていた。
食事は、後宮の皆が食べる食事なので、侯爵家出身とはいえ、毎日が贅沢な食事ばかりである。
住まいは、『美しい妃』が来るはずの宮だったので、大変美しい宮である。
けれど、国王陛下ですら、他の妃すら、誰も私の宮を訪れない。
実家からは便りのひとつもなかった。
「寂しいわ」
そう思いながらも、これで我が家はなんとかなるだろう。
「それでいいわ。家族の役に立てたんだから」
そう思っていた。
年老いた国王陛下に輿入れするだけ。それで、家族の役に立てたのだから。
◆
そうして三年が経った。
様子を見ていたアンジェリーナは、婚期ギリギリとはいっても相変わらず美しく、婚約話に事欠かなかった。結局、一応王家とは遠縁の公爵家の令息と結婚したのだという。
本来は、国王陛下の息子、王子殿下たちに輿入れさせたかったそうなのだが、アンジェリーナと私の入れ替えの件もあり、申し入れもしにくくなり、諦めたのだそうだ。
そして、私はおそらく国王陛下がご存命の間くらいは衣食住には困らない。
──これでいいのだ。
私は目を瞑ってそう思うのだった。
私は朽ちていく。
この宮で、人知れず、静かに──。
そう思っていたのだった。
◆
そうして使用人を除いてほぼ一人で生きていたある日。
「ピイィッ!」
と私の宮の裏の草むらから何かの鳴き声がした。
扉を開けていると、遠くから「アレはどこだ──! 見つけ次第殺せ──!」と声がした。
──そんなに怖いものが紛れ込んだのかしら。
声も近い。どうしよう。悲鳴を上げて侍女を呼んでおくべき?
悲鳴をあげれば、侍女の一人か二人がやってきて庇ってくれるだろう。
──『白妃』を本当に庇ってくれるかは疑問だけれど。
そんな妄想に私が耽っていると……。
「ピィ! ピィ!」
カサリ、と小さな葉擦れの音を立てて姿を表したのは小竜。
小さいとはいえ獣の姿に危機感を覚える。
「……おねがい、たすけて……!」
すると、その小竜は見た目三歳ほどの小さな子供の姿に変化して、人の言葉で私に救いを求めてきた。
「まあ、こんな小さな子だったのね」
それに、小竜でもあり、人間の姿に変化できるとあれば、ただの獣の竜ではなく、隣国の竜人族の子供だろう。そしてその証に、頭に二つの小さな角を持っていた。どうしてこんなところに迷い込んだのだろう。
外の叫んでいる男たちの声を聞きながら私は思う。
「……この子、殺しちゃまずい気がするんだけど」
そう呟くと、人の姿の小竜が私にぎゅっとしがみつく。
「おねがい。たしゅけて。あのひとたちに、わたしゃないで……!」
そう言って、必死に私に救いを求めるのである。
──どうしたものかしら。
隣国の竜人族が統べる国、ドラゴニア帝国は、人間から『亜人』と謗りを受けた、獣人たちをまとめ上げた国である。しかも、竜の姿をとれるものは、王族や、それに近しい血を持つものが多いと聞く。
だから、本来、しかるべき手段をとって、丁重にお返しするのが筋なんだけれど……。
「バント王国この国って、ドラゴニア帝国と敵対しているのよね……」
そう考えると、この子を追っている人間たちに、引き渡した後が怖かった。敵である隣国の、王族に近しい子供。一体どんな扱いを受けるのだろう。
──外の人間も殺せっていっているものね……。
「ねえ、おねえたま。ボクをかくまってくれない?」
舌ったらずな口調で、「匿って」などという。
──一体この子幾つなのかしら?
ドラゴニア帝国の人々は種族によって寿命も年齢による外見もさまざまなのだという。この子は実際は見た目の三歳くらいなのには、実年齢には当てはまらないのかしら?
でも、舌ったらずな子供っぽさもあるのよね。
私がそう考えていると、「あ、イタタタ」という声がした。
私の宮に入り込んだ小竜だ。
「勝手に……!」
入らないでと言おうとした時、彼が怪我をしているのが目についた。
「怪我をしているなら、治さないとね」
どうも私の方が捕まってしまったらしい、仕方ない。と思いながら、私は、裏の草むらの草の中から薬草になる草を選び取り、そして、部屋に戻った。
「追われていたからか、随分と汚れているわね。それと、あちこちに傷が……」
汚れは長く清めていないようなものではない。あくまで表面的なものだ。そして、傷も、深いものではなく、転んで擦ったり、追っ手たちの刃を掠めたような、浅いものばかりだった。
「薬草のほかに、体と傷を清めるための水がいるわね……」
そうなると、自分一人ではできない。自分付きの侍女に頼まないとならないのだ。
「ちょっとそこ、クローゼットの中で一人で、静かに隠れていられるかしら?」
そう、小竜に尋ねた。
すると、コクコク、と縦に頷いて見せた。
私はクローゼットを開けて、彼の背を優しく押して、中に入るよう促す。すると、素直に中に入り、体をキュッとさせて小さくさせる。
「ボク、ここでしずかに、いいこにしてる」
「うん、お願いね」
そういって、パタンとクローゼットを閉めると、「ミランダ」と私付きの次女を呼ぶ。
「お呼びですか?」
そういって現れたミランダは、『白妃』を軽んじていて、私に使えることを倦んでいる。そんな彼女は、常に事務的にことを運ぼうとする。
今はそれが功を奏するといえるだろう。きっと彼女は部屋の中の異変などかけらも気づかないに違いない。
「たらいに水と、布を持ってきて欲しいのよ。少し清拭したくて」
「お手伝いは……」
「いらないわ」
「承知しました」
それで終わりである。
そうしてミランダが水を持って来てくれる間に、薬草を乳鉢で擦って、薬になる成分を絞り出す。
この簡単な薬作りは、昔私が昔の家事をさせられていたときにできた、あかぎれを治したりするのに覚えたものだった。だから、そこまであっという間に治ってしまうような驚くような効力のあるものではない。
けれど、毎日少しずつ塗っていけば、彼の傷も治るだろう、と。そう思って必要な量を擦っていた。
「水と布をお持ちしました」
「ありがとう」
やがて、ミランダが水を持ってやってきて、興味もなさそうに帰っていった。私も形式的に礼を返す。
「さて、出てきてもいいわよ。小さなお客さま」
そうクローゼットに向かって声をかけると、キィと小さく音を立てて、狭く内側から扉が開けられる。
「……だいじょぉぶ?」
「ええ、もう大丈夫よ」
そう答えると、扉が大きく開かれて、人の姿の子が私の腕の中に飛び込んできた。
「……怖かったの?」
「うん。しらないひと、きたから」
私は彼が腕の中に飛び込んできたとき、既に彼を受け入れてしまったようだ。優しく髪を指で梳きながら、穏やかに問いかけた。
「ちょっと汚れているわね。それと、傷があるわ。体を綺麗にして、傷に薬を塗らなきゃいけないわ」
「くすり、いや」
そういうと、子供は腕の中から逃げていって、部屋の隅に逃げてしまう。イヤイヤする姿は子供そのものだ。愛らしくて、思わす、くすくすと笑ってしまう。
「大丈夫よ。痛くないようにしたお薬を用意したから。ね?」
「ほんとうに、ほんとう? うそ、ついてない?」
こくんと首を傾げて尋ねてくる姿は、愛らしい。
「本当に。全く、かわいいわね。……ほら、いらっしゃい」
私が両腕を伸ばすと、おずおずと腕の中に戻ってくる。
「服を脱がすわね。体を拭いた方がいいから」
「うん」
そうして清拭している間もおとなしい。
──名前を聞けたりしないかしら?
この国で名乗るのは難しいかしら?
そんなことを考えながら私は清拭を終えた肌の、赤い部分に、刷毛で優しく薬を塗りつける。
「……いたくない」
子供はポツリとつぶやいた。
「良かった。……ねえ、お話しするのに不便だから、名前を教えてくれると嬉しいわ。私はアデリナっていうのよ」
「うそつかなかった」
「ん?」
「いたくなかった」
「ふふ。それなら良かったわ」
私は綺麗になって、薬を塗り終えた体に、もともと彼がきていた服を着直させた。
「ボクはね、ウソをつかないひとがすきなの」
にっこり笑って私に抱きついてくる。
「だから、おしえてあげる。ボクは、ドラコルト」
「そうなの。ドラコルト、よろしくね?」
「よろしく、アデリナ。ボクはドラコでいいよ」
そうお互いに挨拶してから、ドラコは部屋のあちこちを見て回る。さすがにさっきの今なので、外から見えそうな窓や扉の近くは止めたけれど。
「アデリナは。ここで、ひとりで、すんでるの?」
「……どうしてそんなことがわかるの?」
陛下の訪れがあれば、そんな返事を返す必要はなかったのかもしれない。けれど、この部屋、宮は、用がなければ誰の訪れもなく、私ただ一人で住んでいるといって過言はなかった。
「め、がね、さみしそう、だったから」
そういって、そっと私の目元に手を差し出してきた。暖かく、弾力のある、柔らかな指先が目元に触れる。それだけで、今までの悲しかったことが込み上げてきて、ぽろぽろと私は涙をこぼした。
「さみしいの? アデリナ?」
急に慌てて、服の袖でこぼれる涙を拭ってくれる。
「うん、そうだったのかもしれない」
そう、感じないように生きてきた。けれど、私は寂しかったのかもしれない。父母や妹に蔑ろにされ、一応夫である国王陛下には一度も夜の訪れを受けず。
「ボクが、いてあげようか?」
ドラコはそういって、ぎゅーっとする。
「何いっているの。帰るあてもなくて、ここに居候しようとしているくせに」
そういって私が揶揄すれば。
「ふふふ」
と笑って、私の胸元に顔を擦り付けてくる。
──もし子供がいたらこんな感じなのかしら。
人間にはあり得ない、銀の煌めく髪を持ち、瞳は黄金色。顔は非常に整っている方だろう。こども特有のきめ細かい肌は触れていて心地良い。
きっと、ご両親がいたら、かなりの美形に違いない。そして、耳は上側の先端が、人のそれより尖っていた。
そんな彼は、もうすっかり気を許し、すりすりと甘えてくるドラコの頬や耳たぶに優しくふれれば、ふにっ、と柔らかな弾力が返ってくる。色もまるで真っ赤に紅葉したもみじのよう。
思わず彼の存在の全ての愛らしさに、私は微笑んでしまう。
とはいえ、敵国である隣国の王族に近しそうな子供である。本当は彼を匿うのは不用心だろうな。
──それでも、この単調な一人の生活に寂しさを覚えてしまって。限界だったのだ。
「ちゃんと傷が癒えるまでここに隠れていなさいね」
思わず自分から言ってしまう。
すると彼はこうだ。
「かえりかた、わからない。むかえ、くるまで、アデリナといっしょ」
そう言って、私の膝に顔を擦り付けてきた。
することなすことが愛らしくあざとい。いや、あざといのではなく、何も考えずにやっているのだろうけれど。
と、そんなとき、部屋の外から声がした。
「お食事のお支度が整い、お持ちしました」
侍女のミランダだ。私は、終始体に触れてくるドラコの体温が心地よかったので、隠れさせるために離れるのも離れがたく、このまま受け取ることにした。
「しーっ」
私は彼の唇に人差し指を添えて、おとなしくするよう諭す。それから、ミランダに扉ごしに声をかけた。
「食事は外に置いておいて。これからも。ああ、そうそう、食事量を少し増やして欲しいのよ」
「……ご懐妊ですか?」
ミランダは抑揚もなく、彼女だってありもしないとわかっていることを聞く。
「食事は妃方の体調に合わせて作られています。多くするというのは……」
「皆が相手にしない白妃の体型が多少変わったとして、何か問題があるのかしら?」
くすりと笑って嫌味を返す。こんな強気に出られたことは初めてだ。
「いいえ、それは、その……」
モゴモゴと答えられずにいるミランダ。少し弑虐心を満足させられて、私の口は笑みの形を作ってします。
「そういうことなの。いいわね。調理室者たちにも伝えておいて」
「……それでは、この食事も変えた方がよろしいのでは……?」
私の珍しい攻勢に押されたのだろうか。自ら引いて、ありがたい提案を申し出てきた。
私は、床に座っている私の膝の上に顔を埋めているドラコを見下ろす。彼は今、傷を負って食事もしっかり必要だろう。私の分を分けるつもりだったが、彼の分ほど……とはいかずとも、増やしてもらった方がいいに違いない。
「……そうね、お願い」
「でしたら、一度御膳を下げてもう一度新しいものを用意させます。失礼します」
そういうと、カタンと御膳をもって立ち上がる気配がして、その後、足音が遠ざかるのが聞こえた。
「……ドラコ、もう大丈夫よ。」
そう言って、膝に顔を伏せて静かにしていた彼の髪を梳いてやる。
すると、ゆるゆると彼は顔を上げる。
「ごはん、ふやしたの?」
「ええ、あなたの分がいるでしょう?」
「バレて、しまったり、しない?」
そう言って、心配そうに潤んだ目で私を見上げてくる。
「大丈夫よ。結果として私が太るでもしなければ、咎められないわ。私は、他に我儘の一つも言っていないのだもの。これくらいは通るわよ」
そういうと、ニコッとドラコが笑う。
「食事がきたら、後で一緒に食べましょうね」
「うん。アデリナ、だいしゅき」
私に全面的に受け入れられたことを感じ取ったのだろう。
私の座る床は毛足の長いカーペット敷だ。そこから、ドラコは今度は堂々と私の膝の上に乗って、私に抱きつく。
「やさしい、アデリナ、だいしゅき。いっしょ、かえるといい」
そう言って顔を埋められると、彼の髪が私の鼻先をくすぐる。子供特有のまだ幼い匂いがして、その小さな存在が、愛らしくて愛おしくて。もう離れられない存在のように感じてしまった。
何より、前の寂しい環境にはもう戻れない。
「うん、一緒に帰るわ」
だから、私はあまり事態を重く考えず、返答を返してしまった。
「じゃあ、ゆびきり、げんまん」
小指を絡めることを求めてきた。私は、その時は児戯と軽んじており、安易にそれに応じたのだった──。
やがて、再びミランダが食事を持ってきた。彼女を早々に返してしまうと、にぎやかな二人での食事の開始である。
「やっぱりお箸はまだ無理ね? じゃあスプーンはどう? ……うーん、自分だと危なかしいわね」
何で食べさせても自分ではポリポロボロボロとこぼしてしまうドラコに、仕方ない、と私がスプーンを持つ。そして、子供が好みそうな甘い煮付けをスプーンに掬った。
「ほら、アーンして?」
「アーン」
そうして、差し出された煮付けをパクりと食べる。食べ方には問題があったが、体力の回復中だからなのか、追われていて食事にありつけなかったのか、食べっぷりはよく、初回は私の分まで少し食べる勢いだった。
「よく食べたわね。えらいわ。そうやって、傷を治して、大きくなりましょう? そうしたらきっと帰れるわ」
「……とうさま、きてくれる。たぶん。だから、だいじょうぶ」
「え……」
おそらく彼の父親といったら、龍神族の王族に近しい……。
──ええい、ままよ!
私は考えを切り替える。
いいじゃないか。この国に成人の竜人が来ようとも。
私は、もう一人ではいられない。ドラコとの生活が手放せなくなってしまったのだから。
そうして、私は彼、ドラコとの生活を受け入れるのだった。
彼の隠れ家は私のクローゼット。ミランダや、そのほかの人が来る場合には、静かに隠れさせる。
そうやって、日々を過ごしていった──。
私は、誰もいない部屋で、テーブルの椅子に腰掛けて、私は肘をつきながらぼうっとしていた。
ある意味、前の家ではやることは侍女の如く山のように合った。それとはうって変わって妃となって、何もすることがなくなって、正直、時を持て余していた。
衣食住にも事欠かない。
衣装は、前の家では考えられないような美しい衣を、体裁上、困らない程度に与えられていた。
食事は、後宮の皆が食べる食事なので、侯爵家出身とはいえ、毎日が贅沢な食事ばかりである。
住まいは、『美しい妃』が来るはずの宮だったので、大変美しい宮である。
けれど、国王陛下ですら、他の妃すら、誰も私の宮を訪れない。
実家からは便りのひとつもなかった。
「寂しいわ」
そう思いながらも、これで我が家はなんとかなるだろう。
「それでいいわ。家族の役に立てたんだから」
そう思っていた。
年老いた国王陛下に輿入れするだけ。それで、家族の役に立てたのだから。
◆
そうして三年が経った。
様子を見ていたアンジェリーナは、婚期ギリギリとはいっても相変わらず美しく、婚約話に事欠かなかった。結局、一応王家とは遠縁の公爵家の令息と結婚したのだという。
本来は、国王陛下の息子、王子殿下たちに輿入れさせたかったそうなのだが、アンジェリーナと私の入れ替えの件もあり、申し入れもしにくくなり、諦めたのだそうだ。
そして、私はおそらく国王陛下がご存命の間くらいは衣食住には困らない。
──これでいいのだ。
私は目を瞑ってそう思うのだった。
私は朽ちていく。
この宮で、人知れず、静かに──。
そう思っていたのだった。
◆
そうして使用人を除いてほぼ一人で生きていたある日。
「ピイィッ!」
と私の宮の裏の草むらから何かの鳴き声がした。
扉を開けていると、遠くから「アレはどこだ──! 見つけ次第殺せ──!」と声がした。
──そんなに怖いものが紛れ込んだのかしら。
声も近い。どうしよう。悲鳴を上げて侍女を呼んでおくべき?
悲鳴をあげれば、侍女の一人か二人がやってきて庇ってくれるだろう。
──『白妃』を本当に庇ってくれるかは疑問だけれど。
そんな妄想に私が耽っていると……。
「ピィ! ピィ!」
カサリ、と小さな葉擦れの音を立てて姿を表したのは小竜。
小さいとはいえ獣の姿に危機感を覚える。
「……おねがい、たすけて……!」
すると、その小竜は見た目三歳ほどの小さな子供の姿に変化して、人の言葉で私に救いを求めてきた。
「まあ、こんな小さな子だったのね」
それに、小竜でもあり、人間の姿に変化できるとあれば、ただの獣の竜ではなく、隣国の竜人族の子供だろう。そしてその証に、頭に二つの小さな角を持っていた。どうしてこんなところに迷い込んだのだろう。
外の叫んでいる男たちの声を聞きながら私は思う。
「……この子、殺しちゃまずい気がするんだけど」
そう呟くと、人の姿の小竜が私にぎゅっとしがみつく。
「おねがい。たしゅけて。あのひとたちに、わたしゃないで……!」
そう言って、必死に私に救いを求めるのである。
──どうしたものかしら。
隣国の竜人族が統べる国、ドラゴニア帝国は、人間から『亜人』と謗りを受けた、獣人たちをまとめ上げた国である。しかも、竜の姿をとれるものは、王族や、それに近しい血を持つものが多いと聞く。
だから、本来、しかるべき手段をとって、丁重にお返しするのが筋なんだけれど……。
「バント王国この国って、ドラゴニア帝国と敵対しているのよね……」
そう考えると、この子を追っている人間たちに、引き渡した後が怖かった。敵である隣国の、王族に近しい子供。一体どんな扱いを受けるのだろう。
──外の人間も殺せっていっているものね……。
「ねえ、おねえたま。ボクをかくまってくれない?」
舌ったらずな口調で、「匿って」などという。
──一体この子幾つなのかしら?
ドラゴニア帝国の人々は種族によって寿命も年齢による外見もさまざまなのだという。この子は実際は見た目の三歳くらいなのには、実年齢には当てはまらないのかしら?
でも、舌ったらずな子供っぽさもあるのよね。
私がそう考えていると、「あ、イタタタ」という声がした。
私の宮に入り込んだ小竜だ。
「勝手に……!」
入らないでと言おうとした時、彼が怪我をしているのが目についた。
「怪我をしているなら、治さないとね」
どうも私の方が捕まってしまったらしい、仕方ない。と思いながら、私は、裏の草むらの草の中から薬草になる草を選び取り、そして、部屋に戻った。
「追われていたからか、随分と汚れているわね。それと、あちこちに傷が……」
汚れは長く清めていないようなものではない。あくまで表面的なものだ。そして、傷も、深いものではなく、転んで擦ったり、追っ手たちの刃を掠めたような、浅いものばかりだった。
「薬草のほかに、体と傷を清めるための水がいるわね……」
そうなると、自分一人ではできない。自分付きの侍女に頼まないとならないのだ。
「ちょっとそこ、クローゼットの中で一人で、静かに隠れていられるかしら?」
そう、小竜に尋ねた。
すると、コクコク、と縦に頷いて見せた。
私はクローゼットを開けて、彼の背を優しく押して、中に入るよう促す。すると、素直に中に入り、体をキュッとさせて小さくさせる。
「ボク、ここでしずかに、いいこにしてる」
「うん、お願いね」
そういって、パタンとクローゼットを閉めると、「ミランダ」と私付きの次女を呼ぶ。
「お呼びですか?」
そういって現れたミランダは、『白妃』を軽んじていて、私に使えることを倦んでいる。そんな彼女は、常に事務的にことを運ぼうとする。
今はそれが功を奏するといえるだろう。きっと彼女は部屋の中の異変などかけらも気づかないに違いない。
「たらいに水と、布を持ってきて欲しいのよ。少し清拭したくて」
「お手伝いは……」
「いらないわ」
「承知しました」
それで終わりである。
そうしてミランダが水を持って来てくれる間に、薬草を乳鉢で擦って、薬になる成分を絞り出す。
この簡単な薬作りは、昔私が昔の家事をさせられていたときにできた、あかぎれを治したりするのに覚えたものだった。だから、そこまであっという間に治ってしまうような驚くような効力のあるものではない。
けれど、毎日少しずつ塗っていけば、彼の傷も治るだろう、と。そう思って必要な量を擦っていた。
「水と布をお持ちしました」
「ありがとう」
やがて、ミランダが水を持ってやってきて、興味もなさそうに帰っていった。私も形式的に礼を返す。
「さて、出てきてもいいわよ。小さなお客さま」
そうクローゼットに向かって声をかけると、キィと小さく音を立てて、狭く内側から扉が開けられる。
「……だいじょぉぶ?」
「ええ、もう大丈夫よ」
そう答えると、扉が大きく開かれて、人の姿の子が私の腕の中に飛び込んできた。
「……怖かったの?」
「うん。しらないひと、きたから」
私は彼が腕の中に飛び込んできたとき、既に彼を受け入れてしまったようだ。優しく髪を指で梳きながら、穏やかに問いかけた。
「ちょっと汚れているわね。それと、傷があるわ。体を綺麗にして、傷に薬を塗らなきゃいけないわ」
「くすり、いや」
そういうと、子供は腕の中から逃げていって、部屋の隅に逃げてしまう。イヤイヤする姿は子供そのものだ。愛らしくて、思わす、くすくすと笑ってしまう。
「大丈夫よ。痛くないようにしたお薬を用意したから。ね?」
「ほんとうに、ほんとう? うそ、ついてない?」
こくんと首を傾げて尋ねてくる姿は、愛らしい。
「本当に。全く、かわいいわね。……ほら、いらっしゃい」
私が両腕を伸ばすと、おずおずと腕の中に戻ってくる。
「服を脱がすわね。体を拭いた方がいいから」
「うん」
そうして清拭している間もおとなしい。
──名前を聞けたりしないかしら?
この国で名乗るのは難しいかしら?
そんなことを考えながら私は清拭を終えた肌の、赤い部分に、刷毛で優しく薬を塗りつける。
「……いたくない」
子供はポツリとつぶやいた。
「良かった。……ねえ、お話しするのに不便だから、名前を教えてくれると嬉しいわ。私はアデリナっていうのよ」
「うそつかなかった」
「ん?」
「いたくなかった」
「ふふ。それなら良かったわ」
私は綺麗になって、薬を塗り終えた体に、もともと彼がきていた服を着直させた。
「ボクはね、ウソをつかないひとがすきなの」
にっこり笑って私に抱きついてくる。
「だから、おしえてあげる。ボクは、ドラコルト」
「そうなの。ドラコルト、よろしくね?」
「よろしく、アデリナ。ボクはドラコでいいよ」
そうお互いに挨拶してから、ドラコは部屋のあちこちを見て回る。さすがにさっきの今なので、外から見えそうな窓や扉の近くは止めたけれど。
「アデリナは。ここで、ひとりで、すんでるの?」
「……どうしてそんなことがわかるの?」
陛下の訪れがあれば、そんな返事を返す必要はなかったのかもしれない。けれど、この部屋、宮は、用がなければ誰の訪れもなく、私ただ一人で住んでいるといって過言はなかった。
「め、がね、さみしそう、だったから」
そういって、そっと私の目元に手を差し出してきた。暖かく、弾力のある、柔らかな指先が目元に触れる。それだけで、今までの悲しかったことが込み上げてきて、ぽろぽろと私は涙をこぼした。
「さみしいの? アデリナ?」
急に慌てて、服の袖でこぼれる涙を拭ってくれる。
「うん、そうだったのかもしれない」
そう、感じないように生きてきた。けれど、私は寂しかったのかもしれない。父母や妹に蔑ろにされ、一応夫である国王陛下には一度も夜の訪れを受けず。
「ボクが、いてあげようか?」
ドラコはそういって、ぎゅーっとする。
「何いっているの。帰るあてもなくて、ここに居候しようとしているくせに」
そういって私が揶揄すれば。
「ふふふ」
と笑って、私の胸元に顔を擦り付けてくる。
──もし子供がいたらこんな感じなのかしら。
人間にはあり得ない、銀の煌めく髪を持ち、瞳は黄金色。顔は非常に整っている方だろう。こども特有のきめ細かい肌は触れていて心地良い。
きっと、ご両親がいたら、かなりの美形に違いない。そして、耳は上側の先端が、人のそれより尖っていた。
そんな彼は、もうすっかり気を許し、すりすりと甘えてくるドラコの頬や耳たぶに優しくふれれば、ふにっ、と柔らかな弾力が返ってくる。色もまるで真っ赤に紅葉したもみじのよう。
思わず彼の存在の全ての愛らしさに、私は微笑んでしまう。
とはいえ、敵国である隣国の王族に近しそうな子供である。本当は彼を匿うのは不用心だろうな。
──それでも、この単調な一人の生活に寂しさを覚えてしまって。限界だったのだ。
「ちゃんと傷が癒えるまでここに隠れていなさいね」
思わず自分から言ってしまう。
すると彼はこうだ。
「かえりかた、わからない。むかえ、くるまで、アデリナといっしょ」
そう言って、私の膝に顔を擦り付けてきた。
することなすことが愛らしくあざとい。いや、あざといのではなく、何も考えずにやっているのだろうけれど。
と、そんなとき、部屋の外から声がした。
「お食事のお支度が整い、お持ちしました」
侍女のミランダだ。私は、終始体に触れてくるドラコの体温が心地よかったので、隠れさせるために離れるのも離れがたく、このまま受け取ることにした。
「しーっ」
私は彼の唇に人差し指を添えて、おとなしくするよう諭す。それから、ミランダに扉ごしに声をかけた。
「食事は外に置いておいて。これからも。ああ、そうそう、食事量を少し増やして欲しいのよ」
「……ご懐妊ですか?」
ミランダは抑揚もなく、彼女だってありもしないとわかっていることを聞く。
「食事は妃方の体調に合わせて作られています。多くするというのは……」
「皆が相手にしない白妃の体型が多少変わったとして、何か問題があるのかしら?」
くすりと笑って嫌味を返す。こんな強気に出られたことは初めてだ。
「いいえ、それは、その……」
モゴモゴと答えられずにいるミランダ。少し弑虐心を満足させられて、私の口は笑みの形を作ってします。
「そういうことなの。いいわね。調理室者たちにも伝えておいて」
「……それでは、この食事も変えた方がよろしいのでは……?」
私の珍しい攻勢に押されたのだろうか。自ら引いて、ありがたい提案を申し出てきた。
私は、床に座っている私の膝の上に顔を埋めているドラコを見下ろす。彼は今、傷を負って食事もしっかり必要だろう。私の分を分けるつもりだったが、彼の分ほど……とはいかずとも、増やしてもらった方がいいに違いない。
「……そうね、お願い」
「でしたら、一度御膳を下げてもう一度新しいものを用意させます。失礼します」
そういうと、カタンと御膳をもって立ち上がる気配がして、その後、足音が遠ざかるのが聞こえた。
「……ドラコ、もう大丈夫よ。」
そう言って、膝に顔を伏せて静かにしていた彼の髪を梳いてやる。
すると、ゆるゆると彼は顔を上げる。
「ごはん、ふやしたの?」
「ええ、あなたの分がいるでしょう?」
「バレて、しまったり、しない?」
そう言って、心配そうに潤んだ目で私を見上げてくる。
「大丈夫よ。結果として私が太るでもしなければ、咎められないわ。私は、他に我儘の一つも言っていないのだもの。これくらいは通るわよ」
そういうと、ニコッとドラコが笑う。
「食事がきたら、後で一緒に食べましょうね」
「うん。アデリナ、だいしゅき」
私に全面的に受け入れられたことを感じ取ったのだろう。
私の座る床は毛足の長いカーペット敷だ。そこから、ドラコは今度は堂々と私の膝の上に乗って、私に抱きつく。
「やさしい、アデリナ、だいしゅき。いっしょ、かえるといい」
そう言って顔を埋められると、彼の髪が私の鼻先をくすぐる。子供特有のまだ幼い匂いがして、その小さな存在が、愛らしくて愛おしくて。もう離れられない存在のように感じてしまった。
何より、前の寂しい環境にはもう戻れない。
「うん、一緒に帰るわ」
だから、私はあまり事態を重く考えず、返答を返してしまった。
「じゃあ、ゆびきり、げんまん」
小指を絡めることを求めてきた。私は、その時は児戯と軽んじており、安易にそれに応じたのだった──。
やがて、再びミランダが食事を持ってきた。彼女を早々に返してしまうと、にぎやかな二人での食事の開始である。
「やっぱりお箸はまだ無理ね? じゃあスプーンはどう? ……うーん、自分だと危なかしいわね」
何で食べさせても自分ではポリポロボロボロとこぼしてしまうドラコに、仕方ない、と私がスプーンを持つ。そして、子供が好みそうな甘い煮付けをスプーンに掬った。
「ほら、アーンして?」
「アーン」
そうして、差し出された煮付けをパクりと食べる。食べ方には問題があったが、体力の回復中だからなのか、追われていて食事にありつけなかったのか、食べっぷりはよく、初回は私の分まで少し食べる勢いだった。
「よく食べたわね。えらいわ。そうやって、傷を治して、大きくなりましょう? そうしたらきっと帰れるわ」
「……とうさま、きてくれる。たぶん。だから、だいじょうぶ」
「え……」
おそらく彼の父親といったら、龍神族の王族に近しい……。
──ええい、ままよ!
私は考えを切り替える。
いいじゃないか。この国に成人の竜人が来ようとも。
私は、もう一人ではいられない。ドラコとの生活が手放せなくなってしまったのだから。
そうして、私は彼、ドラコとの生活を受け入れるのだった。
彼の隠れ家は私のクローゼット。ミランダや、そのほかの人が来る場合には、静かに隠れさせる。
そうやって、日々を過ごしていった──。