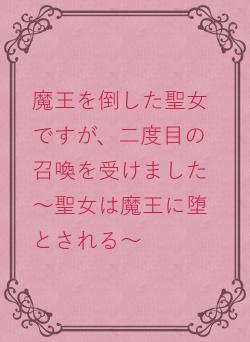それは十八歳の貴族学園卒業パーティーでのことだった。
「アンネリーゼ・バーデン伯爵令嬢! 私はこのサラサ・カガミとの『真実の愛』を知った。その上、彼女は私の子を身ごもっている。わかるか? この国の跡取りがいるということだよ! だから、妻には彼女を迎える。よって、私はお前との婚約を破棄することをここに宣言する!」
「は……? 真実の、愛? 子供?」
私を名指しする彼は、この国の王太子カイン・バウムガルデン殿下。彼のいう、アンネリーゼ・バーデンとは私のことだ。
十八歳という歳で、結婚の儀も間近に控えていたはず。けれど、突然婚約破棄とはどういうことだろう。
私は突然降ってわいた宣告に呆然とした。
「アンネリーゼ。お前は、私の側にいるサラサに嫉妬して、彼女にきつく叱責したり、彼女の制服を破ったり、挙げ句の果てには彼女のことを階段の上から突き落としただろう!」
その彼が私を指さして威(い)丈(たけ)高(だか)に叫ぶ。彼の声は、しんと静まりかえったきらびやかなホールに響き渡った。
そして、彼とサラサを援護するように、騎士団長の子息や、学園で教鞭を執っていた教師、神官長の子息、確かサラサの身元引受人になった貴族の家の子息といった、学園内では有名なメンバーが、王太子殿下とサラサの周りを囲んでいた。
きっと、彼らは王太子殿下とサラサとの恋路を支持するといった意思表明なのだろう。
確かに私は、彼女に「婚約者が既にいらっしゃる殿方になれなれしくしてはなりませんよ」と諭したこともある。サラサが、既に婚約者のいる騎士団長の子息や、神官長の子息、学園の担任をしていた教師や、サラサの身元引受人の兄君にと、次々と秋波を送っていたからだ。
ただ、「まだこの世界にきて日が浅いから、そういった常識をまだ知らないのだろう」と考慮して、やんわり諭しただけのはずだった。
さらにいわせてもらえば、制服を破ったのは私ではない。私以外の、自分の婚約者に色目を使われた他の女性たちであった。私は、彼女たちにその話を聞いて、彼女たちの愚痴に頷きつつ、やりすぎは良くないと諭し、サラサに対しては、彼女が困らないように新しい制服を贈ったはずだ。
階段から突き落としたというのも身に覚えはない。強いていえば、ちょうど学園の階段の上ですれ違ったときに、勝手に彼女が階段から落ちたのだった。
だから、私はぽかんとする。
──ええと? 身に覚えがないんですけど。
それに私たち、女王陛下直々にお決めになられた婚約者同士でしたよね?
王太子殿下は、先ほどいったとおり私の婚約者でもある男性である。彼が指をさして名指ししている令嬢、彼の婚約者であるはずの私。そして、その婚約をお決めになったのはこの国のトップのアレクサンドラ・バウムガルデン女王陛下、彼のお母さまである。
絶対君主制のこの国の頂点に立つ人。女性ながらも身内の血の粛清を厭わずにその玉座を手にした人で、彼女に逆らえる人は片手の指が余るほどしかいない。強いていえば、彼女の夫である王配、エドワルド王配殿下ぐらいだろうか。
……って、話がそれたので戻しましょう。
そう、「真実の愛」とやらの話である。
そりゃあ空前のブームであるので、私ですら「真実の愛」については知っている。それがどんなに貴族社会に混乱をもたらしているかも。だがしかしそれは、まだ、庶民や貴族の間だけに流行るものだった。
婚約者のいる貴族男性が、平民である商家の生まれの女性と恋に落ち、身分を捨てて駆け落ちしてしまったり。
婚約者のいる貴族男性が、本来の婚約者である姉にではなく、妹と恋に落ち、家内でなんとか収拾をつけたりとか。
そんな騒ぎをよく聞くようになってきた。
やがてそれは、高位貴族でもちらほらと耳にするようになってきていて、私の友人の貴族令嬢が婚約破棄されて泣くのを宥めたことも一度や二度ではない。
女性の方が家格が上で、断固として婚約破棄を受け入れなかったとしても、それはそれで結婚後に愛情のない寒い結婚生活が待っているのだった。その上、「真実の愛」で結ばれた女性との愛人関係に目をつむるという、酷い例もあるのだった。
けれども、さすがに王族の結婚や婚約に「真実の愛」などというものは、側室や妾などを持つことを除けば、前例はない。少なくともこの国、バウムガルデン王国では聞いたことがなかった。
王族にとっての結婚とは、家と家、血と血、ときには国と国とを結びつける。国の行く末を決めるためのものだから、「真実の愛」ブームとは無縁のはずだ……った。
ちなみに王太子殿下と私の婚約は、この国の女王陛下アレクサンドラさまが、私が十歳を過ぎたときにお決めになったことだ。その女王陛下のお決めになったことを、王太子殿下が独断で覆そうというのだろうか。それとも、女王陛下もご存じということだろうか。
──いや、それはないだろう。
だったら、女王陛下からの命で婚約が解消されるはずだ。もしくは、女王陛下の御前で王太子殿下が代弁なさるだろう。
そして私に落ち度があるのであればそれを糾弾されて破談とされる。そうでなく、私に落ち度がなく、王家の問題であるのであるならば、我が家へ多額の謝罪金と共に申し出があるのが普通なのだ。しかも、婚前交渉のあげくに他の女性を身ごもらせたのだから。
そうして当の女王陛下は今、国の祭事で王配殿下と共に国の辺境にいらっしゃる時期だ。今年の豊作の祈りを神々に捧げるための祭司として、女王陛下及び王配殿下揃ってお出かけになっている。
だから、そのタイミングで婚約解消の話など出るはずがないのだ。本来なら。この国の重要事項を決めるべき女王陛下はご不在なのだから。
女王陛下はとても美しい方。けれど、とても苛烈な女(ひと)だ。それこそ身内の血の粛清すら厭わないその性格から、「赤の女王」と呼ばれるほどに。そしてそれを受け入れる豪胆さ。
彼女の命令は絶対。そしてそれを覆そうとするものがいれば、躊躇なく断罪する。それは身内であってもだ。今王位に立っているのですら、兄君の血の上になりたったものだ。彼の退廃的で浪費の激しい生活は、やがて国を滅ぼすと、彼を王に値しないと判断し、自分を支持する貴族たちと共にクーデターを起こし、彼を退位させ、高い鉄塔の上にある牢の中に永久幽閉したのちに断罪──粛正していた。
ちなみに、兄君が政治への興味がないことをいいように利用して、国で定めた税率以上の課税をかけ、稼いでいた貴族たちは、すべからく断頭台へと送られている。
そうして「赤の女王」と恐れられる反面、女王陛下はとても有能な方でもあった。だからこそ、家内での血で血を争った上で在位していることを黙認されているのだ。
そう。女王陛下に逆らうことはとても恐ろしいことなのだ。
だから私はとても迷った。
「殿下。そのご下命は、女王陛下もご了承のものと受けとめてもよろしいでしょうか?」
違うだろうと、薄々思いながらも、私は相手の様子を探ってみることにする。
すうと深呼吸をしてから、なんとか頭の混乱を鎮め、問いかけた。
「ははう……、いや、女王陛下にはお帰りになった際にこのサラサの引き合わせも兼ねて報告をする。母上だって、我が王族に、希少な聖女の血が混ざることを心から喜んでくださるに違いない! しかも、すでに我が王国の跡取りが希少な聖女の身に宿っているんだ!」
──は? 事後承諾? しかもできちゃった婚? あの女王に? って、馬鹿──!?
息子なのに、自分の母親である女王陛下の恐ろしさを知らないの?
私でもことの顛末は想像がつきそうなものなのに!
私は人前にもかかわらず、私は思わぬ返答──いや、想定どおりだろうか──の返しに、ぽかんと開いた口が塞がらない。
彼が彼の側に抱き寄せたのは、茶色い髪の頼りなげな愛らしい少女。サラサ・カガミ。彼女の腹部はまだ妊娠したと分かるほどの膨らみはない。
けれど、周囲には儚げな表情を見せるものの、私と目が合うと、好戦的な、勝ち誇ったような笑みを浮かべる。
私の婚約者を奪えたことに、優越感を感じているのかもしれない。
彼女は招かれ人──要は異世界からの転移者としてこの国に降り立ったのだという。あくまで世界が呼んだものであって、召喚術などを使って意図的に呼ばれたわけではない。ただ、その希少さから、聖女や聖人とあがめ奉られるのが恒例で、この国の有名人だ。
なぜそんなに重用されるのかというと、異世界からの転移者というのは、世界と世界を移動する際に、特別な力を神から授かることが多いからだという。
サラサの場合、一般人では使いこなせない人々を癒す光の魔法を行使することができるそうだ。
そんな彼女が、王太子殿下と親しくしているのは知っていた。けれど、それも彼女がまだこの世界の常識をまだ理解できていないからだと思っていた。
そのことを、確かに私はそのことをサラサに注意したりしたことはあったが、糾弾するようないい方をした覚えはない。
「あの、今、国には女王陛下はいらっしゃいません。それでもこれは決定事項、と認識してよろしいでしょうか」
私は、この事態の収拾を試みた。
いや、このあと女王陛下が戻ってくるまで、これをうやむやにしていたくない。火を見るのは明らか、逃げるが勝ちだ。なんとかして逃げたい。
そしてできるだけ、この大勢の人々の前で、この婚約破棄の決定者は王太子殿下だということを明確にしてしまいたかった。
今ここで王太子殿下が「決定ごとだ」といってしまえば、責任は全て彼のものとなる。苛烈な女王陛下からお叱りを受けるのは、王太子殿下とサラサ、そしてその取り巻きたちだろう。
──今は、今ここで私に非がないことをはっきりさせなければ。
そうでなければ、私を含め、お父さまやお母さま、可愛い双子の弟妹にまで累が及びかねないのだ。
私は、嫌な汗が背中を伝うのを感じながら、今か今かと王太子殿下の口が開かれるのを待つ。
「ああ、決定事項だ。女王陛下並びに王配殿下のいない今、国の裁量は私に委ねられているからな。私の王妃はサラサに、そして私の跡継ぎはサラサの子とする。その私の子を宿しているサラサを階段から突き落とした罪により、そなたをこの国から追放する。この国から早々に出て行くが良い」
──よし、言質はとった。
なにかあっても、責任は全て彼に取ってもらおう。
でも、まさか王太子殿下が婚約破棄までいい出す事態になっていただなんて。しかも孕ませ……いや、言葉が過ぎるか。そんな関係にまでなっていたとは知らなかった。
──なんて馬鹿なんだろう。
私は心の中で思う。
いくら実の息子とはいえ、あの「赤の女王」の決定事項を覆すなんて。
けれど、彼女(サラサ)がいくら希少な存在とはいえども彼女はもとは平民。いや、聖女と見いだされてから、確か伯爵家の養女に迎えられているはず。だったら家格の問題はクリアなのかもしれない。
そして次に、彼女はこの世界での教養はほとんどないといって良いレベルだった。常識的に考えて、今すぐ彼女を婚約者に据えるなど考えられるはずもない。
王太子妃に必要な、語学、淑女教育、社交能力、他国に至るまでの歴史の詰め込み……数えたらキリがないけれど、それを今から、おそらく十八かそこらから身につけようというのか。しかも身重の身で。
しかも、この国の国教は、結婚に際して女性に純潔性を求めるのだ。王族の結婚ともなれば、初夜の血のついたシーツが、翌朝恭しげに飾られるほど。
なのに、それすら覆している。
あの聖女は教会に保護されているのだろうけれど、その教義を足蹴にしているサラサをどこまでかばうのだろうか。
──そこまでの覚悟があっての婚約破棄騒動であれば、「真実の愛」とは見あげたものだと感嘆できる……のだけれど。
──この国の王太子は馬鹿だ。
彼を頼りに婚約者に名乗りをあげたサラサも、どこまでどういう状況下なのかわかっているのだろうか?
女王に打診をせず、不在のおりに、彼女が決めた婚約を勝手に破棄をする。これほど恐ろしい行為はそうそうないだろう。きっと王太子殿下のみでは飽き足らず、サラサ自身にも怒りの矛先が向くに違いない。
おかしなものだ。豊かな知識と実行力を併せ持ち、性格は苛烈で、「赤の女王」の二つ名で呼ばれる女王陛下。そのご子息が庶民の流行に無計画で乗って浮かれているのには、めまいさえ覚えた。
きっと女王陛下は烈火のごとく怒ることだろう。身内でありながらそれすら分からないのだろうか。いや、息子だからこそ、その立場に甘えている?
──さあて、どうしよう。
私は思案する。
彼の言質は取った。次は私の心の整理だ。
私は十歳の頃に婚約者として定められ、相手となったカイン殿下に、恋をしようと努力した。そして、それは次第に私の思考を染めてゆき、私は彼に恋をするようになった。
だから、彼の心変わりが決定的になった今、正直なところ、私は心から傷ついている。貴族令嬢としての矜持があるからこそ、ぐっと我慢をしてはいるものの、今この場で崩れ落ちて泣いてしまいたいほどの心情だ。恋をするよう仕向けた恋でも、それが破られれば、傷つくものなのだ。
それなのに、壇上の殿下とサラサは、そんな傷心の私を尻目にイチャイチャとじゃれ合っている。
それを見て、私は唇を噛んだ。目には涙が滲んできたのだろうか。彼らを眺める視界がぼやけてきている。さらに、身体を支える力が抜けて、床に直に座り込んでしまう。
ようやく、異常事態に固まっていた心と体に、感情が追いついてきたのだろう。
──泣きたい。辛い、逃げたい。誰かこれは現実じゃない、夢だといって。
でも、私を遠目にみる誰も、助けてはくれなかった。なぜならば、次期王太子妃となるものがどちらになるのか、判断しかねているのだろう。確実に王太子妃となるものに肩入れしたい。それまでは様子見をする。貴族とはそういうものだ。
ここにいる者たちは、その貴族の令息、令嬢たちなのだから。
私はぎゅっと唇を噛み、拳を握りしめる。
──さて、どうする?
辺りを見回すが、私は遠巻きにされて、味方になってくれそうな人は見当たらなかった。
──ここはひとまず退場して、状況をお父さまにご報告すべき?
泣いている場合じゃないわ。まずはお父さまに報告しないと。
そうしてようやく頭の整理が付く。
「アンネリーゼさま」
そう考えていた矢先、優しい声音と共に、コツコツと足音が近づいてきて、そっと真っ白い清潔そうなハンカチをて差し出された。私は俯いていたものを、はっとして顔を上げる。
「……エリアス、殿下?」
それは、カイン王太子殿下の弟君の第三王子殿下。この学園の後輩にあたる方であった。私のふたつ年下の方だ。
バウムガルデン王家には、カイン王太子殿下の他に、カール第二王子殿下、そして声をかけてくださったエリアス第三王子殿下がいる。ちなみに、カール第二王子殿下とエリアス第三王子殿下は双子の兄弟だ。
話をもとに戻そう。
私は、じっとエリアス殿下を見つめたあとに、差し出された一つの穢れもない真っ白なハンカチを見つめた。
「エリアス殿下、どうして……」
ここにいるのか、と問おうとすると、そっと唇にハンカチを押し当てられる。真っ白い清潔なハンカチに、私の涙のシミがついてしまう。
「女性がそんなきつく唇をかみしめたり、拳を握ってはいけませんよ。もしも唇が切れてしまったり、手の平に爪が食い込んで、玉の肌に傷が付いてしまったりしたら大変だ。そして、その涙はハンカチの中に隠してしまいましょう?」
誰もが私を遠巻きにしている中に、私に気を配ってくれる人がいたことに安堵した。再びじわり、と私の瞳に涙が浮く。
「ほら、ダメですよ。ここは人前ですから……」
そういって彼は、私を彼の背中の影に隠れるようにしてくれる。
──年下の十六歳の彼の背中はこんなに大きかったかしら?
私たちの間にはあまり接点はない。学園に入学する頃には、私はすでに王太子殿下の婚約者であったから、他の男性とは距離を置いていた。記憶に残っているのは、エリアス第三王子殿下が、彼の入学式のときに生徒代表として壇上で挨拶をするのを遠目で聞いたとき以来だ。そのときの彼は、まだ幼さの残る顔立ちをしていたはず。
そう記憶をたどっていると、大衆のざわめきの中からひときわ大きな声がした。私を取り巻く人混みに割れ目ができる。
そこから現れた人の姿を一目見て、気が緩んだ私の頬に、とうとう涙が伝った。
「アンヌ!」
アンヌ、それは私の愛称だ。家族以外にそれを使う人はいない。
「……お父さま!」
私は、一番の味方が来て、名指しされてからずっと硬かった表情が和らぐのを感じる。
お父さまは私の側に来る。すると、エリアス殿下がお父さまと位置を交代して、私を正面から優しく抱きしめてくださった。
「お父さま、お仕事中じゃ……?」
「子細をエリアス殿下にお聞きして、飛んできたよ。今は私の大切なアンヌの危機なんだ。なにを置いても君のもとへ駆けつけるのが父親として当然だ。なんでも酷い目に遭わされたんだって? 今はお前も動揺して落ち着いて判断もできないだろう。この場は辞退しよう、家に帰るんだ。いいな?」
「いいんですか?」
逆に私はお父さまに問う。するとお父さまはさも不思議そうに首を傾げた。
「どういうことだい?」
「私は王太子殿下から婚約破棄を命じられました。私たちの婚約は、女王陛下が直々にお決めになったもの。ただ婚約が解消して終わりになるとは思えません。私は私に落ち度があったとは思いません。けれど、関係者の私をかばえば、家にもご迷惑をかけてしまうかも……」
そう告げると、お父さまは首を横に振る。
「大丈夫。今はどう手をこまねいても女王陛下と王配殿下は揃っていらっしゃらない。だからまだ女王陛下はこの事態を知ってすらいないはず。だから手の打ちようはないんだ。な? まずは、家に帰って落ち着こう? それからこれからのことを考えればいい」
私はお父さまの言葉にコクン、と素直に頷いた。
嬉しかった。
だから、思わず子供の頃のように両手をお父さまに伸ばす。すると、お父さまは座り込んでしまっていた私を両手で支えながら起き上がらせてくれる。そして、私が立ち上がると優しく抱きしめてくれた。
お父さまの抱擁は温かかった。大きな背中がやっと温もりと安心をくれた。
私を窮地に陥れた弟君のエリアス殿下しか助けてくれない衆人の注目の中、もっとも頼りになる人のひとり、お父さまが駆けつけてくれたから。心からの安心を得ることができた。
しばらくの間、私たちが抱きしめ合っている間見守るように立っていらっしゃったエリアス殿下を私は見る。それと彼の貸してくださった真っ白いハンカチも。彼が貸してくださったそのハンカチは、涙で汚れてしまっていた。薄く施していた化粧の色も、ハンカチについてしまっている。
「殿下、このハンカチ……」
子供だとばかり思っていた彼は、まだ幼さが残る顔つきながらも穏やかで優しげな表情でにっこりと微笑んでくれた。
「大丈夫。それは使い捨ててしまってくれていいよ。それとね。この件、兄上の勝手な持論で進まないよう、私から母上にもきちんと伝えておく。だから、安心するといい」
そう約束して、にっこり笑ってくれた。
──結婚前に他の令嬢を孕ませるような方、こちらから願い下げなんですけど……。
ようやく気力が戻ってきて、心の内で思うが、さすがに口には出さなかった。
「それにしてもタイミングが良かったな」
「それはどういう?」
「この国の宰相である君のお父さまはね、ちょうどこの卒業式でご自身の部下とする文官にふさわしい人物を見定めにいらっしゃっていたんだ」
エリアス殿下とお父さまが目配せをし合う。
それが聞こえると、ざわっと辺りがざわめいた。きっと文官の職を欲しいと願っている子息たちだろう。
「こんな事態を良かったというのもなんだけれど、不幸中の幸いというところかな。騒ぎになってすぐ、私が呼んだんだよ。だから君を護りに来ていただけた。……だって、私より、やはりお父さまの方が頼りがいがあるだろう?」
最後のそのひと言に、少し寂しそうな陰りがあったのは気のせいだろうか? 確かに、エリアスさまはお優しいけれど頼りがいがあるかといわれると、ちょっと……という感じなのだけれど。
ともかく私は、一番の身内のお父さまの腕の中で、ほっとして脱力する。お父さまの腕に再びしがみつく形で倒れそうになってしまった。
「可哀想に、アンヌ……」
お父さまが、私を楽にしようと抱き上げようとする。
「バーデン卿、私が……」
そういいかけるエリアス殿下を、お父さまがきつい口調で制止する。
「殿下。娘の危機にお呼び下さったことは感謝いたします。……ですが、私は今のこの場で娘を傷つけた者の弟君に、娘の身を預ける気は毛頭はございません」
私はともかく、お父さまは王太子殿下おひとりだけではなく、王家全体に対して反感を覚えたらしい。
そうきつめにいうと、軽々と私を姫抱きに抱き上げてくれる。
「……お父さま……」
普段は優しいお父さま。けれど、その怖さも、この場では頼もしく感じて、安堵感を覚えた私は頭をお父さまの肩に預けて瞳を閉じた。
「くっ……」
エリアス殿下は、苦しげに唇を噛んで下を向いたけれど、なぜだろう。私は所詮顔見知りの上級生、そして、一貴族の娘。そしてたまたま、彼の兄の婚約者だった女というだけだというのに。
エリアス殿下の思惑は分からなかったけれど、お父さまは、王族への最低限の礼だけを執って、その場を辞することになった。私は抱き上げられたまま頭を垂れることしかできなかったけれど。
衆人の好奇の目からは、お父さまの大きな背中が守ってくれた。
「アンネリーゼ・バーデン伯爵令嬢! 私はこのサラサ・カガミとの『真実の愛』を知った。その上、彼女は私の子を身ごもっている。わかるか? この国の跡取りがいるということだよ! だから、妻には彼女を迎える。よって、私はお前との婚約を破棄することをここに宣言する!」
「は……? 真実の、愛? 子供?」
私を名指しする彼は、この国の王太子カイン・バウムガルデン殿下。彼のいう、アンネリーゼ・バーデンとは私のことだ。
十八歳という歳で、結婚の儀も間近に控えていたはず。けれど、突然婚約破棄とはどういうことだろう。
私は突然降ってわいた宣告に呆然とした。
「アンネリーゼ。お前は、私の側にいるサラサに嫉妬して、彼女にきつく叱責したり、彼女の制服を破ったり、挙げ句の果てには彼女のことを階段の上から突き落としただろう!」
その彼が私を指さして威(い)丈(たけ)高(だか)に叫ぶ。彼の声は、しんと静まりかえったきらびやかなホールに響き渡った。
そして、彼とサラサを援護するように、騎士団長の子息や、学園で教鞭を執っていた教師、神官長の子息、確かサラサの身元引受人になった貴族の家の子息といった、学園内では有名なメンバーが、王太子殿下とサラサの周りを囲んでいた。
きっと、彼らは王太子殿下とサラサとの恋路を支持するといった意思表明なのだろう。
確かに私は、彼女に「婚約者が既にいらっしゃる殿方になれなれしくしてはなりませんよ」と諭したこともある。サラサが、既に婚約者のいる騎士団長の子息や、神官長の子息、学園の担任をしていた教師や、サラサの身元引受人の兄君にと、次々と秋波を送っていたからだ。
ただ、「まだこの世界にきて日が浅いから、そういった常識をまだ知らないのだろう」と考慮して、やんわり諭しただけのはずだった。
さらにいわせてもらえば、制服を破ったのは私ではない。私以外の、自分の婚約者に色目を使われた他の女性たちであった。私は、彼女たちにその話を聞いて、彼女たちの愚痴に頷きつつ、やりすぎは良くないと諭し、サラサに対しては、彼女が困らないように新しい制服を贈ったはずだ。
階段から突き落としたというのも身に覚えはない。強いていえば、ちょうど学園の階段の上ですれ違ったときに、勝手に彼女が階段から落ちたのだった。
だから、私はぽかんとする。
──ええと? 身に覚えがないんですけど。
それに私たち、女王陛下直々にお決めになられた婚約者同士でしたよね?
王太子殿下は、先ほどいったとおり私の婚約者でもある男性である。彼が指をさして名指ししている令嬢、彼の婚約者であるはずの私。そして、その婚約をお決めになったのはこの国のトップのアレクサンドラ・バウムガルデン女王陛下、彼のお母さまである。
絶対君主制のこの国の頂点に立つ人。女性ながらも身内の血の粛清を厭わずにその玉座を手にした人で、彼女に逆らえる人は片手の指が余るほどしかいない。強いていえば、彼女の夫である王配、エドワルド王配殿下ぐらいだろうか。
……って、話がそれたので戻しましょう。
そう、「真実の愛」とやらの話である。
そりゃあ空前のブームであるので、私ですら「真実の愛」については知っている。それがどんなに貴族社会に混乱をもたらしているかも。だがしかしそれは、まだ、庶民や貴族の間だけに流行るものだった。
婚約者のいる貴族男性が、平民である商家の生まれの女性と恋に落ち、身分を捨てて駆け落ちしてしまったり。
婚約者のいる貴族男性が、本来の婚約者である姉にではなく、妹と恋に落ち、家内でなんとか収拾をつけたりとか。
そんな騒ぎをよく聞くようになってきた。
やがてそれは、高位貴族でもちらほらと耳にするようになってきていて、私の友人の貴族令嬢が婚約破棄されて泣くのを宥めたことも一度や二度ではない。
女性の方が家格が上で、断固として婚約破棄を受け入れなかったとしても、それはそれで結婚後に愛情のない寒い結婚生活が待っているのだった。その上、「真実の愛」で結ばれた女性との愛人関係に目をつむるという、酷い例もあるのだった。
けれども、さすがに王族の結婚や婚約に「真実の愛」などというものは、側室や妾などを持つことを除けば、前例はない。少なくともこの国、バウムガルデン王国では聞いたことがなかった。
王族にとっての結婚とは、家と家、血と血、ときには国と国とを結びつける。国の行く末を決めるためのものだから、「真実の愛」ブームとは無縁のはずだ……った。
ちなみに王太子殿下と私の婚約は、この国の女王陛下アレクサンドラさまが、私が十歳を過ぎたときにお決めになったことだ。その女王陛下のお決めになったことを、王太子殿下が独断で覆そうというのだろうか。それとも、女王陛下もご存じということだろうか。
──いや、それはないだろう。
だったら、女王陛下からの命で婚約が解消されるはずだ。もしくは、女王陛下の御前で王太子殿下が代弁なさるだろう。
そして私に落ち度があるのであればそれを糾弾されて破談とされる。そうでなく、私に落ち度がなく、王家の問題であるのであるならば、我が家へ多額の謝罪金と共に申し出があるのが普通なのだ。しかも、婚前交渉のあげくに他の女性を身ごもらせたのだから。
そうして当の女王陛下は今、国の祭事で王配殿下と共に国の辺境にいらっしゃる時期だ。今年の豊作の祈りを神々に捧げるための祭司として、女王陛下及び王配殿下揃ってお出かけになっている。
だから、そのタイミングで婚約解消の話など出るはずがないのだ。本来なら。この国の重要事項を決めるべき女王陛下はご不在なのだから。
女王陛下はとても美しい方。けれど、とても苛烈な女(ひと)だ。それこそ身内の血の粛清すら厭わないその性格から、「赤の女王」と呼ばれるほどに。そしてそれを受け入れる豪胆さ。
彼女の命令は絶対。そしてそれを覆そうとするものがいれば、躊躇なく断罪する。それは身内であってもだ。今王位に立っているのですら、兄君の血の上になりたったものだ。彼の退廃的で浪費の激しい生活は、やがて国を滅ぼすと、彼を王に値しないと判断し、自分を支持する貴族たちと共にクーデターを起こし、彼を退位させ、高い鉄塔の上にある牢の中に永久幽閉したのちに断罪──粛正していた。
ちなみに、兄君が政治への興味がないことをいいように利用して、国で定めた税率以上の課税をかけ、稼いでいた貴族たちは、すべからく断頭台へと送られている。
そうして「赤の女王」と恐れられる反面、女王陛下はとても有能な方でもあった。だからこそ、家内での血で血を争った上で在位していることを黙認されているのだ。
そう。女王陛下に逆らうことはとても恐ろしいことなのだ。
だから私はとても迷った。
「殿下。そのご下命は、女王陛下もご了承のものと受けとめてもよろしいでしょうか?」
違うだろうと、薄々思いながらも、私は相手の様子を探ってみることにする。
すうと深呼吸をしてから、なんとか頭の混乱を鎮め、問いかけた。
「ははう……、いや、女王陛下にはお帰りになった際にこのサラサの引き合わせも兼ねて報告をする。母上だって、我が王族に、希少な聖女の血が混ざることを心から喜んでくださるに違いない! しかも、すでに我が王国の跡取りが希少な聖女の身に宿っているんだ!」
──は? 事後承諾? しかもできちゃった婚? あの女王に? って、馬鹿──!?
息子なのに、自分の母親である女王陛下の恐ろしさを知らないの?
私でもことの顛末は想像がつきそうなものなのに!
私は人前にもかかわらず、私は思わぬ返答──いや、想定どおりだろうか──の返しに、ぽかんと開いた口が塞がらない。
彼が彼の側に抱き寄せたのは、茶色い髪の頼りなげな愛らしい少女。サラサ・カガミ。彼女の腹部はまだ妊娠したと分かるほどの膨らみはない。
けれど、周囲には儚げな表情を見せるものの、私と目が合うと、好戦的な、勝ち誇ったような笑みを浮かべる。
私の婚約者を奪えたことに、優越感を感じているのかもしれない。
彼女は招かれ人──要は異世界からの転移者としてこの国に降り立ったのだという。あくまで世界が呼んだものであって、召喚術などを使って意図的に呼ばれたわけではない。ただ、その希少さから、聖女や聖人とあがめ奉られるのが恒例で、この国の有名人だ。
なぜそんなに重用されるのかというと、異世界からの転移者というのは、世界と世界を移動する際に、特別な力を神から授かることが多いからだという。
サラサの場合、一般人では使いこなせない人々を癒す光の魔法を行使することができるそうだ。
そんな彼女が、王太子殿下と親しくしているのは知っていた。けれど、それも彼女がまだこの世界の常識をまだ理解できていないからだと思っていた。
そのことを、確かに私はそのことをサラサに注意したりしたことはあったが、糾弾するようないい方をした覚えはない。
「あの、今、国には女王陛下はいらっしゃいません。それでもこれは決定事項、と認識してよろしいでしょうか」
私は、この事態の収拾を試みた。
いや、このあと女王陛下が戻ってくるまで、これをうやむやにしていたくない。火を見るのは明らか、逃げるが勝ちだ。なんとかして逃げたい。
そしてできるだけ、この大勢の人々の前で、この婚約破棄の決定者は王太子殿下だということを明確にしてしまいたかった。
今ここで王太子殿下が「決定ごとだ」といってしまえば、責任は全て彼のものとなる。苛烈な女王陛下からお叱りを受けるのは、王太子殿下とサラサ、そしてその取り巻きたちだろう。
──今は、今ここで私に非がないことをはっきりさせなければ。
そうでなければ、私を含め、お父さまやお母さま、可愛い双子の弟妹にまで累が及びかねないのだ。
私は、嫌な汗が背中を伝うのを感じながら、今か今かと王太子殿下の口が開かれるのを待つ。
「ああ、決定事項だ。女王陛下並びに王配殿下のいない今、国の裁量は私に委ねられているからな。私の王妃はサラサに、そして私の跡継ぎはサラサの子とする。その私の子を宿しているサラサを階段から突き落とした罪により、そなたをこの国から追放する。この国から早々に出て行くが良い」
──よし、言質はとった。
なにかあっても、責任は全て彼に取ってもらおう。
でも、まさか王太子殿下が婚約破棄までいい出す事態になっていただなんて。しかも孕ませ……いや、言葉が過ぎるか。そんな関係にまでなっていたとは知らなかった。
──なんて馬鹿なんだろう。
私は心の中で思う。
いくら実の息子とはいえ、あの「赤の女王」の決定事項を覆すなんて。
けれど、彼女(サラサ)がいくら希少な存在とはいえども彼女はもとは平民。いや、聖女と見いだされてから、確か伯爵家の養女に迎えられているはず。だったら家格の問題はクリアなのかもしれない。
そして次に、彼女はこの世界での教養はほとんどないといって良いレベルだった。常識的に考えて、今すぐ彼女を婚約者に据えるなど考えられるはずもない。
王太子妃に必要な、語学、淑女教育、社交能力、他国に至るまでの歴史の詰め込み……数えたらキリがないけれど、それを今から、おそらく十八かそこらから身につけようというのか。しかも身重の身で。
しかも、この国の国教は、結婚に際して女性に純潔性を求めるのだ。王族の結婚ともなれば、初夜の血のついたシーツが、翌朝恭しげに飾られるほど。
なのに、それすら覆している。
あの聖女は教会に保護されているのだろうけれど、その教義を足蹴にしているサラサをどこまでかばうのだろうか。
──そこまでの覚悟があっての婚約破棄騒動であれば、「真実の愛」とは見あげたものだと感嘆できる……のだけれど。
──この国の王太子は馬鹿だ。
彼を頼りに婚約者に名乗りをあげたサラサも、どこまでどういう状況下なのかわかっているのだろうか?
女王に打診をせず、不在のおりに、彼女が決めた婚約を勝手に破棄をする。これほど恐ろしい行為はそうそうないだろう。きっと王太子殿下のみでは飽き足らず、サラサ自身にも怒りの矛先が向くに違いない。
おかしなものだ。豊かな知識と実行力を併せ持ち、性格は苛烈で、「赤の女王」の二つ名で呼ばれる女王陛下。そのご子息が庶民の流行に無計画で乗って浮かれているのには、めまいさえ覚えた。
きっと女王陛下は烈火のごとく怒ることだろう。身内でありながらそれすら分からないのだろうか。いや、息子だからこそ、その立場に甘えている?
──さあて、どうしよう。
私は思案する。
彼の言質は取った。次は私の心の整理だ。
私は十歳の頃に婚約者として定められ、相手となったカイン殿下に、恋をしようと努力した。そして、それは次第に私の思考を染めてゆき、私は彼に恋をするようになった。
だから、彼の心変わりが決定的になった今、正直なところ、私は心から傷ついている。貴族令嬢としての矜持があるからこそ、ぐっと我慢をしてはいるものの、今この場で崩れ落ちて泣いてしまいたいほどの心情だ。恋をするよう仕向けた恋でも、それが破られれば、傷つくものなのだ。
それなのに、壇上の殿下とサラサは、そんな傷心の私を尻目にイチャイチャとじゃれ合っている。
それを見て、私は唇を噛んだ。目には涙が滲んできたのだろうか。彼らを眺める視界がぼやけてきている。さらに、身体を支える力が抜けて、床に直に座り込んでしまう。
ようやく、異常事態に固まっていた心と体に、感情が追いついてきたのだろう。
──泣きたい。辛い、逃げたい。誰かこれは現実じゃない、夢だといって。
でも、私を遠目にみる誰も、助けてはくれなかった。なぜならば、次期王太子妃となるものがどちらになるのか、判断しかねているのだろう。確実に王太子妃となるものに肩入れしたい。それまでは様子見をする。貴族とはそういうものだ。
ここにいる者たちは、その貴族の令息、令嬢たちなのだから。
私はぎゅっと唇を噛み、拳を握りしめる。
──さて、どうする?
辺りを見回すが、私は遠巻きにされて、味方になってくれそうな人は見当たらなかった。
──ここはひとまず退場して、状況をお父さまにご報告すべき?
泣いている場合じゃないわ。まずはお父さまに報告しないと。
そうしてようやく頭の整理が付く。
「アンネリーゼさま」
そう考えていた矢先、優しい声音と共に、コツコツと足音が近づいてきて、そっと真っ白い清潔そうなハンカチをて差し出された。私は俯いていたものを、はっとして顔を上げる。
「……エリアス、殿下?」
それは、カイン王太子殿下の弟君の第三王子殿下。この学園の後輩にあたる方であった。私のふたつ年下の方だ。
バウムガルデン王家には、カイン王太子殿下の他に、カール第二王子殿下、そして声をかけてくださったエリアス第三王子殿下がいる。ちなみに、カール第二王子殿下とエリアス第三王子殿下は双子の兄弟だ。
話をもとに戻そう。
私は、じっとエリアス殿下を見つめたあとに、差し出された一つの穢れもない真っ白なハンカチを見つめた。
「エリアス殿下、どうして……」
ここにいるのか、と問おうとすると、そっと唇にハンカチを押し当てられる。真っ白い清潔なハンカチに、私の涙のシミがついてしまう。
「女性がそんなきつく唇をかみしめたり、拳を握ってはいけませんよ。もしも唇が切れてしまったり、手の平に爪が食い込んで、玉の肌に傷が付いてしまったりしたら大変だ。そして、その涙はハンカチの中に隠してしまいましょう?」
誰もが私を遠巻きにしている中に、私に気を配ってくれる人がいたことに安堵した。再びじわり、と私の瞳に涙が浮く。
「ほら、ダメですよ。ここは人前ですから……」
そういって彼は、私を彼の背中の影に隠れるようにしてくれる。
──年下の十六歳の彼の背中はこんなに大きかったかしら?
私たちの間にはあまり接点はない。学園に入学する頃には、私はすでに王太子殿下の婚約者であったから、他の男性とは距離を置いていた。記憶に残っているのは、エリアス第三王子殿下が、彼の入学式のときに生徒代表として壇上で挨拶をするのを遠目で聞いたとき以来だ。そのときの彼は、まだ幼さの残る顔立ちをしていたはず。
そう記憶をたどっていると、大衆のざわめきの中からひときわ大きな声がした。私を取り巻く人混みに割れ目ができる。
そこから現れた人の姿を一目見て、気が緩んだ私の頬に、とうとう涙が伝った。
「アンヌ!」
アンヌ、それは私の愛称だ。家族以外にそれを使う人はいない。
「……お父さま!」
私は、一番の味方が来て、名指しされてからずっと硬かった表情が和らぐのを感じる。
お父さまは私の側に来る。すると、エリアス殿下がお父さまと位置を交代して、私を正面から優しく抱きしめてくださった。
「お父さま、お仕事中じゃ……?」
「子細をエリアス殿下にお聞きして、飛んできたよ。今は私の大切なアンヌの危機なんだ。なにを置いても君のもとへ駆けつけるのが父親として当然だ。なんでも酷い目に遭わされたんだって? 今はお前も動揺して落ち着いて判断もできないだろう。この場は辞退しよう、家に帰るんだ。いいな?」
「いいんですか?」
逆に私はお父さまに問う。するとお父さまはさも不思議そうに首を傾げた。
「どういうことだい?」
「私は王太子殿下から婚約破棄を命じられました。私たちの婚約は、女王陛下が直々にお決めになったもの。ただ婚約が解消して終わりになるとは思えません。私は私に落ち度があったとは思いません。けれど、関係者の私をかばえば、家にもご迷惑をかけてしまうかも……」
そう告げると、お父さまは首を横に振る。
「大丈夫。今はどう手をこまねいても女王陛下と王配殿下は揃っていらっしゃらない。だからまだ女王陛下はこの事態を知ってすらいないはず。だから手の打ちようはないんだ。な? まずは、家に帰って落ち着こう? それからこれからのことを考えればいい」
私はお父さまの言葉にコクン、と素直に頷いた。
嬉しかった。
だから、思わず子供の頃のように両手をお父さまに伸ばす。すると、お父さまは座り込んでしまっていた私を両手で支えながら起き上がらせてくれる。そして、私が立ち上がると優しく抱きしめてくれた。
お父さまの抱擁は温かかった。大きな背中がやっと温もりと安心をくれた。
私を窮地に陥れた弟君のエリアス殿下しか助けてくれない衆人の注目の中、もっとも頼りになる人のひとり、お父さまが駆けつけてくれたから。心からの安心を得ることができた。
しばらくの間、私たちが抱きしめ合っている間見守るように立っていらっしゃったエリアス殿下を私は見る。それと彼の貸してくださった真っ白いハンカチも。彼が貸してくださったそのハンカチは、涙で汚れてしまっていた。薄く施していた化粧の色も、ハンカチについてしまっている。
「殿下、このハンカチ……」
子供だとばかり思っていた彼は、まだ幼さが残る顔つきながらも穏やかで優しげな表情でにっこりと微笑んでくれた。
「大丈夫。それは使い捨ててしまってくれていいよ。それとね。この件、兄上の勝手な持論で進まないよう、私から母上にもきちんと伝えておく。だから、安心するといい」
そう約束して、にっこり笑ってくれた。
──結婚前に他の令嬢を孕ませるような方、こちらから願い下げなんですけど……。
ようやく気力が戻ってきて、心の内で思うが、さすがに口には出さなかった。
「それにしてもタイミングが良かったな」
「それはどういう?」
「この国の宰相である君のお父さまはね、ちょうどこの卒業式でご自身の部下とする文官にふさわしい人物を見定めにいらっしゃっていたんだ」
エリアス殿下とお父さまが目配せをし合う。
それが聞こえると、ざわっと辺りがざわめいた。きっと文官の職を欲しいと願っている子息たちだろう。
「こんな事態を良かったというのもなんだけれど、不幸中の幸いというところかな。騒ぎになってすぐ、私が呼んだんだよ。だから君を護りに来ていただけた。……だって、私より、やはりお父さまの方が頼りがいがあるだろう?」
最後のそのひと言に、少し寂しそうな陰りがあったのは気のせいだろうか? 確かに、エリアスさまはお優しいけれど頼りがいがあるかといわれると、ちょっと……という感じなのだけれど。
ともかく私は、一番の身内のお父さまの腕の中で、ほっとして脱力する。お父さまの腕に再びしがみつく形で倒れそうになってしまった。
「可哀想に、アンヌ……」
お父さまが、私を楽にしようと抱き上げようとする。
「バーデン卿、私が……」
そういいかけるエリアス殿下を、お父さまがきつい口調で制止する。
「殿下。娘の危機にお呼び下さったことは感謝いたします。……ですが、私は今のこの場で娘を傷つけた者の弟君に、娘の身を預ける気は毛頭はございません」
私はともかく、お父さまは王太子殿下おひとりだけではなく、王家全体に対して反感を覚えたらしい。
そうきつめにいうと、軽々と私を姫抱きに抱き上げてくれる。
「……お父さま……」
普段は優しいお父さま。けれど、その怖さも、この場では頼もしく感じて、安堵感を覚えた私は頭をお父さまの肩に預けて瞳を閉じた。
「くっ……」
エリアス殿下は、苦しげに唇を噛んで下を向いたけれど、なぜだろう。私は所詮顔見知りの上級生、そして、一貴族の娘。そしてたまたま、彼の兄の婚約者だった女というだけだというのに。
エリアス殿下の思惑は分からなかったけれど、お父さまは、王族への最低限の礼だけを執って、その場を辞することになった。私は抱き上げられたまま頭を垂れることしかできなかったけれど。
衆人の好奇の目からは、お父さまの大きな背中が守ってくれた。