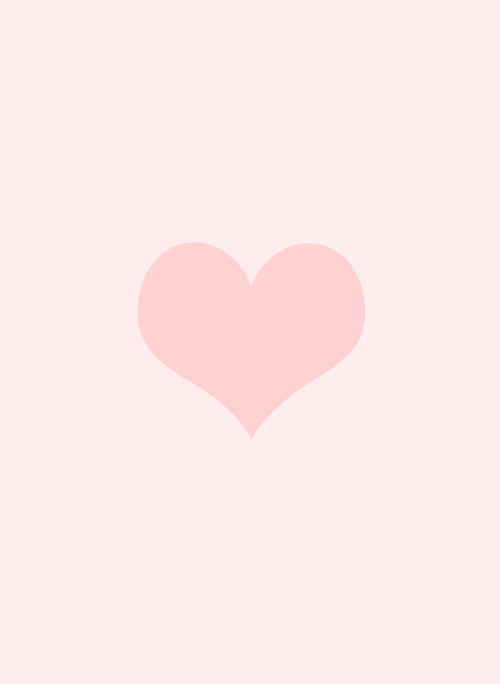時間は数日前に遡る。
日が経つのは早いもので、気づけば建国祭も終盤に差し掛かっていた。
建国祭らしい派手な夜会と催しの数々。市井ですらお祭り騒ぎ。それを隠れ蓑として反逆者たちの調査を行っているが、予め切り捨てるために用意していたと思われる何も知らない下っ端を捕らえただけで今のところ核心的な部分には辿り着けていない。
ルヴァルは夜空を眺めため息をつく。
「まるで嵐の前の静けさ、だな」
焼き尽くした魔物が湧いた沼地からは、結局何の痕跡も見つからなかった。おそらくノルディア側が仕掛けたのだろうが、どうやって任意の場所に沼地を作り出したのかわからないし、深追いしたところでノルディアが関与した証拠など出て来ないだろう。
建国祭として他国から来賓を招いている以上正当な理由なく催しの予定を遅らせるわけにはいかない。そんなわけで警備を強化した上で狩猟大会も予定通り開催するらしい。
「嫌な感じだ」
全身の皮膚がピリピリとささくれ立つような澱んだ気配にルヴァルは眉根を寄せ警戒する。
王城からやや離れた郊外であるこの地でさえ、地下を何かよくないモノが這うような気配を感じる。
その気配は日増しに色濃くなってなっているというのに、それに一切気づかず整備された野山で獣と追いかけっこに興じたいなどルヴァルには上位貴族の体面と思考が理解できない。
まぁ、アーサーがやると言えばそれまでだし、彼の無茶振りはいつものことなので理解する気もないのだが。
「……止められるんだろうか、今度は」
ルヴァルは手袋を外し、右手の甲に浮かぶ雪の結晶のような形をした痣を撫でる。
1回目の死の間際に神獣によって刻まれた契約印。それを見ていると否が応でも死んだ時の雪の冷たさと苦しい記憶を思い出す。
『リオは、嘘をついている」
エレナの秘密を聞いた時、ルヴァルはエレナに一つ密命を出した。
誰にも悟らせずリオレートが"嘘"をついていないか見破って欲しい、と。
それは1回目のエレナの人生でマリナがエレナの特異性に気づき、ノルディアの王太子に捕まってやらされたエレナにとっての"怖い事"だった。
ブラフが絶対に通じないどころか、一切魔法を使わず安全な場所から情報を抜かれる。それは情報戦において致命的で、バーレーが落とされた原因の一つと言っても過言ではない。
それをエレナに告げてしまえば、回帰前の人生でエレナの能力が国を危機に追いやったのだと彼女に知られてしまうことになる。
ようやく立ち上がったエレナにまた悲痛な思いをさせたくなくて、ルヴァルは詳しい事情を何一つエレナに話せなかった。
だというのに、エレナは察したように笑って望みを聞いてくれた。
そして彼女の耳が聞き取った音は、ルヴァルにとってあって欲しくない結果であった。
1回目の人生で、リオレートとエレナが直接的に関わる事はなかったと思う。あの時と状況が変わって来ている以上、もしかしたらまだノルディア側とリオレートが手を組んでいないのではないか?
そんな淡い期待は脆く崩れ、ルヴァルは決断をせねばならなかった。
リオレートがノルディア側と繋がっていると自分が把握していることを、まだ彼は知らない。
おそらくバーレーの人間ならリオレートが反逆の片棒を担いでいるなど疑う者はいないだろう。自分だって1回目の人生では背後から刺されるその瞬間まで気づかなかった。
その状況を逆手に取り、泳がせて、絡め取り、切り捨てる。
この国にとって脅威となり得る者は何人たりとも放置できない。たとえそれが、兄弟のように苦楽を共にした相手であったとしても。
「とっても悲しい音がする。それに、怖い顔」
「……レナ」
声をかけられて、初めてその存在に気づく。嫌な気配にばかり気を取られ、悪意のない彼女にはまるで気づかなかった。
ひょこっと顔を覗かせ危なっかしい足取りで屋根を伝って来たエレナは、
「見て、ルル! 私、今日は自分の足でここまで来られたわ」
ドヤ顔ですごい? と尋ねる。
「ああ、驚いた。どうやって登って来たんだ?」
「教えてもらった縄のかけ方実践してみたの
! リーファ監修の筋トレの効果かしら」
一番奥の窓から屋根に上がったのとエレナは得意げに説明し、ルヴァルの隣に腰を下ろし、ルヴァルの心音を聞く。
その音は苦しそうで、物悲しくて、泣きそうだった。
その音の響きに共感したエレナはトンっとルヴァルに身体を寄せる。
内心ではこんなにもたくさんの葛藤を抱えているのに、ルヴァルが全く表情を変えないものだから、余計胸が締め付けられる。
まるで、実家にいた時の自分のようだ。
「ねぇ、ルル。一曲歌はいかがかしら?」
それを癒せる方法をエレナはひとつしか知らない。
「ああ、聞きたい」
ルヴァルの返事を聞いて、エレナはゆっくり旋律を紡ぐ。
静かで、優しい、歌声が静まり返った夜空に響いた。
「なんて歌なんだ?」
「これはね"誰かの幸せ"を願う歌」
一曲歌い終わり、エレナはルヴァルの頬に手を伸ばす。
「ねぇ、ルル。あなたは強いヒトなのかもしれないけれど、楽しいや嬉しいだけじゃなくて、ルルの悲しいも苦しいも私に分けて欲しい」
ルヴァルを見つめる紫水晶の瞳は優しい色をしていて。
「ルルはいつも大切なモノを背負って誰かのために戦うでしょう? それなら私は、誰よりもあなたの幸せを願いたい」
あなたを愛しているから、一緒に背負いたいのとエレナは告げる。
「リオを切り捨てないで。彼はあなたにとってもバーレーにとっても必要なヒトよ」
あなたが自分の望みを言わないのなら、私が代わりにわがままを言うわとエレナは歌うようにそう告げる。
「だが、このままでは」
「もし、それが自分の意志ではどうにもできない事象によって、ルルを裏切らざるを得ないのだとしても? 今なお葛藤し、あなたと同じく運命に抗おうと、ルルやバーレーのためにひとりで必死で抵抗しているのだとしても?」
そこに情状酌量の余地はない? と問うエレナの声に、ルヴァルの青灰の瞳が見開かれる。
「私は"音"を聞き間違えたりしない。耳には自信があるの」
リオレートの体内で異なる魔力が爆ぜ、混ざり、澱む苦しくて痛い不協和音。何かがずっと彼を縛る。
その音の正体は"魅了"。術者が他者を支配する禁術だ。
「ノルディアの王太子は声を媒介に魅了を使うわ。踊っている時にかけられたから間違いない」
ダンスの時にカルマに引き寄せられ耳元で甘く囁かれたその声に脳が痺れ身体と心を支配されそうになった感覚を思い出しエレナは顔を顰める。
今思い出しても嫌な感覚だった。あの時はルヴァルの声を探すことで何故か発動しなかったが、カルマを相手にするならば魅了対策が必要だ。
「多分リオの場合は魅了だけじゃなくて、血の制約がかかっているんだと思う。それも何代にも渡る呪術が」
「リオに呪術が? そんなもの、一体いつ?」
「リオは……フィリアの生き残り、それもノーラの血縁なんじゃないかと思う」
「フィリアの?」
驚くルヴァルにエレナは頷き、血縁者は魔法の音が似るのだとエレナは説明する。
「もし、その昔ノーラがノルディアの王に傷つけられたあの時にすでに呪いを埋め込まれていて、血を介して現在も受け継がれているのだとしたら、それを解除しない限りリオはノルディアの言いなりだわ」
小さな国とはいえ、大国であるノルディアに支援を求められるほど高度な魔法が発展していた魔法技術国家フィリア。
だが、王族が内側から支配されていたのだとしたら、フィリアはなす術もなかっただろう。
「リオは子どもの頃に父が戦争孤児として連れ帰って来た。うちに来た時は随分酷い怪我をしていたし、バーレーに来る前の情報は本人が話さないから知らないんだが……そうか。フィリア、か」
ルヴァルは腑に落ちたようにそうつぶやく。
故郷を失い、多くの犠牲と思いを託されて生き残ったリオレートの悪夢はきっとまだ続いている。
「バーレーは特区。領地での犯罪は特別自治法によって領主の裁量でその量刑を決めることができる」
これでもたくさん勉強したのよとエレナは笑う。
「それに一番大きな権力に多大な貸しがあるんだから、関与が露呈していない今なら片目くらいは瞑ってくれるはずよ。国を転覆させようとする黒幕を捉えるために、わざと情報を流させた、と」
だから、まだ間に合うとエレナはルヴァルにそう告げる。
「犯罪の隠蔽はダメ絶対、じゃなかったのか?」
エレナの描く筋書きに口角を上げて楽しそうにルヴァルは尋ねる。
「私、いい子はやめたの。それにバレなければいいんでしょ?」
辻褄さえ合っていれば問題ないわといつかのルヴァルの言葉を持ち出してエレナは応戦する。
「ああ、そうだな」
ルヴァルは手を伸ばし、エレナの髪をぐしゃぐしゃとやや乱暴な動作で撫でる。
「戦えるか? レナ」
「音の魔法において、私は誰にも負けない」
勝ち気な紫水晶の瞳に、ルヴァルは頼もしい限りだと頷いて、
「全部片して全員で帰るぞ。バーレーに」
方針を告げる。
そう言ったルヴァルの声には一切の迷いはなくなっていた。
日が経つのは早いもので、気づけば建国祭も終盤に差し掛かっていた。
建国祭らしい派手な夜会と催しの数々。市井ですらお祭り騒ぎ。それを隠れ蓑として反逆者たちの調査を行っているが、予め切り捨てるために用意していたと思われる何も知らない下っ端を捕らえただけで今のところ核心的な部分には辿り着けていない。
ルヴァルは夜空を眺めため息をつく。
「まるで嵐の前の静けさ、だな」
焼き尽くした魔物が湧いた沼地からは、結局何の痕跡も見つからなかった。おそらくノルディア側が仕掛けたのだろうが、どうやって任意の場所に沼地を作り出したのかわからないし、深追いしたところでノルディアが関与した証拠など出て来ないだろう。
建国祭として他国から来賓を招いている以上正当な理由なく催しの予定を遅らせるわけにはいかない。そんなわけで警備を強化した上で狩猟大会も予定通り開催するらしい。
「嫌な感じだ」
全身の皮膚がピリピリとささくれ立つような澱んだ気配にルヴァルは眉根を寄せ警戒する。
王城からやや離れた郊外であるこの地でさえ、地下を何かよくないモノが這うような気配を感じる。
その気配は日増しに色濃くなってなっているというのに、それに一切気づかず整備された野山で獣と追いかけっこに興じたいなどルヴァルには上位貴族の体面と思考が理解できない。
まぁ、アーサーがやると言えばそれまでだし、彼の無茶振りはいつものことなので理解する気もないのだが。
「……止められるんだろうか、今度は」
ルヴァルは手袋を外し、右手の甲に浮かぶ雪の結晶のような形をした痣を撫でる。
1回目の死の間際に神獣によって刻まれた契約印。それを見ていると否が応でも死んだ時の雪の冷たさと苦しい記憶を思い出す。
『リオは、嘘をついている」
エレナの秘密を聞いた時、ルヴァルはエレナに一つ密命を出した。
誰にも悟らせずリオレートが"嘘"をついていないか見破って欲しい、と。
それは1回目のエレナの人生でマリナがエレナの特異性に気づき、ノルディアの王太子に捕まってやらされたエレナにとっての"怖い事"だった。
ブラフが絶対に通じないどころか、一切魔法を使わず安全な場所から情報を抜かれる。それは情報戦において致命的で、バーレーが落とされた原因の一つと言っても過言ではない。
それをエレナに告げてしまえば、回帰前の人生でエレナの能力が国を危機に追いやったのだと彼女に知られてしまうことになる。
ようやく立ち上がったエレナにまた悲痛な思いをさせたくなくて、ルヴァルは詳しい事情を何一つエレナに話せなかった。
だというのに、エレナは察したように笑って望みを聞いてくれた。
そして彼女の耳が聞き取った音は、ルヴァルにとってあって欲しくない結果であった。
1回目の人生で、リオレートとエレナが直接的に関わる事はなかったと思う。あの時と状況が変わって来ている以上、もしかしたらまだノルディア側とリオレートが手を組んでいないのではないか?
そんな淡い期待は脆く崩れ、ルヴァルは決断をせねばならなかった。
リオレートがノルディア側と繋がっていると自分が把握していることを、まだ彼は知らない。
おそらくバーレーの人間ならリオレートが反逆の片棒を担いでいるなど疑う者はいないだろう。自分だって1回目の人生では背後から刺されるその瞬間まで気づかなかった。
その状況を逆手に取り、泳がせて、絡め取り、切り捨てる。
この国にとって脅威となり得る者は何人たりとも放置できない。たとえそれが、兄弟のように苦楽を共にした相手であったとしても。
「とっても悲しい音がする。それに、怖い顔」
「……レナ」
声をかけられて、初めてその存在に気づく。嫌な気配にばかり気を取られ、悪意のない彼女にはまるで気づかなかった。
ひょこっと顔を覗かせ危なっかしい足取りで屋根を伝って来たエレナは、
「見て、ルル! 私、今日は自分の足でここまで来られたわ」
ドヤ顔ですごい? と尋ねる。
「ああ、驚いた。どうやって登って来たんだ?」
「教えてもらった縄のかけ方実践してみたの
! リーファ監修の筋トレの効果かしら」
一番奥の窓から屋根に上がったのとエレナは得意げに説明し、ルヴァルの隣に腰を下ろし、ルヴァルの心音を聞く。
その音は苦しそうで、物悲しくて、泣きそうだった。
その音の響きに共感したエレナはトンっとルヴァルに身体を寄せる。
内心ではこんなにもたくさんの葛藤を抱えているのに、ルヴァルが全く表情を変えないものだから、余計胸が締め付けられる。
まるで、実家にいた時の自分のようだ。
「ねぇ、ルル。一曲歌はいかがかしら?」
それを癒せる方法をエレナはひとつしか知らない。
「ああ、聞きたい」
ルヴァルの返事を聞いて、エレナはゆっくり旋律を紡ぐ。
静かで、優しい、歌声が静まり返った夜空に響いた。
「なんて歌なんだ?」
「これはね"誰かの幸せ"を願う歌」
一曲歌い終わり、エレナはルヴァルの頬に手を伸ばす。
「ねぇ、ルル。あなたは強いヒトなのかもしれないけれど、楽しいや嬉しいだけじゃなくて、ルルの悲しいも苦しいも私に分けて欲しい」
ルヴァルを見つめる紫水晶の瞳は優しい色をしていて。
「ルルはいつも大切なモノを背負って誰かのために戦うでしょう? それなら私は、誰よりもあなたの幸せを願いたい」
あなたを愛しているから、一緒に背負いたいのとエレナは告げる。
「リオを切り捨てないで。彼はあなたにとってもバーレーにとっても必要なヒトよ」
あなたが自分の望みを言わないのなら、私が代わりにわがままを言うわとエレナは歌うようにそう告げる。
「だが、このままでは」
「もし、それが自分の意志ではどうにもできない事象によって、ルルを裏切らざるを得ないのだとしても? 今なお葛藤し、あなたと同じく運命に抗おうと、ルルやバーレーのためにひとりで必死で抵抗しているのだとしても?」
そこに情状酌量の余地はない? と問うエレナの声に、ルヴァルの青灰の瞳が見開かれる。
「私は"音"を聞き間違えたりしない。耳には自信があるの」
リオレートの体内で異なる魔力が爆ぜ、混ざり、澱む苦しくて痛い不協和音。何かがずっと彼を縛る。
その音の正体は"魅了"。術者が他者を支配する禁術だ。
「ノルディアの王太子は声を媒介に魅了を使うわ。踊っている時にかけられたから間違いない」
ダンスの時にカルマに引き寄せられ耳元で甘く囁かれたその声に脳が痺れ身体と心を支配されそうになった感覚を思い出しエレナは顔を顰める。
今思い出しても嫌な感覚だった。あの時はルヴァルの声を探すことで何故か発動しなかったが、カルマを相手にするならば魅了対策が必要だ。
「多分リオの場合は魅了だけじゃなくて、血の制約がかかっているんだと思う。それも何代にも渡る呪術が」
「リオに呪術が? そんなもの、一体いつ?」
「リオは……フィリアの生き残り、それもノーラの血縁なんじゃないかと思う」
「フィリアの?」
驚くルヴァルにエレナは頷き、血縁者は魔法の音が似るのだとエレナは説明する。
「もし、その昔ノーラがノルディアの王に傷つけられたあの時にすでに呪いを埋め込まれていて、血を介して現在も受け継がれているのだとしたら、それを解除しない限りリオはノルディアの言いなりだわ」
小さな国とはいえ、大国であるノルディアに支援を求められるほど高度な魔法が発展していた魔法技術国家フィリア。
だが、王族が内側から支配されていたのだとしたら、フィリアはなす術もなかっただろう。
「リオは子どもの頃に父が戦争孤児として連れ帰って来た。うちに来た時は随分酷い怪我をしていたし、バーレーに来る前の情報は本人が話さないから知らないんだが……そうか。フィリア、か」
ルヴァルは腑に落ちたようにそうつぶやく。
故郷を失い、多くの犠牲と思いを託されて生き残ったリオレートの悪夢はきっとまだ続いている。
「バーレーは特区。領地での犯罪は特別自治法によって領主の裁量でその量刑を決めることができる」
これでもたくさん勉強したのよとエレナは笑う。
「それに一番大きな権力に多大な貸しがあるんだから、関与が露呈していない今なら片目くらいは瞑ってくれるはずよ。国を転覆させようとする黒幕を捉えるために、わざと情報を流させた、と」
だから、まだ間に合うとエレナはルヴァルにそう告げる。
「犯罪の隠蔽はダメ絶対、じゃなかったのか?」
エレナの描く筋書きに口角を上げて楽しそうにルヴァルは尋ねる。
「私、いい子はやめたの。それにバレなければいいんでしょ?」
辻褄さえ合っていれば問題ないわといつかのルヴァルの言葉を持ち出してエレナは応戦する。
「ああ、そうだな」
ルヴァルは手を伸ばし、エレナの髪をぐしゃぐしゃとやや乱暴な動作で撫でる。
「戦えるか? レナ」
「音の魔法において、私は誰にも負けない」
勝ち気な紫水晶の瞳に、ルヴァルは頼もしい限りだと頷いて、
「全部片して全員で帰るぞ。バーレーに」
方針を告げる。
そう言ったルヴァルの声には一切の迷いはなくなっていた。