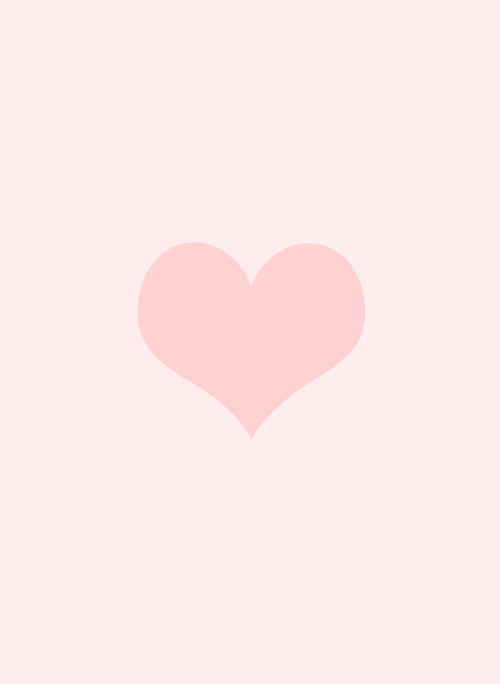「うぅ、迷った」
困ったと、泣きそうな声でつぶやいたエレナは、一般公開されている庭園で1人うずくまる。
誰かに道を尋ねようにも先日の騒動の関係もあってか庭園に人はほとんどおらず、エレナが思っていた以上に城内の敷地はずっと広かった。
子どもの時分、母に連れられて王城を出入りしていた頃の記憶だけを頼りにここまで来たのだけれど、年月が経過したそれはずいぶんと曖昧で朧気で。
正直エレナは今自分がどこにいるのかさえわからない。
「お屋敷で素直にルルの帰りを待てば良かった」
なぜ行けると思ったんだ、とエレナは後悔する。
城内は広い。そして仮にルヴァルが出向いたであろう王城付近に辿り着けたとしても身分証すら持っていない状態でルヴァルに取り継いでもらえるわけもない。
冷静になれば分かる事に思い至らないほど、目が覚めた時のエレナはただルヴァルに会いたいという気持ちしかなかったのだ。
「しかも書き置きすらしてない。絶対、怒られる」
今更かもと思いながら手紙をくくりつけた魔馬に屋敷に戻るよう頼んだ。
とても賢い子でエレナの言葉を理解したらしく、優しく身体を擦り付けたあと静かに屋敷の方向に歩いていった。
「ルルに会えないどころかお屋敷に戻れなかったら、どうしよう」
いい歳をして完全なる迷子。
こういう場合に自分が取るべき行動って何だっけ? とエレナはぼんやり考える。
そしてふとこの城内の敷地でルヴァルに出会った時の事を思い出す。
あの時の自分も迷子をやっていて。ルヴァルに助けてもらったのだ。
「そういえば、あれから10年……ね」
とても短い時間の関わりを、きっとルヴァルは覚えてなどいないだろう。エレナだってあの時の黒髪の少年がルヴァルだと気づいたのはつい最近の事なのだ。
瞳の色も髪色も変えて一人王都で暮らさなければならなかった少年は、今では辺境伯として国の防衛最前線を支える立派な領主になっているというのに。
「私、10年じゃ絶世の淑女にはなれなかったな」
絶対謝らせるだなんて大口を叩いた割に、未だそれになれていない自分。
だから、"これから"が欲しいとエレナは思う。
「絶世の淑女になりたいな」
10年という時間の経過。
約束とも言えないそれを果たすことはできていないけれど、もし待ってもらえるのなら少しでもそんな自分に近づきたい。
彼の隣に立つために、俯いている時間すら惜しい。
「よし、反省おしまい」
状況を改善しないととエレナは屋敷に戻る方法を考える。
『迷子になった時は歌を歌えばいいのよ』
不意に母の言葉が蘇る。
そうだ、城内の庭園でルヴァルとはぐれてしまった時も歌を歌っていたのだったとエレナは思い出す。
「"迷子の時は歌を歌うの。そうしたら、きっと誰かが見つけてくれるから"」
そして、あの時はルヴァルのために歌ったのだ。彼が怪我をしないように、と祈りと魔法を込めて。
今の自分では魔法を歌に込める事はできないが。
「〜〜〜♪ーーー♪」
願うことはできる。
エレナはルヴァルを想いながら、あの日と同じ旋律を紡ぐ。
回帰したルヴァルが今世では彼が願う未来に辿り着く事を祈って。
一曲歌い終わったエレナの頭上に影ができる。
「やっと見つけた」
「……ルル」
会いたい、と願った人が目の前にいることに驚いてエレナは紫水晶の瞳を瞬かせる。
「大したもんだ。ウチの連中を撒くなんて」
楽しげに口角を上げたルヴァルは、エレナに手を伸ばしいつもみたいに少し乱暴な動作で髪をくしゃくしゃと撫でる。
「どう、して?」
どうしてここにルヴァルがいるんだろうと不思議そうに見上げてくる紫水晶の瞳をルヴァルは愛おしそうに覗き込む。
「この辺りでエレナが歌っている気がした」
ルヴァル自身にも何故ここにエレナがいると分かったのか上手く説明できない。
ただ、エレナに呼ばれたような気がしたのだ。
「歌、聞こえたの?」
びっくりしたように尋ねるエレナに首を振り、
「強いて言えば、レナに共鳴したのかもしれない」
だから迎えに来たと告げる。
一度目の生で神獣と契約を交わした際に言われた"共鳴の力"。
エレナを妻として迎えた時には全く分からなかったソレ。
だが、時を重ねエレナが信頼を寄せてくれるようになるにつれ、時折エレナの感情に共鳴するようになった。
エレナが悲しいと思えば、深く心に突き刺さり、楽しいと思えばルヴァル自身も嬉しくなる。それはまるで自分の感情のように激しくルヴァルを揺さぶった。
そして、それが強く感じ取れた時にはエレナの居場所さえも把握できた。
それは言葉にできない、だがエレナとルヴァルの間に確かに存在する絆のようなモノだった。
「帰るか。一緒に」
そう言って伸ばされたルヴァルの手にエレナは視線を落とす。
当たり前のように、彼は何度だって手を差し伸べてくれる。
だけど、それが"当たり前の事"ではないとエレナは知っている。
「……ごめん、なさい」
実家では誰かに気遣ってもらうことなど全くなかった。
この世界のどこにも自分の居場所なんてなくて、消えてなくなりたいと思った事もある。
だけど、今は。
「勝手に屋敷を抜け出して、しかも迷子になって、いっぱい迷惑かけてごめんなさい!」
エレナはルヴァルの腕に飛び込んで、
「迎えに来てくれてありがとう」
この居心地の良い人の隣を誰にも譲りたくないと強く願う。
「何だ。どこか目的地があるのかと思ってたんだが、迷子かよ」
泣き出したエレナの背をトントンと叩きながらルヴァルは可笑しそうに笑う。
「だって、起きたらルルがお屋敷にいないからぁ〜」
置いていかれたと思ったんだものとエレナは抗議の声をあげる。
「面会謝絶喰らってたんだよ」
「なんでぇ〜〜?」
「俺が聞きてぇわ」
ぐずぐずと泣くエレナに泣き虫と揶揄うように言ったルヴァルは、
「まぁ、でもリーファはすっげぇ心配してたから、あとで怒られろよ」
「……一緒に怒られてくれる?」
ナイフ飛んで来ても避けられる気がしないと小さな声でエレナはそう返す。
「安心しろ。既にナイフ投げつけられた後だ」
「安心ってどこがぁ?」
安心できる要素が見当たらないというエレナの黒髪をゆっくり撫でて、
「リーファはエレナに手をあげるヤツじゃないだろ」
と問いかける。
「そんな人、バーレーにはいないわ」
そう、実家とは違うのだ。
バーレーでは理不尽に振り下ろされる暴力などない、とエレナは知っている。
「じゃあ安心して怒られとけ」
一緒に怒られてやると言ったルヴァルの腕の中で、泣き止んだエレナはクスクスと笑う。
きっと、幸せとはこんな何気ない日常の名前なのだろうとエレナは思う。
母亡きあとの実家にいた時には、決して得られなかった、幸せ。
これを失うのは、耐えられない。けれど、後悔もしたくない。
勇気を出すなら、今だろう。
「ルル」
エレナは少し身体を離し、まっすぐ青灰の瞳を見ながらその名を呼ぶ。
「私、バーレーに帰りたい。誰一人欠けずに、みんなと一緒に」
見上げてくる紫水晶の瞳がはっきりと自分の意思を示す。
「ルルの憂いは私が払う。私は、もう二度と降りかかる理不尽に負けない」
ソフィアに魔力回路再生治療を施してもらっている最中のまだ未完全な自分の身体。
だけど、これから起こる事と戦うための方法は知っている。
「だから、私をあなたの一番側に置いて欲しい」
名目上の妻ではなく、信頼できる相手として。
背筋を凛と伸ばし、胸に手を当てそう宣言するエレナ。
そんなエレナの姿にルヴァルは思わず息を呑む。
そこには尊厳を奪われ、理不尽に虐げられて自信を失っていた頃の面影など微塵もなく、堂々と自身の誇りを賭けて立ち向かう美しい淑女の姿があった。
「……レナ」
ルヴァルが口を開くより早く、エレナはそれを遮って言葉を重ねる。
「もう後悔したくないから、伝えておくね! 私、ルルが好き。大好き……なの」
その声は少し震えていて。
「ルルが私に"妻"としての役割を求めてないのは分かってる。ルルが目的を遂げて、いつか本当にこの椅子に相応しい人が現れたら、私は出て行かなきゃいけないんでしょう?」
今にも泣きそうなのに、言葉にしなければと強い意思を持っていて。
「私はバーレーのみんなみたいに強くはない。だけど、私はいつかルルの本当のお嫁さんになりたいの! 絶世の淑女……にはまだなれてないけど。でも、これから頑張るから」
猶予期間を貰えないでしょうか? とエレナは顔を紅くしながらルヴァルにそう問いかけた。
全部言いたい事は言い切った。あとはルヴァルの答えを待つだけだ。
逃げ出したくなる衝動を抑えて、エレナはじっとその時を待つ。
そっとルヴァルの指が伸びて来て、割れ物に触るかのように優しくエレナの頬に触れる。
「……ルル?」
「……っとに、もう。全部先に言いやがって。俺の立つ瀬がねぇじゃねぇか」
そう言ったルヴァルは盛大にため息をつく。
花束は預けて来てしまったし、宝石なんて持ち歩いていない。
最も、こんな風に自分の全部を賭けてプロポーズされた後では、どう足掻いても格好なんてつけようがない。
「無理。猶予なんかやらねぇ」
言葉少なくそう言ったルヴァルは、エレナの頭を軽くポンと叩く。
「へ? あの、ルル?」
「レナはもう立派なバーレーの女主人だろうが」
だから勝手に出ていく事は許さないとルヴァルははっきりそう告げる。
傍若無人なその物言いは、彼の為人を知らない人間が聞けば顔を顰めるかもしれない。だが、ルヴァルが何を告げたいのか今のエレナには理解できる。
"エレナの居場所は、自分の隣である"と。
"猶予など必要なく、妻であり立派な淑女だ"と。
隣に居ても良いのだと理解して、エレナはほっとしたような安堵の表情を浮かべる。そんなエレナを見て、今まで言葉にしなかったことでどれほど彼女を不安にさせたのかとルヴァルは不甲斐ない自分に舌打ちしたくなった。
『態度でわかるだろうなんて、傲慢すぎる』
とアーサーに言われた言葉が実感を伴って身に染みる。非常に不本意ではあるが、彼の助言は正しかったようだ。
「俺は北部を預かる要塞都市バーレーの頭で、国に繋がれた番犬だ」
エレナから少し離れたルヴァルは帯刀していた剣を手に取り鞘に納めたまま、エレナにそれを見せる。
「代々の辺境伯がそうであったように、国に安寧がもたらされるまで、俺はこの剣を取り戦い続ける」
そういって国の防衛最前線に立ち続けることを宣言するルヴァル。
「この手がどれだけ血に汚れても。誰に後ろ指を差されても。俺は、俺が信じ、俺が守ると決めたモノのために剣を取る。辺境伯としての名を継いだ時、代々受け継がれるこの剣にそう誓った」
エレナはその重たい剣をじっと眺め静かに頷く。
それはルヴァルにとって何より重たい誓いであり、"ルヴァルの誇り"なのだろう。
「この剣に誓う」
ルヴァルはエレナに傅くと、鞘から剣を抜き地面に突き立てる。
「俺が生涯妻とし、愛するのは"エレナ・アルヴィン"ただ一人だ」
真っ直ぐ、短い、誇りを賭けた誓い。
その言葉を耳で拾ったエレナは紫水晶の瞳を瞬かせる。
「レナ。何かあれば俺を呼べ。どこにいても必ず駆けつける」
だから、何があってもそれまで生き延びることを諦めるなとルヴァルはエレナに約束を乞う。
ルヴァルの言葉に嘘偽りなどなく、その声の響きは何より信頼できる"愛情"の形で。
それを受け取ったエレナの瞳から大粒の涙が落ち頬を濡らす。
「また泣く」
少し呆れたような声でそう言ったルヴァルは剣を鞘に納めて立ち上がり、エレナの涙を指先で拭う。
「だって、ルルが泣かすような事をするから!」
こんな温かな気持ちは知らなかった。
誰かを想い、そして気持ちを返されるなんて、奇跡のようで。
こんなに幸せでいいんだろうかと少し怖くもなる。
「レナ、返事は」
だけど、失くすことが怖いなら、手放さなければいいだけの話だ。
「……はい」
ルヴァルの手を取ったエレナは青灰の瞳を見ながら、
「なら私はこれから先、ルルのためにだけ歌う」
歌姫として、最大限の誇りと最愛を誓う。
「それは贅沢だな」
エレナをふわりと抱え上げ、彼女の瞳を覗き込んだルヴァルは、
「もう、逃げるなよ」
そう言ってエレナに優しく口付けた。
困ったと、泣きそうな声でつぶやいたエレナは、一般公開されている庭園で1人うずくまる。
誰かに道を尋ねようにも先日の騒動の関係もあってか庭園に人はほとんどおらず、エレナが思っていた以上に城内の敷地はずっと広かった。
子どもの時分、母に連れられて王城を出入りしていた頃の記憶だけを頼りにここまで来たのだけれど、年月が経過したそれはずいぶんと曖昧で朧気で。
正直エレナは今自分がどこにいるのかさえわからない。
「お屋敷で素直にルルの帰りを待てば良かった」
なぜ行けると思ったんだ、とエレナは後悔する。
城内は広い。そして仮にルヴァルが出向いたであろう王城付近に辿り着けたとしても身分証すら持っていない状態でルヴァルに取り継いでもらえるわけもない。
冷静になれば分かる事に思い至らないほど、目が覚めた時のエレナはただルヴァルに会いたいという気持ちしかなかったのだ。
「しかも書き置きすらしてない。絶対、怒られる」
今更かもと思いながら手紙をくくりつけた魔馬に屋敷に戻るよう頼んだ。
とても賢い子でエレナの言葉を理解したらしく、優しく身体を擦り付けたあと静かに屋敷の方向に歩いていった。
「ルルに会えないどころかお屋敷に戻れなかったら、どうしよう」
いい歳をして完全なる迷子。
こういう場合に自分が取るべき行動って何だっけ? とエレナはぼんやり考える。
そしてふとこの城内の敷地でルヴァルに出会った時の事を思い出す。
あの時の自分も迷子をやっていて。ルヴァルに助けてもらったのだ。
「そういえば、あれから10年……ね」
とても短い時間の関わりを、きっとルヴァルは覚えてなどいないだろう。エレナだってあの時の黒髪の少年がルヴァルだと気づいたのはつい最近の事なのだ。
瞳の色も髪色も変えて一人王都で暮らさなければならなかった少年は、今では辺境伯として国の防衛最前線を支える立派な領主になっているというのに。
「私、10年じゃ絶世の淑女にはなれなかったな」
絶対謝らせるだなんて大口を叩いた割に、未だそれになれていない自分。
だから、"これから"が欲しいとエレナは思う。
「絶世の淑女になりたいな」
10年という時間の経過。
約束とも言えないそれを果たすことはできていないけれど、もし待ってもらえるのなら少しでもそんな自分に近づきたい。
彼の隣に立つために、俯いている時間すら惜しい。
「よし、反省おしまい」
状況を改善しないととエレナは屋敷に戻る方法を考える。
『迷子になった時は歌を歌えばいいのよ』
不意に母の言葉が蘇る。
そうだ、城内の庭園でルヴァルとはぐれてしまった時も歌を歌っていたのだったとエレナは思い出す。
「"迷子の時は歌を歌うの。そうしたら、きっと誰かが見つけてくれるから"」
そして、あの時はルヴァルのために歌ったのだ。彼が怪我をしないように、と祈りと魔法を込めて。
今の自分では魔法を歌に込める事はできないが。
「〜〜〜♪ーーー♪」
願うことはできる。
エレナはルヴァルを想いながら、あの日と同じ旋律を紡ぐ。
回帰したルヴァルが今世では彼が願う未来に辿り着く事を祈って。
一曲歌い終わったエレナの頭上に影ができる。
「やっと見つけた」
「……ルル」
会いたい、と願った人が目の前にいることに驚いてエレナは紫水晶の瞳を瞬かせる。
「大したもんだ。ウチの連中を撒くなんて」
楽しげに口角を上げたルヴァルは、エレナに手を伸ばしいつもみたいに少し乱暴な動作で髪をくしゃくしゃと撫でる。
「どう、して?」
どうしてここにルヴァルがいるんだろうと不思議そうに見上げてくる紫水晶の瞳をルヴァルは愛おしそうに覗き込む。
「この辺りでエレナが歌っている気がした」
ルヴァル自身にも何故ここにエレナがいると分かったのか上手く説明できない。
ただ、エレナに呼ばれたような気がしたのだ。
「歌、聞こえたの?」
びっくりしたように尋ねるエレナに首を振り、
「強いて言えば、レナに共鳴したのかもしれない」
だから迎えに来たと告げる。
一度目の生で神獣と契約を交わした際に言われた"共鳴の力"。
エレナを妻として迎えた時には全く分からなかったソレ。
だが、時を重ねエレナが信頼を寄せてくれるようになるにつれ、時折エレナの感情に共鳴するようになった。
エレナが悲しいと思えば、深く心に突き刺さり、楽しいと思えばルヴァル自身も嬉しくなる。それはまるで自分の感情のように激しくルヴァルを揺さぶった。
そして、それが強く感じ取れた時にはエレナの居場所さえも把握できた。
それは言葉にできない、だがエレナとルヴァルの間に確かに存在する絆のようなモノだった。
「帰るか。一緒に」
そう言って伸ばされたルヴァルの手にエレナは視線を落とす。
当たり前のように、彼は何度だって手を差し伸べてくれる。
だけど、それが"当たり前の事"ではないとエレナは知っている。
「……ごめん、なさい」
実家では誰かに気遣ってもらうことなど全くなかった。
この世界のどこにも自分の居場所なんてなくて、消えてなくなりたいと思った事もある。
だけど、今は。
「勝手に屋敷を抜け出して、しかも迷子になって、いっぱい迷惑かけてごめんなさい!」
エレナはルヴァルの腕に飛び込んで、
「迎えに来てくれてありがとう」
この居心地の良い人の隣を誰にも譲りたくないと強く願う。
「何だ。どこか目的地があるのかと思ってたんだが、迷子かよ」
泣き出したエレナの背をトントンと叩きながらルヴァルは可笑しそうに笑う。
「だって、起きたらルルがお屋敷にいないからぁ〜」
置いていかれたと思ったんだものとエレナは抗議の声をあげる。
「面会謝絶喰らってたんだよ」
「なんでぇ〜〜?」
「俺が聞きてぇわ」
ぐずぐずと泣くエレナに泣き虫と揶揄うように言ったルヴァルは、
「まぁ、でもリーファはすっげぇ心配してたから、あとで怒られろよ」
「……一緒に怒られてくれる?」
ナイフ飛んで来ても避けられる気がしないと小さな声でエレナはそう返す。
「安心しろ。既にナイフ投げつけられた後だ」
「安心ってどこがぁ?」
安心できる要素が見当たらないというエレナの黒髪をゆっくり撫でて、
「リーファはエレナに手をあげるヤツじゃないだろ」
と問いかける。
「そんな人、バーレーにはいないわ」
そう、実家とは違うのだ。
バーレーでは理不尽に振り下ろされる暴力などない、とエレナは知っている。
「じゃあ安心して怒られとけ」
一緒に怒られてやると言ったルヴァルの腕の中で、泣き止んだエレナはクスクスと笑う。
きっと、幸せとはこんな何気ない日常の名前なのだろうとエレナは思う。
母亡きあとの実家にいた時には、決して得られなかった、幸せ。
これを失うのは、耐えられない。けれど、後悔もしたくない。
勇気を出すなら、今だろう。
「ルル」
エレナは少し身体を離し、まっすぐ青灰の瞳を見ながらその名を呼ぶ。
「私、バーレーに帰りたい。誰一人欠けずに、みんなと一緒に」
見上げてくる紫水晶の瞳がはっきりと自分の意思を示す。
「ルルの憂いは私が払う。私は、もう二度と降りかかる理不尽に負けない」
ソフィアに魔力回路再生治療を施してもらっている最中のまだ未完全な自分の身体。
だけど、これから起こる事と戦うための方法は知っている。
「だから、私をあなたの一番側に置いて欲しい」
名目上の妻ではなく、信頼できる相手として。
背筋を凛と伸ばし、胸に手を当てそう宣言するエレナ。
そんなエレナの姿にルヴァルは思わず息を呑む。
そこには尊厳を奪われ、理不尽に虐げられて自信を失っていた頃の面影など微塵もなく、堂々と自身の誇りを賭けて立ち向かう美しい淑女の姿があった。
「……レナ」
ルヴァルが口を開くより早く、エレナはそれを遮って言葉を重ねる。
「もう後悔したくないから、伝えておくね! 私、ルルが好き。大好き……なの」
その声は少し震えていて。
「ルルが私に"妻"としての役割を求めてないのは分かってる。ルルが目的を遂げて、いつか本当にこの椅子に相応しい人が現れたら、私は出て行かなきゃいけないんでしょう?」
今にも泣きそうなのに、言葉にしなければと強い意思を持っていて。
「私はバーレーのみんなみたいに強くはない。だけど、私はいつかルルの本当のお嫁さんになりたいの! 絶世の淑女……にはまだなれてないけど。でも、これから頑張るから」
猶予期間を貰えないでしょうか? とエレナは顔を紅くしながらルヴァルにそう問いかけた。
全部言いたい事は言い切った。あとはルヴァルの答えを待つだけだ。
逃げ出したくなる衝動を抑えて、エレナはじっとその時を待つ。
そっとルヴァルの指が伸びて来て、割れ物に触るかのように優しくエレナの頬に触れる。
「……ルル?」
「……っとに、もう。全部先に言いやがって。俺の立つ瀬がねぇじゃねぇか」
そう言ったルヴァルは盛大にため息をつく。
花束は預けて来てしまったし、宝石なんて持ち歩いていない。
最も、こんな風に自分の全部を賭けてプロポーズされた後では、どう足掻いても格好なんてつけようがない。
「無理。猶予なんかやらねぇ」
言葉少なくそう言ったルヴァルは、エレナの頭を軽くポンと叩く。
「へ? あの、ルル?」
「レナはもう立派なバーレーの女主人だろうが」
だから勝手に出ていく事は許さないとルヴァルははっきりそう告げる。
傍若無人なその物言いは、彼の為人を知らない人間が聞けば顔を顰めるかもしれない。だが、ルヴァルが何を告げたいのか今のエレナには理解できる。
"エレナの居場所は、自分の隣である"と。
"猶予など必要なく、妻であり立派な淑女だ"と。
隣に居ても良いのだと理解して、エレナはほっとしたような安堵の表情を浮かべる。そんなエレナを見て、今まで言葉にしなかったことでどれほど彼女を不安にさせたのかとルヴァルは不甲斐ない自分に舌打ちしたくなった。
『態度でわかるだろうなんて、傲慢すぎる』
とアーサーに言われた言葉が実感を伴って身に染みる。非常に不本意ではあるが、彼の助言は正しかったようだ。
「俺は北部を預かる要塞都市バーレーの頭で、国に繋がれた番犬だ」
エレナから少し離れたルヴァルは帯刀していた剣を手に取り鞘に納めたまま、エレナにそれを見せる。
「代々の辺境伯がそうであったように、国に安寧がもたらされるまで、俺はこの剣を取り戦い続ける」
そういって国の防衛最前線に立ち続けることを宣言するルヴァル。
「この手がどれだけ血に汚れても。誰に後ろ指を差されても。俺は、俺が信じ、俺が守ると決めたモノのために剣を取る。辺境伯としての名を継いだ時、代々受け継がれるこの剣にそう誓った」
エレナはその重たい剣をじっと眺め静かに頷く。
それはルヴァルにとって何より重たい誓いであり、"ルヴァルの誇り"なのだろう。
「この剣に誓う」
ルヴァルはエレナに傅くと、鞘から剣を抜き地面に突き立てる。
「俺が生涯妻とし、愛するのは"エレナ・アルヴィン"ただ一人だ」
真っ直ぐ、短い、誇りを賭けた誓い。
その言葉を耳で拾ったエレナは紫水晶の瞳を瞬かせる。
「レナ。何かあれば俺を呼べ。どこにいても必ず駆けつける」
だから、何があってもそれまで生き延びることを諦めるなとルヴァルはエレナに約束を乞う。
ルヴァルの言葉に嘘偽りなどなく、その声の響きは何より信頼できる"愛情"の形で。
それを受け取ったエレナの瞳から大粒の涙が落ち頬を濡らす。
「また泣く」
少し呆れたような声でそう言ったルヴァルは剣を鞘に納めて立ち上がり、エレナの涙を指先で拭う。
「だって、ルルが泣かすような事をするから!」
こんな温かな気持ちは知らなかった。
誰かを想い、そして気持ちを返されるなんて、奇跡のようで。
こんなに幸せでいいんだろうかと少し怖くもなる。
「レナ、返事は」
だけど、失くすことが怖いなら、手放さなければいいだけの話だ。
「……はい」
ルヴァルの手を取ったエレナは青灰の瞳を見ながら、
「なら私はこれから先、ルルのためにだけ歌う」
歌姫として、最大限の誇りと最愛を誓う。
「それは贅沢だな」
エレナをふわりと抱え上げ、彼女の瞳を覗き込んだルヴァルは、
「もう、逃げるなよ」
そう言ってエレナに優しく口付けた。