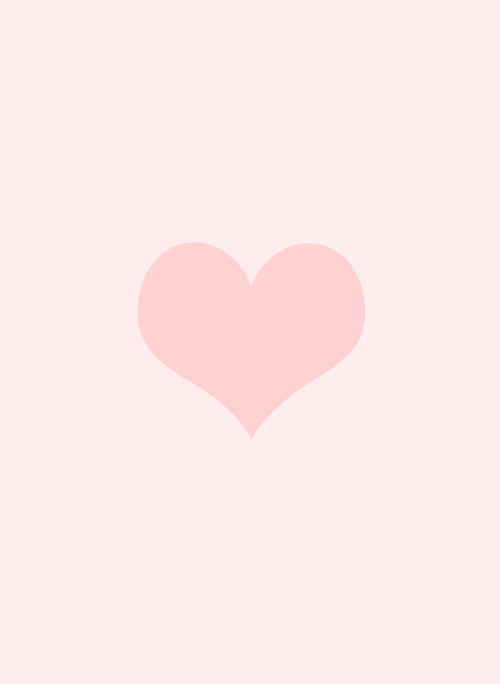エレナについて話したい事がある、と顔面蒼白になったエリオットに呼び出されたジルハルトは指定された場所と愚弟の姿を探して宴の会場から抜け出していた。
「エレナ・サザンドラ……いや、今はアルヴィン辺境伯夫人、か」
久しぶりに目にした彼女は俯く事もなく、あるがままの現状を受け入れて淡々と感情のない瞳で日々を消化していた頃とは見違えるほど美しくなっていた。
「エレナが辺境伯に大事にされているようで良かった」
ルヴァルが好条件を提示しエレナを貰い受けたいと圧をかけてきた時、早々にエレナを手放すよう両親を説得したのはジルハルトだった。
ジルハルトはエリオットがエレナに背を向けマリナに心変わりしたことに気づいていた。
だが、エレナはたった一人サザンドラ子爵家の血を引く正当な継承者。そもそも受傷し価値を失くしたカナリアの引き取り手など見つからない。
婚約者のいる自分が引き取るわけにもいかずエレナの処遇に悩んでいたジルハルトにとってルヴァルの申し出は渡りに船だった。
エレナをようやく愚弟から解放してやれる。
意思が弱く、逃避しがちなエリオットの背を押すのは簡単だった。
エレナはエリオットを慕っていたようだったが、今日のエレナの装いを見て彼女を手放させる選択は正解であったとジルハルトは思う。
元々エレナは出来のいい子だった。ほんの2、3の助言でも真摯に受け止めて、自分のモノにできる子で、実質彼女がサザンドラ子爵領の運営に携わるようになってから代替わりし傾きかけた領地はあっと言う間に上方修正された。
サザンドラ子爵領や南部はカナリアの歌の魔法のおかげで豊作で安泰だなんて勘違いしている人間もいるが、癒やしの歌の魔法だけで領地が適切に治められるわけもない。
そう言った意味でもジルハルトはエレナの事を高く評価していた。
「しっかり釘を刺さねばな」
ようやく幸せを掴んだらしい、義妹になる予定だったエレナ。
アルヴィン辺境伯との関係を考えても、これ以上エリオットに引っ掻き回させるわけにはいかない。
普段なら愚弟の戯言など聞く耳を持たないジルハルトがわざわざエリオットの呼び出しに応じたのはそんな理由からだった。
「それにしても、エリオットの奴一体どこまで歩かせる気だ」
淡い光がところどころに浮いている。間隔をあけてジルハルトを誘導するその光の魔法はエリオットの能力だ。
ジルハルトはそっとその淡い光に指先で触れる。特に熱もなく、触れた感覚もないその光は、まるでシャボン玉のように儚く消えた。
『素敵! 絵本で見た雪みたい』
まだエレナが小さく、2人が婚約を結ぶ前に侯爵家の庭で見かけた光景を思い出す。
南部の生まれで雪を見たことのない彼女は、エリオットの魔法に感動し、紫水晶の瞳を輝かせ何度もこれを強請っていた。
『私、この魔法大好きです。この光はエリオット様みたいにすごく優しいから』
エレナにそう言われ、エリオットは誇らしげな顔をして笑っていた。
「2人があのまま素直に寄り添って育っていたら、違う未来もあったんだろうな」
音もなく手の上で消えた淡い光を見ながら、ジルハルトはそんな事を思う。
エリオットがエレナの婚約者に選ばれたのは単に次男だったからではない。エリオットに魔力の適正があったからだ。
とはいえウェイン侯爵家自体は魔力保持者の家系ではない。たまたま母方の祖母に魔力適正が有り、隔世遺伝でエリオットに魔力が宿っていただけだ。
だから授かったその力が魔術師になれるほど強いものではなかったのは、仕方ない事だった。
でもエリオットにとってはそうではなかったのだろう。
後から魔法を学び始めた婚約者はあっという間にエリオットを追い抜かしてしまった。
エレナは元々魔力保持者の家系の人間で。
そうでなくとも傍目から見ても魔法の修練に割く時間も傾ける情熱も努力を惜しまない姿勢もエリオットと比べ圧倒的で。
だからそれは当然の結果と言えたのだが、"本物の天才"を前に、エリオットの心が折れた心情は、魔力保持者ではない家族には共感できないものだった。
「エリオット、いるか?」
光の数が多くなってきた所でジルハルトは足を止める。
エリオットからの返事はなく、ため息をついたジルハルトは更に奥に進む。
暗闇の先でがさっと音がする。何かがいる気配を見つけて安堵したジルハルトはズカズカと進み、言葉を続ける。
「あのなぁ、エリオット。カナリアではないエレナはもうウチの管轄ではないんだ。お前が選んだ事なのだから大人しく身を引いてだな」
そう続けていた言葉が不意に途切れる。
「なっ」
地響きのような呻き声と暗闇に光る無数の目。
それらに一斉に視線を向けられ、ジルハルトは息の仕方さえ忘れそうになる。
「魔……物」
淡い光が映し出したそれらは、異形の形をしていた。
会場から離れた場所とはいえ、ここは王室の敷地内だ。
何故、こんなところに。
ジルハルトがそう思ったのと、ドス黒いオーラを纏った長い爪がジルハルトに襲いかかったのはほぼ同時だった。
目を閉じる事も敵わず"死"という単語が頭を掠めた瞬間、ジルハルトは大きな衝撃と共に地面に倒れ、長い爪は何もない場所に刺さっていた。
「……!?」
「立って! 直ぐに次が来ます!!」
ジルハルトの目に映ったのは、頬に泥がついたエレナの紫水晶の瞳。
「こっちです、ジルハルトお兄様」
エレナに促され手を引かれたジルハルトは弾かれたように彼女と共に走り出した。
「魔物とは、自我を失った暴走思念体に近い存在……なのだそうです。実体はあるが肉体と精神の結びつきが極めて不安定。だから、彼らは自分でも目的も分からないまま新鮮な容れ物を求めて襲ってくるのだそうです」
逃げ込んだ建物は休憩所のような所で、エレナは手際よく窓際にバリケードを築いていく。
ポケットから取り出した小さめの魔石。それは万が一のためにとルヴァルに渡された物だった。
「これには、魔物避けの目眩しの魔法が組まれています。ルヴァル様の魔力が込められていますから、多少なりと時間稼ぎになるはずです」
王都に来る前にバーレーで学んだ"身の守り方"を実践しながら、エレナは説明する。
「詳しいな、エレナ」
「バーレーでは命のやり取りは日常なので」
私これでもバーレーの女主人ですからと微笑むエレナは、ノクス製の特殊ナイフで魔石を砕き、
「建物の外、四方に設置してきます。これで簡易的な結界を作れるはずなので」
とこれからやる事を告げる。
「なら、俺も」
そう言ったジルハルトに首を振ったエレナは、
「ジルハルトお兄様は決してアレに触れてはなりません。魔力耐性のない人間はそれだけで意識を持っていかれる。あとは魔物に喰われるだけです」
決してここから出ないでくださいと断る。
「警備にあたっている騎士団員も多くは会場周辺に配置されているはずです。私はこの事態の報告と助けを呼んで参ります」
今からの事を手短に告げたエレナは、すっと立ち上がり耳を澄ませる。
あの魔物は足が遅そうだが、数が多い。それに呻き声が先程より増えた。
魔物の湧く黒い沼地が発生したのかもしれない。
このままでは魔物が会場に雪崩れ込み、無関係な人間を巻き込んだ大惨事になってしまう。
「なら尚更エレナ一人に行かせるわけには」
外に出るというエレナの腕を取り引き留めようとしたジルハルトの手に自分の手を重ね、そっとそれを剥がしたエレナは、
「私、バーレーで追いかけっこを日常的にしていたので、足は結構速いです。ルヴァル様がお肉の絶対的信者で、隙あらば私を餌付けするので、体型維持のために始めた運動で体力も持久力もつきましたし」
だから大丈夫、と笑ってみせる。
「ジルハルトお兄様。ここは私を信じて任せては頂けませんか?」
戦う事を選んだ強い意思を持つエレナの瞳にジルハルトはゆっくり頷き手を離す。
「すまない、何もできなくて」
そう言ったジルハルトに首を振ったエレナは、
「私、バーレーでは沢山の人に助けてもらっているんです。今度は私の番」
凛と背を伸ばし立ち上がる。
「今度は私がみんなを守るの。勿論、ジルハルトお兄様も」
だから無事でいてくださいね、そう言って淑女らしくカーテシーをしたエレナは魔物との距離を測りながら勢いよく駆け出した。
「エレナ・サザンドラ……いや、今はアルヴィン辺境伯夫人、か」
久しぶりに目にした彼女は俯く事もなく、あるがままの現状を受け入れて淡々と感情のない瞳で日々を消化していた頃とは見違えるほど美しくなっていた。
「エレナが辺境伯に大事にされているようで良かった」
ルヴァルが好条件を提示しエレナを貰い受けたいと圧をかけてきた時、早々にエレナを手放すよう両親を説得したのはジルハルトだった。
ジルハルトはエリオットがエレナに背を向けマリナに心変わりしたことに気づいていた。
だが、エレナはたった一人サザンドラ子爵家の血を引く正当な継承者。そもそも受傷し価値を失くしたカナリアの引き取り手など見つからない。
婚約者のいる自分が引き取るわけにもいかずエレナの処遇に悩んでいたジルハルトにとってルヴァルの申し出は渡りに船だった。
エレナをようやく愚弟から解放してやれる。
意思が弱く、逃避しがちなエリオットの背を押すのは簡単だった。
エレナはエリオットを慕っていたようだったが、今日のエレナの装いを見て彼女を手放させる選択は正解であったとジルハルトは思う。
元々エレナは出来のいい子だった。ほんの2、3の助言でも真摯に受け止めて、自分のモノにできる子で、実質彼女がサザンドラ子爵領の運営に携わるようになってから代替わりし傾きかけた領地はあっと言う間に上方修正された。
サザンドラ子爵領や南部はカナリアの歌の魔法のおかげで豊作で安泰だなんて勘違いしている人間もいるが、癒やしの歌の魔法だけで領地が適切に治められるわけもない。
そう言った意味でもジルハルトはエレナの事を高く評価していた。
「しっかり釘を刺さねばな」
ようやく幸せを掴んだらしい、義妹になる予定だったエレナ。
アルヴィン辺境伯との関係を考えても、これ以上エリオットに引っ掻き回させるわけにはいかない。
普段なら愚弟の戯言など聞く耳を持たないジルハルトがわざわざエリオットの呼び出しに応じたのはそんな理由からだった。
「それにしても、エリオットの奴一体どこまで歩かせる気だ」
淡い光がところどころに浮いている。間隔をあけてジルハルトを誘導するその光の魔法はエリオットの能力だ。
ジルハルトはそっとその淡い光に指先で触れる。特に熱もなく、触れた感覚もないその光は、まるでシャボン玉のように儚く消えた。
『素敵! 絵本で見た雪みたい』
まだエレナが小さく、2人が婚約を結ぶ前に侯爵家の庭で見かけた光景を思い出す。
南部の生まれで雪を見たことのない彼女は、エリオットの魔法に感動し、紫水晶の瞳を輝かせ何度もこれを強請っていた。
『私、この魔法大好きです。この光はエリオット様みたいにすごく優しいから』
エレナにそう言われ、エリオットは誇らしげな顔をして笑っていた。
「2人があのまま素直に寄り添って育っていたら、違う未来もあったんだろうな」
音もなく手の上で消えた淡い光を見ながら、ジルハルトはそんな事を思う。
エリオットがエレナの婚約者に選ばれたのは単に次男だったからではない。エリオットに魔力の適正があったからだ。
とはいえウェイン侯爵家自体は魔力保持者の家系ではない。たまたま母方の祖母に魔力適正が有り、隔世遺伝でエリオットに魔力が宿っていただけだ。
だから授かったその力が魔術師になれるほど強いものではなかったのは、仕方ない事だった。
でもエリオットにとってはそうではなかったのだろう。
後から魔法を学び始めた婚約者はあっという間にエリオットを追い抜かしてしまった。
エレナは元々魔力保持者の家系の人間で。
そうでなくとも傍目から見ても魔法の修練に割く時間も傾ける情熱も努力を惜しまない姿勢もエリオットと比べ圧倒的で。
だからそれは当然の結果と言えたのだが、"本物の天才"を前に、エリオットの心が折れた心情は、魔力保持者ではない家族には共感できないものだった。
「エリオット、いるか?」
光の数が多くなってきた所でジルハルトは足を止める。
エリオットからの返事はなく、ため息をついたジルハルトは更に奥に進む。
暗闇の先でがさっと音がする。何かがいる気配を見つけて安堵したジルハルトはズカズカと進み、言葉を続ける。
「あのなぁ、エリオット。カナリアではないエレナはもうウチの管轄ではないんだ。お前が選んだ事なのだから大人しく身を引いてだな」
そう続けていた言葉が不意に途切れる。
「なっ」
地響きのような呻き声と暗闇に光る無数の目。
それらに一斉に視線を向けられ、ジルハルトは息の仕方さえ忘れそうになる。
「魔……物」
淡い光が映し出したそれらは、異形の形をしていた。
会場から離れた場所とはいえ、ここは王室の敷地内だ。
何故、こんなところに。
ジルハルトがそう思ったのと、ドス黒いオーラを纏った長い爪がジルハルトに襲いかかったのはほぼ同時だった。
目を閉じる事も敵わず"死"という単語が頭を掠めた瞬間、ジルハルトは大きな衝撃と共に地面に倒れ、長い爪は何もない場所に刺さっていた。
「……!?」
「立って! 直ぐに次が来ます!!」
ジルハルトの目に映ったのは、頬に泥がついたエレナの紫水晶の瞳。
「こっちです、ジルハルトお兄様」
エレナに促され手を引かれたジルハルトは弾かれたように彼女と共に走り出した。
「魔物とは、自我を失った暴走思念体に近い存在……なのだそうです。実体はあるが肉体と精神の結びつきが極めて不安定。だから、彼らは自分でも目的も分からないまま新鮮な容れ物を求めて襲ってくるのだそうです」
逃げ込んだ建物は休憩所のような所で、エレナは手際よく窓際にバリケードを築いていく。
ポケットから取り出した小さめの魔石。それは万が一のためにとルヴァルに渡された物だった。
「これには、魔物避けの目眩しの魔法が組まれています。ルヴァル様の魔力が込められていますから、多少なりと時間稼ぎになるはずです」
王都に来る前にバーレーで学んだ"身の守り方"を実践しながら、エレナは説明する。
「詳しいな、エレナ」
「バーレーでは命のやり取りは日常なので」
私これでもバーレーの女主人ですからと微笑むエレナは、ノクス製の特殊ナイフで魔石を砕き、
「建物の外、四方に設置してきます。これで簡易的な結界を作れるはずなので」
とこれからやる事を告げる。
「なら、俺も」
そう言ったジルハルトに首を振ったエレナは、
「ジルハルトお兄様は決してアレに触れてはなりません。魔力耐性のない人間はそれだけで意識を持っていかれる。あとは魔物に喰われるだけです」
決してここから出ないでくださいと断る。
「警備にあたっている騎士団員も多くは会場周辺に配置されているはずです。私はこの事態の報告と助けを呼んで参ります」
今からの事を手短に告げたエレナは、すっと立ち上がり耳を澄ませる。
あの魔物は足が遅そうだが、数が多い。それに呻き声が先程より増えた。
魔物の湧く黒い沼地が発生したのかもしれない。
このままでは魔物が会場に雪崩れ込み、無関係な人間を巻き込んだ大惨事になってしまう。
「なら尚更エレナ一人に行かせるわけには」
外に出るというエレナの腕を取り引き留めようとしたジルハルトの手に自分の手を重ね、そっとそれを剥がしたエレナは、
「私、バーレーで追いかけっこを日常的にしていたので、足は結構速いです。ルヴァル様がお肉の絶対的信者で、隙あらば私を餌付けするので、体型維持のために始めた運動で体力も持久力もつきましたし」
だから大丈夫、と笑ってみせる。
「ジルハルトお兄様。ここは私を信じて任せては頂けませんか?」
戦う事を選んだ強い意思を持つエレナの瞳にジルハルトはゆっくり頷き手を離す。
「すまない、何もできなくて」
そう言ったジルハルトに首を振ったエレナは、
「私、バーレーでは沢山の人に助けてもらっているんです。今度は私の番」
凛と背を伸ばし立ち上がる。
「今度は私がみんなを守るの。勿論、ジルハルトお兄様も」
だから無事でいてくださいね、そう言って淑女らしくカーテシーをしたエレナは魔物との距離を測りながら勢いよく駆け出した。