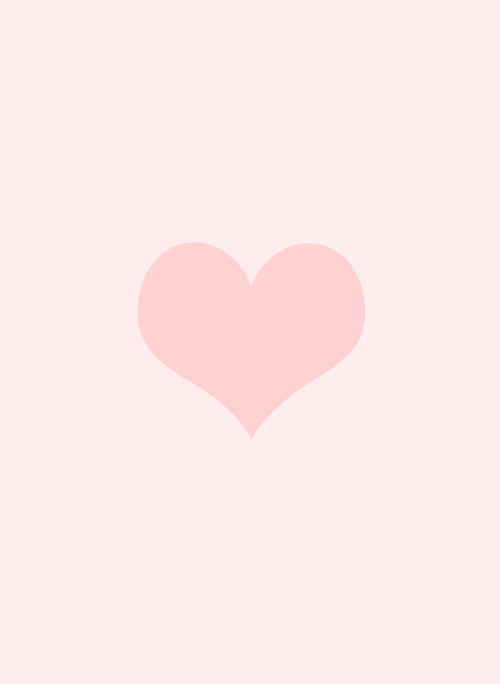マシール王国建国祭。
この国のはじまりを祝う盛大な宴は、伯爵家以上は全員参加する事となっている。
が、基本的に催事や夜会が嫌いなルヴァルは国防の任務を盾に堂々とサボっていた。
それが罷り通るくらいには辺境伯の地位は高く、表立って悪口を吐けないくらいにはルヴァルは権力を持っているのだが。
「なぁ、リオ。コレ絶対行かなきゃダメか?」
招待状を手に取りルヴァルはダメ元でリオレートにそう尋ねる。
「ダメだろ。王太子殿下直々のご命令だぞ」
王太子紋章入りのその封筒を受け取って参加以外の選択肢があると思ってんのかとばかりにリオレートはため息をつく。
「長々書いてあるが、要約すれば"嫁の顔を見せに来い"ってことだろ。見たければ自分で来いつーの」
なんで俺が王城までわざわざ行かなきゃなんねぇんだよとルヴァルは王太子相手に堂々と舌打ちする。
「第一レナは見せもんじゃないし、レナの顔なら見せなくてもあいつ知ってるだろうが」
何せエレナはこの国で唯一のカナリアだったのだ。負傷しその力を失うまで毎年舞台で"祝いの歌"を歌っていたはずで、特等席で鑑賞していただろうアーサーに今更紹介も何もないとルヴァルは思う。
「いや、この場合お前が結婚したって事に意味があるんだと思うぞ」
新しいおもちゃでも見つけたかのような揶揄いを含んだ藍色の瞳にアレコレ聞かれた事を思い出し、リオレートはため息をつく。
「王太子殿下の命令でなくとも、エレナ様にとってはアルヴィン辺境伯夫人として初めての公の場だろ。社交の場は苦手かもしれないが、ここは否が応でも出て頂かなければ」
人見知り気味なエレナの姿を思い浮かべ、リオレートは社交の場に出して大丈夫だろうかと非常に心配になる。
唯我独尊のルヴァルが上手くリードできるとも思えない。
正直この2人が揃って催事出席など不安な要素しか見当たらないが、王太子直々の招待状を持ち帰った手前出てもらわないわけには行かない。
「……まぁ、な。気は進まんが、仕方ない。仕立て屋を呼んでくれ。早急に」
「メリッサを、か?」
もっとゴネるかと思ったのに意外にもあっさりと王都行きを決めた上に、仕立て屋を呼べと言うルヴァルにリオレートは思わず聞き返す。
「うちにメリッサ以外の仕立て屋がいたか?」
他に懇意にしている仕立て屋はいないが、ルヴァルがわざわざ城に呼ぶという事にリオレートは驚きを隠せない。
メリッサの仕立て屋としての腕は確かなのだが、割と面倒くさい性格をしているので必要に迫られなければルヴァルが彼女を城に招く事はない。
エレナを迎え入れた時だって既製品のドレスを送らせたくらいだ。
「ルヴァー。お前、一体何を企んでいるんだ?」
訝しげにそう尋ねるリオレートに青灰の瞳を向けて、
「別に。ただいい機会だから見せつけておこうと思っただけだ。エレナはうちの人間だ、ってな」
誰に、とは言わず、ルヴァルは静かに笑う。
口元は楽しげに笑ってはいるが、目は獲物を狩る時のように一切の隙がなくリオレートはそんなルヴァルの覇気に押されて息を呑む。
「ところで、リオ。王都は変わりないか?」
「……ああ、建国祭前で賑わっている以外は」
ピリピリとしているルヴァルの気配に呑まれたリオレートは一拍遅れてそう返す。
「そうか。息災なようで何よりだ」
淡々とした口調でそう言ったルヴァルは、
「長く城を空ける事になる。準備は念入りに」
と命じてリオレートを下がらせた。
彼の気配が遠ざかってから、
「どんな"音"なんだろうな。"嘘"ってモノは」
ルヴァルは静かな部屋で独り言をつぶやく。
こんな嘘だらけの世界で、彼女の耳は今どんな"音"を拾っているのだろうか?
こんな事を頼んだ自分が言えた義理ではないのだが、願わくばその音の響きが苦痛の少ないモノだといい。
真っ直ぐ自分に向けられた紫水晶の瞳を思い出し、ルヴァルは無性にエレナの歌が聴きたくなった。
この国のはじまりを祝う盛大な宴は、伯爵家以上は全員参加する事となっている。
が、基本的に催事や夜会が嫌いなルヴァルは国防の任務を盾に堂々とサボっていた。
それが罷り通るくらいには辺境伯の地位は高く、表立って悪口を吐けないくらいにはルヴァルは権力を持っているのだが。
「なぁ、リオ。コレ絶対行かなきゃダメか?」
招待状を手に取りルヴァルはダメ元でリオレートにそう尋ねる。
「ダメだろ。王太子殿下直々のご命令だぞ」
王太子紋章入りのその封筒を受け取って参加以外の選択肢があると思ってんのかとばかりにリオレートはため息をつく。
「長々書いてあるが、要約すれば"嫁の顔を見せに来い"ってことだろ。見たければ自分で来いつーの」
なんで俺が王城までわざわざ行かなきゃなんねぇんだよとルヴァルは王太子相手に堂々と舌打ちする。
「第一レナは見せもんじゃないし、レナの顔なら見せなくてもあいつ知ってるだろうが」
何せエレナはこの国で唯一のカナリアだったのだ。負傷しその力を失うまで毎年舞台で"祝いの歌"を歌っていたはずで、特等席で鑑賞していただろうアーサーに今更紹介も何もないとルヴァルは思う。
「いや、この場合お前が結婚したって事に意味があるんだと思うぞ」
新しいおもちゃでも見つけたかのような揶揄いを含んだ藍色の瞳にアレコレ聞かれた事を思い出し、リオレートはため息をつく。
「王太子殿下の命令でなくとも、エレナ様にとってはアルヴィン辺境伯夫人として初めての公の場だろ。社交の場は苦手かもしれないが、ここは否が応でも出て頂かなければ」
人見知り気味なエレナの姿を思い浮かべ、リオレートは社交の場に出して大丈夫だろうかと非常に心配になる。
唯我独尊のルヴァルが上手くリードできるとも思えない。
正直この2人が揃って催事出席など不安な要素しか見当たらないが、王太子直々の招待状を持ち帰った手前出てもらわないわけには行かない。
「……まぁ、な。気は進まんが、仕方ない。仕立て屋を呼んでくれ。早急に」
「メリッサを、か?」
もっとゴネるかと思ったのに意外にもあっさりと王都行きを決めた上に、仕立て屋を呼べと言うルヴァルにリオレートは思わず聞き返す。
「うちにメリッサ以外の仕立て屋がいたか?」
他に懇意にしている仕立て屋はいないが、ルヴァルがわざわざ城に呼ぶという事にリオレートは驚きを隠せない。
メリッサの仕立て屋としての腕は確かなのだが、割と面倒くさい性格をしているので必要に迫られなければルヴァルが彼女を城に招く事はない。
エレナを迎え入れた時だって既製品のドレスを送らせたくらいだ。
「ルヴァー。お前、一体何を企んでいるんだ?」
訝しげにそう尋ねるリオレートに青灰の瞳を向けて、
「別に。ただいい機会だから見せつけておこうと思っただけだ。エレナはうちの人間だ、ってな」
誰に、とは言わず、ルヴァルは静かに笑う。
口元は楽しげに笑ってはいるが、目は獲物を狩る時のように一切の隙がなくリオレートはそんなルヴァルの覇気に押されて息を呑む。
「ところで、リオ。王都は変わりないか?」
「……ああ、建国祭前で賑わっている以外は」
ピリピリとしているルヴァルの気配に呑まれたリオレートは一拍遅れてそう返す。
「そうか。息災なようで何よりだ」
淡々とした口調でそう言ったルヴァルは、
「長く城を空ける事になる。準備は念入りに」
と命じてリオレートを下がらせた。
彼の気配が遠ざかってから、
「どんな"音"なんだろうな。"嘘"ってモノは」
ルヴァルは静かな部屋で独り言をつぶやく。
こんな嘘だらけの世界で、彼女の耳は今どんな"音"を拾っているのだろうか?
こんな事を頼んだ自分が言えた義理ではないのだが、願わくばその音の響きが苦痛の少ないモノだといい。
真っ直ぐ自分に向けられた紫水晶の瞳を思い出し、ルヴァルは無性にエレナの歌が聴きたくなった。