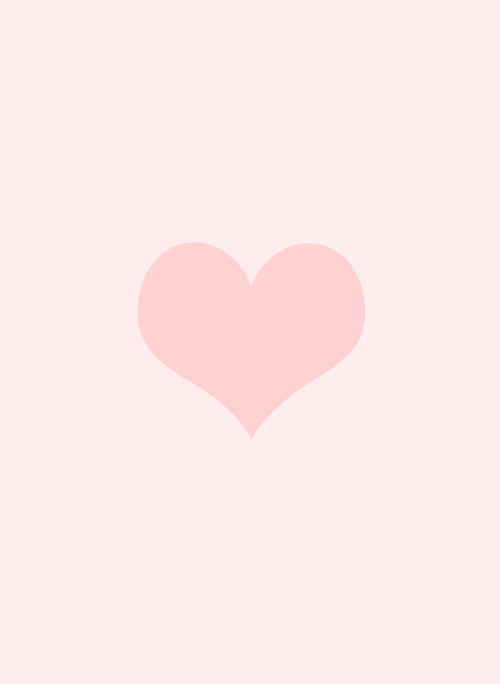「まぁ、確かに荒唐無稽な話ではあるな」
全ての話を聞き終えたルヴァルは、静かにそう言葉を紡ぐ。
こんな無茶苦茶な話、全部を信じて受け入れて……なんて虫の良いこと言えないわねとエレナはそんな事を考えながら紫水晶の瞳を瞬かせる。
エレナがカナリアの能力について正直に告白したのは、ここで生きていきたいと思ったからだ。訳ありしかいないこのバーレーの一員として。
だが、ルヴァルに信じてもらえないのなら、なるべく早くここから出なければ。
ここで出会った大事な人達に、自分のせいで危害が及ぶ事がないように、何処か遠く。ノルディアの手が届かない程、遠くへ。
月を仰ぎ見て覚悟を決めたエレナの口から別れの言葉が紡がれるより早く、
「けど、ま。信じるしかねぇよなぁ」
どこか楽しげなルヴァルの声がエレナの耳に届く。
ぐしゃぐしゃといつもみたいに少し荒っぽい手つきでエレナの黒髪を撫でながら、
「レナのそんな大きな声、初めて聞いた」
とルヴァルはそう言って笑う。
自分が時を戻しやり直しの人生を生きているのだ。
エレナがエレナとして生きるより以前の記憶を有していると主張するのなら、きっとそうなのだろうとルヴァルは思う。
「なぁ、レナ。俺も2回目を生きてるって言ったら信じるか?」
物のついでのようにさらっとそんな事を問いかけられて、驚いたエレナが思わず身を捩り後ろを振り返れば、
「危ないっつーの」
微かに笑う青灰の瞳と視線が交じり、べしっと軽い手刀が落ちてきた。
「……っ!?」
しっかり前を見ていろと後ろから体をホールドされ直したエレナの耳元で、
「付き合ってやる。仕方ないから」
ルヴァルの低い声が響く。
その聞き覚えのある言い回しにエレナは紫水晶の瞳を大きくする。
そうだ、コレは幼少期に王城で出会った黒髪の騎士見習いの彼に言われたのだ。
足早に去っていく彼に追いつけなくて迷子になってしまった自分の事をわざわざ探しに来てくれて、手を差し伸べてくれた。
『付き合ってやる。仕方ないから』
そんなぶっきらぼうな言葉を添えて。
言葉とは裏腹に差し出された手と声の響きがとても優しかった事を覚えている。
「……ルル、だったんだ」
ぽつりと小さく漏らしたエレナの声を風が攫う。
「どうした?」
聞き取れなかった言葉を聞き返すルヴァルに寄りかかるように身を寄せたエレナは、ふふっと楽しげに笑って、
「私も"信じる"って言ったの!」
今度ははっきり聞こえるように言葉にする。
ここは部外秘の多い要塞都市バーレーだ。その出身の彼なら髪や瞳の色を変える術を持っていたとしても不思議ではない。
「そうか」
言葉少なめにそう言って、ルヴァルはまたエレナの頭をくしゃくしゃと撫でる。
姿も、声も、関係も、あの時とは違うけれど。
少し不器用で分かりにくい、ルヴァルの優しい所は変わらない。
規則正しくリズムを刻む心地よいルヴァルの心音を聞きながら、ずっとルヴァルの側にいたいとエレナは改めて思った。
夜会飛行を終えた後、くしゃみを連続でしたエレナは問答無用でルヴァルの部屋に連行された。
上着は着ていたが長時間の飛行で身体が冷えたらしい。とはいえ別にたいした事はないのだが、慌てた様子で温かい飲み物とブランケットを差し出すルヴァルの厚意を無下にはできずエレナはそれらを大人しく受け取った。
初めて通されたルヴァルの私室でふかふかのソファに腰掛けたエレナは、差し出されたホットミルクをゆっくり口にする。
「……美味しい」
蜂蜜入りだぁと幸せそうな声を上げ、無防備にそれを飲むエレナを見てルヴァルはため息を漏らす。
「……にしても、だ。俺はさっきの話も踏まえてレナに言わねばならない事ができた」
おもむろにルヴァルにそう切り出され、エレナはきょとんとルヴァルを見返す。
「お前はもう少し警戒心を持て。無防備が過ぎる」
部屋に連れ込んだ自分が言うのも何だが、最初の頃の警戒心はどこに置いてきた!? というほどエレナは自分に対して警戒心がなさ過ぎるとルヴァルは思う。
ルヴァルの言葉を聞きながら、益々言われている事の意味が分からないと首を傾げるエレナ。
「あのなぁ、レナ。菓子くれるって言っても良く知りもしない人間に付いて行くな」
そんなエレナにまるで子どもにでも言い聞かせるかの様にルヴァルは告げる。
「お菓子……は好きだけど、初回で誰かに付いて行った覚え、ない」
エレナは自分の行いを振り返り、ふるふると首を振りルヴァルにそう返事をする。
「初回じゃなくても、だ。菓子くらいでホイホイ絆されてるんじゃねぇよ。肉なら分かるけど」
「……お肉なら付いて行って良いの?」
「良いわけあるか!」
ペシッと額に軽くデコピンを受けたエレナは、
「前から思っていたんだけど、ルルのそのお肉に対しての絶対的信頼は何なの!?」
うぅっと額をさすりながら暴力反対とつぶやく。
「ガキの頃鍛錬兼ねて食料は自分で調達しろってばーさんに言われて肉に飢えてた……って、なんだよ」
「ふふ、ルルはおばあちゃん子なのね」
いいなぁとエレナに微笑ましそうに言われ、バツが悪そうに視線を逸らしたルヴァルは、
「……俺の話はどうでもいいんだよ」
と強引に脱線しかかった話を元に戻し、
「あのなぁ、レナ。お前は男を見る目がなさ過ぎる」
周りに碌な奴いねぇじゃねぇかとため息をついた。
「そう、かしら?」
そう言われたエレナは自分の周りにいる人間を思い浮かべる。
ぱっと思い浮かぶのはルヴァルにリオレートにノクス。それからいつも声をかけてくれる使用人と騎士の方々。
「みんなとてもお世話になってるし、私の周りにいる人はとてもいい人よ?」
このバーレーで出会った人達からは嫌な音が聞こえない。
苦しかった南部での生活を忘れられそうなくらい、ここに来てから沢山の優しさをもらった。
「秘密を話したからかしら? つっかえずに声も出るようになったし、今度はちゃんと挨拶頑張る」
ぐっと両手を握り、決意を新たにそう宣言してエレナがふわりと笑う。
その仕草が小動物にしか見えず、あまりに可愛らしかったので、うっかり絆されそうになったルヴァルは、邪な感情から目を逸らすように保護対象物、保護対象物と繰り返し唱えた。
全ての話を聞き終えたルヴァルは、静かにそう言葉を紡ぐ。
こんな無茶苦茶な話、全部を信じて受け入れて……なんて虫の良いこと言えないわねとエレナはそんな事を考えながら紫水晶の瞳を瞬かせる。
エレナがカナリアの能力について正直に告白したのは、ここで生きていきたいと思ったからだ。訳ありしかいないこのバーレーの一員として。
だが、ルヴァルに信じてもらえないのなら、なるべく早くここから出なければ。
ここで出会った大事な人達に、自分のせいで危害が及ぶ事がないように、何処か遠く。ノルディアの手が届かない程、遠くへ。
月を仰ぎ見て覚悟を決めたエレナの口から別れの言葉が紡がれるより早く、
「けど、ま。信じるしかねぇよなぁ」
どこか楽しげなルヴァルの声がエレナの耳に届く。
ぐしゃぐしゃといつもみたいに少し荒っぽい手つきでエレナの黒髪を撫でながら、
「レナのそんな大きな声、初めて聞いた」
とルヴァルはそう言って笑う。
自分が時を戻しやり直しの人生を生きているのだ。
エレナがエレナとして生きるより以前の記憶を有していると主張するのなら、きっとそうなのだろうとルヴァルは思う。
「なぁ、レナ。俺も2回目を生きてるって言ったら信じるか?」
物のついでのようにさらっとそんな事を問いかけられて、驚いたエレナが思わず身を捩り後ろを振り返れば、
「危ないっつーの」
微かに笑う青灰の瞳と視線が交じり、べしっと軽い手刀が落ちてきた。
「……っ!?」
しっかり前を見ていろと後ろから体をホールドされ直したエレナの耳元で、
「付き合ってやる。仕方ないから」
ルヴァルの低い声が響く。
その聞き覚えのある言い回しにエレナは紫水晶の瞳を大きくする。
そうだ、コレは幼少期に王城で出会った黒髪の騎士見習いの彼に言われたのだ。
足早に去っていく彼に追いつけなくて迷子になってしまった自分の事をわざわざ探しに来てくれて、手を差し伸べてくれた。
『付き合ってやる。仕方ないから』
そんなぶっきらぼうな言葉を添えて。
言葉とは裏腹に差し出された手と声の響きがとても優しかった事を覚えている。
「……ルル、だったんだ」
ぽつりと小さく漏らしたエレナの声を風が攫う。
「どうした?」
聞き取れなかった言葉を聞き返すルヴァルに寄りかかるように身を寄せたエレナは、ふふっと楽しげに笑って、
「私も"信じる"って言ったの!」
今度ははっきり聞こえるように言葉にする。
ここは部外秘の多い要塞都市バーレーだ。その出身の彼なら髪や瞳の色を変える術を持っていたとしても不思議ではない。
「そうか」
言葉少なめにそう言って、ルヴァルはまたエレナの頭をくしゃくしゃと撫でる。
姿も、声も、関係も、あの時とは違うけれど。
少し不器用で分かりにくい、ルヴァルの優しい所は変わらない。
規則正しくリズムを刻む心地よいルヴァルの心音を聞きながら、ずっとルヴァルの側にいたいとエレナは改めて思った。
夜会飛行を終えた後、くしゃみを連続でしたエレナは問答無用でルヴァルの部屋に連行された。
上着は着ていたが長時間の飛行で身体が冷えたらしい。とはいえ別にたいした事はないのだが、慌てた様子で温かい飲み物とブランケットを差し出すルヴァルの厚意を無下にはできずエレナはそれらを大人しく受け取った。
初めて通されたルヴァルの私室でふかふかのソファに腰掛けたエレナは、差し出されたホットミルクをゆっくり口にする。
「……美味しい」
蜂蜜入りだぁと幸せそうな声を上げ、無防備にそれを飲むエレナを見てルヴァルはため息を漏らす。
「……にしても、だ。俺はさっきの話も踏まえてレナに言わねばならない事ができた」
おもむろにルヴァルにそう切り出され、エレナはきょとんとルヴァルを見返す。
「お前はもう少し警戒心を持て。無防備が過ぎる」
部屋に連れ込んだ自分が言うのも何だが、最初の頃の警戒心はどこに置いてきた!? というほどエレナは自分に対して警戒心がなさ過ぎるとルヴァルは思う。
ルヴァルの言葉を聞きながら、益々言われている事の意味が分からないと首を傾げるエレナ。
「あのなぁ、レナ。菓子くれるって言っても良く知りもしない人間に付いて行くな」
そんなエレナにまるで子どもにでも言い聞かせるかの様にルヴァルは告げる。
「お菓子……は好きだけど、初回で誰かに付いて行った覚え、ない」
エレナは自分の行いを振り返り、ふるふると首を振りルヴァルにそう返事をする。
「初回じゃなくても、だ。菓子くらいでホイホイ絆されてるんじゃねぇよ。肉なら分かるけど」
「……お肉なら付いて行って良いの?」
「良いわけあるか!」
ペシッと額に軽くデコピンを受けたエレナは、
「前から思っていたんだけど、ルルのそのお肉に対しての絶対的信頼は何なの!?」
うぅっと額をさすりながら暴力反対とつぶやく。
「ガキの頃鍛錬兼ねて食料は自分で調達しろってばーさんに言われて肉に飢えてた……って、なんだよ」
「ふふ、ルルはおばあちゃん子なのね」
いいなぁとエレナに微笑ましそうに言われ、バツが悪そうに視線を逸らしたルヴァルは、
「……俺の話はどうでもいいんだよ」
と強引に脱線しかかった話を元に戻し、
「あのなぁ、レナ。お前は男を見る目がなさ過ぎる」
周りに碌な奴いねぇじゃねぇかとため息をついた。
「そう、かしら?」
そう言われたエレナは自分の周りにいる人間を思い浮かべる。
ぱっと思い浮かぶのはルヴァルにリオレートにノクス。それからいつも声をかけてくれる使用人と騎士の方々。
「みんなとてもお世話になってるし、私の周りにいる人はとてもいい人よ?」
このバーレーで出会った人達からは嫌な音が聞こえない。
苦しかった南部での生活を忘れられそうなくらい、ここに来てから沢山の優しさをもらった。
「秘密を話したからかしら? つっかえずに声も出るようになったし、今度はちゃんと挨拶頑張る」
ぐっと両手を握り、決意を新たにそう宣言してエレナがふわりと笑う。
その仕草が小動物にしか見えず、あまりに可愛らしかったので、うっかり絆されそうになったルヴァルは、邪な感情から目を逸らすように保護対象物、保護対象物と繰り返し唱えた。