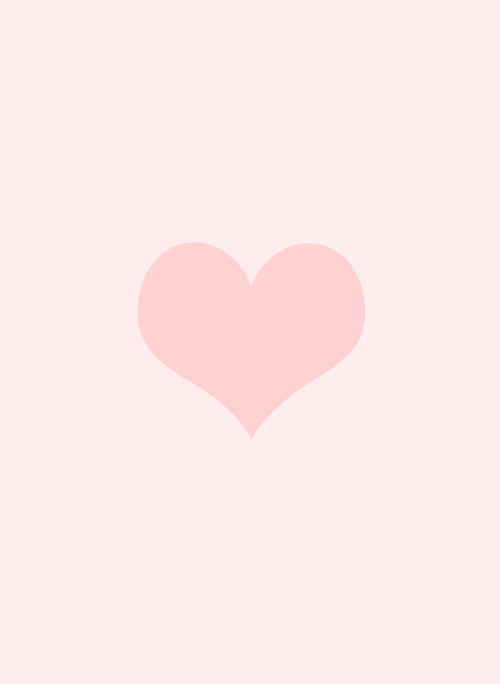いつも通り散策をしていたカリアは、その日大きな土地の気の綻びを見つけた。
そこは魔力が混ざって澱み、沢山溜まって大きな黒い沼になっていた。
ボコボコと音を立てて魔力が混ざり合う音が聞こえる。その黒い沼からは大きな魔物が生まれ、沼から這いずり出てきており、すでにその土地は魔物が暴れ瘴気に触れて傷ついている状態だった。
「こんなの、見た事ないわ」
その時カリアが感じたのは未知に対する恐怖心。
だが、それ以上に世界が軋む不協和音に心が痛んだ。
嘆く音に共鳴し、心が苦しくなる。
「世界に溢れる音は優しいモノでないと」
自分ならきっとこの綻びを直せる。使命感にも似た心持ちでカリアはその事態に立ち向かった。
カリアは魔力を込めて歌う。
傷ついた全てを癒せるように、と願いを込めて。
そうして事態が収まり、周囲を見回っていた時、カリアは沢山の人間が倒れている所に遭遇した。
そのほとんどは息を引き取っていて、自分が来るより前に魔物に襲われたのだと悟る。
どうにもならないその光景に、カリアは自然淘汰とつぶやいて去るつもりだった。
だが、カリアの耳が一つだけ"生きている者"の音を拾う。
『ヒトに近づいてはいけない』
という母の警告が耳の奥に響いたが、微かな呼吸と生きようとする懸命な鼓動に動かされ、カリアはその青年に手を伸ばす。
どうせ気を失っているのだし、自分の存在を認知されることもないだろうという軽い気持ちで。
青年の手を握ったカリアは音で身体の中の不協和音を聞き分け、癒しの歌を紡ぐ。
処置が終わったカリアは規則正しく流れる魔力と心音を聞いてホッと胸を撫で下ろす。あとは青年の生命力に任せるしかない。
そう思った時、小さな呻き声と共に閉じられていた瞼がゆっくりと開き、その深い緑色の瞳と目が合った。
カリアは慌てて手を離し、青年を残してその場を去る。
別に感謝されたかったわけではないし、母の言いつけを初めて破った後ろめたさもあった。
(まだ、意識がぼんやりしていたし、大丈夫……よね?)
大丈夫、大丈夫とカリアは自分に言い聞かせる。
混濁した意識に残るものはきっとない、と。
だが、カリアは一つだけ失念していた。
自分はこの国で忌み嫌われる大層目立つ"黒髪"を持っている、ということを。
それからしばらくの間、カリアは自分が失態をやらかした場所には出向かなかったが、それでも時折あの青年のその後が気になった。
海のような蒼い髪と森の木々のような深い緑色の目を思い出す。
自分の紡いだ魔法は一体どの程度ヒトに有効なのだろう?
ヒトに対してはやった事がないのでその結果は分からず、無事に家族の元に帰れていればいいと祈る事しかできない。
そんな日々が続き、気になり過ぎたのでせめて黒い沼の消失だけでも確認しようとカリアはこっそり出かけることにした。
「良かった。澱みは解消されたみたい」
もう、この土地は大丈夫だろう。
澄んだ気の流れを確認し、傷を負った森の植物を憂いたカリアは、そっと魔力を込めて歌を紡ぐ。
『みんなが元気になりますように』
そんな願いを織り交ぜながら。
一曲歌い終わった時だった。
後方でガサっと音がすると同時に、
「やっと、見つけたっ!」
カリアは腕を掴まれ、驚いたように目を瞬かせる。
その瞳に映っていたのは見間違いようもなく、海のような蒼い髪と深緑の瞳。あの時の青年だった。
掴まれた腕の力強さと突然の出来事に驚いたカリアは、逃げなければと必死に抵抗を試みる。
「逃げないで欲しい。危害を加えたりはしないから」
その手から逃れようとジタバタともがくカリアのことを落ち着けるように声をかけた青年は、そう言ってそっと手を離す。
「すまない、礼を言いたかっただけなんだ」
後方に距離を取り警戒心を滲ませたカリアに青年は静かにそう言った。
「君だろう? 私を助けてくれたのは」
あれだけ意識が朦朧としていたのに覚えていたのか、とカリアは素直に驚く。
「……人違い。私、あなたなんか知らないわ」
「そんな目立つ黒髪、忘れようがない」
そう言われてカリアは自分が捨てられた理由を思い出す。
『破滅の魔女の生まれ変わり』
久しくヒトから離れた生活を送っていたため、そんな迷信すっかり忘れていた。
カリアは自分を捨てた人達の事を思い出し、目一杯嫌そうな顔をして舌打ちする。
「破滅の魔女は、古文書の中にしか存在しないんだと思っていた。魔女殿は随分若くて可愛いらしいんだねぇ」
カリアの舌打ちに嫌な顔をせず揶揄うように笑った青年は、
「私はノーラ・ルディ・ファリアーノと申します。改めまして、助けて頂きありがとうございます」
そう言って紳士らしく礼をした。
その日以降、ノーラと名乗ったその魔術師は、カリアが行く先々にふらりと現れては興味深そうにカリアの紡ぐ魔法の歌を聴き、カリアの事を観察するようになった。
初めは警戒して逃げ回っていたカリアだったが、ノーラから危害を加えられる事がない事と、毎回ノーラが持ってくるカリアが知らないお菓子の数々に釣られていつしか言葉を交わすようになり、気づけば一緒にいる時間が増えていた。
『ヒトに近づいてはいけない』
と、"母"である神獣から言われた事を忘れたわけではなかったし、後ろめたさもある。
それでも、自分以外の人間がそこにいて、黒髪を忌避されることもなく、何気ない言葉を交わすその時間が、いつしかカリアは楽しみになっていた。
「ノーラは、この国のヒトじゃないの?」
「違うよ。同盟国の魔術師として、技術支援に来てるだけ。もうすぐ、任期が終わって国に帰るんだ」
「……そう」
せっかく仲良くなったのにノーラはいなくなるのか、と少し残念に思いながらカリアは静かにそう返す。
「なぁ、カリア。……その、良かったらうちの国に来ないか?」
「え?」
「この国だとカリアは隠れて暮らさないといけないんだろ? 髪の色くらいで人里離れて生活するなんて馬鹿げてる」
意を決したようにノーラは口を開くと、真剣な声音でカリアに話しかける。
「それに、カリアのその不思議な魔法はとても貴重だ。魔術師としても興味深いし、研究すればもっと色んな事に役立てられるし。カリアの魔法の有用性とカリアが危険な存在でないと示せたら、きっと誰も君を"破滅の魔女"だなんて呼ばなくなる」
この国を、この土地を離れる?
そんな事今まで一度も考えた事のなかったカリアは驚いて目を瞬かせる。
「ヒトはヒトの中で生きる方がいい。ヒトは一人では生きていけないから」
戸惑いの色を示すカリアの紫色の瞳を覗き込みながら、ノーラは優しい口調で言葉を紡ぐ。
「私の国なら、誰も君を迫害したりしない。世界は、カリアの知らない事で溢れている。ねぇ、カリア。君は沢山の人に囲まれて、言葉をかわして、一緒に学んで研鑽したり、街に出て遊んだり、今まで知らなかった文化に触れる。そんな風に過ごしてみたいとは思わないかい?」
沢山の人、は正直に言えば怖い。
だけど、ノーラがいつも話してくれる知らない世界の話はとても興味深くて、せっかく得た視力で様々なモノを見てみたい気はした。
「カリアの歌は素晴らしい。もっと評価されるべきだと思うし、私は君の歌が好きだよ」
歌、と言われカリアは視線を落とす。
この力をくれたのは、音の紡ぎ方を教えてくれたのは、輝くような金の羽を持つ神獣だ。
「私……は」
ここから去ってしまったら、神獣達に歌を捧げる事ができなくなる。
今まで大切に守ってくれた彼女の側を離れるなんて、できないとカリアは断ろうと顔を上げれば、熱の籠った深緑の瞳と目が合った。
「私はカリアともっと一緒にいたい。私はこれでも自国ではそれなりの地位があるから、君を保護してあげられるし。……だから」
ノーラはそっとカリアの髪を救い、そこに口付けを落とす。
「一緒に来てくれないか?」
真剣な声音にカリアの心音は高鳴った。
今まで知らなかった音を立てる心音に耳を傾けながら、返事をできず俯くカリアを見て、
「すぐに返事をくれなくていいから、考えてみて」
ノーラは優しく笑った。
そこは魔力が混ざって澱み、沢山溜まって大きな黒い沼になっていた。
ボコボコと音を立てて魔力が混ざり合う音が聞こえる。その黒い沼からは大きな魔物が生まれ、沼から這いずり出てきており、すでにその土地は魔物が暴れ瘴気に触れて傷ついている状態だった。
「こんなの、見た事ないわ」
その時カリアが感じたのは未知に対する恐怖心。
だが、それ以上に世界が軋む不協和音に心が痛んだ。
嘆く音に共鳴し、心が苦しくなる。
「世界に溢れる音は優しいモノでないと」
自分ならきっとこの綻びを直せる。使命感にも似た心持ちでカリアはその事態に立ち向かった。
カリアは魔力を込めて歌う。
傷ついた全てを癒せるように、と願いを込めて。
そうして事態が収まり、周囲を見回っていた時、カリアは沢山の人間が倒れている所に遭遇した。
そのほとんどは息を引き取っていて、自分が来るより前に魔物に襲われたのだと悟る。
どうにもならないその光景に、カリアは自然淘汰とつぶやいて去るつもりだった。
だが、カリアの耳が一つだけ"生きている者"の音を拾う。
『ヒトに近づいてはいけない』
という母の警告が耳の奥に響いたが、微かな呼吸と生きようとする懸命な鼓動に動かされ、カリアはその青年に手を伸ばす。
どうせ気を失っているのだし、自分の存在を認知されることもないだろうという軽い気持ちで。
青年の手を握ったカリアは音で身体の中の不協和音を聞き分け、癒しの歌を紡ぐ。
処置が終わったカリアは規則正しく流れる魔力と心音を聞いてホッと胸を撫で下ろす。あとは青年の生命力に任せるしかない。
そう思った時、小さな呻き声と共に閉じられていた瞼がゆっくりと開き、その深い緑色の瞳と目が合った。
カリアは慌てて手を離し、青年を残してその場を去る。
別に感謝されたかったわけではないし、母の言いつけを初めて破った後ろめたさもあった。
(まだ、意識がぼんやりしていたし、大丈夫……よね?)
大丈夫、大丈夫とカリアは自分に言い聞かせる。
混濁した意識に残るものはきっとない、と。
だが、カリアは一つだけ失念していた。
自分はこの国で忌み嫌われる大層目立つ"黒髪"を持っている、ということを。
それからしばらくの間、カリアは自分が失態をやらかした場所には出向かなかったが、それでも時折あの青年のその後が気になった。
海のような蒼い髪と森の木々のような深い緑色の目を思い出す。
自分の紡いだ魔法は一体どの程度ヒトに有効なのだろう?
ヒトに対してはやった事がないのでその結果は分からず、無事に家族の元に帰れていればいいと祈る事しかできない。
そんな日々が続き、気になり過ぎたのでせめて黒い沼の消失だけでも確認しようとカリアはこっそり出かけることにした。
「良かった。澱みは解消されたみたい」
もう、この土地は大丈夫だろう。
澄んだ気の流れを確認し、傷を負った森の植物を憂いたカリアは、そっと魔力を込めて歌を紡ぐ。
『みんなが元気になりますように』
そんな願いを織り交ぜながら。
一曲歌い終わった時だった。
後方でガサっと音がすると同時に、
「やっと、見つけたっ!」
カリアは腕を掴まれ、驚いたように目を瞬かせる。
その瞳に映っていたのは見間違いようもなく、海のような蒼い髪と深緑の瞳。あの時の青年だった。
掴まれた腕の力強さと突然の出来事に驚いたカリアは、逃げなければと必死に抵抗を試みる。
「逃げないで欲しい。危害を加えたりはしないから」
その手から逃れようとジタバタともがくカリアのことを落ち着けるように声をかけた青年は、そう言ってそっと手を離す。
「すまない、礼を言いたかっただけなんだ」
後方に距離を取り警戒心を滲ませたカリアに青年は静かにそう言った。
「君だろう? 私を助けてくれたのは」
あれだけ意識が朦朧としていたのに覚えていたのか、とカリアは素直に驚く。
「……人違い。私、あなたなんか知らないわ」
「そんな目立つ黒髪、忘れようがない」
そう言われてカリアは自分が捨てられた理由を思い出す。
『破滅の魔女の生まれ変わり』
久しくヒトから離れた生活を送っていたため、そんな迷信すっかり忘れていた。
カリアは自分を捨てた人達の事を思い出し、目一杯嫌そうな顔をして舌打ちする。
「破滅の魔女は、古文書の中にしか存在しないんだと思っていた。魔女殿は随分若くて可愛いらしいんだねぇ」
カリアの舌打ちに嫌な顔をせず揶揄うように笑った青年は、
「私はノーラ・ルディ・ファリアーノと申します。改めまして、助けて頂きありがとうございます」
そう言って紳士らしく礼をした。
その日以降、ノーラと名乗ったその魔術師は、カリアが行く先々にふらりと現れては興味深そうにカリアの紡ぐ魔法の歌を聴き、カリアの事を観察するようになった。
初めは警戒して逃げ回っていたカリアだったが、ノーラから危害を加えられる事がない事と、毎回ノーラが持ってくるカリアが知らないお菓子の数々に釣られていつしか言葉を交わすようになり、気づけば一緒にいる時間が増えていた。
『ヒトに近づいてはいけない』
と、"母"である神獣から言われた事を忘れたわけではなかったし、後ろめたさもある。
それでも、自分以外の人間がそこにいて、黒髪を忌避されることもなく、何気ない言葉を交わすその時間が、いつしかカリアは楽しみになっていた。
「ノーラは、この国のヒトじゃないの?」
「違うよ。同盟国の魔術師として、技術支援に来てるだけ。もうすぐ、任期が終わって国に帰るんだ」
「……そう」
せっかく仲良くなったのにノーラはいなくなるのか、と少し残念に思いながらカリアは静かにそう返す。
「なぁ、カリア。……その、良かったらうちの国に来ないか?」
「え?」
「この国だとカリアは隠れて暮らさないといけないんだろ? 髪の色くらいで人里離れて生活するなんて馬鹿げてる」
意を決したようにノーラは口を開くと、真剣な声音でカリアに話しかける。
「それに、カリアのその不思議な魔法はとても貴重だ。魔術師としても興味深いし、研究すればもっと色んな事に役立てられるし。カリアの魔法の有用性とカリアが危険な存在でないと示せたら、きっと誰も君を"破滅の魔女"だなんて呼ばなくなる」
この国を、この土地を離れる?
そんな事今まで一度も考えた事のなかったカリアは驚いて目を瞬かせる。
「ヒトはヒトの中で生きる方がいい。ヒトは一人では生きていけないから」
戸惑いの色を示すカリアの紫色の瞳を覗き込みながら、ノーラは優しい口調で言葉を紡ぐ。
「私の国なら、誰も君を迫害したりしない。世界は、カリアの知らない事で溢れている。ねぇ、カリア。君は沢山の人に囲まれて、言葉をかわして、一緒に学んで研鑽したり、街に出て遊んだり、今まで知らなかった文化に触れる。そんな風に過ごしてみたいとは思わないかい?」
沢山の人、は正直に言えば怖い。
だけど、ノーラがいつも話してくれる知らない世界の話はとても興味深くて、せっかく得た視力で様々なモノを見てみたい気はした。
「カリアの歌は素晴らしい。もっと評価されるべきだと思うし、私は君の歌が好きだよ」
歌、と言われカリアは視線を落とす。
この力をくれたのは、音の紡ぎ方を教えてくれたのは、輝くような金の羽を持つ神獣だ。
「私……は」
ここから去ってしまったら、神獣達に歌を捧げる事ができなくなる。
今まで大切に守ってくれた彼女の側を離れるなんて、できないとカリアは断ろうと顔を上げれば、熱の籠った深緑の瞳と目が合った。
「私はカリアともっと一緒にいたい。私はこれでも自国ではそれなりの地位があるから、君を保護してあげられるし。……だから」
ノーラはそっとカリアの髪を救い、そこに口付けを落とす。
「一緒に来てくれないか?」
真剣な声音にカリアの心音は高鳴った。
今まで知らなかった音を立てる心音に耳を傾けながら、返事をできず俯くカリアを見て、
「すぐに返事をくれなくていいから、考えてみて」
ノーラは優しく笑った。