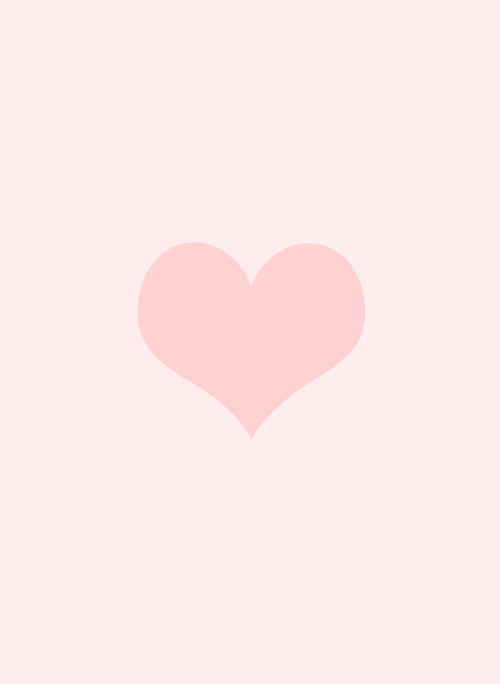『何かご用でしたか?』
と冷静さを取り戻したエレナはスケッチブックに文字を綴る。
「用は特にないんだが、ピアノの音がしたのが懐かしくてな」
ばーさんの道楽ピアノはまだ生きていたんだなと、ルヴァルは懐かしそうに鍵盤に触れる。
『勝手をして申し訳ありません』
ハーマンからもリーファからもご自由にと言われたから好意に甘えてしまったが、よく考えたらルヴァル本人に直接ピアノに触れる許可を取っていなかったとエレナは慌てて謝罪する。
「構わない。城の隅っこで埃を被っているくらいなら、演奏者がいた方がコレもばーさんも喜ぶだろう」
ルヴァルは咎めることもなく、好きにすればいいと軽く許可を出す。
"ばーさん"と懐かし気に祖母の事を口にするルヴァルの横顔がどこか優しげで、彼にとって大事な人であったのだろうと分かる。
『大切な方なのですね』
「まぁ、母親代わりだったからな」
母親代わり、と聞いてエレナは紫水晶の瞳を大きく見開く。
「そんな顔をするな。ここでは誰かがいなくなるのも日常だ」
ルヴァルはエレナの頭をポンと撫で、
「確かに母の事など俺は覚えてないが、父が言うには赤子を抱えて一人で街一つ護って戦えるカッコいい女なんだと。俺は母に似ているらしくてな、それはもう何百回と耳にタコができるほど母親について聞かされて育ったから、尊敬はしている。まぁ、今頃あの世で2人仲良くやってるだろうさ」
と彼にしては珍しく長話をしてくれた。
『お祖母様は、どんな方だったのですか?』
「ん? 俺のばーさんか? すっげぇー礼儀作法に厳しい、偏屈ババア」
礼儀作法に厳しい、と言う割にルヴァルはだいぶおおらかというか言動に若干、かなり問題がある上に自由が過ぎる気がするのだが、確かに食事の所作などはかなり美しく頷ける面もある。
「修行と称して俺を谷底に突き落としたり、雪山にナイフ一本で放り込んだり。ちょっとしたイタズラで機関銃ぶっ放して追いかけられたりな」
礼儀作法とは一体、という疑問がエレナの頭をよぎったがルヴァルがどこか楽し気に祖母との思い出を語るので、
『よくご無事でしたね』
文化が違えばまぁそんな事もあるのだろうとエレナはスルーする事にした。
「まぁ、ガキの頃から強かったからな」
謙遜しないルヴァルにエレナはクスクスと笑って、
『せっかくなので、どれか弾きましょうか?』
と楽譜を見せる。
「俺は楽譜は読めん。から任せる」
コクリと頷いたエレナは、一番古く何度も開いた跡のついている曲を選びピアノを奏でる。それはとても短い曲で切ない旋律を響かせた。
「綺麗な曲だな」
『聴き覚えはないのですか?』
「あるのかもしれないが、忘れたな。ばーさんが全盛期でピアノの演奏会やってたらしい時期、俺は諸事情でここには居なかったし」
ルヴァルは遠くを見つめてぽつりと漏らす。ルヴァルは祖母から突然王都行きを命じられ、王城で暮らしながら騎士団長にしごかれていた時期を思い出す。
もうおそらくあの頃には祖母の身体には病魔が巣くっていたのだろう。
自分では、強過ぎる魔力を持って生まれてきた孫に稽古の一つもつけてやれないほどに。
黙ってしまったルヴァルの精悍な顔を見つめたエレナはゆっくりと息を吸い込むと、
「〜〜〜----♪」
静かに旋律を紡ぎ出す。
それは先程エレナが演奏した曲で、異国の言葉でエレナから紡がれるその歌をルヴァルは静かに聞き入った。
『どうか、どうか、無事でいて。あなたの帰りを待っているから。そんな願いが込められた歌なんですよ』
エレナは開き切った楽譜のページをそっと大切そうに撫でる。
きっとルヴァルの祖母は彼の無事を祈ってこの曲を聴いていたのではないだろうか? そんな事を考えながら。
エレナの書いた文字を辿ったルヴァルは青灰色の目を細め、そうかと小さくつぶやいて、彼女の黒髪を優しく撫でた。
「エレナは歌っている時が一番楽しそうだな」
エレナはコクンと頷くと、
「……すき、な……の」
ゆっくりと自分の気持ちを声に出す。
「……エレナ」
ルヴァルはエレナの口から出た"好き"と言う単語と笑みに驚き目を瞬かせる。
「歌、が」
やっと取り返した自分の『好きな事』
エレナは楽譜を握りしめて、幸せそうに笑う。
「歌。うん、歌が好き、な。知ってた」
ふいっと視線を逸らし、ルヴァルはそう繰り返す。
そんなルヴァルを見て首を傾げたエレナはやっぱりまだ聞き取り辛いわよねと喉に手を当てる。
ソフィアのリハビリは受けているが、まだまだ筆談が続きそうだとスケッチブックを引き寄せた。
「エレナは、子どもの時からこうなのか?」
わざとらしく咳をして仕切り直したルヴァルはエレナにそう尋ねる。
こう、とは? と首を傾げるエレナを見て、
「歌が楽しいのは」
ルヴァルは言葉を足す。
エレナはコクンと頷いて、
『幼い時は、ただ楽しかったです。カナリアとしての義務もなかったし。好きに歌えたから』
それはまだ母が生きていた時の話。
カナリアである彼女の後ろをついてまわり、音を耳で学んでいった。
『お母様に付いて王城に出入りしていた事もあるのですよ』
南部のサザンドラ子爵家から年に数度、王都に向かい王城で歌っていた母の姿を思い出す。
『お母様のお仕事中にこっそり抜け出して、庭園に入り込んだりして』
楽しかった記憶が自分の中にもちゃんとあったのだと思い出したエレナは幸せそうに笑う。
記憶を辿っていったエレナは、ふと庭園の隅で出会った黒髪の少年の事を思い出す。
傷だらけで、膝を抱えていた騎士訓練生の制服を纏っていたその人は、不機嫌そうなのになんだか泣き出しそうな目をしていた。
「げんき、かな」
「どうした?」
『いえ、ただふと王城で出会った黒髪の騎士見習いの子を思い出しまして』
文字を綴ったエレナはふふっと楽し気に笑う。
黒髪の騎士見習いと聞いてルヴァルは驚いたようにエレナを見つめ、
「……そいつが、どうかしたのか?」
と静かに尋ねる。
『楽しかったなって。不機嫌そうな顔をしていたのに結構世話焼きで、後ろを追いかけて迷子になりかけた私を探しに戻ってきてくれたりして』
エレナは懐かしそうに目を細め、彼の事を思い出す。仕方なさそうに手を差し伸べて王城を案内してくれた面倒見のいい少し年上のお兄さん。
「歌、たくさん……歌った……です」
まだカナリアとしての能力が発現したばかりで、非公式に力を使ったあの日。彼だけのために歌を紡いだ。
怪我をしませんように。
魔力が暴走することがありませんように。
強くと願う彼が、誰かを守れるようになれますように。
そんな祈りを込めて。
「泣いて、ない、と……い、いな」
もう随分と時間を経た今ではきっと彼は立派な騎士になっている事だろう。
そんな黒髪の騎士を想像したエレナは、彼が怪我をせずに済めばいいなと思いを馳せる。
「……泣いてねぇよ」
ぽつりと小さくつぶやいた声はエレナが拾うには充分な声量で、不思議そうに自分を見返すエレナの頭をルヴァルは乱暴に撫でた。
「……???」
ルヴァルはじっとエレナの紫水晶の瞳を覗き込む。髪色を変えて身分を隠していたのだから当然なのだが、疑問符を浮かべるエレナがあの時の騎士見習いが目の前にいると気づいた様子はない。
初めて領地を出て放り込まれた王城での生活はルヴァルにとって"楽しいもの"とは言い難かった。訓練自体は大した事はないが、その才は常に人を引き寄せ悪意と害意と嫉妬に晒された。
そんな中で出会ったエレナと過ごしたわずかな時間は、ルヴァルが王城で過ごした日々で唯一色づいた記憶だった。
その時間を共有したエレナが"楽しかった"といい、記憶に留めてくれている。
おそらくあまり幸せだったとは言い難い彼女の人生の中で、楽しいと感じた瞬間の中に自分がいるのだと思うと、不意にルヴァルはエレナを抱きしめたくなった。
(この気持ちは、なんて言うんだろうな)
エレナの気持ちなんて置き去りで、バーレーに連れて来て形だけの妻にした。それなのに身勝手なのは十分承知で、エレナを手放したくないと思う。
ルヴァルはエレナの黒髪をそっと掬ってそこに口付けを落とす。
流れるようなその動作をただ見ていたエレナは、自身の心臓が破裂しそうなくらい早くなるのを聞きながら、ルヴァルの青灰の瞳を見つめる。
「ル……あ、の」
「俺の名前、呼ばないのか?」
じっと見つめられたエレナは頬に熱が集まるのを感じながら、
「まだ……うまく」
出ない音があるのだとしどろもどろに口にする。
「いいから」
気にする様子のないルヴァルはとても優しい声で続きを促す。
「ル……ァル、さ、ま」
やはりまだ中一音が掠れて上手く発音できず、ルヴァルの名前にならない。それなのに、ルヴァルは満足気にエレナを見つめて、
「上出来」
とエレナの黒髪を撫でながら褒めた。
最近のルヴァル様は私を甘やかし過ぎではないかしら? とエレナは両手で頬を押さえる。
そんな彼女を見てクスッと笑ったルヴァルは、
「ルは出るならルルって呼べばいい。様も敬語もいらない」
と優しい口調でそう言った。
「そ、ん」
そんなわけには、と目で訴える彼女の紫水晶を覗き、
「俺がいいって言えばいいんだよ。ここで一番偉いのは俺だからな」
お願いと命令どっちがいい? とルヴァルが揶揄うような口調でエレナに迫る。
うぅっと少し悩んだエレナは、どちらにしても答えはハイかイエスしかないじゃないと観念して小さく頷いた。
「……レナ」
ルヴァルの口から溢れた音を耳で拾ったエレナは、
「え?」
驚いて聞き返す。
「音が足らずに気になるなら、俺も一音削ろうかと思って」
つまり、これからは愛称で呼ぶと言う事らしいと理解し、エレナはマジマジとルヴァルを見返す。
「嫌か?」
尋ねられたエレナはブンブンと首を振る。その呼び方は今はもういない母や祖父が、自分を甘やかす時に呼んでくれた愛称だ。
もう、誰にも呼ばれる事がないと思っていたレナという愛称。
それを他の誰でもないルヴァルが呼ぶと言う。
「レナ」
自分を呼ぶその声が、音の響きが優しくて、甘くて、エレナは泣きそうになる。
「ル……ル」
ルヴァルに対してどんどん"好き"が積み重なっていくのに、いつかこの場所を失ってしまう日が来るかもしれないのが怖くて。
「どうした?」
俯いたエレナの頭上に淡々とした口調のルヴァルの声が降ってくる。
「なつ、かし……て。も、誰も……そんな……よ、びかた」
エレナの言葉を最後まで聞かず、ルヴァルはエレナを引き寄せ抱きしめる。
「レナ。これからは俺が何回でも呼ぶ」
ルヴァルはまだか細いその肩を抱きながら、エレナを大事にしたいと強く思う。
「……っ」
エレナは抱きしめられたままコクリと頷くと紫水晶の瞳から静かに雫が溢れ落ちる。
(力が欲しい。彼の隣に立てる力が)
自分の中にある願望に、エレナははっきりと気づく。
もし、自分にルヴァルの隣に立てるだけの"何か"があるのなら、この場所を誰にも明け渡さずに済む。
エレナは目を閉じて、
(ルルの憂いは私が祓う)
そう誓う。それは、エレナが戦うことを選んだ瞬間だった。
と冷静さを取り戻したエレナはスケッチブックに文字を綴る。
「用は特にないんだが、ピアノの音がしたのが懐かしくてな」
ばーさんの道楽ピアノはまだ生きていたんだなと、ルヴァルは懐かしそうに鍵盤に触れる。
『勝手をして申し訳ありません』
ハーマンからもリーファからもご自由にと言われたから好意に甘えてしまったが、よく考えたらルヴァル本人に直接ピアノに触れる許可を取っていなかったとエレナは慌てて謝罪する。
「構わない。城の隅っこで埃を被っているくらいなら、演奏者がいた方がコレもばーさんも喜ぶだろう」
ルヴァルは咎めることもなく、好きにすればいいと軽く許可を出す。
"ばーさん"と懐かし気に祖母の事を口にするルヴァルの横顔がどこか優しげで、彼にとって大事な人であったのだろうと分かる。
『大切な方なのですね』
「まぁ、母親代わりだったからな」
母親代わり、と聞いてエレナは紫水晶の瞳を大きく見開く。
「そんな顔をするな。ここでは誰かがいなくなるのも日常だ」
ルヴァルはエレナの頭をポンと撫で、
「確かに母の事など俺は覚えてないが、父が言うには赤子を抱えて一人で街一つ護って戦えるカッコいい女なんだと。俺は母に似ているらしくてな、それはもう何百回と耳にタコができるほど母親について聞かされて育ったから、尊敬はしている。まぁ、今頃あの世で2人仲良くやってるだろうさ」
と彼にしては珍しく長話をしてくれた。
『お祖母様は、どんな方だったのですか?』
「ん? 俺のばーさんか? すっげぇー礼儀作法に厳しい、偏屈ババア」
礼儀作法に厳しい、と言う割にルヴァルはだいぶおおらかというか言動に若干、かなり問題がある上に自由が過ぎる気がするのだが、確かに食事の所作などはかなり美しく頷ける面もある。
「修行と称して俺を谷底に突き落としたり、雪山にナイフ一本で放り込んだり。ちょっとしたイタズラで機関銃ぶっ放して追いかけられたりな」
礼儀作法とは一体、という疑問がエレナの頭をよぎったがルヴァルがどこか楽し気に祖母との思い出を語るので、
『よくご無事でしたね』
文化が違えばまぁそんな事もあるのだろうとエレナはスルーする事にした。
「まぁ、ガキの頃から強かったからな」
謙遜しないルヴァルにエレナはクスクスと笑って、
『せっかくなので、どれか弾きましょうか?』
と楽譜を見せる。
「俺は楽譜は読めん。から任せる」
コクリと頷いたエレナは、一番古く何度も開いた跡のついている曲を選びピアノを奏でる。それはとても短い曲で切ない旋律を響かせた。
「綺麗な曲だな」
『聴き覚えはないのですか?』
「あるのかもしれないが、忘れたな。ばーさんが全盛期でピアノの演奏会やってたらしい時期、俺は諸事情でここには居なかったし」
ルヴァルは遠くを見つめてぽつりと漏らす。ルヴァルは祖母から突然王都行きを命じられ、王城で暮らしながら騎士団長にしごかれていた時期を思い出す。
もうおそらくあの頃には祖母の身体には病魔が巣くっていたのだろう。
自分では、強過ぎる魔力を持って生まれてきた孫に稽古の一つもつけてやれないほどに。
黙ってしまったルヴァルの精悍な顔を見つめたエレナはゆっくりと息を吸い込むと、
「〜〜〜----♪」
静かに旋律を紡ぎ出す。
それは先程エレナが演奏した曲で、異国の言葉でエレナから紡がれるその歌をルヴァルは静かに聞き入った。
『どうか、どうか、無事でいて。あなたの帰りを待っているから。そんな願いが込められた歌なんですよ』
エレナは開き切った楽譜のページをそっと大切そうに撫でる。
きっとルヴァルの祖母は彼の無事を祈ってこの曲を聴いていたのではないだろうか? そんな事を考えながら。
エレナの書いた文字を辿ったルヴァルは青灰色の目を細め、そうかと小さくつぶやいて、彼女の黒髪を優しく撫でた。
「エレナは歌っている時が一番楽しそうだな」
エレナはコクンと頷くと、
「……すき、な……の」
ゆっくりと自分の気持ちを声に出す。
「……エレナ」
ルヴァルはエレナの口から出た"好き"と言う単語と笑みに驚き目を瞬かせる。
「歌、が」
やっと取り返した自分の『好きな事』
エレナは楽譜を握りしめて、幸せそうに笑う。
「歌。うん、歌が好き、な。知ってた」
ふいっと視線を逸らし、ルヴァルはそう繰り返す。
そんなルヴァルを見て首を傾げたエレナはやっぱりまだ聞き取り辛いわよねと喉に手を当てる。
ソフィアのリハビリは受けているが、まだまだ筆談が続きそうだとスケッチブックを引き寄せた。
「エレナは、子どもの時からこうなのか?」
わざとらしく咳をして仕切り直したルヴァルはエレナにそう尋ねる。
こう、とは? と首を傾げるエレナを見て、
「歌が楽しいのは」
ルヴァルは言葉を足す。
エレナはコクンと頷いて、
『幼い時は、ただ楽しかったです。カナリアとしての義務もなかったし。好きに歌えたから』
それはまだ母が生きていた時の話。
カナリアである彼女の後ろをついてまわり、音を耳で学んでいった。
『お母様に付いて王城に出入りしていた事もあるのですよ』
南部のサザンドラ子爵家から年に数度、王都に向かい王城で歌っていた母の姿を思い出す。
『お母様のお仕事中にこっそり抜け出して、庭園に入り込んだりして』
楽しかった記憶が自分の中にもちゃんとあったのだと思い出したエレナは幸せそうに笑う。
記憶を辿っていったエレナは、ふと庭園の隅で出会った黒髪の少年の事を思い出す。
傷だらけで、膝を抱えていた騎士訓練生の制服を纏っていたその人は、不機嫌そうなのになんだか泣き出しそうな目をしていた。
「げんき、かな」
「どうした?」
『いえ、ただふと王城で出会った黒髪の騎士見習いの子を思い出しまして』
文字を綴ったエレナはふふっと楽し気に笑う。
黒髪の騎士見習いと聞いてルヴァルは驚いたようにエレナを見つめ、
「……そいつが、どうかしたのか?」
と静かに尋ねる。
『楽しかったなって。不機嫌そうな顔をしていたのに結構世話焼きで、後ろを追いかけて迷子になりかけた私を探しに戻ってきてくれたりして』
エレナは懐かしそうに目を細め、彼の事を思い出す。仕方なさそうに手を差し伸べて王城を案内してくれた面倒見のいい少し年上のお兄さん。
「歌、たくさん……歌った……です」
まだカナリアとしての能力が発現したばかりで、非公式に力を使ったあの日。彼だけのために歌を紡いだ。
怪我をしませんように。
魔力が暴走することがありませんように。
強くと願う彼が、誰かを守れるようになれますように。
そんな祈りを込めて。
「泣いて、ない、と……い、いな」
もう随分と時間を経た今ではきっと彼は立派な騎士になっている事だろう。
そんな黒髪の騎士を想像したエレナは、彼が怪我をせずに済めばいいなと思いを馳せる。
「……泣いてねぇよ」
ぽつりと小さくつぶやいた声はエレナが拾うには充分な声量で、不思議そうに自分を見返すエレナの頭をルヴァルは乱暴に撫でた。
「……???」
ルヴァルはじっとエレナの紫水晶の瞳を覗き込む。髪色を変えて身分を隠していたのだから当然なのだが、疑問符を浮かべるエレナがあの時の騎士見習いが目の前にいると気づいた様子はない。
初めて領地を出て放り込まれた王城での生活はルヴァルにとって"楽しいもの"とは言い難かった。訓練自体は大した事はないが、その才は常に人を引き寄せ悪意と害意と嫉妬に晒された。
そんな中で出会ったエレナと過ごしたわずかな時間は、ルヴァルが王城で過ごした日々で唯一色づいた記憶だった。
その時間を共有したエレナが"楽しかった"といい、記憶に留めてくれている。
おそらくあまり幸せだったとは言い難い彼女の人生の中で、楽しいと感じた瞬間の中に自分がいるのだと思うと、不意にルヴァルはエレナを抱きしめたくなった。
(この気持ちは、なんて言うんだろうな)
エレナの気持ちなんて置き去りで、バーレーに連れて来て形だけの妻にした。それなのに身勝手なのは十分承知で、エレナを手放したくないと思う。
ルヴァルはエレナの黒髪をそっと掬ってそこに口付けを落とす。
流れるようなその動作をただ見ていたエレナは、自身の心臓が破裂しそうなくらい早くなるのを聞きながら、ルヴァルの青灰の瞳を見つめる。
「ル……あ、の」
「俺の名前、呼ばないのか?」
じっと見つめられたエレナは頬に熱が集まるのを感じながら、
「まだ……うまく」
出ない音があるのだとしどろもどろに口にする。
「いいから」
気にする様子のないルヴァルはとても優しい声で続きを促す。
「ル……ァル、さ、ま」
やはりまだ中一音が掠れて上手く発音できず、ルヴァルの名前にならない。それなのに、ルヴァルは満足気にエレナを見つめて、
「上出来」
とエレナの黒髪を撫でながら褒めた。
最近のルヴァル様は私を甘やかし過ぎではないかしら? とエレナは両手で頬を押さえる。
そんな彼女を見てクスッと笑ったルヴァルは、
「ルは出るならルルって呼べばいい。様も敬語もいらない」
と優しい口調でそう言った。
「そ、ん」
そんなわけには、と目で訴える彼女の紫水晶を覗き、
「俺がいいって言えばいいんだよ。ここで一番偉いのは俺だからな」
お願いと命令どっちがいい? とルヴァルが揶揄うような口調でエレナに迫る。
うぅっと少し悩んだエレナは、どちらにしても答えはハイかイエスしかないじゃないと観念して小さく頷いた。
「……レナ」
ルヴァルの口から溢れた音を耳で拾ったエレナは、
「え?」
驚いて聞き返す。
「音が足らずに気になるなら、俺も一音削ろうかと思って」
つまり、これからは愛称で呼ぶと言う事らしいと理解し、エレナはマジマジとルヴァルを見返す。
「嫌か?」
尋ねられたエレナはブンブンと首を振る。その呼び方は今はもういない母や祖父が、自分を甘やかす時に呼んでくれた愛称だ。
もう、誰にも呼ばれる事がないと思っていたレナという愛称。
それを他の誰でもないルヴァルが呼ぶと言う。
「レナ」
自分を呼ぶその声が、音の響きが優しくて、甘くて、エレナは泣きそうになる。
「ル……ル」
ルヴァルに対してどんどん"好き"が積み重なっていくのに、いつかこの場所を失ってしまう日が来るかもしれないのが怖くて。
「どうした?」
俯いたエレナの頭上に淡々とした口調のルヴァルの声が降ってくる。
「なつ、かし……て。も、誰も……そんな……よ、びかた」
エレナの言葉を最後まで聞かず、ルヴァルはエレナを引き寄せ抱きしめる。
「レナ。これからは俺が何回でも呼ぶ」
ルヴァルはまだか細いその肩を抱きながら、エレナを大事にしたいと強く思う。
「……っ」
エレナは抱きしめられたままコクリと頷くと紫水晶の瞳から静かに雫が溢れ落ちる。
(力が欲しい。彼の隣に立てる力が)
自分の中にある願望に、エレナははっきりと気づく。
もし、自分にルヴァルの隣に立てるだけの"何か"があるのなら、この場所を誰にも明け渡さずに済む。
エレナは目を閉じて、
(ルルの憂いは私が祓う)
そう誓う。それは、エレナが戦うことを選んだ瞬間だった。