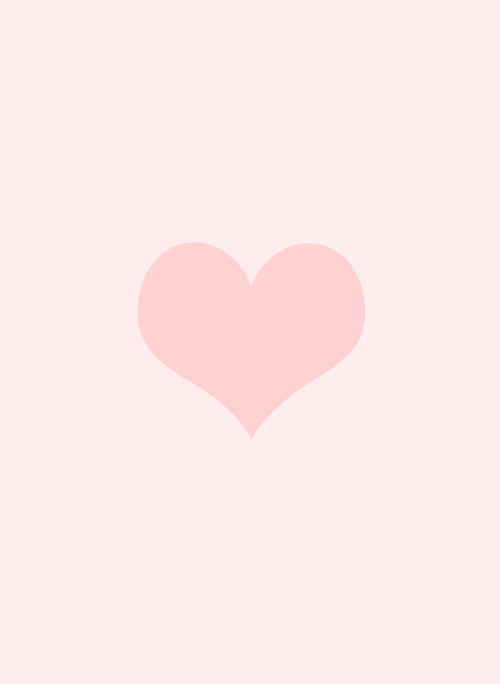その後リーファは一人の錬金術師を連れて来た。
エレナは目の前の光景に驚き、紫水晶の目を瞬かせる。
「だぁーからぁ! 俺は忙しいって何回いやぁー分かるんだよ。この怪力破壊魔がぁぁぁーーー!」
シャーっとまるで猫のように威嚇する若草色の髪をした背の低い青年は、とても嫌そうな顔をしてリーファに抵抗する。
だが、リーファは一切気にせず彼の首根っこを掴んだまま、
「エレナ様、ご所望の錬金術師を1匹捕まえて来ました」
まるで狩ってきたうさぎでも見せるかのように満面の笑顔でそう言った。
『リーファ、乱暴はやめて』
とエレナが止めに入り、リーファから解放された彼、ノクス・ロットと名乗ったその錬金術師は明らかに機嫌が悪そうだった。
「じゃ、さっそくなんだけど、コレ直して」
ぐっと親指でピアノを指したリーファは雑にノクスに頼む。
「"じゃ"じゃねぇよ!"じゃ"じゃ。お前、まず俺に謝れや!!」
メガネ越しに黄色の瞳はリーファを睨む。
「毎度毎度いきなり、工房に殴り込んで来やがってぇぇぇ! 俺は便利屋じゃねぇんだよ!!」
不機嫌を隠さないノクスは拳を握りしめて、バンバンと机を叩きながら全力でそう訴える。
「えー似たようなモノでしょ? さっとパッと終わらせて戻れば好きなだけ実験できるじゃない」
「なんで毎度毎度俺なんだよ! もっといるだろ!! 他に暇な奴がぁ!!」
毎度毎度猫みたいに首根っこ掴まえやがってと騒がしく叫ぶノクスに対し、
「いや、だってノクスが一番腕いいし」
リーファは肩を竦めてサラッとそう言う。
「私の足もだけど、ノクスに造れないものなんてないじゃない。発想力も創造力も未知を探求する好奇心も誰もあなたには敵わない」
紅玉の瞳は真っ直ぐに黄色の瞳を捉え、ただただ事実を述べていく。
「お、おぅ。当たり前だ、俺様は天才だからな」
急に褒められたノクスは毒気を抜かれたように勢いを失くす。
「頼まれてよ、私の大事なお嬢様が使うピアノなの。適当な相手には任せられない」
真剣に自分を見つめる紅玉の瞳にたじろぎ、息を飲んだノクスは乱暴に自分の若草色の頭を掻いたあとチッと舌打ちをして、
「しゃぁーねぇな。俺様超ーーいい奴」
視線を逸らし、渋々っと言った感じで引き受けた。
「さっすがノクス! チョロさも城内イチ」
ぐっと親指を立てたリーファを見て、
「お前、マジでしばくぞ」
褒めるならキッチリ最後まで褒めろよ!! と吠えたノクスはその後文句を言いながらもあっという間にピアノを調整してくれた。
あれ以来ノクスはふらっとやってきてはピアノの調子を見てくれ、リーファとじゃれ合いのような掛け合いをしていく。
初めは過激なやり取りに驚いたが、今ではすっかり慣れてしまった。
本当に2人は仲がいいのだなと普段のやり取りを思い出し、エレナはクスリと笑みを浮かべる。
(私も、ルヴァル様とあんな風になれたらいいのになぁ)
お飾り妻がそんな事を思うなんて、烏滸がましいにも程がある。それでも、自覚してしまった感情は自分の意思とは関係なく育つのだ。
ルヴァルの顔を思い浮かべながら紡いだ最後の一音が部屋に響き、エレナは一曲目を終えた。
その後も何曲かエレナは演奏しながら歌を奏でる。
それは歌を学び始めた頃の純粋に楽しかった記憶を思い出すような心地よい時間で、勝手気ままに好きなだけ音を楽しんだ。
休憩、と一息ついたエレナは自分の喉をそっと撫でる。
(歌う時と同じくらい、声が出ればいいのに)
全く声のでなかった少し前とは違い、今は少しずつ自分の中に音を取り戻しつつある。
それでも壊れた楽器のようにまだ出せない音がいくつもあって、特に相手がいる『会話』だと思うとどうにも上手く声を出せない。
エレナはソフィアから出された課題を思い出しため息をついて膝を抱える。
『お休みの間にエレナ様にとって"好きな人"の名前が1人言えるようになってください。できたらレッスンを再開しましょう』
好きな人のワードに思いっきり反応してしまった自分とニヤニヤと意地悪気に見つめてくる藍色の瞳を思い出し、エレナは両手で顔を覆う。
こんな時こそ長年鍛えられた無表情を貫ければ良かったのに、バーレーに来てから色んな人に笑いかけられながら日々を過ごすうち、いつの間にか感情を表に出すのが当たり前に変わっていった。
それはとても幸せなことなのだとエレナは思う。
(でも、結構な人数に筒抜けなのはどうかと思う)
正直暖かく見守られているのが居た堪れなくて、そして切ない。多分、この思いが叶う日は来ないだろうから。
ルヴァルは何らかの目的があって自分を側に置いているのだということは理解している。そして、妻として求められていないことも。
いつかルヴァルに愛する人ができたなら、そのときはこの席を潔く開け渡さなくてはならないとエレナは自分に言い聞かせる。
"愛する人"
自分で勝手に想像して、エレナはきゅっと苦しくなった胸を押さえる。
エリオットの腕に自身の腕を絡めしだれかかっていたマリナ。2人が並び愛し合っているのだと実際に目にしたあの光景の何十倍も胸が締め付けられるような苦しさで、息が止まりそうだった。
(エリオット様に婚約破棄された時は簡単に諦められたのに想像だけで泣けるわ。私、本当にルヴァル様の事が)
好き、なのだ。
そんな風に思える相手に出会えた事も、一時とはいえ"嫁"だなんて言ってもらえる立場にいられるだけでも、きっと自分は運がいい。
(課題、だもの)
自分に言い訳をしながらエレナは、小さな声でそっとその名を口にする。
「ル……ル、さ……ま」
まだ一音出せなくて、キチンと彼を呼べない。このままでは、レッスンの再開はまだ先になりそうだ、とエレナは小さくため息をつく。
「エレナは何をそんなに悩んでいるんだ?」
「〜〜〜----っ!!?」
驚き過ぎて声にならない叫びと共にビクッと肩を震わせたエレナは、ぎこちない動作で声のした方に目を向ける。
「部屋を訪ねる時は随分前から分かっているようなのに、一体何にそんなに驚く」
くくっとおかしそうに喉を震わせたルヴァルと目が合い、エレナは口を開くが声は出ない。
(もしかしたら来るかもって意識を傾けてないのに、足音なんて聞こえないわよ)
そう抗議をしようとして、これでは常に聞き耳を立てている変質者みたいじゃないかと思い直したエレナは、せめて自身の顔が赤くなっていない事を祈りつつ両手で顔を覆った。
エレナは目の前の光景に驚き、紫水晶の目を瞬かせる。
「だぁーからぁ! 俺は忙しいって何回いやぁー分かるんだよ。この怪力破壊魔がぁぁぁーーー!」
シャーっとまるで猫のように威嚇する若草色の髪をした背の低い青年は、とても嫌そうな顔をしてリーファに抵抗する。
だが、リーファは一切気にせず彼の首根っこを掴んだまま、
「エレナ様、ご所望の錬金術師を1匹捕まえて来ました」
まるで狩ってきたうさぎでも見せるかのように満面の笑顔でそう言った。
『リーファ、乱暴はやめて』
とエレナが止めに入り、リーファから解放された彼、ノクス・ロットと名乗ったその錬金術師は明らかに機嫌が悪そうだった。
「じゃ、さっそくなんだけど、コレ直して」
ぐっと親指でピアノを指したリーファは雑にノクスに頼む。
「"じゃ"じゃねぇよ!"じゃ"じゃ。お前、まず俺に謝れや!!」
メガネ越しに黄色の瞳はリーファを睨む。
「毎度毎度いきなり、工房に殴り込んで来やがってぇぇぇ! 俺は便利屋じゃねぇんだよ!!」
不機嫌を隠さないノクスは拳を握りしめて、バンバンと机を叩きながら全力でそう訴える。
「えー似たようなモノでしょ? さっとパッと終わらせて戻れば好きなだけ実験できるじゃない」
「なんで毎度毎度俺なんだよ! もっといるだろ!! 他に暇な奴がぁ!!」
毎度毎度猫みたいに首根っこ掴まえやがってと騒がしく叫ぶノクスに対し、
「いや、だってノクスが一番腕いいし」
リーファは肩を竦めてサラッとそう言う。
「私の足もだけど、ノクスに造れないものなんてないじゃない。発想力も創造力も未知を探求する好奇心も誰もあなたには敵わない」
紅玉の瞳は真っ直ぐに黄色の瞳を捉え、ただただ事実を述べていく。
「お、おぅ。当たり前だ、俺様は天才だからな」
急に褒められたノクスは毒気を抜かれたように勢いを失くす。
「頼まれてよ、私の大事なお嬢様が使うピアノなの。適当な相手には任せられない」
真剣に自分を見つめる紅玉の瞳にたじろぎ、息を飲んだノクスは乱暴に自分の若草色の頭を掻いたあとチッと舌打ちをして、
「しゃぁーねぇな。俺様超ーーいい奴」
視線を逸らし、渋々っと言った感じで引き受けた。
「さっすがノクス! チョロさも城内イチ」
ぐっと親指を立てたリーファを見て、
「お前、マジでしばくぞ」
褒めるならキッチリ最後まで褒めろよ!! と吠えたノクスはその後文句を言いながらもあっという間にピアノを調整してくれた。
あれ以来ノクスはふらっとやってきてはピアノの調子を見てくれ、リーファとじゃれ合いのような掛け合いをしていく。
初めは過激なやり取りに驚いたが、今ではすっかり慣れてしまった。
本当に2人は仲がいいのだなと普段のやり取りを思い出し、エレナはクスリと笑みを浮かべる。
(私も、ルヴァル様とあんな風になれたらいいのになぁ)
お飾り妻がそんな事を思うなんて、烏滸がましいにも程がある。それでも、自覚してしまった感情は自分の意思とは関係なく育つのだ。
ルヴァルの顔を思い浮かべながら紡いだ最後の一音が部屋に響き、エレナは一曲目を終えた。
その後も何曲かエレナは演奏しながら歌を奏でる。
それは歌を学び始めた頃の純粋に楽しかった記憶を思い出すような心地よい時間で、勝手気ままに好きなだけ音を楽しんだ。
休憩、と一息ついたエレナは自分の喉をそっと撫でる。
(歌う時と同じくらい、声が出ればいいのに)
全く声のでなかった少し前とは違い、今は少しずつ自分の中に音を取り戻しつつある。
それでも壊れた楽器のようにまだ出せない音がいくつもあって、特に相手がいる『会話』だと思うとどうにも上手く声を出せない。
エレナはソフィアから出された課題を思い出しため息をついて膝を抱える。
『お休みの間にエレナ様にとって"好きな人"の名前が1人言えるようになってください。できたらレッスンを再開しましょう』
好きな人のワードに思いっきり反応してしまった自分とニヤニヤと意地悪気に見つめてくる藍色の瞳を思い出し、エレナは両手で顔を覆う。
こんな時こそ長年鍛えられた無表情を貫ければ良かったのに、バーレーに来てから色んな人に笑いかけられながら日々を過ごすうち、いつの間にか感情を表に出すのが当たり前に変わっていった。
それはとても幸せなことなのだとエレナは思う。
(でも、結構な人数に筒抜けなのはどうかと思う)
正直暖かく見守られているのが居た堪れなくて、そして切ない。多分、この思いが叶う日は来ないだろうから。
ルヴァルは何らかの目的があって自分を側に置いているのだということは理解している。そして、妻として求められていないことも。
いつかルヴァルに愛する人ができたなら、そのときはこの席を潔く開け渡さなくてはならないとエレナは自分に言い聞かせる。
"愛する人"
自分で勝手に想像して、エレナはきゅっと苦しくなった胸を押さえる。
エリオットの腕に自身の腕を絡めしだれかかっていたマリナ。2人が並び愛し合っているのだと実際に目にしたあの光景の何十倍も胸が締め付けられるような苦しさで、息が止まりそうだった。
(エリオット様に婚約破棄された時は簡単に諦められたのに想像だけで泣けるわ。私、本当にルヴァル様の事が)
好き、なのだ。
そんな風に思える相手に出会えた事も、一時とはいえ"嫁"だなんて言ってもらえる立場にいられるだけでも、きっと自分は運がいい。
(課題、だもの)
自分に言い訳をしながらエレナは、小さな声でそっとその名を口にする。
「ル……ル、さ……ま」
まだ一音出せなくて、キチンと彼を呼べない。このままでは、レッスンの再開はまだ先になりそうだ、とエレナは小さくため息をつく。
「エレナは何をそんなに悩んでいるんだ?」
「〜〜〜----っ!!?」
驚き過ぎて声にならない叫びと共にビクッと肩を震わせたエレナは、ぎこちない動作で声のした方に目を向ける。
「部屋を訪ねる時は随分前から分かっているようなのに、一体何にそんなに驚く」
くくっとおかしそうに喉を震わせたルヴァルと目が合い、エレナは口を開くが声は出ない。
(もしかしたら来るかもって意識を傾けてないのに、足音なんて聞こえないわよ)
そう抗議をしようとして、これでは常に聞き耳を立てている変質者みたいじゃないかと思い直したエレナは、せめて自身の顔が赤くなっていない事を祈りつつ両手で顔を覆った。