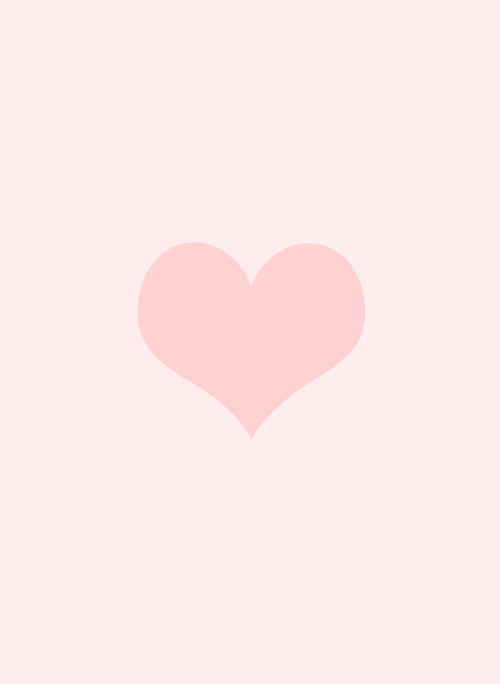崖のすぐそばにドラゴンの小屋が建てられているのは、ここからすぐ飛び立てるようにしているからなのだと居住スペースの奥の壁が開け放たれた事でエレナは理解する。
「行けるな」
ルヴァルに応えるように一声鳴いたドラゴンは谷底から噴き上げる風を掴み一気に上空まで飛んだ。
(うわぁ!)
初めての飛行に感動したようにエレナは上空から地上を見下ろす。
普段自分の部屋のある棟以外からはほとんど出ないエレナは、この地に来てようやくこの城とその城下にある街の全貌を目にした。
要塞都市という名に相応しく堅固な城壁でぐるりと囲われた領地。その中にこの城とそして城から少し離れた場所に街がある。
遠くに見える山は夏季だというのに白い雪を被せており、上空にはひんやりとした空気が漂う。
「ここは見た通りもともとが要塞。そこに街ができた場所だ。この城を拠点として、魔物の討伐や紛争調停に出向いている。あの街にいるのは城内に勤めている人間の家族がほとんどだ」
ルヴァルはエレナが落ちる事がないようしっかり支えながら、バーレーについて説明する。
「領地自体は広くて、ここから離れた場所は特殊な魔物避けによる結界の設置と兵を常駐させている以外は他領とそう変わらない」
そこには当たり前に人の営みがあり、魔物に脅かされる事なく平和を享受できているようだった。
「諍いが起きるのはこのバーレーから東西に伸びた国境線付近。魔物が暴れれば俺たちは昼夜問わず行かなくてはならない」
淡々とした口調で語るルヴァルの声に耳を傾けながらエレナはバーレーからそう遠くない国境線を見つめる。
「皇室には服従で、国防の要。見返りとして特区としての運営が認められるくらい危険の多い場所だ。俺は使える人間なら経歴は問わない。まぁ、だからうちには多少荒っぽい人間や訳ありも多い」
訳ありと聞いてエレナは身を硬くする。
そんなエレナの雰囲気を察したようにルヴァルは笑う。
「そう身構えるな。カナリアの力を失った事は経緯も含めて知っている」
エレナはその声を聞きながら、どこか遠くを見つめる。
魔物と対峙して怖かったこと。
それでもエリオットを守らなければと力の限り歌い続けたこと。
魔物の消失と同時にプツッと何かが切れる音が聞こえ、自分の中の魔力すら感じ取れなくなったときのこと。
病室で目覚めたとき、エリオットが生きていると知って嬉しかったこと。
そのことがずっと彼を苦しめてしまう原因になって心苦しかったこと。
沢山の感情を伴って、エレナの中でポツリポツリと記憶が浮かぶ。
「利用して欲しい、と言ったな。もう、利用している」
ルヴァルの声で現実に引き戻されたエレナは、じっと彼の声に耳を傾ける。
「俺は、俺の都合でエレナを迎え入れた。だから、お前が受け取るものに対して恩を感じる必要もなければ、引け目を感じる必要もない」
神獣と契約したなんて突破な話、詳細を語れるはずもないのだが、少しでもエレナが今の状況に居心地の悪さを感じずに済めばいい。そんな思いでルヴァルは言葉を紡ぐ。
「奪うだけの人生だった」
それはどこか懺悔にも似た響きを持っていた。
「きっと、俺には何かを与えることはできないのだろう」
人生をやり直す機会をもらったとしても、結局自分本位に動く自分は、奪う人生を繰り返す。
「玉座に一番近い悪友には敵が多くてな。だから俺は、この場所をなんとしても死守しなくてはならない」
玉座に一番近い、と聞いてエレナは王太子の姿を思い出す。カナリアとして役目を果たす際、遠目で見た事があるその人は、圧倒的支配者に見えた。
「でなければ、国が揺らぐ。一番に被害を受けるのはこの領地だ。ここに生きる誰もが地獄を見ることになる。アルヴィン辺境伯を信じ、ここに根付いた全員が」
そうさせるわけにはいかない。だから、反逆の芽は自らの手で絶つしかないのだ。
それが、長年苦楽を共にした親友と言える相手を自らの手で裁くことになるのだとしても。
「何が望みか、と聞いたな。俺は、悪夢を終わらせたいんだ」
そのためにお前を連れて来たとルヴァルは静かにエレナに告げる。
「復讐が無意味だなんて、それはきっと奪う側の言い分だ。奪うなら、奪われる覚悟を持たなくてはならないと俺は思う」
そして、奪われないために武器を取る。諍いはどちらかが絶えるまで、終わらない。
「俺に譲れないモノがあるように、あちらにも言い分があるのだろう。だから、俺は選ばなくてはならない」
奪う側でも、奪われる側でも、対峙した瞬間互いに地獄を見ることになるのは分かっている。
それでも、自分を背後から刺した時の後悔と苦悩に滲んだ彼の目が忘れられない。
裏切ると分かっている相手に対して甘過ぎる考えなのかもしれない。それでも今こうして共にいるとどうしても思ってしまうのだ。
違う未来はなかったのか、と。
「変革は、エレナだけがもたらせる。俺は、それに期待している」
この繰り返しの時間はエレナを救うために神獣がもたらしたものなのだから、彼女がここにいる事で変わりはしないだろうかと望んでしまう。
そんな事、エレナには知ったことではないだろうけれど。
「エレナの都合も、エレナの気持ちも、全て考慮する事もなく、完全に俺の事情だけを押し付けて今お前はここにいる」
エレナの肩書を妻としたのも、それが迎え入れるのに一番手間がかからなかったからに他ならない。
「だから、エレナに妻としての役割を求めたり、何かを無理強いする気はない。その点は安心していい」
先程ドラゴンに向けていたエレナの笑顔を思い出す。自然と溢れるように笑うその様は子どもの頃笑いかけてくれた笑顔そのままで。
自分には向ける事のないあんな優しげな顔で、本来の婚約者には笑いかけていたのだろうか? などと思ってしまった。
エレナとは本来関わるはずのない人生だった。慕っている人がいたはずのエレナ。南部に置いておく事ができなかったとはいえ、肩書を妻にしたところで彼女が自分のモノになるわけもない。
なのに、今自分の中にある寂寥感はなんなのか。ルヴァル自身にも説明ができない。
「エレナの役割、は俺にもよくわからない」
ここにいていい理由が欲しいとエレナは言った。
だが、エレナが死なないために何を回避すればいいのか、まだ判断できない現状では今すぐ明確な役目を言い渡すことはルヴァルにはできない。
だが、ふと頭を掠めたのは、
『じゃあ、元気が出るように特別に歌ってあげます!』
と少し得意げに笑いながら言った紫水晶の瞳と心地良く耳に響くエレナの声。
「声が出るようになって気が向いたらまた歌を聞かせてくれ」
元々この地ではカナリアの力を必要としていないからとルヴァルはそう言って言葉を締めくくった。
静かにルヴァルの話を聞いていたエレナは、目を閉じてここに来てからの日々を思う。
(そう、かしら?)
エレナはルヴァルの言葉に首を傾げる。
(ルヴァル様は、本当に"奪う"だけかしら?)
もし、本当に彼がそんな人であったなら、きっとルヴァルの周りには彼を慕う人間など居ないのではないかと思う。
(与える事ができない人が、こんなにも私を気にかけられるわけがないわ)
ルヴァルは自分の都合だけを押し付けていると言ったけれど、エレナは自分の都合だけを主張して、他人の事など構う事なく振り回し、当たり前に搾取していく人間達がどんなモノであるかを知っている。
少なくとも、エレナの基準でいけばルヴァルはそれに該当しない。
(ここに来て、私は久しぶりに息ができている気がする。それをくれたのは紛れもなく、ルヴァル様だわ)
そしてエレナは思う。この人に必要とされたい、と。
ルヴァルの話す内容は全てが腑に落ちるものではなかったけれど。
(ルヴァル様にとっての悪夢って、何なのかしら?)
今きっとそれを聞いたところでルヴァルは詳細を話してはくれないだろう。
まるでこれから先良くない事が起きると知っているかのような口ぶりと時折ルヴァルの声に寂しさと悲しみ、孤独の混じった音の響きを感じたエレナは胸の奥が締め付けられるような思いで急に泣きたくなる。
(音に共鳴するなんて、久しぶりね)
ルヴァルは一体何を抱えているのだろう?
エレナは込み上げてくる衝動がわからないまま、ただルヴァルの心に触れたくなる。
(カナリアの力がない私が歌った所で、癒す事はできないけれど)
それでも、少しでもルヴァルが抱える痛みを和らげる事ができたらいいのにと思う。
『ねぇ、エレナ。歌を紡ぐ時に大事なモノってなんだと思う?』
不意に母エリアナの言葉を思い出す。
『歌姫はね、心に湧き上がってくる感情を身体に巡らせて音を紡ぐの』
何のために、歌いたい?
誰のために、歌いたい?
そんな事を考えなくても、カナリアとして魔法を込める事はできた。
そして、何の問題もなく求められた役目を果たす事ができていた。
『"音"の響きを楽しんで』
カナリアとは歌わずにはいられない生き物なのだから。
そう話す母はいつも楽しそうに歌っていた。あの気難しい父でさえ、その歌に聞き入る程に。
最後に歌う事が楽しいと思ったのはいつだろう?
エレナにとっていつしか歌うことはカナリアとしての"義務"でしかなくなっていた。
(私はもう、カナリアではないけれど)
気が向いたら歌って欲しいとルヴァルが望んでくれたから。
エレナは湧き上がる衝動のままに音を紡いでみたくなる。
何故か喉のつかえも痛みも今は不思議なほど感じない。
まだキチンとした言葉を乗せることは難しいけれど、音を繋げるだけならできるかもしれない。
そう思ったらもう止める事はできなかった。
「〜〜〜♪----♪」
それは、ただ本当にメロディを口ずさむだけの、詩のない歌。
静かな旋律のそれは、ただただ美しく空に響いていた。
「行けるな」
ルヴァルに応えるように一声鳴いたドラゴンは谷底から噴き上げる風を掴み一気に上空まで飛んだ。
(うわぁ!)
初めての飛行に感動したようにエレナは上空から地上を見下ろす。
普段自分の部屋のある棟以外からはほとんど出ないエレナは、この地に来てようやくこの城とその城下にある街の全貌を目にした。
要塞都市という名に相応しく堅固な城壁でぐるりと囲われた領地。その中にこの城とそして城から少し離れた場所に街がある。
遠くに見える山は夏季だというのに白い雪を被せており、上空にはひんやりとした空気が漂う。
「ここは見た通りもともとが要塞。そこに街ができた場所だ。この城を拠点として、魔物の討伐や紛争調停に出向いている。あの街にいるのは城内に勤めている人間の家族がほとんどだ」
ルヴァルはエレナが落ちる事がないようしっかり支えながら、バーレーについて説明する。
「領地自体は広くて、ここから離れた場所は特殊な魔物避けによる結界の設置と兵を常駐させている以外は他領とそう変わらない」
そこには当たり前に人の営みがあり、魔物に脅かされる事なく平和を享受できているようだった。
「諍いが起きるのはこのバーレーから東西に伸びた国境線付近。魔物が暴れれば俺たちは昼夜問わず行かなくてはならない」
淡々とした口調で語るルヴァルの声に耳を傾けながらエレナはバーレーからそう遠くない国境線を見つめる。
「皇室には服従で、国防の要。見返りとして特区としての運営が認められるくらい危険の多い場所だ。俺は使える人間なら経歴は問わない。まぁ、だからうちには多少荒っぽい人間や訳ありも多い」
訳ありと聞いてエレナは身を硬くする。
そんなエレナの雰囲気を察したようにルヴァルは笑う。
「そう身構えるな。カナリアの力を失った事は経緯も含めて知っている」
エレナはその声を聞きながら、どこか遠くを見つめる。
魔物と対峙して怖かったこと。
それでもエリオットを守らなければと力の限り歌い続けたこと。
魔物の消失と同時にプツッと何かが切れる音が聞こえ、自分の中の魔力すら感じ取れなくなったときのこと。
病室で目覚めたとき、エリオットが生きていると知って嬉しかったこと。
そのことがずっと彼を苦しめてしまう原因になって心苦しかったこと。
沢山の感情を伴って、エレナの中でポツリポツリと記憶が浮かぶ。
「利用して欲しい、と言ったな。もう、利用している」
ルヴァルの声で現実に引き戻されたエレナは、じっと彼の声に耳を傾ける。
「俺は、俺の都合でエレナを迎え入れた。だから、お前が受け取るものに対して恩を感じる必要もなければ、引け目を感じる必要もない」
神獣と契約したなんて突破な話、詳細を語れるはずもないのだが、少しでもエレナが今の状況に居心地の悪さを感じずに済めばいい。そんな思いでルヴァルは言葉を紡ぐ。
「奪うだけの人生だった」
それはどこか懺悔にも似た響きを持っていた。
「きっと、俺には何かを与えることはできないのだろう」
人生をやり直す機会をもらったとしても、結局自分本位に動く自分は、奪う人生を繰り返す。
「玉座に一番近い悪友には敵が多くてな。だから俺は、この場所をなんとしても死守しなくてはならない」
玉座に一番近い、と聞いてエレナは王太子の姿を思い出す。カナリアとして役目を果たす際、遠目で見た事があるその人は、圧倒的支配者に見えた。
「でなければ、国が揺らぐ。一番に被害を受けるのはこの領地だ。ここに生きる誰もが地獄を見ることになる。アルヴィン辺境伯を信じ、ここに根付いた全員が」
そうさせるわけにはいかない。だから、反逆の芽は自らの手で絶つしかないのだ。
それが、長年苦楽を共にした親友と言える相手を自らの手で裁くことになるのだとしても。
「何が望みか、と聞いたな。俺は、悪夢を終わらせたいんだ」
そのためにお前を連れて来たとルヴァルは静かにエレナに告げる。
「復讐が無意味だなんて、それはきっと奪う側の言い分だ。奪うなら、奪われる覚悟を持たなくてはならないと俺は思う」
そして、奪われないために武器を取る。諍いはどちらかが絶えるまで、終わらない。
「俺に譲れないモノがあるように、あちらにも言い分があるのだろう。だから、俺は選ばなくてはならない」
奪う側でも、奪われる側でも、対峙した瞬間互いに地獄を見ることになるのは分かっている。
それでも、自分を背後から刺した時の後悔と苦悩に滲んだ彼の目が忘れられない。
裏切ると分かっている相手に対して甘過ぎる考えなのかもしれない。それでも今こうして共にいるとどうしても思ってしまうのだ。
違う未来はなかったのか、と。
「変革は、エレナだけがもたらせる。俺は、それに期待している」
この繰り返しの時間はエレナを救うために神獣がもたらしたものなのだから、彼女がここにいる事で変わりはしないだろうかと望んでしまう。
そんな事、エレナには知ったことではないだろうけれど。
「エレナの都合も、エレナの気持ちも、全て考慮する事もなく、完全に俺の事情だけを押し付けて今お前はここにいる」
エレナの肩書を妻としたのも、それが迎え入れるのに一番手間がかからなかったからに他ならない。
「だから、エレナに妻としての役割を求めたり、何かを無理強いする気はない。その点は安心していい」
先程ドラゴンに向けていたエレナの笑顔を思い出す。自然と溢れるように笑うその様は子どもの頃笑いかけてくれた笑顔そのままで。
自分には向ける事のないあんな優しげな顔で、本来の婚約者には笑いかけていたのだろうか? などと思ってしまった。
エレナとは本来関わるはずのない人生だった。慕っている人がいたはずのエレナ。南部に置いておく事ができなかったとはいえ、肩書を妻にしたところで彼女が自分のモノになるわけもない。
なのに、今自分の中にある寂寥感はなんなのか。ルヴァル自身にも説明ができない。
「エレナの役割、は俺にもよくわからない」
ここにいていい理由が欲しいとエレナは言った。
だが、エレナが死なないために何を回避すればいいのか、まだ判断できない現状では今すぐ明確な役目を言い渡すことはルヴァルにはできない。
だが、ふと頭を掠めたのは、
『じゃあ、元気が出るように特別に歌ってあげます!』
と少し得意げに笑いながら言った紫水晶の瞳と心地良く耳に響くエレナの声。
「声が出るようになって気が向いたらまた歌を聞かせてくれ」
元々この地ではカナリアの力を必要としていないからとルヴァルはそう言って言葉を締めくくった。
静かにルヴァルの話を聞いていたエレナは、目を閉じてここに来てからの日々を思う。
(そう、かしら?)
エレナはルヴァルの言葉に首を傾げる。
(ルヴァル様は、本当に"奪う"だけかしら?)
もし、本当に彼がそんな人であったなら、きっとルヴァルの周りには彼を慕う人間など居ないのではないかと思う。
(与える事ができない人が、こんなにも私を気にかけられるわけがないわ)
ルヴァルは自分の都合だけを押し付けていると言ったけれど、エレナは自分の都合だけを主張して、他人の事など構う事なく振り回し、当たり前に搾取していく人間達がどんなモノであるかを知っている。
少なくとも、エレナの基準でいけばルヴァルはそれに該当しない。
(ここに来て、私は久しぶりに息ができている気がする。それをくれたのは紛れもなく、ルヴァル様だわ)
そしてエレナは思う。この人に必要とされたい、と。
ルヴァルの話す内容は全てが腑に落ちるものではなかったけれど。
(ルヴァル様にとっての悪夢って、何なのかしら?)
今きっとそれを聞いたところでルヴァルは詳細を話してはくれないだろう。
まるでこれから先良くない事が起きると知っているかのような口ぶりと時折ルヴァルの声に寂しさと悲しみ、孤独の混じった音の響きを感じたエレナは胸の奥が締め付けられるような思いで急に泣きたくなる。
(音に共鳴するなんて、久しぶりね)
ルヴァルは一体何を抱えているのだろう?
エレナは込み上げてくる衝動がわからないまま、ただルヴァルの心に触れたくなる。
(カナリアの力がない私が歌った所で、癒す事はできないけれど)
それでも、少しでもルヴァルが抱える痛みを和らげる事ができたらいいのにと思う。
『ねぇ、エレナ。歌を紡ぐ時に大事なモノってなんだと思う?』
不意に母エリアナの言葉を思い出す。
『歌姫はね、心に湧き上がってくる感情を身体に巡らせて音を紡ぐの』
何のために、歌いたい?
誰のために、歌いたい?
そんな事を考えなくても、カナリアとして魔法を込める事はできた。
そして、何の問題もなく求められた役目を果たす事ができていた。
『"音"の響きを楽しんで』
カナリアとは歌わずにはいられない生き物なのだから。
そう話す母はいつも楽しそうに歌っていた。あの気難しい父でさえ、その歌に聞き入る程に。
最後に歌う事が楽しいと思ったのはいつだろう?
エレナにとっていつしか歌うことはカナリアとしての"義務"でしかなくなっていた。
(私はもう、カナリアではないけれど)
気が向いたら歌って欲しいとルヴァルが望んでくれたから。
エレナは湧き上がる衝動のままに音を紡いでみたくなる。
何故か喉のつかえも痛みも今は不思議なほど感じない。
まだキチンとした言葉を乗せることは難しいけれど、音を繋げるだけならできるかもしれない。
そう思ったらもう止める事はできなかった。
「〜〜〜♪----♪」
それは、ただ本当にメロディを口ずさむだけの、詩のない歌。
静かな旋律のそれは、ただただ美しく空に響いていた。