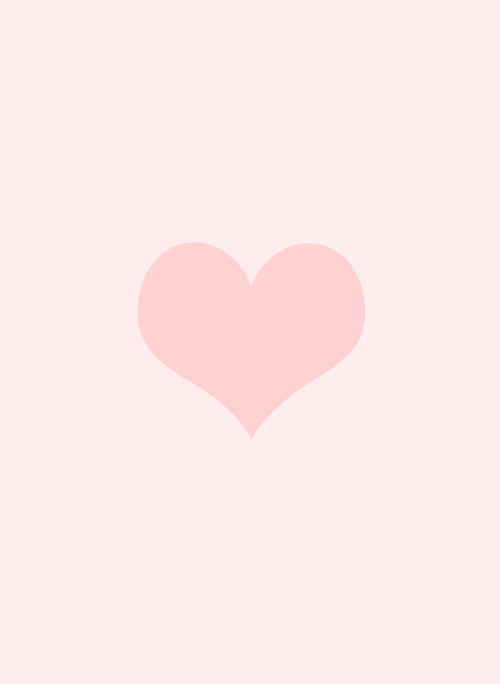部屋でのんびり本を読んで過ごしていたエレナが突然本を置き、じっとドアの方を見つめた。
「エレナ様、どうかしましたか?」
側でお茶の準備をしていたリーファが手を止め、エレナに声をかける。
エレナは少し考える素振りをして、リーファが準備しているカップを指さした後、指を2本立てた。
「えっと、2人分のご準備という事でしょうか?」
来客予定は聞いていないがと首を傾げつつリーファはエレナの行動をそう解釈し、尋ねる。
聞かれたエレナが静かに頷くので、疑問に思いながらもリーファがカップの数を増やした所で部屋にノックの音が響いた。
ノックをしたその人は入室の許可を部屋の住人が出すより早くドアを開ける。顔を覗かせたのはルヴァルだった。
「お館様、来られる時は事前にご連絡をくださいと」
何度も言っていると言いかけてリーファは手を止める。手元には既に2人分のお茶の準備が整っていた。
ルヴァルの前に立ったエレナは彼が来る事を承知していたかのように動じる事なくその前に立ち、優雅な動作でカーテシーを行う。
これで笑顔と口上が伴っていたなら、どこからどう見ても名門貴族のご令嬢のそれである。
エレナはルヴァルに命じられる前に顔を上げる。会う度に何度もそう畏まらなくていいとルヴァルに言われ続け、その通りにするようになったのはほんの数日前からだった。
「それでお館様。本日のご用向きはなんでしょうか?」
声が出せないエレナの代わりにリーファはルヴァルにそう尋ねる。
促されたルヴァルは、ああと小さく頷くとエレナに近づき、
「エレナ。口を開けろ」
短くそう言った。素直に従ったエレナの口に何かが放り込まれ、途端に口内に甘くて優しい味が広がり、ふわりと溶けてなくなった。
エレナは驚いたように目を瞬かせると、ルヴァルと彼が手に持つ箱に視線を向ける。
「気に入ったようだな」
それはほんの僅かな変化であったが、エレナが表情を崩したことを微笑ましげに見たルヴァルはクスッと笑い、
「やる」
とエレナに箱を差し出した。
エレナは驚いたようにルヴァルと箱を見てどうするべきなのか戸惑う。
「なんですか、それ?」
そんなエレナに助け船を出すようにリーファがルヴァルに尋ねた。
「卵を使った菓子」
これはちゃんとソフィアの許可を得ていると箱からひとつ摘んだルヴァルはリーファに見せる。
リーファは一口大のコロンと丸いお菓子を見て、
「わぁ、卵ボーロ。子どもの頃よく頂きました」
と懐かしそうに話した。
「卵は栄養価高いからな」
「子どものおやつって印象でしたけど、これなら確かにエレナ様が召し上がっても大丈夫ですね! 美味しいですし」
パチンと手を叩き嬉しそうに声を上げたリーファを見ながら、ルヴァルはエレナの口にボーロを入れる。
「これはエレナ用に作らせたからな。食べたかったら自分で注文しろよ」
エレナは素直にそれを食べながら、
(ルヴァル様は餌付けの趣味でもあるのかしら?)
などとエレナは首を傾げて考える。
お肉といいお菓子といい、ルヴァルは隙あらばとにかく自分に何かを食べさせようとする。
(でも、これはとっても美味しいわ)
あっという間に口の中でなくなってしまい、それが少し名残り惜しくてエレナはルヴァルが手に持つ箱に視線を向ける。
それに気づいたルヴァルは今度ははっきり分かるほど形のいい唇で弧を描き、ふっと笑う。
「エレナは甘い物が好きなんだな」
今までで一番反応がいいと言ってエレナの口にもう一つお菓子を入れた。
「肉はまた今度な。食べられるようになったら、熊でも猪でも鹿でも食わせてやる」
「なんでジビエばっかりなんですか!? お肉といえば牛と羊でしょう!!」
うちの名産を食べさせなくてどうしますとリーファが猛抗議をする。
「あー冬季限定じっくり煮込んだ子羊のシチューが食べたくなってきました。焼きたてのパンを添えて」
ローストビーフも捨てがたいとうっとりしながら語るリーファを見ながら、エレナは思わず小さく笑う。
「エレナ様! 冬までには絶対食べられるようになりましょうね!」
美味しいんですよと嬉しそうにそう言ったリーファにエレナは静かに頷いた。
ここに来て数日。
初夜に呼ばれることもなく、それ以外にも女主人としての仕事も妻らしい役割もルヴァルに求められることはない。
代わりに求められるのは食べる事だけで、そうして自分の反応を見るたびに彼はどことなく機嫌の良さそうな顔をする。
エレナにはそれがとても不思議で仕方なかった。
「とにかく食え。で、体力つけろ」
「そうですねぇ。何をするにも身体が基本ですし。食べて運動することが身体作りには大事ですし。エレナ様、後でお散歩でもしましょうか?」
(ここの人達は、みんな優しい)
そして、それがエレナには少し怖かった。
今までの実家での生活で自分に与えられて来たのは、蔑む視線と絶え間ない嫌がらせの数々で。
優しい言葉をくれるエリオットでさえ、
『子爵達を刺激して、エレナがもっと酷い目に遭う事があっては大変だから、今は耐えて欲しい』
と困った顔をするだけだったのに。
(カナリアでなくなった私は、ここの人達に何も返せないのに。そんな私が受け取ってしまってもいいの?)
きゅっと下を向きそうになったエレナに、
「まぁ、とにかくこれは髪紐の礼だ」
とルヴァルは銀糸を結える濃紺の紐をエレナに見せる。
それはエレナが編んだもので、感謝を記した手紙につけてルヴァルに届けてもらったものだった。
「綺麗な色だ。気に入った」
そう言われたエレナは紫水晶の瞳を大きく見開く。
ルヴァルの言葉は飾り気がなくて、言葉数は少ないかもしれない。
でも優しいだけの言葉の数々よりもずっと真っ直ぐ自分の中に落ちて来て、胸に詰まって何が込み上げる。
「これは確か南部では相手の無事を祈る物だったな。感謝する。ありがとう」
ルヴァルの言葉を耳が拾った瞬間、エレナの中で感情が溢れて、頬を涙が伝った。
「……エレナ?」
誰かになんの躊躇いもなく"ありがとう"なんて言われたのは、どれくらいぶりだろうか?
(これは、違うの!)
そう言い訳をしたくても、声の出ないエレナは言葉を紡ぐことができない。
せめて、早く涙を止めなければ。
そう思うのに、一度零れた感情はとめどなく溢れて来て、涙となってエレナの頬濡らす。
エレナはずっとサザンドラ子爵家の後継者が些細な事で泣くなどみっともないと叱責され、感情を表に出すなと言われ続けてきた。
(早く、泣き止まなきゃ……困らせてしまう、のに)
そうでなくとも感情のままに反抗し泣き叫べば、義母と異母妹を喜ばせるだけで。
だからもう、人前で泣くまいと決めていたのに。
苦しくて、苦しくて、苦しくて。
だけどいくら泣いたって現実は何一つ変わらなくて。
エリオットに婚約破棄を告げられたあの日でさえ、泣く事はなかったのに。
「……っ、ぅ……」
エレナから声にならない嗚咽が漏れる。
(突然泣き出すなんて、きっとみっともないと呆れられてしまうわ)
だけど止めなければと思うほど、今まで見ないようにしていた沢山の感情が混ざり合って、収拾がつかなくなる。
「好きにすればいい」
そんなエレナを前にして、ルヴァルは淡々とした口調でそう言った。
俯き目を擦るエレナの頭にルヴァルの大きな手が乗る。
「俺が許すのだから、エレナを咎められる者はここにはいない」
ポンポンと軽く頭を撫でながらルヴァルの言葉が落ちてくる。
「この領地で一番偉い俺に逆らう人間などいないのだからな」
何故泣いているのかと尋ねるのでも、優しく慰めるのでもない。
ルヴァルのその物言いは、とても尊大で受け取る人間によっては傲慢にさえ聞こえてしまうかもしれない。
(私は、こんなに優しい人を他に知らない)
だけど、エレナにはルヴァルから安心して泣いていいのだとそう言われた気がした。
「エレナ様、どうかしましたか?」
側でお茶の準備をしていたリーファが手を止め、エレナに声をかける。
エレナは少し考える素振りをして、リーファが準備しているカップを指さした後、指を2本立てた。
「えっと、2人分のご準備という事でしょうか?」
来客予定は聞いていないがと首を傾げつつリーファはエレナの行動をそう解釈し、尋ねる。
聞かれたエレナが静かに頷くので、疑問に思いながらもリーファがカップの数を増やした所で部屋にノックの音が響いた。
ノックをしたその人は入室の許可を部屋の住人が出すより早くドアを開ける。顔を覗かせたのはルヴァルだった。
「お館様、来られる時は事前にご連絡をくださいと」
何度も言っていると言いかけてリーファは手を止める。手元には既に2人分のお茶の準備が整っていた。
ルヴァルの前に立ったエレナは彼が来る事を承知していたかのように動じる事なくその前に立ち、優雅な動作でカーテシーを行う。
これで笑顔と口上が伴っていたなら、どこからどう見ても名門貴族のご令嬢のそれである。
エレナはルヴァルに命じられる前に顔を上げる。会う度に何度もそう畏まらなくていいとルヴァルに言われ続け、その通りにするようになったのはほんの数日前からだった。
「それでお館様。本日のご用向きはなんでしょうか?」
声が出せないエレナの代わりにリーファはルヴァルにそう尋ねる。
促されたルヴァルは、ああと小さく頷くとエレナに近づき、
「エレナ。口を開けろ」
短くそう言った。素直に従ったエレナの口に何かが放り込まれ、途端に口内に甘くて優しい味が広がり、ふわりと溶けてなくなった。
エレナは驚いたように目を瞬かせると、ルヴァルと彼が手に持つ箱に視線を向ける。
「気に入ったようだな」
それはほんの僅かな変化であったが、エレナが表情を崩したことを微笑ましげに見たルヴァルはクスッと笑い、
「やる」
とエレナに箱を差し出した。
エレナは驚いたようにルヴァルと箱を見てどうするべきなのか戸惑う。
「なんですか、それ?」
そんなエレナに助け船を出すようにリーファがルヴァルに尋ねた。
「卵を使った菓子」
これはちゃんとソフィアの許可を得ていると箱からひとつ摘んだルヴァルはリーファに見せる。
リーファは一口大のコロンと丸いお菓子を見て、
「わぁ、卵ボーロ。子どもの頃よく頂きました」
と懐かしそうに話した。
「卵は栄養価高いからな」
「子どものおやつって印象でしたけど、これなら確かにエレナ様が召し上がっても大丈夫ですね! 美味しいですし」
パチンと手を叩き嬉しそうに声を上げたリーファを見ながら、ルヴァルはエレナの口にボーロを入れる。
「これはエレナ用に作らせたからな。食べたかったら自分で注文しろよ」
エレナは素直にそれを食べながら、
(ルヴァル様は餌付けの趣味でもあるのかしら?)
などとエレナは首を傾げて考える。
お肉といいお菓子といい、ルヴァルは隙あらばとにかく自分に何かを食べさせようとする。
(でも、これはとっても美味しいわ)
あっという間に口の中でなくなってしまい、それが少し名残り惜しくてエレナはルヴァルが手に持つ箱に視線を向ける。
それに気づいたルヴァルは今度ははっきり分かるほど形のいい唇で弧を描き、ふっと笑う。
「エレナは甘い物が好きなんだな」
今までで一番反応がいいと言ってエレナの口にもう一つお菓子を入れた。
「肉はまた今度な。食べられるようになったら、熊でも猪でも鹿でも食わせてやる」
「なんでジビエばっかりなんですか!? お肉といえば牛と羊でしょう!!」
うちの名産を食べさせなくてどうしますとリーファが猛抗議をする。
「あー冬季限定じっくり煮込んだ子羊のシチューが食べたくなってきました。焼きたてのパンを添えて」
ローストビーフも捨てがたいとうっとりしながら語るリーファを見ながら、エレナは思わず小さく笑う。
「エレナ様! 冬までには絶対食べられるようになりましょうね!」
美味しいんですよと嬉しそうにそう言ったリーファにエレナは静かに頷いた。
ここに来て数日。
初夜に呼ばれることもなく、それ以外にも女主人としての仕事も妻らしい役割もルヴァルに求められることはない。
代わりに求められるのは食べる事だけで、そうして自分の反応を見るたびに彼はどことなく機嫌の良さそうな顔をする。
エレナにはそれがとても不思議で仕方なかった。
「とにかく食え。で、体力つけろ」
「そうですねぇ。何をするにも身体が基本ですし。食べて運動することが身体作りには大事ですし。エレナ様、後でお散歩でもしましょうか?」
(ここの人達は、みんな優しい)
そして、それがエレナには少し怖かった。
今までの実家での生活で自分に与えられて来たのは、蔑む視線と絶え間ない嫌がらせの数々で。
優しい言葉をくれるエリオットでさえ、
『子爵達を刺激して、エレナがもっと酷い目に遭う事があっては大変だから、今は耐えて欲しい』
と困った顔をするだけだったのに。
(カナリアでなくなった私は、ここの人達に何も返せないのに。そんな私が受け取ってしまってもいいの?)
きゅっと下を向きそうになったエレナに、
「まぁ、とにかくこれは髪紐の礼だ」
とルヴァルは銀糸を結える濃紺の紐をエレナに見せる。
それはエレナが編んだもので、感謝を記した手紙につけてルヴァルに届けてもらったものだった。
「綺麗な色だ。気に入った」
そう言われたエレナは紫水晶の瞳を大きく見開く。
ルヴァルの言葉は飾り気がなくて、言葉数は少ないかもしれない。
でも優しいだけの言葉の数々よりもずっと真っ直ぐ自分の中に落ちて来て、胸に詰まって何が込み上げる。
「これは確か南部では相手の無事を祈る物だったな。感謝する。ありがとう」
ルヴァルの言葉を耳が拾った瞬間、エレナの中で感情が溢れて、頬を涙が伝った。
「……エレナ?」
誰かになんの躊躇いもなく"ありがとう"なんて言われたのは、どれくらいぶりだろうか?
(これは、違うの!)
そう言い訳をしたくても、声の出ないエレナは言葉を紡ぐことができない。
せめて、早く涙を止めなければ。
そう思うのに、一度零れた感情はとめどなく溢れて来て、涙となってエレナの頬濡らす。
エレナはずっとサザンドラ子爵家の後継者が些細な事で泣くなどみっともないと叱責され、感情を表に出すなと言われ続けてきた。
(早く、泣き止まなきゃ……困らせてしまう、のに)
そうでなくとも感情のままに反抗し泣き叫べば、義母と異母妹を喜ばせるだけで。
だからもう、人前で泣くまいと決めていたのに。
苦しくて、苦しくて、苦しくて。
だけどいくら泣いたって現実は何一つ変わらなくて。
エリオットに婚約破棄を告げられたあの日でさえ、泣く事はなかったのに。
「……っ、ぅ……」
エレナから声にならない嗚咽が漏れる。
(突然泣き出すなんて、きっとみっともないと呆れられてしまうわ)
だけど止めなければと思うほど、今まで見ないようにしていた沢山の感情が混ざり合って、収拾がつかなくなる。
「好きにすればいい」
そんなエレナを前にして、ルヴァルは淡々とした口調でそう言った。
俯き目を擦るエレナの頭にルヴァルの大きな手が乗る。
「俺が許すのだから、エレナを咎められる者はここにはいない」
ポンポンと軽く頭を撫でながらルヴァルの言葉が落ちてくる。
「この領地で一番偉い俺に逆らう人間などいないのだからな」
何故泣いているのかと尋ねるのでも、優しく慰めるのでもない。
ルヴァルのその物言いは、とても尊大で受け取る人間によっては傲慢にさえ聞こえてしまうかもしれない。
(私は、こんなに優しい人を他に知らない)
だけど、エレナにはルヴァルから安心して泣いていいのだとそう言われた気がした。