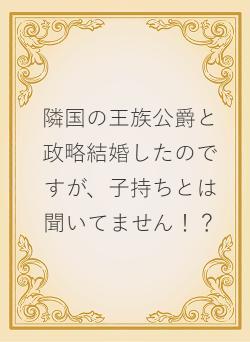男なんて、嫌い。
失恋したばかりの私はその夜、この国の第一王子ウィリアム殿下の寝所にいた。
使い手の少ない『変身の魔法』を使って猫に姿を変えての極秘の護衛任務だ。任務のことを知らせていないので、殿下は私のことを普通の猫だと思っている。
「お前は頭がいいね。私の言うことをすべて理解しているみたいだ」
切れ長の緑の瞳が、きらきらしている。
優しい声で言って、ウィリアム殿下が猫の私を抱っこする。
美しい殿下だ。でも、男だ。
頬を寄せられて、殿下の茶色い髪が私の猫ヒゲに触れる。くすぐったい。
「今夜は一緒に寝ようか? よし、よし」
殿下の長い指が、私を優しく撫でてくれる。
この殿下は、猫を撫でるのがお上手だ。撫でられるのは気持ちがいい。でも、男だ。
「ふーっ!!」
「んー、いい匂い。やわらかい、あったかい……ああ、ごめんね、嫌だったのかい? お嬢さん。君、私が好きな人に似た綺麗な色の目をしているね……」
殿下は幸せそうに仰り、猫の私の機嫌を取るようにあやした。
そして、自分の胸板の上に乗っけてお休みになられた。
「可愛いなあ。シュアファルカ伯爵に明日手紙を書こう。猫はとても気に入ったよって……ご令嬢はお元気ですかって……」
すやすやと眠るウィリアム殿下は、私よりも二つ年下。優秀らしいけれど、今まであまり話したことがない人だ。避けられているのでは、と思うくらい接点がなくて、パーティなどで目が合っても逸らされることが多かった。嫌われているのかもしれない。
「明日も明後日も、一緒に寝ようね。おやすみ、メイメイ」
変な名前がつけられた。猫の名前らしい。
「にゃぁ……」
猫になりきって王子の夜を守る私は、伯爵令嬢であり宮廷魔法使いとしての肩書きも持つ、アシュリー・メイ・シュアファルカ。
婚約者に浮気されて婚約破棄された、可哀想な『寝取られ』令嬢と貴族社会で噂される女だ。
失恋したばかりの私はその夜、この国の第一王子ウィリアム殿下の寝所にいた。
使い手の少ない『変身の魔法』を使って猫に姿を変えての極秘の護衛任務だ。任務のことを知らせていないので、殿下は私のことを普通の猫だと思っている。
「お前は頭がいいね。私の言うことをすべて理解しているみたいだ」
切れ長の緑の瞳が、きらきらしている。
優しい声で言って、ウィリアム殿下が猫の私を抱っこする。
美しい殿下だ。でも、男だ。
頬を寄せられて、殿下の茶色い髪が私の猫ヒゲに触れる。くすぐったい。
「今夜は一緒に寝ようか? よし、よし」
殿下の長い指が、私を優しく撫でてくれる。
この殿下は、猫を撫でるのがお上手だ。撫でられるのは気持ちがいい。でも、男だ。
「ふーっ!!」
「んー、いい匂い。やわらかい、あったかい……ああ、ごめんね、嫌だったのかい? お嬢さん。君、私が好きな人に似た綺麗な色の目をしているね……」
殿下は幸せそうに仰り、猫の私の機嫌を取るようにあやした。
そして、自分の胸板の上に乗っけてお休みになられた。
「可愛いなあ。シュアファルカ伯爵に明日手紙を書こう。猫はとても気に入ったよって……ご令嬢はお元気ですかって……」
すやすやと眠るウィリアム殿下は、私よりも二つ年下。優秀らしいけれど、今まであまり話したことがない人だ。避けられているのでは、と思うくらい接点がなくて、パーティなどで目が合っても逸らされることが多かった。嫌われているのかもしれない。
「明日も明後日も、一緒に寝ようね。おやすみ、メイメイ」
変な名前がつけられた。猫の名前らしい。
「にゃぁ……」
猫になりきって王子の夜を守る私は、伯爵令嬢であり宮廷魔法使いとしての肩書きも持つ、アシュリー・メイ・シュアファルカ。
婚約者に浮気されて婚約破棄された、可哀想な『寝取られ』令嬢と貴族社会で噂される女だ。