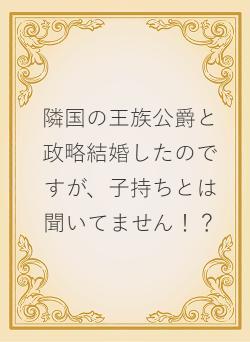2、パパはイケおじ、テンション高すぃ
『闇堕ち公爵』スローテス・ファストレイヴンは、現国王の従兄弟だ。
容姿端麗で、グレーの髪に紫の瞳の中年男性……いわゆるイケおじ様である。
さっきから近くでちらちらと見てるんだけど、瞳がほんとうに綺麗。宝石のアメジストみたい。
妻は病で亡くなっていて、娘を溺愛していることで有名だった。でも、娘はあるとき、ライバル貴族が雇った賊に攫われてしまう。
公爵家のお抱え騎士団は娘を連れて逃げる馬車を追った。
しかし、賊が必死に逃げた結果、なんと馬車は崖から落ちてしまう。
崖下には急流の川があって、遺体すら見つからなかった……。
悲劇だ。
この部分については実は裏設定もあり、「えーっ、悪役キャラがかわいそう」といわれて悪役父娘の人気につながっていた。
さて、そんな「かわいそうな悪役」である私とパパは、公爵家に「帰宅」した。
「おうちに帰ってきたよ、ロザリット。パパとロザリットのおうちだ。わかるよね? さあパパと呼んでおくれ」
「パ、パパ。わ、わーい。おうち、うれしい。わかる」
「なぜわかるんだ? 君はロザリットじゃないのに」
「えっ」
調子を合わせたのに急に冷静になってつっこみしないでほしい!
パパがジーっと見てくるから、私は全力で愛想笑いした。
「え、えへへ」
「はぁ……、私は何を言ってるんだ。この子はこんなに小さくて何もわかってないんだ。娘の代わりにしようなんて、どうかしてる。しかし、それにしてもよく似てる」
……うわっ、パパが黒いオーラを出して頭を抱えてる!
私は知ってる。
原作のパパはリリーを事あるごとに「ロザリットらしく振る舞えるよね?」と試していく。
そして原作のリリーは期待外れな反応を返し続けて、パパを大きく傷つけてしまうんだ。
追い打ちのように家令やメイド長が「その娘はロザリットお嬢様ではありませんよ!」「ロザリットお嬢様はお亡くなりになられたのです!」と現実を突きつける。
結果、パパは激昂、闇堕ち。
リリーは「このおじさま、おかしいよ。こわいよ」と怯えてしまい、双方ともに一緒にいればいるほどメンタルがガリガリ削られる最悪の関係を深めていくのだ。
でも私は原作知識があるから、そんなことにはさせないっ!
「パ、パパ。頭が痛いの? おうち、入らないの……ですか?」
パパ~、闇堕ちしないで~! パパー、正気に戻ってー!
祈りながら話しかけると、パパはガバッとこっちを見た。わ、目がキラキラだ。
「君は声も似てるな! すばらすぃっ! 敬語は使わなくてよろすぃっ!」
パパ、テンション高すぃっ!
あと、「似てる」ということは、私が本人ではないと思ってるんだな。
「私の名はスローテス。ここはファストレイヴン公爵家だ。リリー、君は今日から私の養女になるんだよ……ロザリットだ。今日から君は、ロザリットという貴族の娘になるんだ」
パパは早口だ。それに、すごく真剣な顔。
「綺麗なドレスが着れる。お菓子もいっぱい食べていい。お勉強もできるぞ。高貴な王子様とダンスだってできる」
途中で言葉が詰まって、ぎゅうっと抱きしめられる。服の布地が滑らかな触り心地。清潔ないい匂いがする。
「パパが今度こそ守るから、世界一安全なんだ。危ない目には、二度と遭わないんだ……」
大きなパパの体が小刻みに震えている。
嗚咽が聞こえてくる――泣いている。
「パ、パパ……」
愛娘を守れなかった後悔と喪失感が伝わって、私は胸が締め付けられるような気持ちになった。
「パパ……泣かないで。私、ロザリットだよ」
一生懸命言えば、パパは泣き笑いみたいな表情で涙をぬぐった。
「ロザリットになってくれるのか。ありがとう」
屋敷に入り、パパは私を使用人に預けて入浴と着替えを命じた。
服を脱がしてくれたメイドが「あら?」とペンダントを見るので、私は「これは大切なんです」と守った。
原作の知識の中に、このペンダントに関する情報はない。「取り上げられたら大変」と思ったのだ。
「ブリッジボート伯爵家の紋章に見えたけど……ああ、取り上げたりしないから大丈夫ですよ、ええと……お客様――お嬢様」
ブリッジボート伯爵家?
それは、ファストレイヴン公爵家をライバル視している貴族の家だ。
なんでリリーが紋章ペンダントを持ってるんだろう?
裏設定にも書かれてない隠し設定みたいなやつかな?
メイドたちは、仲良さそうにパパの話で盛り上がっている。
「旦那様はおかしくなってしまわれたのでは?」
おかしくなってるよ!
「お嬢様の代わりにするのですって……」
代わりになるよ!
疑問は解消しないまま、メイドが何人かがかりで世話をしてくれる。するりと服が脱がされたタイミングで、背中側にいたメイドが小さく悲鳴をあげた。
「きゃっ、どうしたの、この傷」
私の背中には、大きな傷があるのだ。どこでどのようにしてできた傷なのかは、わからない。
「虐待されていたの? ひどい傷」
「かわいそうに」
メイドたちは憐れみ全開になってお世話をしてくれた。
お風呂はあったかくて、自分の全身が他人の手で綺麗にされていく感覚は気持ちよかった。
「まあまあ、お嬢様のドレスがよく似合うこと」
「なんだか、お嬢様がほんとうに生き返ったみたいで泣いてしまうわ」
「私も……」
涙声のメイドたちが着せてくれた公爵令嬢らしさのある豪奢なドレスは、サイズがぴったりだった。私は彼女たちの名前を思い出せたので、呼んでみた。
「お世話してくれてありがとう、マーサ、ミレニア」
「えっ? お嬢様?」
「わ、私たちの名前をご存じで?」
ふふ、驚いている。
私はにっこり笑い、パパのもとへと向かった。
『闇堕ち公爵』スローテス・ファストレイヴンは、現国王の従兄弟だ。
容姿端麗で、グレーの髪に紫の瞳の中年男性……いわゆるイケおじ様である。
さっきから近くでちらちらと見てるんだけど、瞳がほんとうに綺麗。宝石のアメジストみたい。
妻は病で亡くなっていて、娘を溺愛していることで有名だった。でも、娘はあるとき、ライバル貴族が雇った賊に攫われてしまう。
公爵家のお抱え騎士団は娘を連れて逃げる馬車を追った。
しかし、賊が必死に逃げた結果、なんと馬車は崖から落ちてしまう。
崖下には急流の川があって、遺体すら見つからなかった……。
悲劇だ。
この部分については実は裏設定もあり、「えーっ、悪役キャラがかわいそう」といわれて悪役父娘の人気につながっていた。
さて、そんな「かわいそうな悪役」である私とパパは、公爵家に「帰宅」した。
「おうちに帰ってきたよ、ロザリット。パパとロザリットのおうちだ。わかるよね? さあパパと呼んでおくれ」
「パ、パパ。わ、わーい。おうち、うれしい。わかる」
「なぜわかるんだ? 君はロザリットじゃないのに」
「えっ」
調子を合わせたのに急に冷静になってつっこみしないでほしい!
パパがジーっと見てくるから、私は全力で愛想笑いした。
「え、えへへ」
「はぁ……、私は何を言ってるんだ。この子はこんなに小さくて何もわかってないんだ。娘の代わりにしようなんて、どうかしてる。しかし、それにしてもよく似てる」
……うわっ、パパが黒いオーラを出して頭を抱えてる!
私は知ってる。
原作のパパはリリーを事あるごとに「ロザリットらしく振る舞えるよね?」と試していく。
そして原作のリリーは期待外れな反応を返し続けて、パパを大きく傷つけてしまうんだ。
追い打ちのように家令やメイド長が「その娘はロザリットお嬢様ではありませんよ!」「ロザリットお嬢様はお亡くなりになられたのです!」と現実を突きつける。
結果、パパは激昂、闇堕ち。
リリーは「このおじさま、おかしいよ。こわいよ」と怯えてしまい、双方ともに一緒にいればいるほどメンタルがガリガリ削られる最悪の関係を深めていくのだ。
でも私は原作知識があるから、そんなことにはさせないっ!
「パ、パパ。頭が痛いの? おうち、入らないの……ですか?」
パパ~、闇堕ちしないで~! パパー、正気に戻ってー!
祈りながら話しかけると、パパはガバッとこっちを見た。わ、目がキラキラだ。
「君は声も似てるな! すばらすぃっ! 敬語は使わなくてよろすぃっ!」
パパ、テンション高すぃっ!
あと、「似てる」ということは、私が本人ではないと思ってるんだな。
「私の名はスローテス。ここはファストレイヴン公爵家だ。リリー、君は今日から私の養女になるんだよ……ロザリットだ。今日から君は、ロザリットという貴族の娘になるんだ」
パパは早口だ。それに、すごく真剣な顔。
「綺麗なドレスが着れる。お菓子もいっぱい食べていい。お勉強もできるぞ。高貴な王子様とダンスだってできる」
途中で言葉が詰まって、ぎゅうっと抱きしめられる。服の布地が滑らかな触り心地。清潔ないい匂いがする。
「パパが今度こそ守るから、世界一安全なんだ。危ない目には、二度と遭わないんだ……」
大きなパパの体が小刻みに震えている。
嗚咽が聞こえてくる――泣いている。
「パ、パパ……」
愛娘を守れなかった後悔と喪失感が伝わって、私は胸が締め付けられるような気持ちになった。
「パパ……泣かないで。私、ロザリットだよ」
一生懸命言えば、パパは泣き笑いみたいな表情で涙をぬぐった。
「ロザリットになってくれるのか。ありがとう」
屋敷に入り、パパは私を使用人に預けて入浴と着替えを命じた。
服を脱がしてくれたメイドが「あら?」とペンダントを見るので、私は「これは大切なんです」と守った。
原作の知識の中に、このペンダントに関する情報はない。「取り上げられたら大変」と思ったのだ。
「ブリッジボート伯爵家の紋章に見えたけど……ああ、取り上げたりしないから大丈夫ですよ、ええと……お客様――お嬢様」
ブリッジボート伯爵家?
それは、ファストレイヴン公爵家をライバル視している貴族の家だ。
なんでリリーが紋章ペンダントを持ってるんだろう?
裏設定にも書かれてない隠し設定みたいなやつかな?
メイドたちは、仲良さそうにパパの話で盛り上がっている。
「旦那様はおかしくなってしまわれたのでは?」
おかしくなってるよ!
「お嬢様の代わりにするのですって……」
代わりになるよ!
疑問は解消しないまま、メイドが何人かがかりで世話をしてくれる。するりと服が脱がされたタイミングで、背中側にいたメイドが小さく悲鳴をあげた。
「きゃっ、どうしたの、この傷」
私の背中には、大きな傷があるのだ。どこでどのようにしてできた傷なのかは、わからない。
「虐待されていたの? ひどい傷」
「かわいそうに」
メイドたちは憐れみ全開になってお世話をしてくれた。
お風呂はあったかくて、自分の全身が他人の手で綺麗にされていく感覚は気持ちよかった。
「まあまあ、お嬢様のドレスがよく似合うこと」
「なんだか、お嬢様がほんとうに生き返ったみたいで泣いてしまうわ」
「私も……」
涙声のメイドたちが着せてくれた公爵令嬢らしさのある豪奢なドレスは、サイズがぴったりだった。私は彼女たちの名前を思い出せたので、呼んでみた。
「お世話してくれてありがとう、マーサ、ミレニア」
「えっ? お嬢様?」
「わ、私たちの名前をご存じで?」
ふふ、驚いている。
私はにっこり笑い、パパのもとへと向かった。