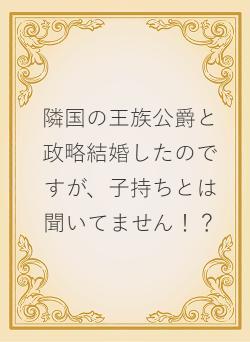32、やっぱり、悪上等ですわ
ダンスパーティの日が近づいて。
わたくしは、ちょっぴり焦ってきました。
なにせ、ダンスは苦手なのです。ダンスだけでなく、運動全般ですが。
オヴリオ様はわたくしがダンス下手でも全く気にすることなく、足を踏まれてもいいと仰っていましたが、やはり踏まずに済むならそれに越したことはないでしょう?
それに、前回のダンスはとても楽しかったのです。
あの時はリードされるばかりでしたけれど、上達したらもっとお互い、楽しくなるんじゃないかしら?
一緒に踊る相手の力量は直接伝わるものですから、わたくしが上達したら、きっとオヴリオ様は驚かれるのではないでしょうか?
……どうせ、パーティで踊る機会はこの先、何度もあるのです。
苦手より、得意にしたほうがよいのでは。
わたくしは、そう思ったのです。
そして、特訓を始めたのでした。コッソリ、内緒で。毎晩。
「わん、つー、わん、つー」
踊るわたくしを、ナイトくんが「がんばれ、がんばれ」という雰囲気で手をぶんぶんさせて応援してくれています。
わたくしが家で苦手なダンスをコッソリ練習するようになると、お父様もいつもコソコソと覗いたり、練習用のダンスフロアに入ってきて、「根を詰め過ぎてはいけないよ」と仰って、見守ったりしてくれました。
「メモリア、パパが相手役になるよ」
ある日、勇気を出したように言って、お父様はキリッとした顔でわたくしの手を取り……ぽよんとしたお腹のお肉をちょっぴり揺らしつつ、優しくわたくしをリードして。
「大きくなったなぁ」
小さく、愛情たっぷりに呟いたのです。
「お父様のおかげです」
わたくしはダンスを中断してお父様にぎゅーっと抱き着いて、甘えたのでした。
「ふふ、嬉しいことを言ってくれるじゃないか。……甘えてくれるのかい。メモリア」
「ええ、ええ。わたくし、ずーっとお父様にべったりですわ」
「それはどうかと……」
これまたコッソリ様子を見に来たらしきカーテイルお兄様が呆れたように言って、「交代」と言って相手役を務めてくれます。
「メモリア」
「はい、お兄様」
「大勢で踊っているパーティは、意外と皆、他人のことなんて見ていない。でも、お前の相手は第二王子殿下なのだから、割と皆、お前を見る。下手なところを見つけると、色々言われるかもしれない」
「……安心させたいのか、怖がらせたいのか、どっちですの、カーテイルお兄様」
「高貴な方に溺愛されているとなると、嫉妬も多くなる。お前はどんなに完璧に踊っても、嫌な思いをすることもあるだろう」
「そ、そうですわね」
お父様が少し離れた場所でもの言いたげな顔をして口を開きかけ、閉じたのが見えました。
くるり。
カーテイルお兄様にリードされて回り、わたくしは続きの言葉を聞きました。
「だったら、完璧に踊る必要なんてない。ニコニコ笑って、のびのびと楽しく踊ってくるといい。そして、何か嫌なことがあったら溜め込まずに第二王子殿下にご相談申し上げるといい」
「そ、そういうお話でしたのね。なるほど」
……カーテイルお兄様が仰る言葉は、以前オヴリオ様が仰ったことと似ていました。
「オヴリオ様も、似たようなことを仰いましたわ」
「そうか」
「でもね、お兄様。わたくしも、結構強くなりましたのよ。この前なんて、悪上等っていう扇を使ってね……」
わたくしがちょっと話を盛って学園生活で起きたことを語ると、カーテイルお兄様は、どこか安心したように微笑んだのでした。
「やっぱり、悪上等ですわ。悪上等は、強いのですわ! インパクトがあるのですわ!」
「正直、その文言を気に入るのはちょっと……いや、お前が楽しいならいいけど」
カーテイルお兄様も、なんだかんだ言って甘いのです。
こうして、優しい家族のおかげで、わたくしのダンススキルはどんどん向上したのです。
そして、ダンスパーティの日がやってきました。
「お嬢様、お綺麗ですよ!」
メイドのアンが一生懸命に褒めて自信をつけてくれるので、わたくしは勇ましい表情で頷きました。
「わたくしは、悪役令嬢ですもの。悪役令嬢をするなら、綺麗でないと」
「そのごっこ遊び、まだやっていらしたんですね」
まだまだ子供ですね、と笑うアンに「そうね」と言って迎えの馬車に向かえば、華やかに着飾ったオヴリオ様はとても格好良くて、わたくしは扇で口元を隠しながら見惚れてしまいました。
オヴリオ様はいつものように手袋をはめた手を差し出した姿勢で、大きく眼を見開いています。
「本日は、エスコートありがとうございます、オヴリオ様」
王族の方に対しても失礼にならぬよう、幼い頃から教えられ指導されて自然と身についている礼をして、楚々として手を重ねると、「ぐう」と唸る声が聞こえました。
……ぐう?
「わ、わたくしがちゃんと礼を尽くしていますのに、ぐうって……なんですの? 獣のよう。第二王子殿下ともあろう方が……親しき中にも礼儀ありと……」
さすがに下品ではありませんか、と首をかしげてみてみれば、オヴリオ様は口元に手をあてて顔を背けています。
あら?
「……もしかして、ご体調が優れないです?」
それでは、無理はさせられませんわ。
ああ、でもでも、今日しか呪いは解けませんのに?
一瞬、蒼褪めたわたくしですが、オヴリオ様はぶんぶんと首を振ってくださいました。
「君が綺麗だったから、……好きじゃないけど」
「まあ」
――綺麗ですって。
「ふふ、わたくし、もう、そのいつものフレーズが逆の意味に聞こえるようになってまいりましたわ」
甘やかに呟けば、オヴリオ様は赤く染まった顔で「実は俺も」と声を返してくださったのでした。
ダンスパーティの日が近づいて。
わたくしは、ちょっぴり焦ってきました。
なにせ、ダンスは苦手なのです。ダンスだけでなく、運動全般ですが。
オヴリオ様はわたくしがダンス下手でも全く気にすることなく、足を踏まれてもいいと仰っていましたが、やはり踏まずに済むならそれに越したことはないでしょう?
それに、前回のダンスはとても楽しかったのです。
あの時はリードされるばかりでしたけれど、上達したらもっとお互い、楽しくなるんじゃないかしら?
一緒に踊る相手の力量は直接伝わるものですから、わたくしが上達したら、きっとオヴリオ様は驚かれるのではないでしょうか?
……どうせ、パーティで踊る機会はこの先、何度もあるのです。
苦手より、得意にしたほうがよいのでは。
わたくしは、そう思ったのです。
そして、特訓を始めたのでした。コッソリ、内緒で。毎晩。
「わん、つー、わん、つー」
踊るわたくしを、ナイトくんが「がんばれ、がんばれ」という雰囲気で手をぶんぶんさせて応援してくれています。
わたくしが家で苦手なダンスをコッソリ練習するようになると、お父様もいつもコソコソと覗いたり、練習用のダンスフロアに入ってきて、「根を詰め過ぎてはいけないよ」と仰って、見守ったりしてくれました。
「メモリア、パパが相手役になるよ」
ある日、勇気を出したように言って、お父様はキリッとした顔でわたくしの手を取り……ぽよんとしたお腹のお肉をちょっぴり揺らしつつ、優しくわたくしをリードして。
「大きくなったなぁ」
小さく、愛情たっぷりに呟いたのです。
「お父様のおかげです」
わたくしはダンスを中断してお父様にぎゅーっと抱き着いて、甘えたのでした。
「ふふ、嬉しいことを言ってくれるじゃないか。……甘えてくれるのかい。メモリア」
「ええ、ええ。わたくし、ずーっとお父様にべったりですわ」
「それはどうかと……」
これまたコッソリ様子を見に来たらしきカーテイルお兄様が呆れたように言って、「交代」と言って相手役を務めてくれます。
「メモリア」
「はい、お兄様」
「大勢で踊っているパーティは、意外と皆、他人のことなんて見ていない。でも、お前の相手は第二王子殿下なのだから、割と皆、お前を見る。下手なところを見つけると、色々言われるかもしれない」
「……安心させたいのか、怖がらせたいのか、どっちですの、カーテイルお兄様」
「高貴な方に溺愛されているとなると、嫉妬も多くなる。お前はどんなに完璧に踊っても、嫌な思いをすることもあるだろう」
「そ、そうですわね」
お父様が少し離れた場所でもの言いたげな顔をして口を開きかけ、閉じたのが見えました。
くるり。
カーテイルお兄様にリードされて回り、わたくしは続きの言葉を聞きました。
「だったら、完璧に踊る必要なんてない。ニコニコ笑って、のびのびと楽しく踊ってくるといい。そして、何か嫌なことがあったら溜め込まずに第二王子殿下にご相談申し上げるといい」
「そ、そういうお話でしたのね。なるほど」
……カーテイルお兄様が仰る言葉は、以前オヴリオ様が仰ったことと似ていました。
「オヴリオ様も、似たようなことを仰いましたわ」
「そうか」
「でもね、お兄様。わたくしも、結構強くなりましたのよ。この前なんて、悪上等っていう扇を使ってね……」
わたくしがちょっと話を盛って学園生活で起きたことを語ると、カーテイルお兄様は、どこか安心したように微笑んだのでした。
「やっぱり、悪上等ですわ。悪上等は、強いのですわ! インパクトがあるのですわ!」
「正直、その文言を気に入るのはちょっと……いや、お前が楽しいならいいけど」
カーテイルお兄様も、なんだかんだ言って甘いのです。
こうして、優しい家族のおかげで、わたくしのダンススキルはどんどん向上したのです。
そして、ダンスパーティの日がやってきました。
「お嬢様、お綺麗ですよ!」
メイドのアンが一生懸命に褒めて自信をつけてくれるので、わたくしは勇ましい表情で頷きました。
「わたくしは、悪役令嬢ですもの。悪役令嬢をするなら、綺麗でないと」
「そのごっこ遊び、まだやっていらしたんですね」
まだまだ子供ですね、と笑うアンに「そうね」と言って迎えの馬車に向かえば、華やかに着飾ったオヴリオ様はとても格好良くて、わたくしは扇で口元を隠しながら見惚れてしまいました。
オヴリオ様はいつものように手袋をはめた手を差し出した姿勢で、大きく眼を見開いています。
「本日は、エスコートありがとうございます、オヴリオ様」
王族の方に対しても失礼にならぬよう、幼い頃から教えられ指導されて自然と身についている礼をして、楚々として手を重ねると、「ぐう」と唸る声が聞こえました。
……ぐう?
「わ、わたくしがちゃんと礼を尽くしていますのに、ぐうって……なんですの? 獣のよう。第二王子殿下ともあろう方が……親しき中にも礼儀ありと……」
さすがに下品ではありませんか、と首をかしげてみてみれば、オヴリオ様は口元に手をあてて顔を背けています。
あら?
「……もしかして、ご体調が優れないです?」
それでは、無理はさせられませんわ。
ああ、でもでも、今日しか呪いは解けませんのに?
一瞬、蒼褪めたわたくしですが、オヴリオ様はぶんぶんと首を振ってくださいました。
「君が綺麗だったから、……好きじゃないけど」
「まあ」
――綺麗ですって。
「ふふ、わたくし、もう、そのいつものフレーズが逆の意味に聞こえるようになってまいりましたわ」
甘やかに呟けば、オヴリオ様は赤く染まった顔で「実は俺も」と声を返してくださったのでした。