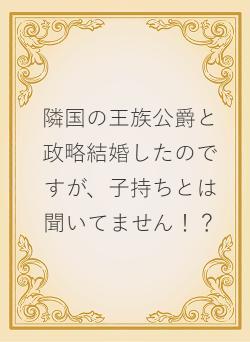2、紅茶が美味しいですわ
第二王子オヴリオ様の仰ることは、意味不明です。
「好きだと言ってはいけない。絶対だ。好きじゃないと言うんだ」
お話される声はおおらかで、あたたかです。しかし、お話の内容ときたら。
「えーとつまり、わたくしは嫌われています? そしてわたくしにも嫌いと言えと?」
「き、嫌いとか言うな……っ。強い言葉は……傷付く」
「はぁ……?」
「オブラートにいこう。好きではない、と」
この王子様ったら、本気の温度感で、真面目にそんなことを仰るのです。
「俺は君のことが好きじゃない。はい、君の番」
「わ……わたくしはあなたのことが好きじゃないですわ」
「……」
なんでちょっとションボリなさるんですのよ!
言わせたのはあなたでしょうに!?
「では、本題を始める」
わたくしが情緒を乱されていると、オヴリオ様は気持ちを切り替えるように紅茶で舌を潤して、話し始めました。
「いいか、君は第一王子であり王太子のユスティス兄上に横恋慕する悪役令嬢なんだ! そして俺は兄の恋人である聖女アミティエに横恋慕する当て馬なんだ!」
「そ、そ、そうでしたか……?」
「俺たちは元々仲が悪かった! だが、手を結ぼうと話し合っていたんだ」
「き……記憶にございませんが……っ?」
「忘れてるんだ!」
「そうでしょうかぁ……!?」
記憶にない人間関係がわたくしを驚かせます。
「君は覚えていないかもしれないが、メモリア嬢は悪役令嬢としてあんなことやこんなことをした。ゆえに、このままだと明日のパーティで、兄に断罪されてしまう」
「覚えがありませんけれど……」
「断罪は回避したいだろ。そう思うだろ?」
「え、ええ……断罪されるなら、回避しないといけませんわね」
「そこで俺たちは婚約することにしたんだ!」
「っ!?」
わたくし、あんなことやこんなことをしましたかしら?
そもそも、わたくし、第一王子ユスティス様に横恋慕していましたかしら?
そして、なぜ婚約することにしたんでしょうかっ?
「メモリア嬢は、記憶が曖昧になっているんだ」
「記憶に関しては、仰る通りですが」
気持ちを落ち着かせようと紅茶を頂けば、香り高くて上品な味わいです。サラッとした口当たりの良さで、不安な気持ちをやわらげてくれる優しい美味しさです。
はぁ……落ち着きますわ。紅茶が美味しいですわ〜。
「俺もこのままだと『恋に破れてざまぁ』とか噂をされるようになってしまうんだ」
オヴリオ様は説明を続けています。
マイペースというか、なんというか。
こちらの疑問なんて勢いでねじ伏せてしまおうというオーラを感じます。
わたくしは仕方なく、相槌を打ちました。
「ざまぁ……されてしまうのですね」
ざまぁ、は貴族の子弟の間で流行している架空の物語によく出てくる展開をあらわす言葉です。
特に、有名な作家エヴァンスが発表した『虐げられた聖女は冷酷な皇帝に溺愛される』という本が有名で。
悪いことをした人が「ざまぁみろ」と言われてしまうのです。勧善懲悪というのですわ、そういうの。
「わたくし、ざまぁがわかります。意外と記憶がありますわ。まるで、一部だけ……直前の記憶だけが抜け落ちているよう」
「物忘れってそんなものだ。俺も今、自分の名前を忘れた」
「それは嘘でしょ……いえ、あなたはオヴリオ様です」
「俺に名前を思い出させてくれてありがとう、メモリア。感謝する。恩に着る。一生かけてこの恩を返す」
「な、な、な、なんですの。結構です。大袈裟すぎます……」
……変。
この王子様、おかしいです!
「それはともかく、俺と君は、ざまぁを回避しようと手を結ぶところだったんだ」
オヴリオ様はそう仰り、わたくしに手を差し出しました。
「それに、恋というのは、押してダメなら引いてみるのもひとつの手。これまで俺たちは相手に自分から好意を伝えてきたが、いっそ別の相手とイチャイチャして見せつけたら相手が嫉妬するのではないかと」
「残念ですけれど、恋心を持っていない相手に見せつけても嫉妬はしてくれないと思いますわ、オヴリオ様」
「恋心があるほうに賭けるんだ、メモリア嬢」
「賭け事はちょっと……」
オヴリオ様の手は、手袋をはめています。
わたくしは、手袋の下の手を思い出せるような気がしました。
剣術をたしなまれる方ならではの、ちょっと皮膚が硬くなっているところがあったり、ごつごつしている、そんな大きな手を見たことがある気がするのです。
「俺の手を握ってほしい。大丈夫だから」
そっとおねだりするように仰る声は、なんだか甘くて切なく聞こえるのです。
「頼む」
……頼む、ですって。
まったく、なんなのでしょう。どうしてそんなに必死な感じなのでしょうか?
「し……仕方ありませんわね……?」
手に手を重ねると、オヴリオ様はウンウンと頷いて、安心した表情を浮かべてくれました。そして。
「名付けて! 『俺たち脇役だけど、幸せになります』作戦だ!」
耳に心地よい美声で、変な作戦名を教えてくださったのでした。
「……オヴリオ様。現実と虚構の区別はついていらっしゃいますか?」
テーブルの端に置かれた本をちらりとみて、わたくしは思わず呟きました。
オヴリオ様には、そんな心配をしてしまうような危うい気配があったものです。
それに、気安く言葉を交わせる、不思議な安心感みたいなものもあったので。
――わたくしとオヴリオ様は、元々親しい間柄だったのでは?
そんな思いが、ふと湧きました。
「……さあ、誓いあおう! 誓いの言葉を書いたから読んで」
ぺらっと見せてくる紙には、本当に誓いの言葉が書いてあるのです。
オヴリオ様が妙なテンションです。なんでしょうこのテンション。変人。王子様、変人です。
わたくしは仕方なく文字を読みました。
「わたくしは悪役令嬢を頑張ります」
「俺は当て馬をあまり頑張る気がない。よし婚約しよう!」
ああ、意味不明!
……ところでこの作戦、婚約する必要あるんですの? あと、今さりげなく頑張る気がないっておっしゃいました?
「これは形だけの婚約だ。本当に恋の相手を変える必要はないぞ。フリだけでいい。ここ、重要だ。試験に出る」
「試験には出ないでしょ……」
「いいな? 俺のことを好きにならなくてもいいんだ。お飾り婚約者ってわけだ」
「わ、わかりましたわ」
「お飾りだから、愛はない。悲しいが」
「は、はい」
「肌と肌が触れ合うとかも極力避けよう」
「……あなた、わたくしのこと実はお嫌いです……?」
わたくし、実は今いじめられています?
「いやっ、そんなことはない。嫌いではないぞ。好きでもないけど! ほら、俺呪われているだろ。うかつに触ると危険なんだよ」
そういえば、呪われているという噂があったかもしれません、この王子様。わたくしはふと、思い出しました。
「触ると……爆発でもするのでしょうか?」
「するかもしれない」
王子様は、真剣な顔で頷いたのでした。
第二王子オヴリオ様の仰ることは、意味不明です。
「好きだと言ってはいけない。絶対だ。好きじゃないと言うんだ」
お話される声はおおらかで、あたたかです。しかし、お話の内容ときたら。
「えーとつまり、わたくしは嫌われています? そしてわたくしにも嫌いと言えと?」
「き、嫌いとか言うな……っ。強い言葉は……傷付く」
「はぁ……?」
「オブラートにいこう。好きではない、と」
この王子様ったら、本気の温度感で、真面目にそんなことを仰るのです。
「俺は君のことが好きじゃない。はい、君の番」
「わ……わたくしはあなたのことが好きじゃないですわ」
「……」
なんでちょっとションボリなさるんですのよ!
言わせたのはあなたでしょうに!?
「では、本題を始める」
わたくしが情緒を乱されていると、オヴリオ様は気持ちを切り替えるように紅茶で舌を潤して、話し始めました。
「いいか、君は第一王子であり王太子のユスティス兄上に横恋慕する悪役令嬢なんだ! そして俺は兄の恋人である聖女アミティエに横恋慕する当て馬なんだ!」
「そ、そ、そうでしたか……?」
「俺たちは元々仲が悪かった! だが、手を結ぼうと話し合っていたんだ」
「き……記憶にございませんが……っ?」
「忘れてるんだ!」
「そうでしょうかぁ……!?」
記憶にない人間関係がわたくしを驚かせます。
「君は覚えていないかもしれないが、メモリア嬢は悪役令嬢としてあんなことやこんなことをした。ゆえに、このままだと明日のパーティで、兄に断罪されてしまう」
「覚えがありませんけれど……」
「断罪は回避したいだろ。そう思うだろ?」
「え、ええ……断罪されるなら、回避しないといけませんわね」
「そこで俺たちは婚約することにしたんだ!」
「っ!?」
わたくし、あんなことやこんなことをしましたかしら?
そもそも、わたくし、第一王子ユスティス様に横恋慕していましたかしら?
そして、なぜ婚約することにしたんでしょうかっ?
「メモリア嬢は、記憶が曖昧になっているんだ」
「記憶に関しては、仰る通りですが」
気持ちを落ち着かせようと紅茶を頂けば、香り高くて上品な味わいです。サラッとした口当たりの良さで、不安な気持ちをやわらげてくれる優しい美味しさです。
はぁ……落ち着きますわ。紅茶が美味しいですわ〜。
「俺もこのままだと『恋に破れてざまぁ』とか噂をされるようになってしまうんだ」
オヴリオ様は説明を続けています。
マイペースというか、なんというか。
こちらの疑問なんて勢いでねじ伏せてしまおうというオーラを感じます。
わたくしは仕方なく、相槌を打ちました。
「ざまぁ……されてしまうのですね」
ざまぁ、は貴族の子弟の間で流行している架空の物語によく出てくる展開をあらわす言葉です。
特に、有名な作家エヴァンスが発表した『虐げられた聖女は冷酷な皇帝に溺愛される』という本が有名で。
悪いことをした人が「ざまぁみろ」と言われてしまうのです。勧善懲悪というのですわ、そういうの。
「わたくし、ざまぁがわかります。意外と記憶がありますわ。まるで、一部だけ……直前の記憶だけが抜け落ちているよう」
「物忘れってそんなものだ。俺も今、自分の名前を忘れた」
「それは嘘でしょ……いえ、あなたはオヴリオ様です」
「俺に名前を思い出させてくれてありがとう、メモリア。感謝する。恩に着る。一生かけてこの恩を返す」
「な、な、な、なんですの。結構です。大袈裟すぎます……」
……変。
この王子様、おかしいです!
「それはともかく、俺と君は、ざまぁを回避しようと手を結ぶところだったんだ」
オヴリオ様はそう仰り、わたくしに手を差し出しました。
「それに、恋というのは、押してダメなら引いてみるのもひとつの手。これまで俺たちは相手に自分から好意を伝えてきたが、いっそ別の相手とイチャイチャして見せつけたら相手が嫉妬するのではないかと」
「残念ですけれど、恋心を持っていない相手に見せつけても嫉妬はしてくれないと思いますわ、オヴリオ様」
「恋心があるほうに賭けるんだ、メモリア嬢」
「賭け事はちょっと……」
オヴリオ様の手は、手袋をはめています。
わたくしは、手袋の下の手を思い出せるような気がしました。
剣術をたしなまれる方ならではの、ちょっと皮膚が硬くなっているところがあったり、ごつごつしている、そんな大きな手を見たことがある気がするのです。
「俺の手を握ってほしい。大丈夫だから」
そっとおねだりするように仰る声は、なんだか甘くて切なく聞こえるのです。
「頼む」
……頼む、ですって。
まったく、なんなのでしょう。どうしてそんなに必死な感じなのでしょうか?
「し……仕方ありませんわね……?」
手に手を重ねると、オヴリオ様はウンウンと頷いて、安心した表情を浮かべてくれました。そして。
「名付けて! 『俺たち脇役だけど、幸せになります』作戦だ!」
耳に心地よい美声で、変な作戦名を教えてくださったのでした。
「……オヴリオ様。現実と虚構の区別はついていらっしゃいますか?」
テーブルの端に置かれた本をちらりとみて、わたくしは思わず呟きました。
オヴリオ様には、そんな心配をしてしまうような危うい気配があったものです。
それに、気安く言葉を交わせる、不思議な安心感みたいなものもあったので。
――わたくしとオヴリオ様は、元々親しい間柄だったのでは?
そんな思いが、ふと湧きました。
「……さあ、誓いあおう! 誓いの言葉を書いたから読んで」
ぺらっと見せてくる紙には、本当に誓いの言葉が書いてあるのです。
オヴリオ様が妙なテンションです。なんでしょうこのテンション。変人。王子様、変人です。
わたくしは仕方なく文字を読みました。
「わたくしは悪役令嬢を頑張ります」
「俺は当て馬をあまり頑張る気がない。よし婚約しよう!」
ああ、意味不明!
……ところでこの作戦、婚約する必要あるんですの? あと、今さりげなく頑張る気がないっておっしゃいました?
「これは形だけの婚約だ。本当に恋の相手を変える必要はないぞ。フリだけでいい。ここ、重要だ。試験に出る」
「試験には出ないでしょ……」
「いいな? 俺のことを好きにならなくてもいいんだ。お飾り婚約者ってわけだ」
「わ、わかりましたわ」
「お飾りだから、愛はない。悲しいが」
「は、はい」
「肌と肌が触れ合うとかも極力避けよう」
「……あなた、わたくしのこと実はお嫌いです……?」
わたくし、実は今いじめられています?
「いやっ、そんなことはない。嫌いではないぞ。好きでもないけど! ほら、俺呪われているだろ。うかつに触ると危険なんだよ」
そういえば、呪われているという噂があったかもしれません、この王子様。わたくしはふと、思い出しました。
「触ると……爆発でもするのでしょうか?」
「するかもしれない」
王子様は、真剣な顔で頷いたのでした。