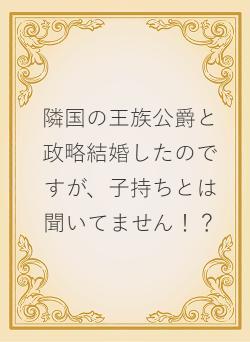23、炎、炎、炎
だって、だって。
あれはわたくしの大切なものなのです。
わたくしの忘れた思い出がつまっているのです。
自分の中からなくなってしまった過去が、あの日記帳の中にはあるのです。
確かにそんな日々があったのだと、わたくしに教えてくれるのです。
「はぁ、……はぁ……、はぁ……っ」
非日常の気配が濃い建物の中。
耳には、警鐘と人々の悲鳴とが絶えず聞こえています。
自分の呼吸の音と、心臓の音も。
「ハ、ハンカチ。ハンカチを」
口元に当てるとよいのでしたわ。
それを思い出して、わたくしはハンカチを口元にあてました。
煙臭いけど、まだきっと大丈夫。急げばきっと、大丈夫。
火らしきものはまだ見えないですし……。
階段を駆け上っていくうちに、脚がガクガクになって、最後は歩くような速さになりました。走りにくい靴も脱いでしまおうかと思ったのですが、床を見ると素足だと怪我をしそうだったので、そこは躊躇ってしまって。はぁはぁと息を乱して、ガクガクと歩いて。ようやくたどり着いたおばあさまのお部屋は、無事でした。
「よかった。ありましたわ」
お部屋に戻って日記を抱きしめると、ナイトくんがぐいぐいとわたくしのドレスを引っ張ります。
ついてきてくれたのですね。
ナイトくんは、とても慌てた様子です。急げ、急げというように手足をバタバタさせています。
「ええ、急いで避難しましょう。エヴァンス叔父様は、大丈夫かしら……こほっ、こほっ」
返す言葉の途中で咳き込んだのは、煙のせいです。
「し、白い……」
全体的に、視界が白い。
煙がすごいのです。わたくしは慌てて頭を下げて、ハンカチを口元に当てました。そのまま日記を抱えて廊下に出ると、ナイトくんが「こっち、こっち」と道を教えてくれます。
その足がぴたっと止まるときは、進もうとしていた階段の先に赤い炎が見えたとき。ゆらゆら揺れているその色は、本能的に「怖い」と感じてしまうような赤でした。
「きゃっ」
も、燃えてる。
わたくしは、心臓がぎゅっと鷲掴みにされたみたいになりました。
喉に何か詰まったみたいになっていて、声がうまく出せる気がしません。
――怖い。
ナイトくんが「こっちはダメだから、あっち」と来た道を戻り、反対側の階段に誘導してくれます。
「は……、はぁ……っ、はぁ……、は……」
疲労だけではなく、恐怖が原因で、脚がぶるぶる震えて、膝を折って座り込んでしまいそうです。
脚を動かさなきゃ、と思うのに、うまく前に出せなくなりそうです。
逃げなきゃ。
逃げなきゃ。
外に出なきゃ。
ガクガク震える足を必死に動かしてついていくと、どんどん煙が増えて、目が痛くなって、息が苦しくて……熱くて。
「――……あっ……」
喉の奥から、とても小さな、引き攣った声がこぼれました。
階段を降りた先は火の海でした。
火の粉がチラチラと舞っていて、熱気がすごいです。
あっちも、こっちも、燃えています。
パチパチという音がして、バキバキという音がして。き、危険。生命の危機って感じがすごいです。
わたくしはそのとき、『死』の気配をひやりと感じました。
噂話で聞いていたときは、あまり気にせず聞き流していたけれど。
火事って、こんな風なんですの?
火災って、こうなりますの?
わたくし、わたくし……死んでしまいますの?
これ、これ――……そんな状況なのでは、ありませんの……っ?
ぶるぶる、ガクガクと全身が震えます。
怖い。怖い。
「……ひゃっ、」
ナイトくんが腰からさげていた布製の剣が突然、ぶわっと燃え上がって、わたくしは自分でも驚くような速さでナイトくんの剣を抜いて遠くに投げました。
「あ、あ、……あ」
意味をなさない声が、口からこぼれています。
今。燃えた。燃えました。
ナイトくんの剣が。
あともう少し剣を投げるのが遅かったら、遅かったら。
きっと、ナイトくんは全身が燃えていました。
「ナイトくん、だめ。動いちゃ、だめ」
ナイトくんはこんがりと全身を焦がしながら火の近くをぽてぽてと跳ねて、「出口はあっち」と教えるようにわたくしを引っ張ります。
その体に火がついて、わたくしは慌ててハンカチをぽふぽふと叩きました。
「あ、ああ! あああ!!」
燃えちゃう。
ナイトくんが。燃えちゃう!
「だめ、……だめ!!」
守らなきゃ。
守らなきゃ!
無我夢中で火を消して、ナイトくんをぎゅっと抱きしめてその場にうずくまった、そのとき。
「――メモリア!」
必死な声がして、わたくしの視界がふわりと高くなります。
――……オヴリオ様です。
気付けば、わたくしはナイトくんを抱きしめたまま、オヴリオ様に横抱きに抱き上げられていました。
赤い炎に照らされて。
煙る視界に、近い距離で整った顔立ちを見て。
衣装ごしに伝わる体温と、逞しい体付きに、目の奥が熱くなって。
鼻がつんとして。じわりと視界が歪んで。
「――……オヴリオ様ぁっ……!!」
「心配した。すごく、……すごく!!」
熱を吐き出すようにオヴリオ様が仰る声が、わたくしに現実を教えてくれて、「もう大丈夫」と言ってくださると、まだ炎の中なのに、本当に大丈夫になったみたいに、全身が弛緩しました。
「ふ……っ、う……、う……、ひっく……っ」
ほろほろと、熱い液体がこぼれて、乾燥した頬が濡れていきます。
子供みたいに泣きじゃくっていると、ナイトくんが焦げた手で一生懸命頬にハンカチをあててくれて、わたくしはもっと泣いてしまうのでした。
「じっとして。できるだけ肌に触れないように」
「あ……っ」
助けにきてくれた……、そんな現実が嬉しくて、同時に「触れないように」という言葉が気になってしまいます。
……アミティエ様には、触れていたのに。
――……そんなことを考えている場合じゃ、ないのに。
だって、だって。
あれはわたくしの大切なものなのです。
わたくしの忘れた思い出がつまっているのです。
自分の中からなくなってしまった過去が、あの日記帳の中にはあるのです。
確かにそんな日々があったのだと、わたくしに教えてくれるのです。
「はぁ、……はぁ……、はぁ……っ」
非日常の気配が濃い建物の中。
耳には、警鐘と人々の悲鳴とが絶えず聞こえています。
自分の呼吸の音と、心臓の音も。
「ハ、ハンカチ。ハンカチを」
口元に当てるとよいのでしたわ。
それを思い出して、わたくしはハンカチを口元にあてました。
煙臭いけど、まだきっと大丈夫。急げばきっと、大丈夫。
火らしきものはまだ見えないですし……。
階段を駆け上っていくうちに、脚がガクガクになって、最後は歩くような速さになりました。走りにくい靴も脱いでしまおうかと思ったのですが、床を見ると素足だと怪我をしそうだったので、そこは躊躇ってしまって。はぁはぁと息を乱して、ガクガクと歩いて。ようやくたどり着いたおばあさまのお部屋は、無事でした。
「よかった。ありましたわ」
お部屋に戻って日記を抱きしめると、ナイトくんがぐいぐいとわたくしのドレスを引っ張ります。
ついてきてくれたのですね。
ナイトくんは、とても慌てた様子です。急げ、急げというように手足をバタバタさせています。
「ええ、急いで避難しましょう。エヴァンス叔父様は、大丈夫かしら……こほっ、こほっ」
返す言葉の途中で咳き込んだのは、煙のせいです。
「し、白い……」
全体的に、視界が白い。
煙がすごいのです。わたくしは慌てて頭を下げて、ハンカチを口元に当てました。そのまま日記を抱えて廊下に出ると、ナイトくんが「こっち、こっち」と道を教えてくれます。
その足がぴたっと止まるときは、進もうとしていた階段の先に赤い炎が見えたとき。ゆらゆら揺れているその色は、本能的に「怖い」と感じてしまうような赤でした。
「きゃっ」
も、燃えてる。
わたくしは、心臓がぎゅっと鷲掴みにされたみたいになりました。
喉に何か詰まったみたいになっていて、声がうまく出せる気がしません。
――怖い。
ナイトくんが「こっちはダメだから、あっち」と来た道を戻り、反対側の階段に誘導してくれます。
「は……、はぁ……っ、はぁ……、は……」
疲労だけではなく、恐怖が原因で、脚がぶるぶる震えて、膝を折って座り込んでしまいそうです。
脚を動かさなきゃ、と思うのに、うまく前に出せなくなりそうです。
逃げなきゃ。
逃げなきゃ。
外に出なきゃ。
ガクガク震える足を必死に動かしてついていくと、どんどん煙が増えて、目が痛くなって、息が苦しくて……熱くて。
「――……あっ……」
喉の奥から、とても小さな、引き攣った声がこぼれました。
階段を降りた先は火の海でした。
火の粉がチラチラと舞っていて、熱気がすごいです。
あっちも、こっちも、燃えています。
パチパチという音がして、バキバキという音がして。き、危険。生命の危機って感じがすごいです。
わたくしはそのとき、『死』の気配をひやりと感じました。
噂話で聞いていたときは、あまり気にせず聞き流していたけれど。
火事って、こんな風なんですの?
火災って、こうなりますの?
わたくし、わたくし……死んでしまいますの?
これ、これ――……そんな状況なのでは、ありませんの……っ?
ぶるぶる、ガクガクと全身が震えます。
怖い。怖い。
「……ひゃっ、」
ナイトくんが腰からさげていた布製の剣が突然、ぶわっと燃え上がって、わたくしは自分でも驚くような速さでナイトくんの剣を抜いて遠くに投げました。
「あ、あ、……あ」
意味をなさない声が、口からこぼれています。
今。燃えた。燃えました。
ナイトくんの剣が。
あともう少し剣を投げるのが遅かったら、遅かったら。
きっと、ナイトくんは全身が燃えていました。
「ナイトくん、だめ。動いちゃ、だめ」
ナイトくんはこんがりと全身を焦がしながら火の近くをぽてぽてと跳ねて、「出口はあっち」と教えるようにわたくしを引っ張ります。
その体に火がついて、わたくしは慌ててハンカチをぽふぽふと叩きました。
「あ、ああ! あああ!!」
燃えちゃう。
ナイトくんが。燃えちゃう!
「だめ、……だめ!!」
守らなきゃ。
守らなきゃ!
無我夢中で火を消して、ナイトくんをぎゅっと抱きしめてその場にうずくまった、そのとき。
「――メモリア!」
必死な声がして、わたくしの視界がふわりと高くなります。
――……オヴリオ様です。
気付けば、わたくしはナイトくんを抱きしめたまま、オヴリオ様に横抱きに抱き上げられていました。
赤い炎に照らされて。
煙る視界に、近い距離で整った顔立ちを見て。
衣装ごしに伝わる体温と、逞しい体付きに、目の奥が熱くなって。
鼻がつんとして。じわりと視界が歪んで。
「――……オヴリオ様ぁっ……!!」
「心配した。すごく、……すごく!!」
熱を吐き出すようにオヴリオ様が仰る声が、わたくしに現実を教えてくれて、「もう大丈夫」と言ってくださると、まだ炎の中なのに、本当に大丈夫になったみたいに、全身が弛緩しました。
「ふ……っ、う……、う……、ひっく……っ」
ほろほろと、熱い液体がこぼれて、乾燥した頬が濡れていきます。
子供みたいに泣きじゃくっていると、ナイトくんが焦げた手で一生懸命頬にハンカチをあててくれて、わたくしはもっと泣いてしまうのでした。
「じっとして。できるだけ肌に触れないように」
「あ……っ」
助けにきてくれた……、そんな現実が嬉しくて、同時に「触れないように」という言葉が気になってしまいます。
……アミティエ様には、触れていたのに。
――……そんなことを考えている場合じゃ、ないのに。