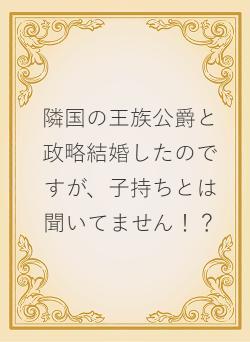9、恋するフィユテページュ、約束をあなたと
パーティが終わって馬車で送ってくださるとき、オヴリオ様はお土産を持たせてくださいました。
可愛らしいお花のブーケと、お菓子です。
「あら、このお花」
星のかたちに似た花弁。押し花のしおりにもしているお花ではありませんか。
「花は君が好きなカランコエ。お菓子は名付けて『恋するフィユテページュ』……白桃のパイケーキだよ」
オヴリオ様はスイーツに名前をつけるのがお好きなのでしょうか。
「可愛らしい名前のパイケーキですわね。ありがとうございます」
「料理名だからな、あくまで料理名。俺と婚約してくれてありがとう、メモリア。好きじゃないけど」
あっ。呼び捨てです。
親しい感じで、心地よい響きです。
「わたくし、呼び捨てにされるのが好きですわ。でも、最後の一言で台無しですの」
「大切なことだから」
「あっ、はい。わたくしも好きじゃないですわ」
薄暗い夜天には控えめに星が光っていて、光の砂をばら撒いたみたいに美しい空でした。
高いところは黒玻璃のようで、地上に近いところは薄く色を変化させていて。
幻想的です。
そんな綺麗な夜空を背負うようにして、オヴリオ様はやさしく微笑んだのです。
「婚約者である君を、俺は幸せにしたい。君を世界で一番幸せにするよ、約束する。恋愛はしないけど」
声はとても優しくて、甘やかでした。
糖分多すぎのスイーツみたい。耳が蕩けてしまいそう。耳たぶと頬が熱いです。
「ま、まあ……なんて言葉を返せばいいのか、わかりませんわ。あとやっぱり最後で台無し」
「大切なことだから」
「大切……なのですね」
銀色の長いまつ毛に彩られ、蠱惑的な色香を放つオヴリオ様の瞳は、不思議な感情を揺らめかせています。
「これはあくまでも、断罪を回避するために必要だったからした、恋愛感情の伴わない婚約。俺はアミティエ嬢が好きで、君は兄上が好きなんだ。それは、大前提なんだよ」
ゆったりと紡がれる言葉は、自分に言い聞かせるようでした。
「俺は君を幸せにするつもりがあるけれど、君の兄上への恋情はそのままでいい。俺を好きにならなくていい。ただ、俺に尽くさせてくれて、周りを気にせずのびのびとして、健やかに贅沢を満喫してくれたらいい……」
どうして。
どうして。
そんなに、一生懸命に熱っぽく、仰るの。
「オヴリオ様」
わたくし、あなたのお兄様への恋情を抱いていないように思うのです。
素敵な方だとは思いますが、アミティエ様と親しくなさっていても、わたくしは全然気になりませんでしたわ。
むしろ、わたくしが心配なのは、あなたなのですが?
わたくしが気になっているのは、あなたですが……?
「メモリア。学園に通うとき、送り迎えをするから、朝は『おはよう』と言って。帰りは『また明日』と言って。一緒にランチタイムを過ごしてくれて、おいしいごはんを食べて、おいしいねと笑ってくれたらいい」
オヴリオ様は、なんだかとても必死な感じでした。
秀麗な眉はきゅっと寄っていて、目には熱がこもっていて。
言葉は、わたくしに優しくきこえるように、傷付けないようにと懸命に選んでいる様子なのです。
わたくしは何も言えず、その真剣さに目を瞠るばかりでした。
「メモリア。兄上とは仲良くしても構わない。でも、他の男とは親しくしないように。君はあくまでも俺の婚約者で、他の男のものにはならないんだ。それは、絶対なんだ」
断言する声はちょっと掠れていて、余裕がなさそうな感じで。
緑色の眼差しには、執着みたいな色があるのです。はっきりと、そんな気配がわかるのです。
そう感じた瞬間、背筋をぞくりとした何かが駆け上るようでした。
それは、決して不快ではなく、どちらかといえば甘く痺れるような、ふわふわとした何かでした。
「オ……オヴリオ、様」
オヴリオ様。
オヴリオ様。
……オヴリオ様。
あなたは一体、なんですの。
わたくしとあなたは、なんですの。
オヴリオ様は苦しそうな顔をして、手袋をはめた指先をわたくしの髪に絡めました。
いつくしむように掬い上げて、髪にキスを落とされると、わたくしは呼吸を一瞬忘れて、くらくらとしてしまいました。
「好きじゃない。恋をしてほしいわけじゃない。むしろ、しなくていいんだ」
――しなくていい。
「仰ることとなさっていることが一致しませんわ」
そんな風に、世界で一番大切な宝物を扱うみたいに髪を撫でられたら、勘違いしてしまいますわ。
「すまない。君の髪が綺麗で、触れてみたくて。つい触ってしまった」
オヴリオ様は言い訳しながら視線を外して、髪を放してくれました。
心臓に悪い方ですわ。
罪作りな方ですわ。
きっとこんな風に、軽い調子で女性に接して、たくさんの女性に勘違いさせているんですわ。
特別ではないのですわ。
わたくしが、自意識過剰なのですわ。大袈裟に受け止めているのですわ。きっと、そう。
きっと……そういうことにしたほうが、いいのですわ。
わたくしは自分に言い聞かせるようにして、頷きました。
「はい、オヴリオ様。約束しますわ。朝は『おはよう』と言って。帰りは『また明日』と言って。一緒にランチタイムを過ごしてくれて、おいしいごはんを食べて、おいしいねと笑う……わたくしたち、そんな婚約者でいましょう」
――オヴリオ様は、わたくしに恋愛は求めていないのですね。わたくしと恋愛をするおつもりは、ないのですね。
「わたくしも貴族の娘ですもの。恋物語に憧れることはございますが、恋や愛のない婚姻にも文句を申したりはいたしませんわ。まして、あなたはとても高貴で、優しくて、わたくしや伯爵家には光栄にすぎるお相手で……その上、わたくしを幸せにしてくださると約束をしてくださるのですもの」
アミティエ様の華麗なお姿が、わたくしの脳裏によぎりました。
わたくしとあの聖女様は、あまりに違いすぎて、対抗する気にもなりません。
以前のわたくしは、どうも悪役令嬢としてあんなことやこんなことをしていたというのですが……以前のわたくし、強気でしたのね。自分とは思えません。
「わたくし、ちゃんと……わきまえておりますわ。ですから、ご安心くださいませ。オヴリオ様」
……あなたに恋愛感情を求めて困らせるような婚約者には、なりません。
わたくしは心の中でそう誓って、日記にも書いておこうと決意したのでした。
「メモリア。君は流行小説に出てくる悪役令嬢みたいに、高笑いしながら他者に偉そうにしてもいいし、取り巻きグループを作って学園を牛耳ってもいい」
「流行小説がお好きですわね、オヴリオ様」
日記にはもうひとつ書き加えないとですね。
……『王子様は、流行小説がお好き』と。
パーティが終わって馬車で送ってくださるとき、オヴリオ様はお土産を持たせてくださいました。
可愛らしいお花のブーケと、お菓子です。
「あら、このお花」
星のかたちに似た花弁。押し花のしおりにもしているお花ではありませんか。
「花は君が好きなカランコエ。お菓子は名付けて『恋するフィユテページュ』……白桃のパイケーキだよ」
オヴリオ様はスイーツに名前をつけるのがお好きなのでしょうか。
「可愛らしい名前のパイケーキですわね。ありがとうございます」
「料理名だからな、あくまで料理名。俺と婚約してくれてありがとう、メモリア。好きじゃないけど」
あっ。呼び捨てです。
親しい感じで、心地よい響きです。
「わたくし、呼び捨てにされるのが好きですわ。でも、最後の一言で台無しですの」
「大切なことだから」
「あっ、はい。わたくしも好きじゃないですわ」
薄暗い夜天には控えめに星が光っていて、光の砂をばら撒いたみたいに美しい空でした。
高いところは黒玻璃のようで、地上に近いところは薄く色を変化させていて。
幻想的です。
そんな綺麗な夜空を背負うようにして、オヴリオ様はやさしく微笑んだのです。
「婚約者である君を、俺は幸せにしたい。君を世界で一番幸せにするよ、約束する。恋愛はしないけど」
声はとても優しくて、甘やかでした。
糖分多すぎのスイーツみたい。耳が蕩けてしまいそう。耳たぶと頬が熱いです。
「ま、まあ……なんて言葉を返せばいいのか、わかりませんわ。あとやっぱり最後で台無し」
「大切なことだから」
「大切……なのですね」
銀色の長いまつ毛に彩られ、蠱惑的な色香を放つオヴリオ様の瞳は、不思議な感情を揺らめかせています。
「これはあくまでも、断罪を回避するために必要だったからした、恋愛感情の伴わない婚約。俺はアミティエ嬢が好きで、君は兄上が好きなんだ。それは、大前提なんだよ」
ゆったりと紡がれる言葉は、自分に言い聞かせるようでした。
「俺は君を幸せにするつもりがあるけれど、君の兄上への恋情はそのままでいい。俺を好きにならなくていい。ただ、俺に尽くさせてくれて、周りを気にせずのびのびとして、健やかに贅沢を満喫してくれたらいい……」
どうして。
どうして。
そんなに、一生懸命に熱っぽく、仰るの。
「オヴリオ様」
わたくし、あなたのお兄様への恋情を抱いていないように思うのです。
素敵な方だとは思いますが、アミティエ様と親しくなさっていても、わたくしは全然気になりませんでしたわ。
むしろ、わたくしが心配なのは、あなたなのですが?
わたくしが気になっているのは、あなたですが……?
「メモリア。学園に通うとき、送り迎えをするから、朝は『おはよう』と言って。帰りは『また明日』と言って。一緒にランチタイムを過ごしてくれて、おいしいごはんを食べて、おいしいねと笑ってくれたらいい」
オヴリオ様は、なんだかとても必死な感じでした。
秀麗な眉はきゅっと寄っていて、目には熱がこもっていて。
言葉は、わたくしに優しくきこえるように、傷付けないようにと懸命に選んでいる様子なのです。
わたくしは何も言えず、その真剣さに目を瞠るばかりでした。
「メモリア。兄上とは仲良くしても構わない。でも、他の男とは親しくしないように。君はあくまでも俺の婚約者で、他の男のものにはならないんだ。それは、絶対なんだ」
断言する声はちょっと掠れていて、余裕がなさそうな感じで。
緑色の眼差しには、執着みたいな色があるのです。はっきりと、そんな気配がわかるのです。
そう感じた瞬間、背筋をぞくりとした何かが駆け上るようでした。
それは、決して不快ではなく、どちらかといえば甘く痺れるような、ふわふわとした何かでした。
「オ……オヴリオ、様」
オヴリオ様。
オヴリオ様。
……オヴリオ様。
あなたは一体、なんですの。
わたくしとあなたは、なんですの。
オヴリオ様は苦しそうな顔をして、手袋をはめた指先をわたくしの髪に絡めました。
いつくしむように掬い上げて、髪にキスを落とされると、わたくしは呼吸を一瞬忘れて、くらくらとしてしまいました。
「好きじゃない。恋をしてほしいわけじゃない。むしろ、しなくていいんだ」
――しなくていい。
「仰ることとなさっていることが一致しませんわ」
そんな風に、世界で一番大切な宝物を扱うみたいに髪を撫でられたら、勘違いしてしまいますわ。
「すまない。君の髪が綺麗で、触れてみたくて。つい触ってしまった」
オヴリオ様は言い訳しながら視線を外して、髪を放してくれました。
心臓に悪い方ですわ。
罪作りな方ですわ。
きっとこんな風に、軽い調子で女性に接して、たくさんの女性に勘違いさせているんですわ。
特別ではないのですわ。
わたくしが、自意識過剰なのですわ。大袈裟に受け止めているのですわ。きっと、そう。
きっと……そういうことにしたほうが、いいのですわ。
わたくしは自分に言い聞かせるようにして、頷きました。
「はい、オヴリオ様。約束しますわ。朝は『おはよう』と言って。帰りは『また明日』と言って。一緒にランチタイムを過ごしてくれて、おいしいごはんを食べて、おいしいねと笑う……わたくしたち、そんな婚約者でいましょう」
――オヴリオ様は、わたくしに恋愛は求めていないのですね。わたくしと恋愛をするおつもりは、ないのですね。
「わたくしも貴族の娘ですもの。恋物語に憧れることはございますが、恋や愛のない婚姻にも文句を申したりはいたしませんわ。まして、あなたはとても高貴で、優しくて、わたくしや伯爵家には光栄にすぎるお相手で……その上、わたくしを幸せにしてくださると約束をしてくださるのですもの」
アミティエ様の華麗なお姿が、わたくしの脳裏によぎりました。
わたくしとあの聖女様は、あまりに違いすぎて、対抗する気にもなりません。
以前のわたくしは、どうも悪役令嬢としてあんなことやこんなことをしていたというのですが……以前のわたくし、強気でしたのね。自分とは思えません。
「わたくし、ちゃんと……わきまえておりますわ。ですから、ご安心くださいませ。オヴリオ様」
……あなたに恋愛感情を求めて困らせるような婚約者には、なりません。
わたくしは心の中でそう誓って、日記にも書いておこうと決意したのでした。
「メモリア。君は流行小説に出てくる悪役令嬢みたいに、高笑いしながら他者に偉そうにしてもいいし、取り巻きグループを作って学園を牛耳ってもいい」
「流行小説がお好きですわね、オヴリオ様」
日記にはもうひとつ書き加えないとですね。
……『王子様は、流行小説がお好き』と。