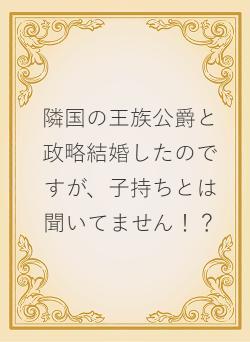京也は桜子の震える指先を包み込み、そのままそっと自分の胸へと導いた。
硬い胸板を通して彼の鼓動が感じられて、桜子はドキリとした。
「桜子さん。ひとつだけ覚えていてほしいことがある」
声の底に灯る温かさと重みは、桜子の心をゆっくりとほどいていく。
いつも――いつもだ。
この落ち着いた温かな『夫』は、桜子を優しいとよく言うが、彼こそが誰よりも優しいのだ――桜子はそう実感した。
京也は理知的な声で穏やかに言葉を紡ぐ。
「人間も、あやかしも、動物も。年頃になれば生命という種が持つ本能で、異性を求め、恋をする。きっかけが容姿での一目惚れだったり、家の都合で決められた結婚だったりしても、そこから恋をして、深く純粋な愛情が育まれることはある」
言われてみれば、そうだ。
桜子は京也の言葉に説得力を覚え、頷いた。
「俺は、君と出会ってからというもの、君の反応のひとつひとつに心を奪われた。今もだよ。君はかわゆい。そして素直で善良だ。君のものの考え方、他者を思いやる優しさ、転んでも立ち上がり、前を向ける強さ。どれも、俺が惚れ直す理由ばかりだ」
彼の声が、少し低くなる。
「だから俺は断言できる。誰がなんと言おうと俺が君を愛しているというこの気持ちは、真実の愛だ。運命の番であろうとなかろうと、俺は自分の好みで君を選んだのだ。俺の意思で、君を想っているのだよ」
そう言って、京也は立ち上がり、枕元の灯をふっと吹き消した。
一瞬で室内が暗くなり、もみじが小さく「きゃっ」と悲鳴のようなはしゃいでいるような声をあげてから、「もみじはいません」と囁く声が可愛い。
おそらく、夫婦の時間を邪魔しないように気配を殺しているのだろう……。
「もみじ。うしまると犬彦のところに行っておいで」
「あい」
京也が甘やかすような声色で言い、もみじがひらりと飛んでいく。
(うしまると犬彦のところ? 近くにいるの?)
考えているうちに闇に慣れた目の前で、京也の輪郭が近づいてくる。
息が触れる距離で、彼はそっと囁いた。
「こほん。仕切り直しをしよう。俺が君を愛しているというこの気持ちは、真実の愛だ。信じてほしい」
「あっ、はい……」
桜子が仕切り直しに応じて真面目な顔をすると、京也はフッと笑って右手の人差し指で桜子の耳をなぞった。
「もっとも――『信じません』なんて台詞は、言わせないがな」
その眼差しは熱っぽく、普段よりも遠慮がない。
桜子はまるで飢えた肉食獣に捕捉された獲物の気分になった。
「もっとも君は今、『はい』と言った。俺の愛を疑わず受け入れてくれるということだ」
低く甘い声と共に、吐息が奪われ――唇が重なる。
優しく、それでいて逃がしてくれない気配の抱擁に、桜子の心臓が激しく高鳴る。
「いつか、教えると言っただろう。桜子さん」
唇を解放して、京也は熱く囁いた。
「何を教えると言われたんだっけ」と考えている間に、問いかけが連なる。
「ゆえに教える。よいだろうか」
有無を言わせぬ口調で言う京也は桜子の黒髪を一筋すくい、大切に口付ける。
髪には神経が通っていないのに、桜子はなぜかぞくぞくと甘く痺れるような感覚がして身を震わせた。
「な……なにを、でしょうか?」
「恋を。愛を。全てを」
全てを知っているのだ、と自信満々に言う夫は、桜子の返事が意に反するものであっても――例えば拒絶であっても――聞かない気配でもある。それが不思議と桜子には嫌ではない。むしろ。
「……嬉しいです。京也様」
桜子は目を閉じ、胸の奥のざわめきを託すように、ゆっくりと両腕を京也の背に回した。
「うむ。俺は世界一の夫ゆえ、君をたくさん嬉しくさせてあげよう」
偉そうに言う彼は、本当に偉いのだ。
――そんな現実が面白くて、心地いい。
再び口付けがされて、彼の鼓動と自分の鼓動がゆっくりとひとつに重なっていく。
夜の暗闇は月明かりと人工の明かりに抗いながら世界を包み込み、二人の旅の初夜を静かに優しく祝福していた。
――了。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
番外編を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
書籍発売から一週間が経ちました。
ご購入くださったみなさま、誠にありがとうございます。
作者も本を入手して、庭春樹様の繊細で雰囲気たっぷり、可愛らしく美麗なイラストやデザイナー様の書影デザイン、ページの厚みなどに惚れ惚れとしています。
たくさんの方のおかげで、一生に一度の書籍作品ができあがったのだなと思うと、感謝の気持ちでいっぱいになります。
「ありがとう」ばかり繰り返しているな、と自覚しているのですが、重ねて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
硬い胸板を通して彼の鼓動が感じられて、桜子はドキリとした。
「桜子さん。ひとつだけ覚えていてほしいことがある」
声の底に灯る温かさと重みは、桜子の心をゆっくりとほどいていく。
いつも――いつもだ。
この落ち着いた温かな『夫』は、桜子を優しいとよく言うが、彼こそが誰よりも優しいのだ――桜子はそう実感した。
京也は理知的な声で穏やかに言葉を紡ぐ。
「人間も、あやかしも、動物も。年頃になれば生命という種が持つ本能で、異性を求め、恋をする。きっかけが容姿での一目惚れだったり、家の都合で決められた結婚だったりしても、そこから恋をして、深く純粋な愛情が育まれることはある」
言われてみれば、そうだ。
桜子は京也の言葉に説得力を覚え、頷いた。
「俺は、君と出会ってからというもの、君の反応のひとつひとつに心を奪われた。今もだよ。君はかわゆい。そして素直で善良だ。君のものの考え方、他者を思いやる優しさ、転んでも立ち上がり、前を向ける強さ。どれも、俺が惚れ直す理由ばかりだ」
彼の声が、少し低くなる。
「だから俺は断言できる。誰がなんと言おうと俺が君を愛しているというこの気持ちは、真実の愛だ。運命の番であろうとなかろうと、俺は自分の好みで君を選んだのだ。俺の意思で、君を想っているのだよ」
そう言って、京也は立ち上がり、枕元の灯をふっと吹き消した。
一瞬で室内が暗くなり、もみじが小さく「きゃっ」と悲鳴のようなはしゃいでいるような声をあげてから、「もみじはいません」と囁く声が可愛い。
おそらく、夫婦の時間を邪魔しないように気配を殺しているのだろう……。
「もみじ。うしまると犬彦のところに行っておいで」
「あい」
京也が甘やかすような声色で言い、もみじがひらりと飛んでいく。
(うしまると犬彦のところ? 近くにいるの?)
考えているうちに闇に慣れた目の前で、京也の輪郭が近づいてくる。
息が触れる距離で、彼はそっと囁いた。
「こほん。仕切り直しをしよう。俺が君を愛しているというこの気持ちは、真実の愛だ。信じてほしい」
「あっ、はい……」
桜子が仕切り直しに応じて真面目な顔をすると、京也はフッと笑って右手の人差し指で桜子の耳をなぞった。
「もっとも――『信じません』なんて台詞は、言わせないがな」
その眼差しは熱っぽく、普段よりも遠慮がない。
桜子はまるで飢えた肉食獣に捕捉された獲物の気分になった。
「もっとも君は今、『はい』と言った。俺の愛を疑わず受け入れてくれるということだ」
低く甘い声と共に、吐息が奪われ――唇が重なる。
優しく、それでいて逃がしてくれない気配の抱擁に、桜子の心臓が激しく高鳴る。
「いつか、教えると言っただろう。桜子さん」
唇を解放して、京也は熱く囁いた。
「何を教えると言われたんだっけ」と考えている間に、問いかけが連なる。
「ゆえに教える。よいだろうか」
有無を言わせぬ口調で言う京也は桜子の黒髪を一筋すくい、大切に口付ける。
髪には神経が通っていないのに、桜子はなぜかぞくぞくと甘く痺れるような感覚がして身を震わせた。
「な……なにを、でしょうか?」
「恋を。愛を。全てを」
全てを知っているのだ、と自信満々に言う夫は、桜子の返事が意に反するものであっても――例えば拒絶であっても――聞かない気配でもある。それが不思議と桜子には嫌ではない。むしろ。
「……嬉しいです。京也様」
桜子は目を閉じ、胸の奥のざわめきを託すように、ゆっくりと両腕を京也の背に回した。
「うむ。俺は世界一の夫ゆえ、君をたくさん嬉しくさせてあげよう」
偉そうに言う彼は、本当に偉いのだ。
――そんな現実が面白くて、心地いい。
再び口付けがされて、彼の鼓動と自分の鼓動がゆっくりとひとつに重なっていく。
夜の暗闇は月明かりと人工の明かりに抗いながら世界を包み込み、二人の旅の初夜を静かに優しく祝福していた。
――了。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
番外編を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
書籍発売から一週間が経ちました。
ご購入くださったみなさま、誠にありがとうございます。
作者も本を入手して、庭春樹様の繊細で雰囲気たっぷり、可愛らしく美麗なイラストやデザイナー様の書影デザイン、ページの厚みなどに惚れ惚れとしています。
たくさんの方のおかげで、一生に一度の書籍作品ができあがったのだなと思うと、感謝の気持ちでいっぱいになります。
「ありがとう」ばかり繰り返しているな、と自覚しているのですが、重ねて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。