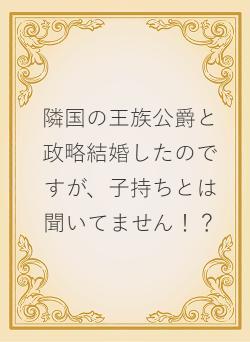夕食が終わると、布団を敷く時間だ。
京也が手際よく布団を敷くのを見て思い出したのは、旅行前に友人の咲花から聞いた言葉だった。
『いいこと、桜子さん。殿方の心を射止めるには、まず距離を近づけること。布団をね、くっつけるのよ』
(……距離を、くっつける)
桜子は意を決して、自分の布団をぴったり隣に敷こうと手を伸ばした。
すると、京也がその手を掴んで制止し、後ろから抱きすくめる。
「桜子さん。俺は思うのだが、同じ布団に入ればいいのでは?」
「~~っ!」
桜子の耳まで真っ赤になりながら、おろおろと頷いた。
(う、頷いちゃった!)
――咲花さん、京也様はお布団をくっつけるどころじゃなかったです!
同じ布団に入ってしまいました!
貴重品と家宝の遠見の鏡を枕元に置き、心の中で咲花に報告する桜子を布団に引き入れて、京也は微笑ましい生き物を慈しむような目になった。
そして、遠見の鏡を指先でとんとんとつついて、桜子に見るようにと促した。
「桜子さん、君の大切な鏡を少し借りてもいいだろうか?」
「は……はい……?」
「ありがとう。では、見てごらん」
表面に月光のような光がゆらりと走り、やがて波紋が広がる。
鏡の中に映ったのは、白い霧に包まれた幻想の風景だった。
天と地の境があやふやな景色の中を、美しい羽を持つ影が空を翔ける。
山の頂には、社があった。
その境内に降り立った『天狗』は、巫女衣裳の娘に迎えられ、柔らかに抱きしめる。
(……愛し合っているんだ)
桜子はそう思った。
感想を裏付けするように、京也はあたたかな声で説明してくれる。
「娘は人の子。天狗は俺の先祖だな。まだ運命の番という習性が俺たちになかった時代のことだ」
鏡の中では、天狗帝が娘の手を取り、何かを語りかけている。
言葉は聞こえないが、空気の温度が伝わってくるようだった。ああ――煌めく指輪を填めている……。
「あやかしは、人間と共に歩もうとする親人間派と、人間を見下し、狩るべきものとする反人間派に分かれていた。まあ、今もだが……」
京也は「今はそれほど過激派は多くない」と安心させるように言葉を続ける。
「娘を溺愛した天狗は反人間派が力を笠に着て暴れるのを見て考えた。あやかしが人を蔑むのは、力の差と心の断絶にある……と」
それは、人間同士でもそうだ。
桜子はそんな考えを抱きつつ、京也の語りを邪魔しないように静かに頷いた。
「……天狗は自分の恋を、世界の形に変えた。運命の番という制度を作り、力あるあやかしの一族を選び、それを本能のように植えつけた」
桜子は息を呑む。
鏡の中では、天狗帝があやかしを集め、大きな扇を振っている。
扇を振るたびに舞う黄金色の花吹雪は、あやかしたちの体に――魂に、溶け込んでいくようだった。
何も知らなければ祝福が授けられているように見える美しい光景だったが、桜子は夏清の言葉を強く思い出してしまった。
『不健全な関係だ』
『愛し合ってると勘違いしてる』
――これは、呪いだ。
京也が少しだけ目を伏せる。
「人間の中にも、強い承事師たちがいた。彼らの多くはあやかしを祓うことを己の使命としていた。そこで天狗帝は、彼らの力を測る結びの儀式を作ったんだ。驚異的な能力者がいれば、その心根を監視する。場合によっては――こほん。人間とあやかしが互いの存在を知り、均衡を保つための措置だ」
危険だと判断されれば、その能力者は命を奪われてしまうのだろうか。
桜子は背筋をぞくりと震わせた。
鏡の映像は、また変わる。
荒れ狂う海、真紅の甲殻を持ち、炎を纏った……蟹?
大きな蟹が、うようよと集まっている。
その怒りの咆哮が空を裂く。
『人間と蟹が番えるかカニ! 笑止カニ!』
(あ、蟹で合ってるみたい)
映像の現場は真剣な雰囲気なのに、桜子は若干、脱力してしまった。
蟹のあやかしは怒っているようなのだが、なんとなく緩い雰囲気で、愛嬌があるのだ。
しかし、そんな可愛い蟹たちに、天狗の声が冷たく響く。
『面倒な火蟹一族め。お前たちは封じておこう。頭を冷やすまで、海の底でな』
『カ、カニー!』
次の瞬間、光の封印が走り、火蟹たちが波間に沈んでいった。
京也は淡々とした声で解説する。
「これは見せしめの効果もあった。見ろ、隅の方で木の葉たぬきの一族がしょぼしょぼしている」
「まあ」
思わず声が出る。
鏡の映像に、額に木の葉を載せたたぬきが映っている。
普通の動物のたぬきとそう変わらない姿をしている木の葉たぬきは、おどおど、とろとろとした風情で頭を下げたり上げたり、きょろきょろしたりしている。
『た、たぬきはですね。乱暴などはしないのでしてね、いいこなのですね……。寿命が短くなっても良いのでして……封印は……』
『お前たちはいい。山へ帰れ』
『よ、よろしいのです? たぬき、ゆるされたです……?』
たぬきが許されてよかった。
桜子は短い時間ですっかりたぬきの味方の気分で安堵の吐息を零した。
それを見て、京也はくくっと喉を鳴らして笑っている。
「桜子さんは優しいな」
鏡面に広がった水の紋が、静かに収束していく。
「……俺の祖先は、火蟹を封じながらも、見捨てはしなかった。封印は定期的に緩くなり、連中はわらわらと漏れ出すのだ。人を襲わなければ構わんが、襲うなら海に戻すし、人間の陰陽師に退治されることもある」
「定期的に……なるほど」
京也の指先が、鏡の縁をなぞる。
彼の横顔は、どこか切なくも誇らしげだった。
「初代天狗帝は、自分の子孫の善良さを信じていなかった。親が人を愛しても、子が同じ道を選ぶとは限らないから。ゆえに、俺たち子孫は運命の番に振り回されている……」
静寂がなんだか苦しい。
桜子は、そっと布団の中で京也の袖をつまんだ。
京也は、運命の番についてどう思っているのだろう。
本当は嫌なのではないか。
だって、話を聞いていると夏清の感想が真っ当に思えてしまうのだ。
――呪いのようなものに縛られてしまって。心が自由ではない。
そんな愛は、偽物ではないか。
押し付けられた愛を受け入れなければ弱って死んでしまうなんて、可哀想なのでは?
「ああ。君が何に心を痛めているか、俺にはわかるよ、桜子さん」
桜子の震える指先を自分の手で包み込み、京也はおっとりと微笑んだ。