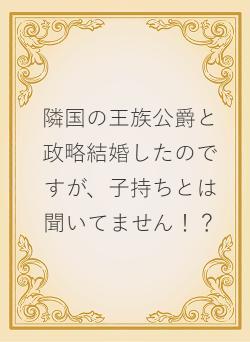木枯らし亭に戻り、売店に立ち寄った桜子は、陳列棚の品物を指して購入報告をした。
「この最中と、こちらの蒲鉾を……」
「ふむ、ふむ。いいと思う。一緒に選べなくてすまなかった……明日は犬彦首輪を選びにいこうか?」
「首輪、本気だったんですか」
部屋に一度立ち寄ってからは、夕食前の入浴時間だ。
男女別の暖簾の前で立ち止まり、「またあとで」と言って別々の浴場を利用する。
「かしきりのおふろもあるのよ、きょうやさま」
「も、もみじちゃん……!」
(京也様と一緒に入浴するなんて、想像しただけで気絶してしまいそう!)
桜子はもみじを連れ去るように脱衣所に駆け込み、浴衣を脱いで浴槽に漬かった。
「あるじさま、はずかしいのね」
もみじがくすくす笑う声が羞恥心を煽る。
紅潮した頬に湯けむりが優しく感じる。
湯はやわらかく肌に馴染み、体の芯までぽかぽかと温めてくれた。
湯から上がって暖簾の外に出ると、京也は先に出ていた。
湯上り所にいる他の宿泊客が京也に視線を寄せている。
桜子を見つけてパッと満面の笑みになり、次いで何を思ったか頬を赤らめて視線を逸らし、数秒間手で口元を覆ってから駆け寄ってくる――そんな一連の挙動に、周囲が一緒になって赤くなったり悶絶したりしているのが、おかしい。
「桜子さんの湯上りの色っぽい姿を俺以外に見せるのはもったいないな。隠してしまいたくなるよ」
顔を近づけてヒソヒソと深刻な表情で内緒話をする京也からふんわりとしたいい匂いがして、桜子はどきりとした。
――周囲が注目するのもわかる。
京也の濡れた黒髪が首筋にかかり、涼やかな目元が灯りに照らされるたび、空気がふっと張りつめる。
女性客だけでなく、通りかかった男たちまで思わず息を呑むほどの美貌と色香。
――この人の魅力は、性別を問わず心を奪うのだ。
部屋に戻ると、夕食の膳が整っていた。
部屋食の会席は、新鮮な海の素材、旬の食材を使用した季節感たっぷり。
贅沢の極み料理だ。
品よく味のある陶器の器は葉っぱの形をしていたり横長だったり。
内側が赤いお椀はお吸い物が入っていて、白い蓮根蒸しの上に人参とほうれん草がちょこんと飾られている。
牛肉の陶板焼きは見ているだけで食欲をそそり、涎が湧く。
「いただきます」
「いただきます」
二人で一緒に挨拶をして、箸を勧める。
「美味しいです!」
「うん、美味しい」
同時に声をあげて、目が合って自然と笑みがこぼれる。
船盛りは旬の鮮魚三種盛りで、極上の味わい。
桜海老天ばら御飯がほかほかだ。
鍋の蓋を取った瞬間、ふわりと立ちのぼる香りに桜子は息を呑んだ。
湯気の向こうに、真紅の脚と甲羅の蟹が、艶やかに光っている。
昆布出汁の上品な香りに、蟹味噌の濃厚な旨味が溶け合って――なんて食欲をそそる匂いだろう!
ごくりと唾を呑んで蟹を見つめていると、京也が不思議なことを言う。
「普通の蟹だから安心しておくれ」
箸を伸ばして脚をつつくと、ハサミで甲羅が着られていて、白い身が見えている。
ほろりとした身を箸でつまむと、糸を引くようにほぐれていく。
口に運ぶと、世界が一瞬、蟹色に染まった。
濃密な甘み、とろけるような旨味が舌いっぱいに広がり、ほのかな塩気が後を引く。
あたたかい出汁がその身の隙間に染み込んで、噛むたびにじゅわりと旨味が滲み出すのだ。
「……蟹ですね……!」
思わず意味不明な賛辞を唱えてしまった。蟹が蟹なのは当たり前なのに。
「桜子さんは正しい。まさしく、これは蟹。皆が蟹と言われて脳裏に思い描く理想の蟹である!」
京也はニコニコしながら湯気越しに頷いて、蟹脚を褒めるように微笑んだ。
「蟹は正直だな。いい湯に浸ければ、ちゃんと応えてくれるのだ。蟹よ。妻を喜ばせてくれてありがとう」
蟹と語り合う優しい声を聞きながら、桜子は続きをいただいた。
蟹の爪を箸先でちょいちょいとほぐして頬張る。
「ん~~!」
美味しい!
ぷりっとした弾力のあとに、口の中でほぐれる繊細な食感が堪らない。
「君の『美味しい』が一番のご馳走だよ……しかし、あまり悩ましい声を出されると俺はドキドキしてしまう」
「な、悩ましい……? 申し訳……?」
「ああいや、謝る必要はない。要するにかわゆいということだ。いつものことだな、うむ」
もみじは時折「ふふふ」「くすくす」と忍び笑いをしつつ、部屋の中をひらひらと舞って遊んでいる。
穏やかな夕食の時間は、こうして、のんびりと過ぎていった。
「この最中と、こちらの蒲鉾を……」
「ふむ、ふむ。いいと思う。一緒に選べなくてすまなかった……明日は犬彦首輪を選びにいこうか?」
「首輪、本気だったんですか」
部屋に一度立ち寄ってからは、夕食前の入浴時間だ。
男女別の暖簾の前で立ち止まり、「またあとで」と言って別々の浴場を利用する。
「かしきりのおふろもあるのよ、きょうやさま」
「も、もみじちゃん……!」
(京也様と一緒に入浴するなんて、想像しただけで気絶してしまいそう!)
桜子はもみじを連れ去るように脱衣所に駆け込み、浴衣を脱いで浴槽に漬かった。
「あるじさま、はずかしいのね」
もみじがくすくす笑う声が羞恥心を煽る。
紅潮した頬に湯けむりが優しく感じる。
湯はやわらかく肌に馴染み、体の芯までぽかぽかと温めてくれた。
湯から上がって暖簾の外に出ると、京也は先に出ていた。
湯上り所にいる他の宿泊客が京也に視線を寄せている。
桜子を見つけてパッと満面の笑みになり、次いで何を思ったか頬を赤らめて視線を逸らし、数秒間手で口元を覆ってから駆け寄ってくる――そんな一連の挙動に、周囲が一緒になって赤くなったり悶絶したりしているのが、おかしい。
「桜子さんの湯上りの色っぽい姿を俺以外に見せるのはもったいないな。隠してしまいたくなるよ」
顔を近づけてヒソヒソと深刻な表情で内緒話をする京也からふんわりとしたいい匂いがして、桜子はどきりとした。
――周囲が注目するのもわかる。
京也の濡れた黒髪が首筋にかかり、涼やかな目元が灯りに照らされるたび、空気がふっと張りつめる。
女性客だけでなく、通りかかった男たちまで思わず息を呑むほどの美貌と色香。
――この人の魅力は、性別を問わず心を奪うのだ。
部屋に戻ると、夕食の膳が整っていた。
部屋食の会席は、新鮮な海の素材、旬の食材を使用した季節感たっぷり。
贅沢の極み料理だ。
品よく味のある陶器の器は葉っぱの形をしていたり横長だったり。
内側が赤いお椀はお吸い物が入っていて、白い蓮根蒸しの上に人参とほうれん草がちょこんと飾られている。
牛肉の陶板焼きは見ているだけで食欲をそそり、涎が湧く。
「いただきます」
「いただきます」
二人で一緒に挨拶をして、箸を勧める。
「美味しいです!」
「うん、美味しい」
同時に声をあげて、目が合って自然と笑みがこぼれる。
船盛りは旬の鮮魚三種盛りで、極上の味わい。
桜海老天ばら御飯がほかほかだ。
鍋の蓋を取った瞬間、ふわりと立ちのぼる香りに桜子は息を呑んだ。
湯気の向こうに、真紅の脚と甲羅の蟹が、艶やかに光っている。
昆布出汁の上品な香りに、蟹味噌の濃厚な旨味が溶け合って――なんて食欲をそそる匂いだろう!
ごくりと唾を呑んで蟹を見つめていると、京也が不思議なことを言う。
「普通の蟹だから安心しておくれ」
箸を伸ばして脚をつつくと、ハサミで甲羅が着られていて、白い身が見えている。
ほろりとした身を箸でつまむと、糸を引くようにほぐれていく。
口に運ぶと、世界が一瞬、蟹色に染まった。
濃密な甘み、とろけるような旨味が舌いっぱいに広がり、ほのかな塩気が後を引く。
あたたかい出汁がその身の隙間に染み込んで、噛むたびにじゅわりと旨味が滲み出すのだ。
「……蟹ですね……!」
思わず意味不明な賛辞を唱えてしまった。蟹が蟹なのは当たり前なのに。
「桜子さんは正しい。まさしく、これは蟹。皆が蟹と言われて脳裏に思い描く理想の蟹である!」
京也はニコニコしながら湯気越しに頷いて、蟹脚を褒めるように微笑んだ。
「蟹は正直だな。いい湯に浸ければ、ちゃんと応えてくれるのだ。蟹よ。妻を喜ばせてくれてありがとう」
蟹と語り合う優しい声を聞きながら、桜子は続きをいただいた。
蟹の爪を箸先でちょいちょいとほぐして頬張る。
「ん~~!」
美味しい!
ぷりっとした弾力のあとに、口の中でほぐれる繊細な食感が堪らない。
「君の『美味しい』が一番のご馳走だよ……しかし、あまり悩ましい声を出されると俺はドキドキしてしまう」
「な、悩ましい……? 申し訳……?」
「ああいや、謝る必要はない。要するにかわゆいということだ。いつものことだな、うむ」
もみじは時折「ふふふ」「くすくす」と忍び笑いをしつつ、部屋の中をひらひらと舞って遊んでいる。
穏やかな夕食の時間は、こうして、のんびりと過ぎていった。