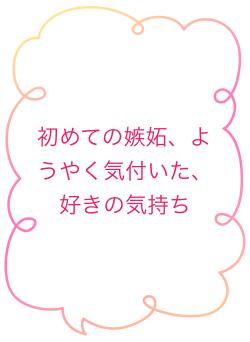「アンタら、相変わらず仲良いね。いっそのこと、付き合っちゃえばいいのに」
私と紫音がくだらない言い合いを続けていると、充希が横からそんなことをいってきた。
「やだよ、紫音なんて」
「俺だって乃彩なんかお断りだっての」
充希のように、二人が付き合えばいいのに、というのは昔からよく言われてきた。
私と紫音は小学校五年生の時からの腐れ縁。
同じクラスになって最初の席替えで隣の席になって以降よく話すようになって、当時男勝りだった私はよく男子と混じってサッカーをしたり虫取りをしたりと活発に活動していて、紫音とも考え方とか話が合うから自然と仲良くなった。
それは中学になっても変わらなくて、奇跡的にクラスが三年間同じだったこともあってよく一緒に行動していた。
初めこそ周りからは『付き合ってる』と噂されたりもしていたけど、私と紫音はあくまでも『友達』だと答えてきたし、私たちの間に、『恋愛』という感情は存在してなかった。
だけど、中学三年の秋くらいに、私の心に変化が訪れた。
それは、初めて紫音が同級生から告白されている現場を目撃した時で、もし、紫音が誰かと付き合ってしまったら、『友達』の私たちは傍に居られなくなってしまうのでは? と気付く。
傍に居られれば、『クラスメイト』でも『友達』でも『腐れ縁』でも良かったけど、異性の『友達』なんて、『恋人』が出来てしまえば一緒に居ることが難しくなると思ったら胸の奥がモヤモヤした。
そして、私は気付いた。
いつの間にか、私は紫音の事を、好きになっていたことに。
だけど、
恋愛にも、異性にも興味の無い紫音。
私も異性だけど、付き合いの長い私だけは特別だと言っていた。
その『特別』という言葉すら、好きだと気付くと、勘違いしてしまう程に舞い上がる。
結局、高校も同じになって、クラスも一緒。
何だかんだで、いつも傍に居る。
高校に入ってからというもの更に格好良くなった紫音はとにかくモテる。
背は高くて頭も良くて、運動神経も良い。
言い方はキツいところもあるし、少しつり目がちで目つきも悪く見えるし、自分のことをそこまで人に話すタイプじゃ無いし人にも無関心だけど、そういうクールなところが人気らしい。
私と紫音がくだらない言い合いを続けていると、充希が横からそんなことをいってきた。
「やだよ、紫音なんて」
「俺だって乃彩なんかお断りだっての」
充希のように、二人が付き合えばいいのに、というのは昔からよく言われてきた。
私と紫音は小学校五年生の時からの腐れ縁。
同じクラスになって最初の席替えで隣の席になって以降よく話すようになって、当時男勝りだった私はよく男子と混じってサッカーをしたり虫取りをしたりと活発に活動していて、紫音とも考え方とか話が合うから自然と仲良くなった。
それは中学になっても変わらなくて、奇跡的にクラスが三年間同じだったこともあってよく一緒に行動していた。
初めこそ周りからは『付き合ってる』と噂されたりもしていたけど、私と紫音はあくまでも『友達』だと答えてきたし、私たちの間に、『恋愛』という感情は存在してなかった。
だけど、中学三年の秋くらいに、私の心に変化が訪れた。
それは、初めて紫音が同級生から告白されている現場を目撃した時で、もし、紫音が誰かと付き合ってしまったら、『友達』の私たちは傍に居られなくなってしまうのでは? と気付く。
傍に居られれば、『クラスメイト』でも『友達』でも『腐れ縁』でも良かったけど、異性の『友達』なんて、『恋人』が出来てしまえば一緒に居ることが難しくなると思ったら胸の奥がモヤモヤした。
そして、私は気付いた。
いつの間にか、私は紫音の事を、好きになっていたことに。
だけど、
恋愛にも、異性にも興味の無い紫音。
私も異性だけど、付き合いの長い私だけは特別だと言っていた。
その『特別』という言葉すら、好きだと気付くと、勘違いしてしまう程に舞い上がる。
結局、高校も同じになって、クラスも一緒。
何だかんだで、いつも傍に居る。
高校に入ってからというもの更に格好良くなった紫音はとにかくモテる。
背は高くて頭も良くて、運動神経も良い。
言い方はキツいところもあるし、少しつり目がちで目つきも悪く見えるし、自分のことをそこまで人に話すタイプじゃ無いし人にも無関心だけど、そういうクールなところが人気らしい。