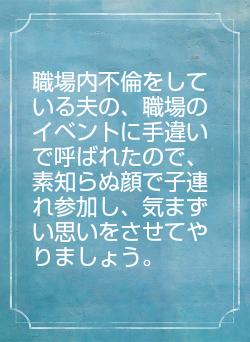妻に伝えてくれと言ったのに、「私はまだマリちゃんの彼と会っていないから〜」となどと言って逃げるのだ。なんと無責任な奴だろう!
責任と言えば、私はマリちゃんの親代わりとして、この怪しい結婚を止めなくても良いのだろうか。果たして彼は真っ当な人間なのだろうか。
……ああ、胃が痛くなってきた。
「ただいま~。」
聞こえてきたのん気な声に、私は背筋が伸びた。
「むっちゃ疲れたわ~。はいおっさん、お土産。」
部屋に入るなり紙袋を渡してきた息子。
こいつにお土産という発想があったのか。
息子の成長に感動しながら少し頬を緩め、紙袋を開けようとした私は、次の言葉を聞いて手を止めた。
「あ、それ、中の小さい方の箱はマリんだから。いや、別に土産なんてやる必要はないんだけどさ。あいつ東京行ったことないだろうしさ〜。まあ、義理だよ、義理!」
「……。」
ああ、どうしよう。
伊藤達夫、六十ニ歳。
哀れな息子をもつ、父親である――。
責任と言えば、私はマリちゃんの親代わりとして、この怪しい結婚を止めなくても良いのだろうか。果たして彼は真っ当な人間なのだろうか。
……ああ、胃が痛くなってきた。
「ただいま~。」
聞こえてきたのん気な声に、私は背筋が伸びた。
「むっちゃ疲れたわ~。はいおっさん、お土産。」
部屋に入るなり紙袋を渡してきた息子。
こいつにお土産という発想があったのか。
息子の成長に感動しながら少し頬を緩め、紙袋を開けようとした私は、次の言葉を聞いて手を止めた。
「あ、それ、中の小さい方の箱はマリんだから。いや、別に土産なんてやる必要はないんだけどさ。あいつ東京行ったことないだろうしさ〜。まあ、義理だよ、義理!」
「……。」
ああ、どうしよう。
伊藤達夫、六十ニ歳。
哀れな息子をもつ、父親である――。