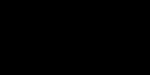でも、そんなことを気にしてないだなんて……。そういうものは必然的に気にするものだと、勝手に思っていた。
「確かに……俺はいずれ、店を継がなければならない。でも、店を継ぐのはまだ先の話だ。……俺は別に、早く結婚したいから奏音のことを好きになった訳じゃない。 奏音の人柄に、奏音の全てに惚れたんだ」
「私の……全て?」
百合原さんは私の頬を優しく包み込み、そっと撫でる。
「そう。奏音は奏音であって、奏音でしかないんだ。……だから誰かと比べたり、家柄とか、そんなの気にするなんて必要ない」
「だって……。私、こういうの、初めてで……」
こんなよく分からない感情になるのもおかしいのかなと思うし、情けない気持ちになるし、意味分かんないくらい泣きたくなるし。
だからこれは全部、百合原さんのせいだと思った。 百合原さんと出会わなければ、私はこんな気持ちになることもなかったし、こんなに悩むこともなかったと思う。
でも私の頭の中にはずっと百合原さんがいて、離れてくれない。
ずっと百合原さんのことが頭に浮かぶから、私はこんなになることはおかしいのかなと思っていた。
「俺は嬉しいよ、奏音の初めてが増えていくのが」
「え……?」