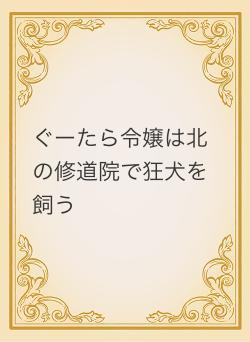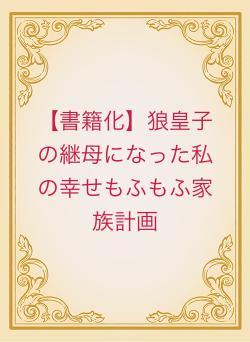リンリエッタは次の日から、何十という数の紹介状を書いた。公爵家の広い屋敷に働く者は多い。しかし、指導が行き届いたクライット公爵家の使用人を欲しがる者は多く、あっという間に次の職が決まっていった。
一人、また一人とクライット公爵家から姿を消していく。リンリエッタは使用人達の新しい門出を笑顔で見送った。
リンリエッタは、己の衣装部屋を見回しながら、苦笑を浮かべる。隣にはカインが控えていた。彼はそんな彼女を見て、眉を顰(ひそ)める。
「荷物の整理はあとこれだけ」
「はい」
「全部持って行きたいの。でも、それはできないのよね」
衣装部屋の中には、カインがこの五年でリンリエッタに作ってきたドレスで埋まっていた。医者から「クライット公爵が亡くなるのも時間の問題」と言われてから、最低限の物を残し、家財も売りに出している。屋敷を払う準備をしてきたリンリエッタであったが、このドレスだけは簡単に手離せないでいた。
「ドレスは嵩張ります」
「ええ、分かっているわ。でも、全部愛しているの」
リンリエッタは一番手前のドレスを抱きしめた。それは、五年前カインが初めて作ったドレス。まだ、粗が目立つ。しかし、リンリエッタはそれすらも愛していた。
リンリエッタにとって、それは物の価値では計れない。五年経った今、サイズも違うドレスは着ることもままならない。しかし、これを処分するという選択は、一度たりとも脳裏に浮かばなかった。
「リンリエッタ様にお渡ししたい物がございます」
「何かしら?」
「暫(しば)しお待ち下さい」
カインは一礼すると、衣装部屋を後にした。想いが通じあった今でも、カインはいつもの態度を崩したりはしない。そんな彼の後ろ姿を見つめながら、リンリエッタはため息を吐いた。
「それでも貴方のことが好きなんだから、困ったものね」
カインにリンリエッタの声は届かない。リンリエッタは真っ直ぐに伸びた背を見つめながら、もう一度笑った。
暫くして、カインは一着の洋服を持ってリンリエッタの前に現れる。ドレスとは違う、細やかなレースも飾りもない、ワンピースだ。
「これは?」
「リンリエッタ様の新しい門出に用意させて頂きました。これが、私の最後の作となるでしょう」
カインはリンリエッタにワンピースを手渡すと、いつものように片膝をついて彼女を見上げた。
「貴女のドレスを作ることが、私の生き甲斐でした。この屋敷を出てからは、貴女を守る事が生き甲斐になる。これを着て、私と共に新たな人生を歩んでいただけますか?」
真っ直ぐに向けられたペリドットにリンリエッタは目を見開いた。見開かれたアクアマリンの瞳には、涙が溜まる。
「カイン、困ったわ」
「如何なさいましたか?」
「両手が塞がっていて、貴方のことを抱きしめることができないの」
リンリエッタの両手には、カインから贈られたワンピースが広がっている。カインは目を細め、頭を横に振った。
「気持ちだけで充分でございます」
「いいえ、私が充分ではないわ」
このままワンピースを抱きしめていると、本人を抱きしめる機会を失う。リンリエッタは口を尖らせ、近くの椅子にワンピースを預けることにした。
「カイン、私をただのリンリエッタにして下さいね」
リンリエッタはにこりと微笑むと、片膝をつくカインの頭を力強く抱きしめた。彼は苦しそうに小さく唸りながらも、頷くことで返事をする。本当は返事を聞く必要など無いのだ。カインの贈ったワンピースが何よりも彼の気持ちを表している。
リンリエッタの顔には、笑顔の花が咲いた。
春乞の宴が終わった頃を見計らって、リンリエッタは伯父である国王と祖父、アデル三世に父親の危篤を伝えていた。ついでのように、自身は王家には頼らず一人で生きていく旨を書き記す。しかし、宮殿から音沙汰がない。
母親が違うとは言え、国王はクライット公爵とは兄弟だ。仲も悪くはなかった。国王が出向くことが無くとも、使者の一人も寄越さなかったのは、リンリエッタにも予想外のことである。
その上、アデルからの連絡も無い。リンリエッタはアデルとは親しいと感じていた。心のどこかで一番に駆けつけてくれるのではないかと期待していたのだ。しかし、蓋を開けてみれば、この屋敷に訪れる者は一人としていなかった。
その答えを携えて宮殿から使者が現れたのは、リンリエッタが、真新しいワンピースを抱きしめて眠った次の日の朝であった。
訪れた使者は、使者とは言い難い。殆ど何も無い応接間の長椅子に座るのは、国王の右腕、宰相である。
宰相の向かいにリンリエッタは堂々と腰を下ろした。いつもは父、クライット公爵が座る席に。そこに座る主人は未だ眠り続けている。リンリエッタはこっそりと、主人を待つ長椅子を慰(なぐさ)めるように撫でた。
リンリエッタの座る椅子の後ろには、カインが彼女を守るように控えている。その隣には最後まで残っていてくれている侍女の一人が。彼女は卒なく客人に紅茶を振る舞った。
「大した歓迎もできず、申し訳ないわ。もう殆ど引き払ってしまったのよ」
宰相は、屋敷を訪れた折、何度も屋敷の中を見回していた。リンリエッタの書状は宰相の目には触れていないのか。国王に届く手紙の殆どは宰相の目にも入る。彼女は不信げに首を傾げた。
応接間に座っても屋敷の様子を不審がる宰相に、リンリエッタはこれまでの事の顛末(てんまつ)を、順を追って説明する。宰相は彼女の話に涙を流した。
「御身がこのようなことになっているとはつゆ知らず、申し訳ございません」
「気にすることはありません。私は貴方と同じ陛下の忠実なる臣下なのですから」
何度も涙を拭う宰相に対し、リンリエッタは困ったように眉尻を下げた。いつもは、少し大きな顔をしている宰相が下手に出ている。それだけでも不可思議だ。
「リンリエッタ様。いいえ、女王陛下。我々は、貴女様を迎えに参ったのでございます」
一人、また一人とクライット公爵家から姿を消していく。リンリエッタは使用人達の新しい門出を笑顔で見送った。
リンリエッタは、己の衣装部屋を見回しながら、苦笑を浮かべる。隣にはカインが控えていた。彼はそんな彼女を見て、眉を顰(ひそ)める。
「荷物の整理はあとこれだけ」
「はい」
「全部持って行きたいの。でも、それはできないのよね」
衣装部屋の中には、カインがこの五年でリンリエッタに作ってきたドレスで埋まっていた。医者から「クライット公爵が亡くなるのも時間の問題」と言われてから、最低限の物を残し、家財も売りに出している。屋敷を払う準備をしてきたリンリエッタであったが、このドレスだけは簡単に手離せないでいた。
「ドレスは嵩張ります」
「ええ、分かっているわ。でも、全部愛しているの」
リンリエッタは一番手前のドレスを抱きしめた。それは、五年前カインが初めて作ったドレス。まだ、粗が目立つ。しかし、リンリエッタはそれすらも愛していた。
リンリエッタにとって、それは物の価値では計れない。五年経った今、サイズも違うドレスは着ることもままならない。しかし、これを処分するという選択は、一度たりとも脳裏に浮かばなかった。
「リンリエッタ様にお渡ししたい物がございます」
「何かしら?」
「暫(しば)しお待ち下さい」
カインは一礼すると、衣装部屋を後にした。想いが通じあった今でも、カインはいつもの態度を崩したりはしない。そんな彼の後ろ姿を見つめながら、リンリエッタはため息を吐いた。
「それでも貴方のことが好きなんだから、困ったものね」
カインにリンリエッタの声は届かない。リンリエッタは真っ直ぐに伸びた背を見つめながら、もう一度笑った。
暫くして、カインは一着の洋服を持ってリンリエッタの前に現れる。ドレスとは違う、細やかなレースも飾りもない、ワンピースだ。
「これは?」
「リンリエッタ様の新しい門出に用意させて頂きました。これが、私の最後の作となるでしょう」
カインはリンリエッタにワンピースを手渡すと、いつものように片膝をついて彼女を見上げた。
「貴女のドレスを作ることが、私の生き甲斐でした。この屋敷を出てからは、貴女を守る事が生き甲斐になる。これを着て、私と共に新たな人生を歩んでいただけますか?」
真っ直ぐに向けられたペリドットにリンリエッタは目を見開いた。見開かれたアクアマリンの瞳には、涙が溜まる。
「カイン、困ったわ」
「如何なさいましたか?」
「両手が塞がっていて、貴方のことを抱きしめることができないの」
リンリエッタの両手には、カインから贈られたワンピースが広がっている。カインは目を細め、頭を横に振った。
「気持ちだけで充分でございます」
「いいえ、私が充分ではないわ」
このままワンピースを抱きしめていると、本人を抱きしめる機会を失う。リンリエッタは口を尖らせ、近くの椅子にワンピースを預けることにした。
「カイン、私をただのリンリエッタにして下さいね」
リンリエッタはにこりと微笑むと、片膝をつくカインの頭を力強く抱きしめた。彼は苦しそうに小さく唸りながらも、頷くことで返事をする。本当は返事を聞く必要など無いのだ。カインの贈ったワンピースが何よりも彼の気持ちを表している。
リンリエッタの顔には、笑顔の花が咲いた。
春乞の宴が終わった頃を見計らって、リンリエッタは伯父である国王と祖父、アデル三世に父親の危篤を伝えていた。ついでのように、自身は王家には頼らず一人で生きていく旨を書き記す。しかし、宮殿から音沙汰がない。
母親が違うとは言え、国王はクライット公爵とは兄弟だ。仲も悪くはなかった。国王が出向くことが無くとも、使者の一人も寄越さなかったのは、リンリエッタにも予想外のことである。
その上、アデルからの連絡も無い。リンリエッタはアデルとは親しいと感じていた。心のどこかで一番に駆けつけてくれるのではないかと期待していたのだ。しかし、蓋を開けてみれば、この屋敷に訪れる者は一人としていなかった。
その答えを携えて宮殿から使者が現れたのは、リンリエッタが、真新しいワンピースを抱きしめて眠った次の日の朝であった。
訪れた使者は、使者とは言い難い。殆ど何も無い応接間の長椅子に座るのは、国王の右腕、宰相である。
宰相の向かいにリンリエッタは堂々と腰を下ろした。いつもは父、クライット公爵が座る席に。そこに座る主人は未だ眠り続けている。リンリエッタはこっそりと、主人を待つ長椅子を慰(なぐさ)めるように撫でた。
リンリエッタの座る椅子の後ろには、カインが彼女を守るように控えている。その隣には最後まで残っていてくれている侍女の一人が。彼女は卒なく客人に紅茶を振る舞った。
「大した歓迎もできず、申し訳ないわ。もう殆ど引き払ってしまったのよ」
宰相は、屋敷を訪れた折、何度も屋敷の中を見回していた。リンリエッタの書状は宰相の目には触れていないのか。国王に届く手紙の殆どは宰相の目にも入る。彼女は不信げに首を傾げた。
応接間に座っても屋敷の様子を不審がる宰相に、リンリエッタはこれまでの事の顛末(てんまつ)を、順を追って説明する。宰相は彼女の話に涙を流した。
「御身がこのようなことになっているとはつゆ知らず、申し訳ございません」
「気にすることはありません。私は貴方と同じ陛下の忠実なる臣下なのですから」
何度も涙を拭う宰相に対し、リンリエッタは困ったように眉尻を下げた。いつもは、少し大きな顔をしている宰相が下手に出ている。それだけでも不可思議だ。
「リンリエッタ様。いいえ、女王陛下。我々は、貴女様を迎えに参ったのでございます」