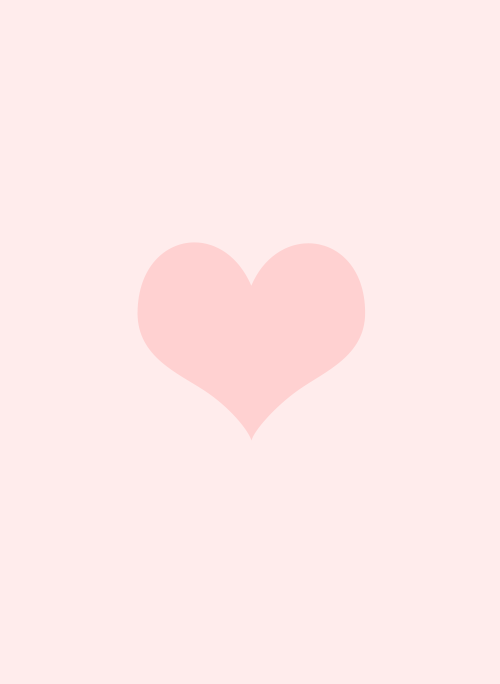何かを諦めたような、どこか冷めたような、だけどその漆黒の暗い瞳からは他とは違う、誰にも気づかれない色が混ざっているように私には見えた。
「ん。俺の名前、知ってたの?」
その低い声には、その質問に絶対に答えなければならないという強制力があった。
昨日は、わたしみたいな庶民がこの街を統率する皇帝のお顔を見るなんて不敬に値すると思って、目を合わせることさえ出来なかったけれど、今日は違う。
わたしは飛鳥馬様に突然腕を引かれ、他の誰からも目をつけられない暗い路地裏に続く角で、“一方的”で“勝手”なキスをされたのだ。
それくらいのことをされたのだから、わたしにだって正面から飛鳥馬様と向き合う権利くらいあるはずだ。
「……っ、はい。当たり前です」
だけど、強気になろうとしてもそう簡単にはいかない。わたしを見据える飛鳥馬様の瞳の中に囚われて、まるで籠の中の鳥のような気持ちだ。
「……それは、おれがこの街を支配する皇帝だから?」
まさか、飛鳥馬様本人の口から自分を“皇帝”と称す言葉が出てくるとは思わなかった。