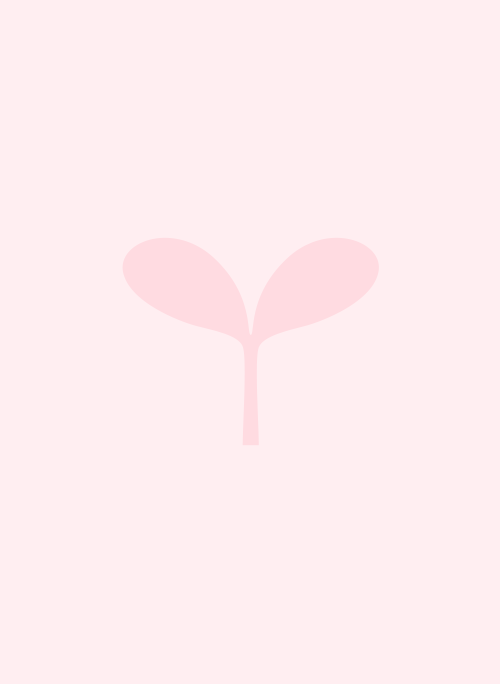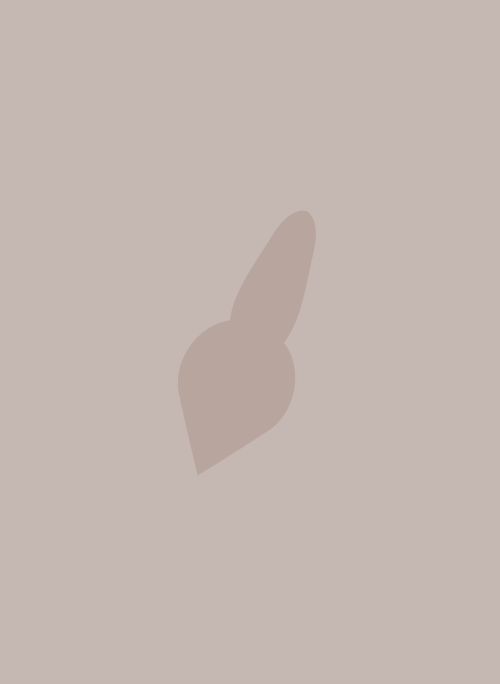清浜町、ここでバスを降りると古い社屋の群れが見えてくる。
その一角に彼が働いている津村商事が在る。 彼はここの古参社員の一人なのである。
終戦後、津村与一郎はこの町で商事会社を立ち上げた。 闇に放り出されていた健三たちは彼に拾われたのである。
以来、飛ぶとも飛ばぬとも分らぬままに彼はここで働いてきた。
玄関を入ると冴えない女が事務所から会釈するのが見える。 健三は何が照れくさいのか、彼女からさっさと逃げて二階の持ち場へと飛び込んでいく。
机に落ち着いて「さあ、これから、、、」と気を引き締めていると後ろから話し声が聞こえてきた。
どうやらお盆明けにやることになっている夏祭りの話題らしい。 「今度さあ、どんなお店を出すのかなあ?」
「どんなお店?」 「ほら、いっつも夏祭りで出してるでしょう?」
放しているのは山下加代子と木村さおりの二人である。 二人とも30半ばで旦那と二人の子供が居る。
「そうねえ、まだ暑いから流し素麺なんかもやるんじゃないかなあ?」 「かもねえ。 課長さんの実家が山を持ってるからまた竹を切ってきてやってくれるかもねえ。」
「それにさあ射的なんかもいいんじゃないかなあ?」 「射的?」
健三は思わず後ろを振り向いた。 「あらあら、吉田さんも聞いてたの?」
「趣味悪ーーーい。」 「いいじゃないか。 聞いてなくても聞こえるんだから。」
「そうだそうだ。 私たちの話を盗み聞きするなんてひどーーーい。」 「いつものことだ。 俺は知らんよ。」
女たちが頬っぺたを膨らませて何か抗議しているのだが健三は何処吹く風で部屋を出た。
廊下を歩いていると課長とか部長とかいう面倒くさい生き物に掴まるから速足で階段を下りていく。
玄関を開けて外に出る。 そしたら健三は表から見えないように脇の看板の陰に隠れて頭を休めるのだ。
会社の前には細い通りが繋がっていて時々車が走って行く。 暇そうな巡査が何か無いかと歩き回っている。
裏には少しばかりの駐車場が有って数人の社員が荷物の点検をしている。
そこへ大きな荷物を抱えて課長の黒田が玄関から出てきた。 彼は掃除をしていた若松敏行と一言二言会話してから裏へ回ってきた。
「おー、健三君じゃないか。 何をしてるんだ?」 「日向ぼっこです。」
「そっか。 あんまり焼き過ぎても体に悪いからな。」 「分かってます。」
「分かってるならよろしい。」 彼はそう言うと裏の社員に声を掛けた。
空にはうっとりするような白い雲が千切れながら流れていくのが見える。 健三は松代が居た頃のことを思い出した。
いつだったか「健ちゃんさあ、好きな子は居るの?」って何度も聞いてきたことが有る。 でもどう言っていいのか分からなかった健三は松代を無視して空地へ歩いて行った。
「ねえ、聞いてるんだから答えてよ。」 松代は半分イライラしながら彼に聞いてきた。
この空き地、小高い丘の上に有る。 見下ろすと健三たちのアパートもはっきりと見ることが出来る。
その片隅には誰の物とも知れぬ赤い車がずっと放置されている。 健三はそのドアを開けて松代を手招きした。
松代はというと珍しく嬉しそうな顔で助手席に座っている。 健三は車を運転する真似をしてみた。
アクセルを踏み込む。 ハンドルを回してみる。
どれくらい前から放置されているのか分からないがガソリンは既に無くなっているらしいから動くわけも無い。 買い物帰りのおばちゃんが近寄ってきた。
「おやおやお二人さん 今日はデートですか?」 「そうなの。 この車でデートするの。」
「お幸せにねえ。 まっちゃん。」 おばさんはニコニコしながら坂を下りて行った。
「ねえ、健ちゃん 聞いてるんだから答えてよ。 好きな子は居るの?」 またまた聞いてくる松代が恨めしくなったのか健三は怒ったようにドアを開けるとそのまま家まで帰ってしまった。
(あの時、素直に言えばよかったんだよな。 たぶん。) そうは思っても過ぎたことである。
今の健三には何も出来なかった。
松代がこの町を出て行ってから何年になるんだろう? 長屋はそのままで残っている。
松代の親父さんもお袋さんも死んでしまった。 以来、長屋に入ることも無くなってしまったが玄関はそのままにしてある。
それだけじゃない。 ここいらの建物は禁止命令でも出たのかと疑いたくなるくらいにみんながみんなそのままで残っている。
子供たちが遊び回っていた公園も姿形はそのままで残されている。 古い遊具もそのままだ。
ここだけ大正から時計が停められているみたいに見える。 「開発してもいいんだけどなあ。」
そんな声は時々聞かれるが丹後原の再開発は知らない間に消えてしまっている。 見向きすらされないらしい。
そんな寂しい町の寂しい中心街の一角に在る小さな会社で健三は働いている。 真面目だからなのか、それともここしか無かったからなのか分からないが、、、。
この会社、津村商事の事務室には康子という30そこそこの女が働いている。 健三だって朝に夕にこの女と顔を合わせる。
「おはようございます。」 出勤してきた健三に康子はいつものように声を掛ける。
ところが何を思ったのか彼はプイっと横を向いて事務室の前を早足で通り過ぎてしまうのである。 (悪い女じゃなさそうなんだがな、、、。)
玄関先でボーっとしている時、課長の黒田が見兼ねたように言ってくる。 「おいおい、健三君。 気分でも悪いのか?」
「いえね、ちょっと飲み過ぎたもんで、、、。」 「ダメだなあ。 康子ちゃんにでも可愛がってもらったらどうだね?」
「康子?」 「そうだ。 あの子だっていい女だぞ。」
「そうですねえ。 考えときます。」 「そうだ。 お前だって嫁さんくらいは欲しいだろう。」
黒田はそんな話をしながら何処かへ行ってしまう。 (嫁さんか、、、。)
興味が無いわけではない。 面倒なわけでもない。
ただただ女と話せないだけである。 どうしてなんだろう?
康子はというと一階の事務室で電話番をしている一見冴えない女である。 周りからは結婚するように急かされているが本人はまるで気に留めていない様子だ。
「あれだってよその会社からすれば評判はいいんだぞ。 人当たりは優しいし仕事は丁寧だし、、、。」 「そうは言うけれど、、、。」
「まあ、お前が興味を持てないんじゃしょうがねえなあ。」
興味が有るとか無いとかそんなんじゃないんだよ。 ただただ声を掛けられないでいるだけだ。
「健三君も50が近いんだからな。」 「そうですね。」
部長の吉田春幸も彼のことを心配しているらしい。 健三は何となく重い気分になって部屋に戻ってきた。
部屋では新米の女の子たちが古株のおじさんたちにお茶を注いで回っている。 「こっちも頼むよ。」
大して出来るようには見えない杉山邦夫が湯飲みを差し出している。 「寛子ちゃん 今夜は空いてるかい?」
「何かご用ですか?」 「良かったら飲まないかい?」
「飲むって、、、お茶ですか?」 高卒の寛子は雑巾を持ったまま振り向いた。
「違うよ。 飲むと言ったら酒だよ。」 「お酒、、、ですか?」
職場の中では手が速い問題児と呼ばれている清水国安が口説いているようだ。
「まあ、、、どうしましょう?」 「いいじゃないか。 酔ったら介抱してあげるよ。」
「やめときなさい。 関わったらどうなるか分からないわよ。」 年輩の風間良子が割って入った。
健三は四方山話に耳を傾けながら書類の整理を続けている。 「金と酒と女しか脳が無いのか。 侘しいもんだねえ。」
「何だと? やい、もう一回言ってみろ!」 「金と酒と女しか脳が無い侘しいやつだって言ったんだよ。」
「てめえ! ふざけるんじゃねえぞ! 外へ出ろ!」 ものすごい剣幕で清水は部屋を出て行ってしまった。
「あの人はあれだからダメなの。 だから奥さんにも逃げられたのよ。」 「そうだったんすか?」
声を掛けられた寛子は窓際で固まっている。 「寛子ちゃんも気を付けたほうがいいわよ。 介抱するってのは抱くってことだからね。」
「抱く?」 「そうよ。 あんな男に抱かれたら人生終わっちゃうわ。」
健三は何気に引き戸を開けてみた。 階下で清水と誰かが大喧嘩をしている。
「行かないほうがいいわよ。 あの人と喧嘩したって勝てっこないんだから。」 清水は柔道3段の巨漢である。
健三はそんなやつと喧嘩する気などさらさら無かった。 関わらない方が得策だろう。
その一角に彼が働いている津村商事が在る。 彼はここの古参社員の一人なのである。
終戦後、津村与一郎はこの町で商事会社を立ち上げた。 闇に放り出されていた健三たちは彼に拾われたのである。
以来、飛ぶとも飛ばぬとも分らぬままに彼はここで働いてきた。
玄関を入ると冴えない女が事務所から会釈するのが見える。 健三は何が照れくさいのか、彼女からさっさと逃げて二階の持ち場へと飛び込んでいく。
机に落ち着いて「さあ、これから、、、」と気を引き締めていると後ろから話し声が聞こえてきた。
どうやらお盆明けにやることになっている夏祭りの話題らしい。 「今度さあ、どんなお店を出すのかなあ?」
「どんなお店?」 「ほら、いっつも夏祭りで出してるでしょう?」
放しているのは山下加代子と木村さおりの二人である。 二人とも30半ばで旦那と二人の子供が居る。
「そうねえ、まだ暑いから流し素麺なんかもやるんじゃないかなあ?」 「かもねえ。 課長さんの実家が山を持ってるからまた竹を切ってきてやってくれるかもねえ。」
「それにさあ射的なんかもいいんじゃないかなあ?」 「射的?」
健三は思わず後ろを振り向いた。 「あらあら、吉田さんも聞いてたの?」
「趣味悪ーーーい。」 「いいじゃないか。 聞いてなくても聞こえるんだから。」
「そうだそうだ。 私たちの話を盗み聞きするなんてひどーーーい。」 「いつものことだ。 俺は知らんよ。」
女たちが頬っぺたを膨らませて何か抗議しているのだが健三は何処吹く風で部屋を出た。
廊下を歩いていると課長とか部長とかいう面倒くさい生き物に掴まるから速足で階段を下りていく。
玄関を開けて外に出る。 そしたら健三は表から見えないように脇の看板の陰に隠れて頭を休めるのだ。
会社の前には細い通りが繋がっていて時々車が走って行く。 暇そうな巡査が何か無いかと歩き回っている。
裏には少しばかりの駐車場が有って数人の社員が荷物の点検をしている。
そこへ大きな荷物を抱えて課長の黒田が玄関から出てきた。 彼は掃除をしていた若松敏行と一言二言会話してから裏へ回ってきた。
「おー、健三君じゃないか。 何をしてるんだ?」 「日向ぼっこです。」
「そっか。 あんまり焼き過ぎても体に悪いからな。」 「分かってます。」
「分かってるならよろしい。」 彼はそう言うと裏の社員に声を掛けた。
空にはうっとりするような白い雲が千切れながら流れていくのが見える。 健三は松代が居た頃のことを思い出した。
いつだったか「健ちゃんさあ、好きな子は居るの?」って何度も聞いてきたことが有る。 でもどう言っていいのか分からなかった健三は松代を無視して空地へ歩いて行った。
「ねえ、聞いてるんだから答えてよ。」 松代は半分イライラしながら彼に聞いてきた。
この空き地、小高い丘の上に有る。 見下ろすと健三たちのアパートもはっきりと見ることが出来る。
その片隅には誰の物とも知れぬ赤い車がずっと放置されている。 健三はそのドアを開けて松代を手招きした。
松代はというと珍しく嬉しそうな顔で助手席に座っている。 健三は車を運転する真似をしてみた。
アクセルを踏み込む。 ハンドルを回してみる。
どれくらい前から放置されているのか分からないがガソリンは既に無くなっているらしいから動くわけも無い。 買い物帰りのおばちゃんが近寄ってきた。
「おやおやお二人さん 今日はデートですか?」 「そうなの。 この車でデートするの。」
「お幸せにねえ。 まっちゃん。」 おばさんはニコニコしながら坂を下りて行った。
「ねえ、健ちゃん 聞いてるんだから答えてよ。 好きな子は居るの?」 またまた聞いてくる松代が恨めしくなったのか健三は怒ったようにドアを開けるとそのまま家まで帰ってしまった。
(あの時、素直に言えばよかったんだよな。 たぶん。) そうは思っても過ぎたことである。
今の健三には何も出来なかった。
松代がこの町を出て行ってから何年になるんだろう? 長屋はそのままで残っている。
松代の親父さんもお袋さんも死んでしまった。 以来、長屋に入ることも無くなってしまったが玄関はそのままにしてある。
それだけじゃない。 ここいらの建物は禁止命令でも出たのかと疑いたくなるくらいにみんながみんなそのままで残っている。
子供たちが遊び回っていた公園も姿形はそのままで残されている。 古い遊具もそのままだ。
ここだけ大正から時計が停められているみたいに見える。 「開発してもいいんだけどなあ。」
そんな声は時々聞かれるが丹後原の再開発は知らない間に消えてしまっている。 見向きすらされないらしい。
そんな寂しい町の寂しい中心街の一角に在る小さな会社で健三は働いている。 真面目だからなのか、それともここしか無かったからなのか分からないが、、、。
この会社、津村商事の事務室には康子という30そこそこの女が働いている。 健三だって朝に夕にこの女と顔を合わせる。
「おはようございます。」 出勤してきた健三に康子はいつものように声を掛ける。
ところが何を思ったのか彼はプイっと横を向いて事務室の前を早足で通り過ぎてしまうのである。 (悪い女じゃなさそうなんだがな、、、。)
玄関先でボーっとしている時、課長の黒田が見兼ねたように言ってくる。 「おいおい、健三君。 気分でも悪いのか?」
「いえね、ちょっと飲み過ぎたもんで、、、。」 「ダメだなあ。 康子ちゃんにでも可愛がってもらったらどうだね?」
「康子?」 「そうだ。 あの子だっていい女だぞ。」
「そうですねえ。 考えときます。」 「そうだ。 お前だって嫁さんくらいは欲しいだろう。」
黒田はそんな話をしながら何処かへ行ってしまう。 (嫁さんか、、、。)
興味が無いわけではない。 面倒なわけでもない。
ただただ女と話せないだけである。 どうしてなんだろう?
康子はというと一階の事務室で電話番をしている一見冴えない女である。 周りからは結婚するように急かされているが本人はまるで気に留めていない様子だ。
「あれだってよその会社からすれば評判はいいんだぞ。 人当たりは優しいし仕事は丁寧だし、、、。」 「そうは言うけれど、、、。」
「まあ、お前が興味を持てないんじゃしょうがねえなあ。」
興味が有るとか無いとかそんなんじゃないんだよ。 ただただ声を掛けられないでいるだけだ。
「健三君も50が近いんだからな。」 「そうですね。」
部長の吉田春幸も彼のことを心配しているらしい。 健三は何となく重い気分になって部屋に戻ってきた。
部屋では新米の女の子たちが古株のおじさんたちにお茶を注いで回っている。 「こっちも頼むよ。」
大して出来るようには見えない杉山邦夫が湯飲みを差し出している。 「寛子ちゃん 今夜は空いてるかい?」
「何かご用ですか?」 「良かったら飲まないかい?」
「飲むって、、、お茶ですか?」 高卒の寛子は雑巾を持ったまま振り向いた。
「違うよ。 飲むと言ったら酒だよ。」 「お酒、、、ですか?」
職場の中では手が速い問題児と呼ばれている清水国安が口説いているようだ。
「まあ、、、どうしましょう?」 「いいじゃないか。 酔ったら介抱してあげるよ。」
「やめときなさい。 関わったらどうなるか分からないわよ。」 年輩の風間良子が割って入った。
健三は四方山話に耳を傾けながら書類の整理を続けている。 「金と酒と女しか脳が無いのか。 侘しいもんだねえ。」
「何だと? やい、もう一回言ってみろ!」 「金と酒と女しか脳が無い侘しいやつだって言ったんだよ。」
「てめえ! ふざけるんじゃねえぞ! 外へ出ろ!」 ものすごい剣幕で清水は部屋を出て行ってしまった。
「あの人はあれだからダメなの。 だから奥さんにも逃げられたのよ。」 「そうだったんすか?」
声を掛けられた寛子は窓際で固まっている。 「寛子ちゃんも気を付けたほうがいいわよ。 介抱するってのは抱くってことだからね。」
「抱く?」 「そうよ。 あんな男に抱かれたら人生終わっちゃうわ。」
健三は何気に引き戸を開けてみた。 階下で清水と誰かが大喧嘩をしている。
「行かないほうがいいわよ。 あの人と喧嘩したって勝てっこないんだから。」 清水は柔道3段の巨漢である。
健三はそんなやつと喧嘩する気などさらさら無かった。 関わらない方が得策だろう。