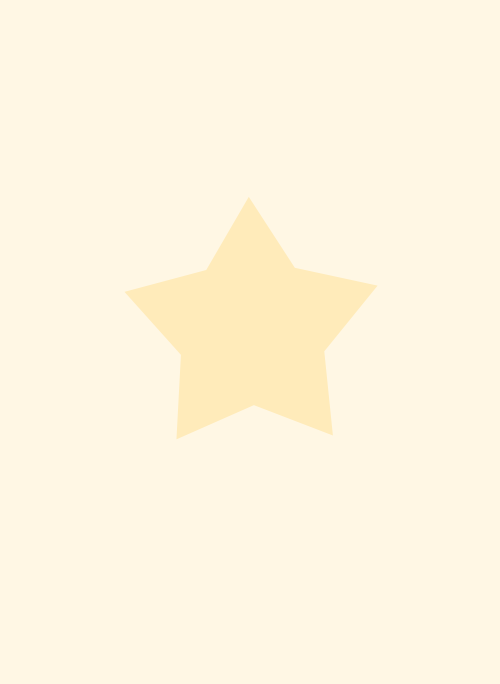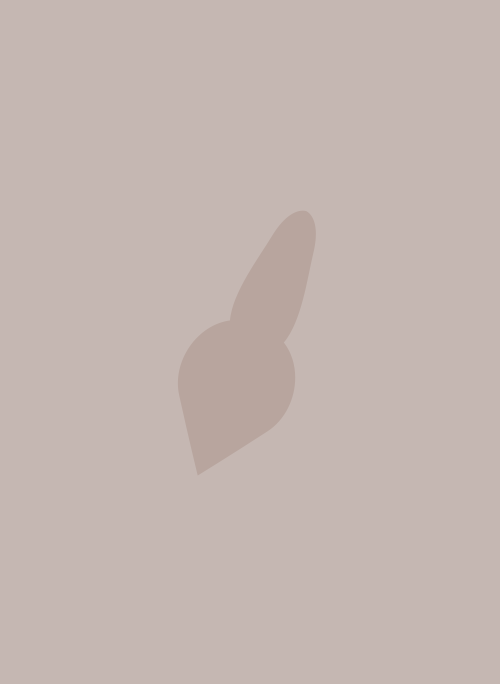「はーい。 そこまでよ。」 「残念だなあ。」
「またいつかさせてあげるからね。」 母ちゃんはそう言うと玄関へ向かった。
「あっどうも。」 どうやら荷物を受け取っているらしい。
何か買ったのかなあ?
「ねえねえ、ロールケーキ食べる? 何処かのシェフが作ったんだって言うから買ったんだけど。」 「ロールケーキ?」
「美味しそうだったから頼んじゃったのよ。 あゆみも好きだからいいかと思って。」 「食べる。」
母ちゃんは包みを開けてロールケーキを取り出した。 「美味そうじゃん。」
そのロールケーキを切った母ちゃんは皿を見詰めながら何か考えている。
「紅茶も入れようね。」 「うん。 これさ、何処で売ってたの?」
「駅前のプリティードールってお店。」 「新しい店じゃん。」
「うん。」 ケーキを頬張る母ちゃんの横顔をそっと見詰める。
時々、フッと溜息を吐く顔が何とも色っぽく見えるんだ。
母ちゃんってさあ、そんなに高くないんだよ。 153センチだっけ、確か。
俺にとってはアイドルみたいな母ちゃんだ。 そんな母ちゃんとやっちゃうなんて、、、。
放心した母ちゃんの横顔も初めて見た気がする。 あれほど後悔した瞬間は無かったな。
「買い物に行ってくるからね。」 「あいよ。」
母ちゃんは買い物袋を下げて出て行った。
その間に俺は初めて母ちゃんの部屋を覗いた。 今まで入ったことは無いんだ。
箪笥を下から開けてみる。 なんだか空き巣にでもなった気分だな。
下のほうは洋服とか下着がたくさん入っている。 残るは最上段。
開けてみるとアルバムが入っていた。 開いた俺は驚いてしまった。
最初のページに貼られている写真は母ちゃんが俺を抱っこしている写真だ。 (これが高校生になれなかった母ちゃん化、、、。)
次のページには親父と母ちゃんが並んでいる。 なんか楽しそう。
でも、その次のページは空白になっている。 なぜ?
写真を箪笥に返すと俺は自分の部屋へ戻った。 「あんな頃が有ったのか。」
複雑な気持ちである。 母さん、いやばあちゃんの写真は抜かれているんだろう。
なんとなく見てはいけない物を見てしまったような気にもなってくる。 玄関のドアが開いた。
「ただいまーーーー。 居ないの?」 「居るよ。」
「ああ、居た居た。 今晩はねえ、お鍋にするから。」 「鍋?」
「あゆみも帰ってくるし疲れてると思うからさあ、、、。」 「じゃあ手伝うよ。」
「サンキュー!」 「軽いなあ。」
俺は母ちゃんの隣で大根や芋の皮を剥いている。 時々、大根で母ちゃんの尻を突っついたりしながらね。
そのたびにワートカキャーとか母ちゃんは声を上げる。 「やめてってば。」
「ごめんごめん。」 「今度やったらお仕置きするからね。」
「チューでもするの?」 「アホか。 ふざけてないでさあさあ、、、。」
「分かったよ。」 涙目で訴えてくる母ちゃんは何とも可愛くてさ、、、。
台所で奮闘していると玄関が開いた。 「ただいまーー。」
「あゆみか。 どうだった?」 「決勝戦で負けちゃった。 悔しい。」
「決勝まで行ったの? すごいじゃない。」 「でもさ、去年は優勝したのよ。」
「去年は去年。 今年は今年だよ。」 「そうは言うけどさあ、、、。」
「夕食はお鍋だからねえ。」 「やったあ。」
あゆみは中学3年。 ずいぶんと女らしくなってきた。
高校は俺よりもいい学校を選ぶんだってさ。 あいつは頭がいいからねえ。
さてさて夕食だ。 「あゆみーーーーーー、ご飯だぞーーーー。」
「そんなに叫ばなくても聞こえてるわよ。」 「なんだ、トイレに居たのか。」
「なんだは無いでしょう? 可愛い妹に向かって。」 「自信過剰ですなあ。」
「何ですって?」 「まあまあ、落ち着きなさいよ。 かえって早々喧嘩しないの。」
「お兄ちゃんが悪いのよ。 怒らせたりするから。」 「ごめんごめん。」
「ったくもう、、、。 ごめんって言えばいいと思って。」 「悪かったよ。 女王様。」
母ちゃんは俺たちの喧嘩を聞きながらカセットコンロをテーブルに置いた。 三人で囲む鍋も久しぶり。
あゆみは肉団子を探しているようだ。 「みっけーーーー。 これはあゆみのだからねえ。」
「それって俺が見付けたやつじゃんか。」 「私のなの。 食べないで。」
「まあまあ、敏夫さん あゆみちゃんにあげなさいよ。」 「分かった。」
「あーら、お母さんの言うことは聞くのねえ。」 「いいだろうがよ。」
「怒らない怒らない。 遠征から帰ったばかりなんだから可愛がってあげなさいよ。 ねえ、敏夫さん。」 そう言い割れたら、、、。
いつの間にか三人とも無口になって食べております。 何も話さんのかね?
翌日は全校集会だ。 遠征の結果報告をするんだって。
あの監督は話が長いからなあ。 お疲れ様だよ。
あんまりに静かだからテレビを点けてやる。 知らないアイドルがラーメンを食べながら喋ってる。
つまんねえの。 ああ、誰か喋ってよ。
でもさあ、ほんとに誰も喋らないんだよ。 誰かのお通夜みたいだ。
ねえねえ、ほんとに頼むから喋ってよ。
とはいうものの、結局は誰も喋らないまま鍋を空っぽにしてしまった。
そのうちにあゆみが寝たいって言い出したので俺も部屋に帰ることにした。 「お風呂はどうする?」
「沸いたら入るよ。」 「じゃあ、沸かしたら呼ぶね。」
あゆみはバスケの選手なんだ。 ポイントメーカーになりたいって言ってたなあ。
俺は中学からずっと走ってる。 短距離は苦手なんだけど、、、。
部屋に戻ってきた俺は取り合えずノートを開いてみた。 「こいつを終わらせないとな、、、。」
辞典と睨めっこしていると母ちゃんが入ってきた。 「お風呂 沸いたわよ。」
「あいよ。」 「あゆみは寝ちゃったみたいね。」
並んで階段を下りる。 なんだかドキドキするのはなぜ?
「先に入って。」 「分かった。」
脱衣所に入る。 母ちゃんとやっちまったことを今でも後悔している。
(見なきゃよかったんだよ。 影が見えたからやりたくなったんだ。) 服を脱ぐ。
浴室に入って湯をかぶる。 浴槽に体を沈めてから天井を仰いでみる。
母ちゃんを押し倒したあの時、俺は何を考えてたんだろう? 気付いたら母ちゃんは泣きそうな顔で俺に訴えてた。
「敏夫とお母さんは親子なのよ。 こんなことしちゃいけないの。」 荒い息を整えながら母ちゃんは懸命に話し続ける。
俺はただ何が何だか分からないままに黙っているしかない。 でも母ちゃんはそんな俺を受け入れてくれていた。
「そろそろいいかな?」 ガラガラっとサッシが開いて母ちゃんが入ってきた。
「母ちゃんも来たの?」 「あゆみも寝てるし、今ならいいかと思ってね。」
湯をかぶると母ちゃんは俺と向かい合って湯に体を沈めた。
「なあに? そんなに見詰めないでよ。 恥ずかしいじゃない。」 「ごめん。」
「お父さんはねえ、仕事の出来る人だった。 でも間違ったのよ。」 「何を?」
「私に子供を産ませたのは、、、。」 「そうかもね。」
でもそうだったら俺は生まれなかったんだ。 あゆみだって。
「敏夫もこれからいろんな人と付き合うのね。 でも相手を悲しませるようなことだけはしないで。」 「分かってる。」
静かに時間が過ぎていく。 思えば母ちゃんと風呂に入ったことって初めてだったな。
体を洗った母ちゃんはパジャマを着ると部屋に帰って行った。
「またいつかさせてあげるからね。」 母ちゃんはそう言うと玄関へ向かった。
「あっどうも。」 どうやら荷物を受け取っているらしい。
何か買ったのかなあ?
「ねえねえ、ロールケーキ食べる? 何処かのシェフが作ったんだって言うから買ったんだけど。」 「ロールケーキ?」
「美味しそうだったから頼んじゃったのよ。 あゆみも好きだからいいかと思って。」 「食べる。」
母ちゃんは包みを開けてロールケーキを取り出した。 「美味そうじゃん。」
そのロールケーキを切った母ちゃんは皿を見詰めながら何か考えている。
「紅茶も入れようね。」 「うん。 これさ、何処で売ってたの?」
「駅前のプリティードールってお店。」 「新しい店じゃん。」
「うん。」 ケーキを頬張る母ちゃんの横顔をそっと見詰める。
時々、フッと溜息を吐く顔が何とも色っぽく見えるんだ。
母ちゃんってさあ、そんなに高くないんだよ。 153センチだっけ、確か。
俺にとってはアイドルみたいな母ちゃんだ。 そんな母ちゃんとやっちゃうなんて、、、。
放心した母ちゃんの横顔も初めて見た気がする。 あれほど後悔した瞬間は無かったな。
「買い物に行ってくるからね。」 「あいよ。」
母ちゃんは買い物袋を下げて出て行った。
その間に俺は初めて母ちゃんの部屋を覗いた。 今まで入ったことは無いんだ。
箪笥を下から開けてみる。 なんだか空き巣にでもなった気分だな。
下のほうは洋服とか下着がたくさん入っている。 残るは最上段。
開けてみるとアルバムが入っていた。 開いた俺は驚いてしまった。
最初のページに貼られている写真は母ちゃんが俺を抱っこしている写真だ。 (これが高校生になれなかった母ちゃん化、、、。)
次のページには親父と母ちゃんが並んでいる。 なんか楽しそう。
でも、その次のページは空白になっている。 なぜ?
写真を箪笥に返すと俺は自分の部屋へ戻った。 「あんな頃が有ったのか。」
複雑な気持ちである。 母さん、いやばあちゃんの写真は抜かれているんだろう。
なんとなく見てはいけない物を見てしまったような気にもなってくる。 玄関のドアが開いた。
「ただいまーーーー。 居ないの?」 「居るよ。」
「ああ、居た居た。 今晩はねえ、お鍋にするから。」 「鍋?」
「あゆみも帰ってくるし疲れてると思うからさあ、、、。」 「じゃあ手伝うよ。」
「サンキュー!」 「軽いなあ。」
俺は母ちゃんの隣で大根や芋の皮を剥いている。 時々、大根で母ちゃんの尻を突っついたりしながらね。
そのたびにワートカキャーとか母ちゃんは声を上げる。 「やめてってば。」
「ごめんごめん。」 「今度やったらお仕置きするからね。」
「チューでもするの?」 「アホか。 ふざけてないでさあさあ、、、。」
「分かったよ。」 涙目で訴えてくる母ちゃんは何とも可愛くてさ、、、。
台所で奮闘していると玄関が開いた。 「ただいまーー。」
「あゆみか。 どうだった?」 「決勝戦で負けちゃった。 悔しい。」
「決勝まで行ったの? すごいじゃない。」 「でもさ、去年は優勝したのよ。」
「去年は去年。 今年は今年だよ。」 「そうは言うけどさあ、、、。」
「夕食はお鍋だからねえ。」 「やったあ。」
あゆみは中学3年。 ずいぶんと女らしくなってきた。
高校は俺よりもいい学校を選ぶんだってさ。 あいつは頭がいいからねえ。
さてさて夕食だ。 「あゆみーーーーーー、ご飯だぞーーーー。」
「そんなに叫ばなくても聞こえてるわよ。」 「なんだ、トイレに居たのか。」
「なんだは無いでしょう? 可愛い妹に向かって。」 「自信過剰ですなあ。」
「何ですって?」 「まあまあ、落ち着きなさいよ。 かえって早々喧嘩しないの。」
「お兄ちゃんが悪いのよ。 怒らせたりするから。」 「ごめんごめん。」
「ったくもう、、、。 ごめんって言えばいいと思って。」 「悪かったよ。 女王様。」
母ちゃんは俺たちの喧嘩を聞きながらカセットコンロをテーブルに置いた。 三人で囲む鍋も久しぶり。
あゆみは肉団子を探しているようだ。 「みっけーーーー。 これはあゆみのだからねえ。」
「それって俺が見付けたやつじゃんか。」 「私のなの。 食べないで。」
「まあまあ、敏夫さん あゆみちゃんにあげなさいよ。」 「分かった。」
「あーら、お母さんの言うことは聞くのねえ。」 「いいだろうがよ。」
「怒らない怒らない。 遠征から帰ったばかりなんだから可愛がってあげなさいよ。 ねえ、敏夫さん。」 そう言い割れたら、、、。
いつの間にか三人とも無口になって食べております。 何も話さんのかね?
翌日は全校集会だ。 遠征の結果報告をするんだって。
あの監督は話が長いからなあ。 お疲れ様だよ。
あんまりに静かだからテレビを点けてやる。 知らないアイドルがラーメンを食べながら喋ってる。
つまんねえの。 ああ、誰か喋ってよ。
でもさあ、ほんとに誰も喋らないんだよ。 誰かのお通夜みたいだ。
ねえねえ、ほんとに頼むから喋ってよ。
とはいうものの、結局は誰も喋らないまま鍋を空っぽにしてしまった。
そのうちにあゆみが寝たいって言い出したので俺も部屋に帰ることにした。 「お風呂はどうする?」
「沸いたら入るよ。」 「じゃあ、沸かしたら呼ぶね。」
あゆみはバスケの選手なんだ。 ポイントメーカーになりたいって言ってたなあ。
俺は中学からずっと走ってる。 短距離は苦手なんだけど、、、。
部屋に戻ってきた俺は取り合えずノートを開いてみた。 「こいつを終わらせないとな、、、。」
辞典と睨めっこしていると母ちゃんが入ってきた。 「お風呂 沸いたわよ。」
「あいよ。」 「あゆみは寝ちゃったみたいね。」
並んで階段を下りる。 なんだかドキドキするのはなぜ?
「先に入って。」 「分かった。」
脱衣所に入る。 母ちゃんとやっちまったことを今でも後悔している。
(見なきゃよかったんだよ。 影が見えたからやりたくなったんだ。) 服を脱ぐ。
浴室に入って湯をかぶる。 浴槽に体を沈めてから天井を仰いでみる。
母ちゃんを押し倒したあの時、俺は何を考えてたんだろう? 気付いたら母ちゃんは泣きそうな顔で俺に訴えてた。
「敏夫とお母さんは親子なのよ。 こんなことしちゃいけないの。」 荒い息を整えながら母ちゃんは懸命に話し続ける。
俺はただ何が何だか分からないままに黙っているしかない。 でも母ちゃんはそんな俺を受け入れてくれていた。
「そろそろいいかな?」 ガラガラっとサッシが開いて母ちゃんが入ってきた。
「母ちゃんも来たの?」 「あゆみも寝てるし、今ならいいかと思ってね。」
湯をかぶると母ちゃんは俺と向かい合って湯に体を沈めた。
「なあに? そんなに見詰めないでよ。 恥ずかしいじゃない。」 「ごめん。」
「お父さんはねえ、仕事の出来る人だった。 でも間違ったのよ。」 「何を?」
「私に子供を産ませたのは、、、。」 「そうかもね。」
でもそうだったら俺は生まれなかったんだ。 あゆみだって。
「敏夫もこれからいろんな人と付き合うのね。 でも相手を悲しませるようなことだけはしないで。」 「分かってる。」
静かに時間が過ぎていく。 思えば母ちゃんと風呂に入ったことって初めてだったな。
体を洗った母ちゃんはパジャマを着ると部屋に帰って行った。