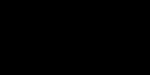そのままベッドに押し倒された私は、思わずカオルを見つめてしまう。
「……か、カオル?」
カオルは私の頬を優しく包み込むように触れる。
「言っておくけど、俺はいつでもミクのこと抱きたいと思ってるから」
「えっ……?」
カオルのこんな真剣な眼差し、初めてかもしれない。
「お前のことが大事だから、ずっと我慢してたけど。 本当は早くミクを抱きたくてたまらないってこと、分かってる?」
そんなこと言われたら、私は何も言えなくなる。
カオルと婚約した時から、私はカオルの妻になる覚悟なんてなかった。
カオルに愛されることが、こんなにも怖いと思わなかった。 私なりにカオルのこと大事にしたいと思っていたけど、やっぱり好きな人がいる私にとって、カオルとの結婚は罪悪感しかなかった。
「あの、その、それは……」
「そのくらいミクを愛してるってこと、頭に刻み込んでおけよ?」
そうやってカオルは私の上から退いたけど、私の心臓はバクバクしてうるさい。
ドキドキして顔が赤くなってしまう私に、カオルは「お前は、俺が必ず幸せにする。だから俺についてこい、ミク」と真剣な顔を見せる。
「……うん」
カオルの真剣さが伝わって、余計ドキドキした。