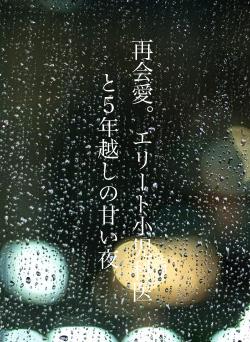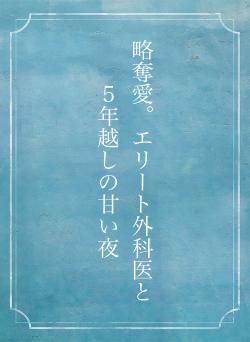つむぎにそう告げると、その場に跪いた。
彼女は申し訳なさそうに「すみません」と小さく呟き、俺の肩に手を乗せる。
彼女の体勢が保たれたところで、ヒール靴を片足履かせてやった。
「ちょうどいいな。足元に気をつけて」
「はい」
ゆっくりと立ち上がり、彼女の腕を支えながら振り返ったそのとき。
つむぎの顔が耳まで赤く染まっているのに気づき、思わず目を見張った。
「君、熱があるんじゃないのか。顔が赤いぞ」
「えっ……うそ……?」
不思議に思って彼女の顔を覗き込むと、さらに朱が差した気がした。
まったく意識はしていなかったが、靴を履かせてやったことに対して照れてしまったのだろうか。
彼女の白い肌は透き通るように美しいが、こういったときは不利に働くんだな。
それも可愛らしいが。
彼女の初心な反応はクセになるな。
さらに動揺することをしてみたいなんて、意地の悪い感情が頭をもたげてしまう。
「つむぎ」
「え?」
一歩距離を縮めると、彼女は大きな目を見開き俺を見上げた。
その距離は数十センチほどだ。
彼女の目線はヒールを履いたことで高くなり、顔を傾ければ優にキスができそうだ。
……さすがに、そこまではしないが。
俺を潤んだ瞳で見つめるつむぎは、先ほどよりもずっと大人びて見える。
「もう自分のことちんちくりんだなんて言うなよ、いつも自信をもって隣を歩いてほしい」
「久斗さん。分かりました」
俺の言葉に嬉しそうに頷いたつむぎは、視線を姿見に移した。
大人びた自分の姿を見て気分をよくしたのか、くるくるとその場で回りスカートの揺れを楽しんでいる。
控えめだが、色っぽさもあるな。
こんなにコロコロと表情が変わる女性は、初めて出会うかもしれない。
それにつむぎは、人を想いやれるとても優しい子だ。
新婚生活は多少不安に思っていたが、わずかな時間でも彼女の人柄が十分に分かり店を出る頃には完全に消え失せていた――。