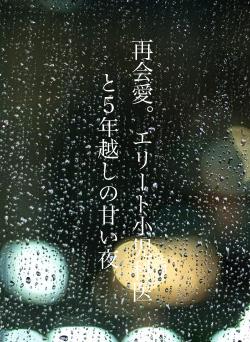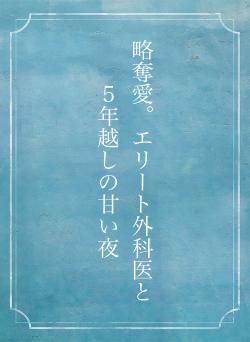黒瀬さんの言葉が悲しかった。
私たちは所詮他人なのだと突き付けられたようだ。
このアフタヌーンティーが終われば、もっと彼は遠い場所にいってしまう。
もし次に顔を合わせるときがあっても、渉さんの妻として振舞うことになるんだ。
「……す、すみません、楽しい時間を壊しちゃうようなこと。デザートたちも可愛そうですね」
「え?」
「美味しい……黒瀬さんもいかがでしょう……?」
お皿に乗ったフォークを手に取り、食べかけのショートケーキを一口食べる。
笑顔で振り返ると、黒瀬さんは安心したようにフッと表情をやわらげた。
「じゃあ、俺も少しだけ頂こうかな」
「どうぞっ……」
せっかく彼が誘ってくれた素敵な時間を、泣き顔で終わらせるのはもったいない。
目尻に浮かんでいた涙を拭い、ティースタンドを中央に寄せて、ケーキとケーキの間から彼の様子を伺った。
黒瀬さんは席に戻り、肘をついて笑顔で私を眺め始める。
「つむぎ、俺が食べたいものを当ててみてくれ」
「えっ……? どれだろう」
メロンのコンポートを指さすと、彼は首を横に振る。
「違うな、もっと甘さを控えたものを頼むよ」
「は、はい。じゃあ、これかなぁ?」
黒瀬さんのペースに合わせていたら、自然と口角が上がった。
彼がさっき言っていた家の事情で結婚を強いられているという話を、それとなく聞きたかった。
もしかしたら、許嫁と言われる相手がいるのかもしれないし……。
何故か私は、それが無性に気になったのだ。