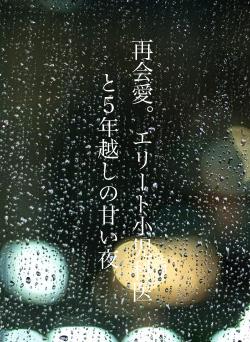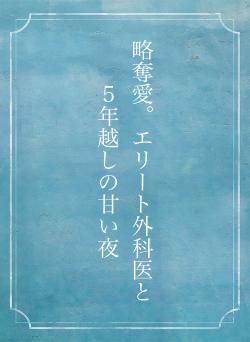ある休日の昼下がり。
お手伝いさんに抱きかかえられた赤ん坊――小春が現れたのは、俺が十になったばかりのときだ。
意味が分からないまま受け入れた妹との生活だったが、小春が成長するにつれ、親戚から嫌味を言われたり俺との差別を受ける姿を見てようやく事の意味を理解していった。
――父は愛人との間に子供を作っていた。しかも母が病に侵されている間に……。
俺の実母が亡くなり、小春の母親は結婚を迫ったようだが、当然黒瀬家に認められることはなく、自暴自棄になって生まれたばかりの赤ん坊を実家の玄関前に置いていなくなった。
長い時間をかけてだが、当時の父は弱っていく母を見るのがつらく、心のよりどころを探していたんだと理解した。
それは献身的に母の闘病生活を支えていた姿を覚えていたからそう結論付けたのだ。
当時、幼い自分は父を激しく軽蔑したし、小春を妹として思いたくないという気持ちでいっぱいで、近寄ることすらなかった。
しかししだいに――。
誰からも愛されない、罪のない小春の姿が見ていて心底可哀想に思えた。
血が繋がっている唯一の兄として、彼女を受け入れて行こうと決めた。
多方面から向けられる攻撃から、小春を守ってやらなければならないと思ったのだ。
そして彼女は俺にすぐ懐いてくれた。
『こはる、おにいたんとけっこんしたい!』