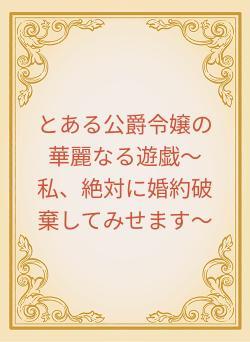「俺も高梨さんくらい勇気があったらな…」
思わずポツリと本音がもれた。
そう、誰もが躊躇した“あの状況"で自分の身をかえりみず、男の子を助けるために飛び出していった彼女みたいに…。
高梨さんは、俺のこと“優しい"とか“爽やか"とか、過大評価してくれてるけど実際の所、八方美人なだけなのだ。
そう考えると、フッと自嘲的な笑みがこぼれた。
結局、自分の身かわいさが先に立ち、正直になれていないうえにそのくせ、人一倍嫉妬深いとかマジでない。
それは、大谷くんに対しても然り。
大谷くんは、男の俺から見てもカッコいいし、正直自分が女だったら、俺みたいなヤツより断然彼を選ぶと思う。
ただ、当の高梨さん本人がなぜか、全く大谷くんからの好意に気づいていないのが不憫というか…。
なんか眠くなってきたな…。
薬が効いてきたのか急な眠気に襲われ、俺はゆっくり目を閉じる。
週末文化祭だし、明日はちゃんと学校行ってクラスの準備して…。
そして。
夏休み明けには、高梨さんに伝えたい。
自分の気持ちを。
今まで言えなかったコトを。
そんな決意を胸に秘め、気づけば俺は眠りについていたのだった――。