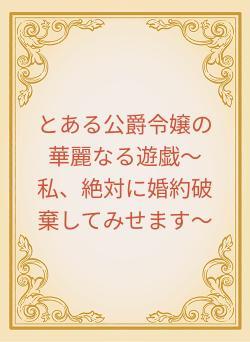「…よし。じゃあ、今日は先に帰るよ。親に相談してみないとだし…今日の夜にでもまた、メッセージ送るよ。あ!あと、明日も準備頑張ろうね」
「う、うん…。また明日ね」
それだけ言い残し、足早に裏庭を後にする観月くんはなんだかとても嬉しそうに見えた。
「なんかやる気に満ち溢れてたね、観月くん」
「ニャン」
残された私とおもちは、そんな彼を見送ることしかできなくて…。
正直、何がそんなに彼をやる気にさせたのかわからなかったけれど…たぶん、おもちのことが本当に心配だったのだろうと私の中で結論づけた。
「おもち、あんた…幸せものだね。あんなやる気になってくれてたし、本当に観月くんの家の子になれるかもしれないよ…?」
「ニャー」
甘えてくるおもちを尻目に私は先ほどのやり取りを思い出す。
それにしても、やっぱりさっき顔が赤いなって思ったのは気の所為だったようだ。
立ち上がった観月くんはいつも通りだったしね。
そんなことを考えながら、私はおもちに向かって小さく笑みをこぼしたのだった。