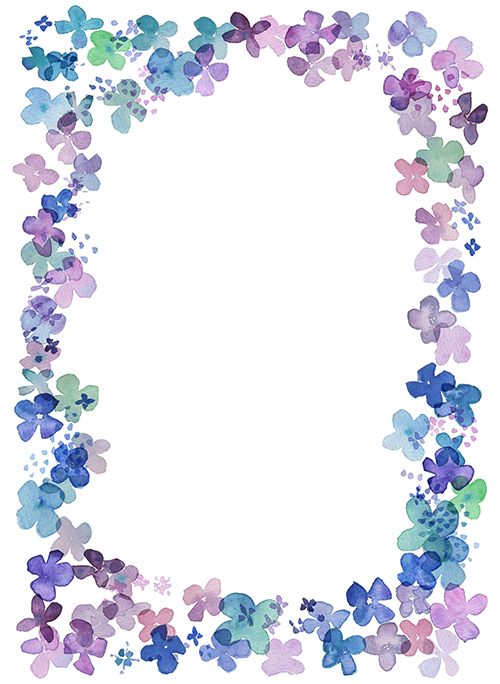「本当に圭は優しい子だな」
そもそも見知らぬ人がいるのだから警戒するのは当たり前だ。
それに対して怒ったりしないなんて普通なのに、何故こんなことを言われるのだろうか。
伊鈴さんは僕の頭を撫でるのが楽しいのか、手を離してくれそうにない。
きっと無理だろうけど、なんとかしてくれないかと悠さんを見ると、何とも言えない顔をしていた。
それから僕のことを「いい子」や「愛らしい」などと褒めながら伊鈴さんが頭を撫でてきて、嬉しいよりも恥ずかしさを感じて五分ほど経った頃、伊鈴さんがやっと手を離してくれる。
こんなにもたくさん褒められることなんて今までなかったので、受け止めきれなくて僕の顔は真っ赤になっていた。
そんな顔を見られるのが恥ずかしくて、足に顔を埋める。
「どうしたのだ?」
「なんでもないので気にしないでください」
「そんなこと言われてのぉ。我何かしてしまったか?」
伊鈴さんが心配してくれている。
ただ恥ずかしくて顔を上げたくないとは言えなくて黙っていると、悠さんの冷たい声が聞こえる。
「本人が気にするなと言っているんだ。気にしなければいい」
「本当にいつから悠はそんな冷たい子になったのだ。我はそんな風に育てた覚えはないぞ」
「うるさいな」
悠さんが小さい声でぽつりと言う。