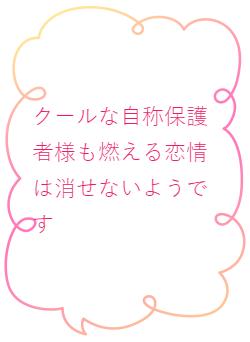夫を見送った後は薔薇の手入れをするのがクシェルの日課だった。
結婚を機に移植させてもらった薔薇たちも、ようやく根を馴染ませ蕾をつけるまでになった。
クシェルが以前に棲んでいた屋敷には、世界各国から集めてもらった多様な種の薔薇が植えられており、それらが一斉に花開いた様は得も言われぬ美しさだった。
社交界デビューをしていないクシェルは、色とりどりの薔薇を貴婦人たちに重ねては、煌びやかな宴な場とはこのような美しさなのだろうかと想像したのだった。
グラウブとクシェルが住まうこの屋敷は、軍人貴族のそれらしく無装飾な石造りで、周りからは城塞のようだと言われていた。
もちろん庭も味気ないものだったが、結婚後もそこで薔薇を育ててよいと許されたのは救いだった。
個性豊かな薔薇たちの世話に没頭し、大輪の花が開けば、つられてやってくる鳥や蝶たちと一緒にその香りに酔いしれる。
その時こそがクシェルにとっての至福であり、唯一の心のよりどころだった。
本音を言えば、このままずっと薔薇だけに囲まれてひっそりと生きて行きたい。
社交界など、想像するだけでいい――そう思っていた。
けれども今は、そういうわけにもいかない、と自分に言い聞かせている。
自分はもう人の妻。
それも、国中から英雄と称され、崇敬と羨望の眼差しを受けているグラウブの妻なのだから。
結婚を機に移植させてもらった薔薇たちも、ようやく根を馴染ませ蕾をつけるまでになった。
クシェルが以前に棲んでいた屋敷には、世界各国から集めてもらった多様な種の薔薇が植えられており、それらが一斉に花開いた様は得も言われぬ美しさだった。
社交界デビューをしていないクシェルは、色とりどりの薔薇を貴婦人たちに重ねては、煌びやかな宴な場とはこのような美しさなのだろうかと想像したのだった。
グラウブとクシェルが住まうこの屋敷は、軍人貴族のそれらしく無装飾な石造りで、周りからは城塞のようだと言われていた。
もちろん庭も味気ないものだったが、結婚後もそこで薔薇を育ててよいと許されたのは救いだった。
個性豊かな薔薇たちの世話に没頭し、大輪の花が開けば、つられてやってくる鳥や蝶たちと一緒にその香りに酔いしれる。
その時こそがクシェルにとっての至福であり、唯一の心のよりどころだった。
本音を言えば、このままずっと薔薇だけに囲まれてひっそりと生きて行きたい。
社交界など、想像するだけでいい――そう思っていた。
けれども今は、そういうわけにもいかない、と自分に言い聞かせている。
自分はもう人の妻。
それも、国中から英雄と称され、崇敬と羨望の眼差しを受けているグラウブの妻なのだから。