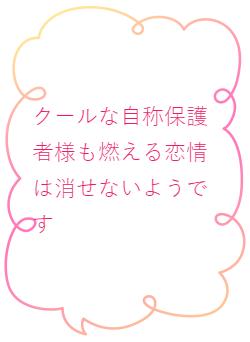クシェルは目を細めた。
煌びやかな軍服をまとった高い上背に、がっしりとした大きな身体。
歴戦を潜り抜けてきた軍人としての冷静さと猛々しさを滲ませた、端正な顔立ち。
一概にしてこの国の国民特有のものであり優美と称賛される金髪碧眼は、この美丈夫については、プラチナブロンドは鋭敏な輝きを放ち、深淵とした碧眼からは野性味すら感じさせる。
筋骨隆々とした黒馬に跨るその様は、見上げるこちらの肌がひりついてしまうような厳然とした雰囲気を放っていた。
勇ましい、神々しいほどの姿。
『軍神』と国中の人々が賞嘆するのも、改めて頷ける。
(この方が、私の夫……)
何度言い聞かせても夢だと思えてしまう。
「いってらっしゃいませ」
崇拝するかのごとくクシェルが深々と頭を下げると、十八歳年上の夫は、容姿に相応しい低く張りのある声で「行ってくる」と重々しくうなずいた。
そうして、ゆっくりと顔を上げた妻をしばらくじっと見つめると、馬を進めて行ったのだった。
クシェル十七歳と夫のグラウブ・フォン・ウィブフェルド三十五歳のいつもの朝である。