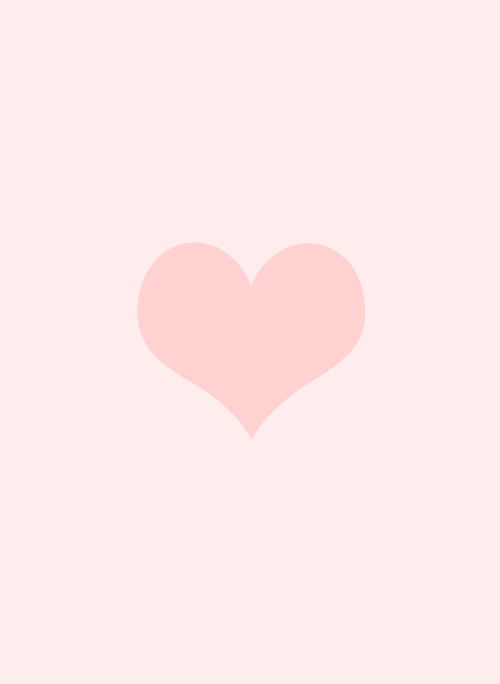私だって、毎日頑張っているんだよ。
怒られたくなくて、こんなに必死になっているのに。
人を見下し、否定する事でしか人を評価出来ない父の娘として、身を削って生きているのに。
どうして、
「お前が俺の娘だなんて、聞いて呆れるわ!」
「ごめんなさ、…!」
私の心ばかりが、擦り切れていくの。
その日、父に強制的に叩き起こされて一方的に叱責され続けた私がその嵐から解放されたのは、体感で20分以上が経ってからの事だった。
父はかなり泥酔していたから、きっと明日の朝…いや、今日の朝には私の部屋に入った事すら忘れているのだろう。
父の酒臭い息を顔面に浴び、それでも謝る事で何とか被害を最小限に留めようと奮闘していた私は、
「っ、…はあっ……」
私に対して日頃の鬱憤を晴らせたことに満足したのか、父が荒々しい足音と共に部屋を出て行ったのを聞き届けて、大きく肩で息を吐いた。
…いつもの事だけど、でも、こんなの狂ってるよ。
右手の肘で目元を覆って呼吸を整えながら、私は上手く働かない頭でぼんやりと考える。
身体を激しく揺り動かされたせいで未だに目が回っているし、少しでも気を抜いたら吐いてしまいそう。
あいつに胸ぐらを掴まれたせいで、パジャマの胸元のボタンが弾け飛んだのが分かる。
頭が痛い、お腹も背中も…心も、痛いよ。
怒られたくなくて、こんなに必死になっているのに。
人を見下し、否定する事でしか人を評価出来ない父の娘として、身を削って生きているのに。
どうして、
「お前が俺の娘だなんて、聞いて呆れるわ!」
「ごめんなさ、…!」
私の心ばかりが、擦り切れていくの。
その日、父に強制的に叩き起こされて一方的に叱責され続けた私がその嵐から解放されたのは、体感で20分以上が経ってからの事だった。
父はかなり泥酔していたから、きっと明日の朝…いや、今日の朝には私の部屋に入った事すら忘れているのだろう。
父の酒臭い息を顔面に浴び、それでも謝る事で何とか被害を最小限に留めようと奮闘していた私は、
「っ、…はあっ……」
私に対して日頃の鬱憤を晴らせたことに満足したのか、父が荒々しい足音と共に部屋を出て行ったのを聞き届けて、大きく肩で息を吐いた。
…いつもの事だけど、でも、こんなの狂ってるよ。
右手の肘で目元を覆って呼吸を整えながら、私は上手く働かない頭でぼんやりと考える。
身体を激しく揺り動かされたせいで未だに目が回っているし、少しでも気を抜いたら吐いてしまいそう。
あいつに胸ぐらを掴まれたせいで、パジャマの胸元のボタンが弾け飛んだのが分かる。
頭が痛い、お腹も背中も…心も、痛いよ。