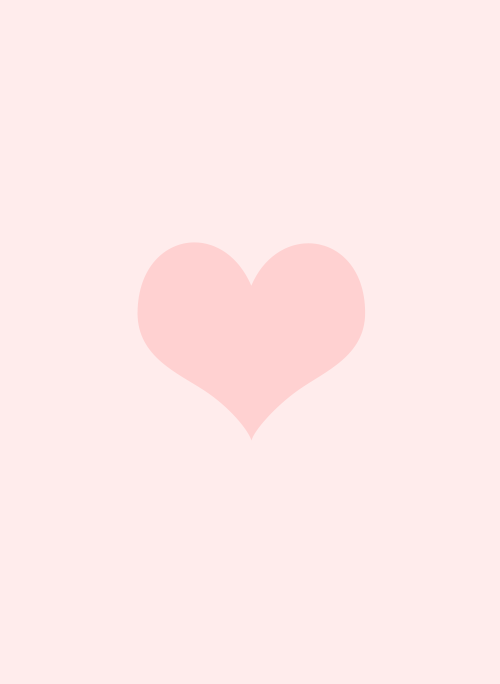呼吸をする度にズキズキと痛む頭を押さえながらぼんやりと窓の方を見ると、真ん丸に輝く月が辺りを照らしているのが見えた。
「…そっか、そういえば今日、十五夜なんだっけ……」
十五夜だからって、特別な事は何もしていない。
巷の人は皆、お月見でも楽しんだのかな。
綺麗だねって、大切な人と顔を見合わせて笑い合ったのかな。
…私はもう、
“綺麗”が何を指すのかすら、分からないよ。
光り輝く金色の丸の中で、兎が餅をついている。
そのリズミカルな動きに合わせるかのように、一粒の雫が頬を濡らしていく。
ああ、本当に虚しい。
そのまま目を瞑った私は、そっと意識を手放した。
翌朝、私が目覚めた時には既に父の姿は無かった。
父は大企業の取締役を務めているから、毎日仕事三昧で忙しい。
職業柄、莫大な金を手に入れた彼のおかげで私達は高級住宅街に住む事が出来ているけれど、今となっては何の感謝の気持ちも湧いてこない。
こんな事になるなら、土地も財産も全部捨てていいから、もっと普通の生活が送りたかった。
眠い目を擦りながらベッドを下りると、その振動で頭の奥の方が揺れたのが感じられた。
…昨晩の後遺症が未だに残っているなんて、珍しい。
泥棒だの父の不法侵入だの、夜中に色々な事がありすぎて寝不足になった気がする。
そんな事を他人事のように考えつつ、私は長い廊下を歩いて行った。
「…そっか、そういえば今日、十五夜なんだっけ……」
十五夜だからって、特別な事は何もしていない。
巷の人は皆、お月見でも楽しんだのかな。
綺麗だねって、大切な人と顔を見合わせて笑い合ったのかな。
…私はもう、
“綺麗”が何を指すのかすら、分からないよ。
光り輝く金色の丸の中で、兎が餅をついている。
そのリズミカルな動きに合わせるかのように、一粒の雫が頬を濡らしていく。
ああ、本当に虚しい。
そのまま目を瞑った私は、そっと意識を手放した。
翌朝、私が目覚めた時には既に父の姿は無かった。
父は大企業の取締役を務めているから、毎日仕事三昧で忙しい。
職業柄、莫大な金を手に入れた彼のおかげで私達は高級住宅街に住む事が出来ているけれど、今となっては何の感謝の気持ちも湧いてこない。
こんな事になるなら、土地も財産も全部捨てていいから、もっと普通の生活が送りたかった。
眠い目を擦りながらベッドを下りると、その振動で頭の奥の方が揺れたのが感じられた。
…昨晩の後遺症が未だに残っているなんて、珍しい。
泥棒だの父の不法侵入だの、夜中に色々な事がありすぎて寝不足になった気がする。
そんな事を他人事のように考えつつ、私は長い廊下を歩いて行った。