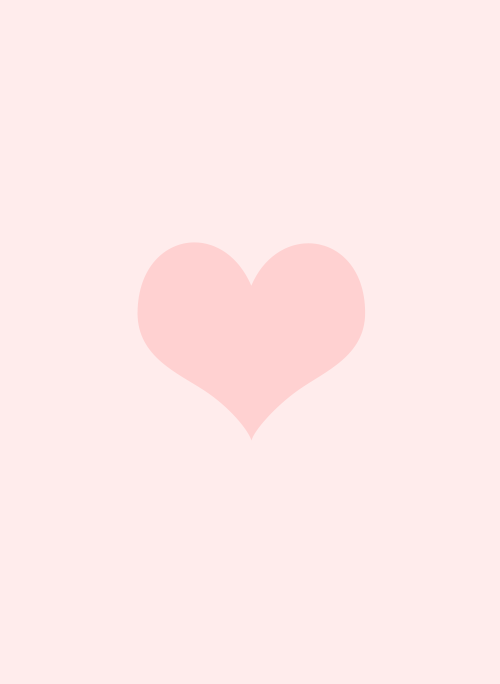変なところで頭の切れる父は私に対して手を上げない代わりに、精神を切り刻んでくる。
父はその行為をすることですっきりするのかもしれないけれど、私にとっては、毎日が地獄との闘いだ。
だって私は、父のストレス発散の為の人形なんかじゃない。
ちゃんとした感情を持った、一人の人間なのだから。
再度深く息を吐いた私は、右手を胸まで下げて窓の方を向いた。
父に指摘された窓は今も開け放されていて、その横にあるアクセサリーがキラキラと光っている。
その装飾品を、自室に差し込んでくる月光を綺麗と思えない私は、もう心が麻痺してしまったのだろうか。
そうして、焦点の合わない目で暫くその光景を眺めていた私は、
「あっ」
ベッドの下に隠したある人の存在を思い出し、がばりと上半身を起こした。
そうだ、父のせいで完全に忘れていたけれど、この部屋には泥棒が居るんだった。
起き上がった時に目眩がして、身体がぐらりと傾く。
「あの…」
胃から逆流してきた何かを飲み込んだ私は、傾いた身体を支える為に伸ばした手でベッドの端を掴み、そっと下を覗いた。
今まで頭上で壮絶な闘いが繰り広げられていたにも関わらず、一言も声を発する事がなかった泥棒の澄んだ左目と、真っ直ぐに視線がぶつかる。
「もう、出て来て、大丈夫です」
父はその行為をすることですっきりするのかもしれないけれど、私にとっては、毎日が地獄との闘いだ。
だって私は、父のストレス発散の為の人形なんかじゃない。
ちゃんとした感情を持った、一人の人間なのだから。
再度深く息を吐いた私は、右手を胸まで下げて窓の方を向いた。
父に指摘された窓は今も開け放されていて、その横にあるアクセサリーがキラキラと光っている。
その装飾品を、自室に差し込んでくる月光を綺麗と思えない私は、もう心が麻痺してしまったのだろうか。
そうして、焦点の合わない目で暫くその光景を眺めていた私は、
「あっ」
ベッドの下に隠したある人の存在を思い出し、がばりと上半身を起こした。
そうだ、父のせいで完全に忘れていたけれど、この部屋には泥棒が居るんだった。
起き上がった時に目眩がして、身体がぐらりと傾く。
「あの…」
胃から逆流してきた何かを飲み込んだ私は、傾いた身体を支える為に伸ばした手でベッドの端を掴み、そっと下を覗いた。
今まで頭上で壮絶な闘いが繰り広げられていたにも関わらず、一言も声を発する事がなかった泥棒の澄んだ左目と、真っ直ぐに視線がぶつかる。
「もう、出て来て、大丈夫です」