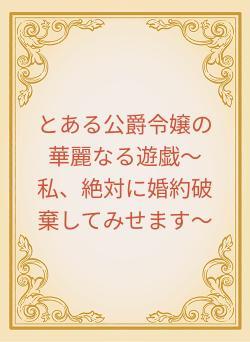「…いいよ、心配しなくても何か適当に食べるから」
「また、そんなこと言って…充希の適当に食べるは信じられない!季里ちゃん聞いて?この子ったら本当に昔から好き嫌い激しくてね…私のご飯も全然食べてくれなくて苦労したのよ…まぁ、充希が食べるように色々工夫してるうちに料理が好きになって、結果、自分の店を開くきっかけになったんだけどねぇ」
懐かしそうに目を細めて、和音さんはフッと微笑んだ。
「…そうだったんですね。でも、そしたら私の料理の腕くらいだったら充希くんを満足させるものは作れないかもです…」
あんなに美味しい和音さんの料理ですら、好き嫌いが激しいなんて…私には荷が重すぎる。
そう考えて、苦笑いを浮かべた時。
「…べつに、今は昔ほど好き嫌いないし。作ってくれるっていうなら…た、食べないこともないけど」
充希くんは私に向かって、口ごもりながらそう言い放った。