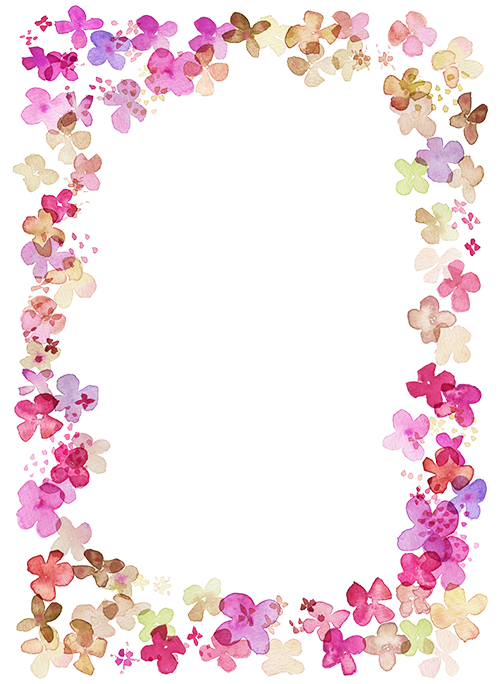「あー、やっぱり母さんの味噌カツ煮定食美味しすぎます」と可愛い声を出していたのはこころだった。
小日向は「んな大袈裟な、何回も来てるだろ」と言った。とういうのも、ここの定食屋は元々小日向が通っており、行きつけだった。そこを、こころにも紹介して、よくジム帰りに二人で行くようになったのだった。
こころはもう何回も来てるのにこの進展の無さは何だと思った。今まで、大抵の男は二、三回食事をした程度で落とすことができたのに、この小日向さんは何回行っても、ただの先輩後輩関係であり、脈を全く感じない。
最初は地位がそこそこ上だったから近づいたものの、気づくと自分が好きになっており、もはや手をつけられなかった。
まあそんなことは小日向は知る由もないので相変わらずなテンションでこころとご飯を食べていた。
こころは「小日向さんって鈍いですよね。そう言われません?」とちょっといつもより攻めたことを聞いてみた。
小日向は「鈍い?せっかちとは言われるけど」と行動のことを言った。
こころは呆れて「そういうとこですよ」と言った。そして「小日向さんはこんな感じで誰かとよくご飯に行きますか?」と言った。
すると、小日向さんが宇賀山の名前を出そうとしたので、「それ以外で」と言った。こころは、この前宇賀山が言っていたことが気になっていた。
小日向さんは「うーん、最近ちょっとした繋がりはできたけど、まだそんなに行ってないよ」と言ったのでこころはそれかと思い、すかさず「ひなこさんでしたっけ?」と宇賀山に聞いておいた名前を出した。
小日向さんは「そうそう」と言うと、「あいつまたペラペラと喋りやがって」と言った。
こころはひなこの正体が知りたかったが、あまり詮索すると小日向さんに嫌がられそうなのでやめておいた。
そして、そっちの話なら、謎に協力的な宇賀山さんの方が聞きやすいと思い、そっちから聞くことにした。
こころは進みきれない関係を煩わしく感じ、目の前の酒をゴクゴクと飲んだ。
それからしばらく経ち、こころはそんなにお酒が強くなかったので、あっという間に酔っ払った。
「こひぃなぁたさんはぁ」とだいぶ呂律が回っておらず、まだ平気な小日向さんに心配された。
こころは酔いに任せて「わぁたぁしはぁ、こひぃにゃたさんがすきぃなぁんですぅ」と言った。小日向さんは「え?気持ち悪い?」と見当外れなことを言い、さらにこころをイラつかせた。
小日向さんは「ほら、水飲め」と優しく介抱してくれたが、こころの気持ちはそれでは収まらなかった。
小日向は「んな大袈裟な、何回も来てるだろ」と言った。とういうのも、ここの定食屋は元々小日向が通っており、行きつけだった。そこを、こころにも紹介して、よくジム帰りに二人で行くようになったのだった。
こころはもう何回も来てるのにこの進展の無さは何だと思った。今まで、大抵の男は二、三回食事をした程度で落とすことができたのに、この小日向さんは何回行っても、ただの先輩後輩関係であり、脈を全く感じない。
最初は地位がそこそこ上だったから近づいたものの、気づくと自分が好きになっており、もはや手をつけられなかった。
まあそんなことは小日向は知る由もないので相変わらずなテンションでこころとご飯を食べていた。
こころは「小日向さんって鈍いですよね。そう言われません?」とちょっといつもより攻めたことを聞いてみた。
小日向は「鈍い?せっかちとは言われるけど」と行動のことを言った。
こころは呆れて「そういうとこですよ」と言った。そして「小日向さんはこんな感じで誰かとよくご飯に行きますか?」と言った。
すると、小日向さんが宇賀山の名前を出そうとしたので、「それ以外で」と言った。こころは、この前宇賀山が言っていたことが気になっていた。
小日向さんは「うーん、最近ちょっとした繋がりはできたけど、まだそんなに行ってないよ」と言ったのでこころはそれかと思い、すかさず「ひなこさんでしたっけ?」と宇賀山に聞いておいた名前を出した。
小日向さんは「そうそう」と言うと、「あいつまたペラペラと喋りやがって」と言った。
こころはひなこの正体が知りたかったが、あまり詮索すると小日向さんに嫌がられそうなのでやめておいた。
そして、そっちの話なら、謎に協力的な宇賀山さんの方が聞きやすいと思い、そっちから聞くことにした。
こころは進みきれない関係を煩わしく感じ、目の前の酒をゴクゴクと飲んだ。
それからしばらく経ち、こころはそんなにお酒が強くなかったので、あっという間に酔っ払った。
「こひぃなぁたさんはぁ」とだいぶ呂律が回っておらず、まだ平気な小日向さんに心配された。
こころは酔いに任せて「わぁたぁしはぁ、こひぃにゃたさんがすきぃなぁんですぅ」と言った。小日向さんは「え?気持ち悪い?」と見当外れなことを言い、さらにこころをイラつかせた。
小日向さんは「ほら、水飲め」と優しく介抱してくれたが、こころの気持ちはそれでは収まらなかった。