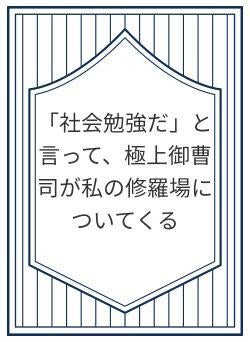目の前で、私が書いた離婚届が真っ二つに真ん中から綺麗に裂かれる。
国治さんは静かにものすごく怒っていた。
「まだ離婚予定日は先ですが、どうか私と離婚して下さい」
「どうして?」
間髪入れずにかえってくる。
テーブルに置かれた二枚になってしまった離婚届を見て、テープで直したら使えるのかな、なんて考える。
私の感情はおかしくなっていた。
とにかく早く、離婚届を提出しないと。
静かなリビングで、何者かに急かされるように再度口を開く。
「これ以上は、ご迷惑はかけられません。どうか私と縁を切って下さい」
頭を下げる。
「ダメです」
即答だ。
早く提出しなきゃ、このままじゃ国治さんにすがってしまう。助けてって、口走ってしまう。
「琴子さん。僕は味方だと言ったばかりです。僕は琴子さんだけを助けます、誰が何といおうと」
こんなにもちゃんとした人に、ここまで言わせてしまうほど巻き込んでしまった。
「それに」
「……なんでしょうか。三百万は、違約金として明日お返しします」
「僕は、まだ琴子さんにもうひとつの約束を守ってもらっていません」
約束? 国治さんの瞳は、うっすらと潤んでいた。
時刻はもう日付が変わるころ。私はキッチンでひたすらパンケーキを焼いていた。
積み重なるパンケーキからは、ひたすら甘い匂いがしていた。
あの日、喫茶店で国治さんに好きなだけパンケーキを焼くと言ったのは私だ。
国治さんは、涙ぐみながらどんどんパンケーキを頬張っている。
私はもう我慢できなくて、泣いていた。
「……僕は、琴子さんと離婚するつもりはありません。ずっと、こうやって僕にパンケーキを焼いてください……好きなんだ、あなたが」
キッチンの向こうで、国治さんが消え入りそうな声で言った。
空耳なんかじゃない、国治さんが私を見ている。
そうして「愛しています」と、はっきりと言葉にしてくれた。
私はコンロの火をとめて、フライ返しも投げて、真っ赤で困ったような顔をした国治さんに抱きついた。
「……琴子さんに気持ちを伝えたら、僕の心臓が苦しくて痛くなってきた。すごいな、死んでしまいそうだ」
国治さんが、ふぅっと大きく息を吐く。
「死なないでください、ずっとパンケーキ焼きますから……私も好きです、国治さん」
私を置いて死なないで、愛して、と呟くと、国治さんはきつく苦しいほど力強く抱きしめてくれた。
国治さんは父に、しばらくは距離を置いて欲しいと話合ってくれた。
妹がどうなったか、母が何て言っているのか私は知らない。
けれど、国治さんから心配しなくて大丈夫だと言われている。
新緑の眩しい五月のある日。
私たちの離婚予定日は、結婚一周年の大切な日になっていた。
おわり
国治さんは静かにものすごく怒っていた。
「まだ離婚予定日は先ですが、どうか私と離婚して下さい」
「どうして?」
間髪入れずにかえってくる。
テーブルに置かれた二枚になってしまった離婚届を見て、テープで直したら使えるのかな、なんて考える。
私の感情はおかしくなっていた。
とにかく早く、離婚届を提出しないと。
静かなリビングで、何者かに急かされるように再度口を開く。
「これ以上は、ご迷惑はかけられません。どうか私と縁を切って下さい」
頭を下げる。
「ダメです」
即答だ。
早く提出しなきゃ、このままじゃ国治さんにすがってしまう。助けてって、口走ってしまう。
「琴子さん。僕は味方だと言ったばかりです。僕は琴子さんだけを助けます、誰が何といおうと」
こんなにもちゃんとした人に、ここまで言わせてしまうほど巻き込んでしまった。
「それに」
「……なんでしょうか。三百万は、違約金として明日お返しします」
「僕は、まだ琴子さんにもうひとつの約束を守ってもらっていません」
約束? 国治さんの瞳は、うっすらと潤んでいた。
時刻はもう日付が変わるころ。私はキッチンでひたすらパンケーキを焼いていた。
積み重なるパンケーキからは、ひたすら甘い匂いがしていた。
あの日、喫茶店で国治さんに好きなだけパンケーキを焼くと言ったのは私だ。
国治さんは、涙ぐみながらどんどんパンケーキを頬張っている。
私はもう我慢できなくて、泣いていた。
「……僕は、琴子さんと離婚するつもりはありません。ずっと、こうやって僕にパンケーキを焼いてください……好きなんだ、あなたが」
キッチンの向こうで、国治さんが消え入りそうな声で言った。
空耳なんかじゃない、国治さんが私を見ている。
そうして「愛しています」と、はっきりと言葉にしてくれた。
私はコンロの火をとめて、フライ返しも投げて、真っ赤で困ったような顔をした国治さんに抱きついた。
「……琴子さんに気持ちを伝えたら、僕の心臓が苦しくて痛くなってきた。すごいな、死んでしまいそうだ」
国治さんが、ふぅっと大きく息を吐く。
「死なないでください、ずっとパンケーキ焼きますから……私も好きです、国治さん」
私を置いて死なないで、愛して、と呟くと、国治さんはきつく苦しいほど力強く抱きしめてくれた。
国治さんは父に、しばらくは距離を置いて欲しいと話合ってくれた。
妹がどうなったか、母が何て言っているのか私は知らない。
けれど、国治さんから心配しなくて大丈夫だと言われている。
新緑の眩しい五月のある日。
私たちの離婚予定日は、結婚一周年の大切な日になっていた。
おわり