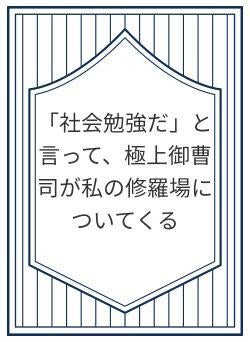洋菓子店の十二月は、それはもう繁忙期だった。
友人の店でいまは働かせてもらっている私も、例に漏れず目が回るほどの忙しさだった。
クリスマスケーキは予約制ではあったけれど、可愛く華やかなカットケーキもどんどん売れていく。
友人は製菓学校時代から、とびぬけてセンスが良かった。
それが更に自分の店を持ちお客様のニーズを細かく取り込むことで、人気のお店になったようだ。
とても勉強になるし、自分の持ちたい店のビジョンが明確になっていく。
材料費や人件費、立地と来客数の関係、内装や外装。
実際のメリットとデメリットを近くで見せてもらうことで、自分のなかに取り込み実になっていく。
早く自分も、こんな風に店を持ちたい。
ずっと夢だった。
ただひとつ、持ち続けた宝物のような夢だ。
この夢があったから、私は家を飛び出せた。
……なのに。
国治さんとの生活が、折り返して残りのほうが少なくなってきているのをとても寂しく感じている。
一緒に暮らして情が移ったのだと思いたかった。
だって、あんな外見も仕事も完璧な人が、いつも寝室でなくした眼鏡を探している。
やたらと私との年の差を気にして、なぜかしょんぼりする。
意外にやんちゃな子供時代の話、実は不器用かもしてない手先。
たくさんご飯を食べるので、作りがいがある。
髭の剃り残し、教えてあげると赤くなる顔。
完璧の裏側にある小さな隙間からのぞく、そういう面にとてつもない魅力があった。
私はそれを知るたびにとても嬉しく思っているのに気づき、考える。
知らなければ良かった。
気づかなければ。
いつの間にか、この気持ちに恋が含まれてるいることなんて。
この気持ちを国治さんに知られなければ、最後の日まで穏やかに暮らせるだろう。
国治さんは『夫』として、私にとても良くしてくれる。身に余るほどで、そこに私は淡い期待をしてしまって苦しい。
誰か助けて欲しいなんて願わなかったのに、最後まで心穏やかに暮らしたかったのに。
私のスマホが、着信を知らせる。
ディスプレイに表示された名前は、大切な私のお金を持ち逃げした妹だった。
友人の店でいまは働かせてもらっている私も、例に漏れず目が回るほどの忙しさだった。
クリスマスケーキは予約制ではあったけれど、可愛く華やかなカットケーキもどんどん売れていく。
友人は製菓学校時代から、とびぬけてセンスが良かった。
それが更に自分の店を持ちお客様のニーズを細かく取り込むことで、人気のお店になったようだ。
とても勉強になるし、自分の持ちたい店のビジョンが明確になっていく。
材料費や人件費、立地と来客数の関係、内装や外装。
実際のメリットとデメリットを近くで見せてもらうことで、自分のなかに取り込み実になっていく。
早く自分も、こんな風に店を持ちたい。
ずっと夢だった。
ただひとつ、持ち続けた宝物のような夢だ。
この夢があったから、私は家を飛び出せた。
……なのに。
国治さんとの生活が、折り返して残りのほうが少なくなってきているのをとても寂しく感じている。
一緒に暮らして情が移ったのだと思いたかった。
だって、あんな外見も仕事も完璧な人が、いつも寝室でなくした眼鏡を探している。
やたらと私との年の差を気にして、なぜかしょんぼりする。
意外にやんちゃな子供時代の話、実は不器用かもしてない手先。
たくさんご飯を食べるので、作りがいがある。
髭の剃り残し、教えてあげると赤くなる顔。
完璧の裏側にある小さな隙間からのぞく、そういう面にとてつもない魅力があった。
私はそれを知るたびにとても嬉しく思っているのに気づき、考える。
知らなければ良かった。
気づかなければ。
いつの間にか、この気持ちに恋が含まれてるいることなんて。
この気持ちを国治さんに知られなければ、最後の日まで穏やかに暮らせるだろう。
国治さんは『夫』として、私にとても良くしてくれる。身に余るほどで、そこに私は淡い期待をしてしまって苦しい。
誰か助けて欲しいなんて願わなかったのに、最後まで心穏やかに暮らしたかったのに。
私のスマホが、着信を知らせる。
ディスプレイに表示された名前は、大切な私のお金を持ち逃げした妹だった。