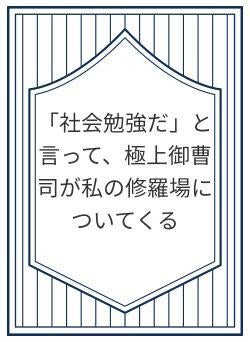不揃いで不格好な僕の餃子は、その見た目とは裏腹にとても美味しかった。
琴子さんが最終的に味付けをしたので美味しいのは当たり前だけど、なんだないつもと違った気がする。
「自分で包むと、なんだか余計に美味しいでしょ?」
頷きながらも、心の中では『二人で協力して作ったから』と付け加えた。
降りしきる雪を窓越しに見て「新しいお菓子のアイデアが浮かぶかもしれない」と、琴子さんは考え込んでいた。
僕はその後ろ姿をソファーから見ながら、琴子さんの心はもう春に向けて準備が出来ているんだと思った。
仮初の暮らしが心地よくなっているのは僕だけで、琴子さんはきちんと割り切っているんだ。
そこに年の差は関係ないけれど、僕はもう琴子さん以外の女性と餃子を作ったりはもうしないだろう。
自分の子供の頃の思い出話も、誰にもしない。
これから先、他人には誰にも。
もし僕が琴子さんと同世代だったらなんて、たまに考えて落ち込むことがある。
仕事にも誇りがあるし、それなりに働けていると自負できる。経済的にも困ってはいないし、体も健康だ。
でも、どうにも意気地がなくなった。
心が傷つけば、治りは遅いだろう。だからそれを乗り越える、思い切りもなくなった。
僕だけがひとり、春がくるのをじわじわと恐れている。
琴子さんが居なくなったこの部屋で、しばらくは名残りと一緒に暮らすんだ。
それもすっかり無くなったあと、やっとこの部屋を引き払うことが出来るのだと思う。
「どう、新作のアイデアは浮かんだ?」
琴子さんの前では素直になれず、聞き分けのいい余裕ある男でいたがる自分が嫌になる。
「んー……何にも浮かびません!」
振り返った琴子さんに変に思われないように、僕はいつも通りの年上の落ち着いた顔をして「そうか」と返事をした。
琴子さんが最終的に味付けをしたので美味しいのは当たり前だけど、なんだないつもと違った気がする。
「自分で包むと、なんだか余計に美味しいでしょ?」
頷きながらも、心の中では『二人で協力して作ったから』と付け加えた。
降りしきる雪を窓越しに見て「新しいお菓子のアイデアが浮かぶかもしれない」と、琴子さんは考え込んでいた。
僕はその後ろ姿をソファーから見ながら、琴子さんの心はもう春に向けて準備が出来ているんだと思った。
仮初の暮らしが心地よくなっているのは僕だけで、琴子さんはきちんと割り切っているんだ。
そこに年の差は関係ないけれど、僕はもう琴子さん以外の女性と餃子を作ったりはもうしないだろう。
自分の子供の頃の思い出話も、誰にもしない。
これから先、他人には誰にも。
もし僕が琴子さんと同世代だったらなんて、たまに考えて落ち込むことがある。
仕事にも誇りがあるし、それなりに働けていると自負できる。経済的にも困ってはいないし、体も健康だ。
でも、どうにも意気地がなくなった。
心が傷つけば、治りは遅いだろう。だからそれを乗り越える、思い切りもなくなった。
僕だけがひとり、春がくるのをじわじわと恐れている。
琴子さんが居なくなったこの部屋で、しばらくは名残りと一緒に暮らすんだ。
それもすっかり無くなったあと、やっとこの部屋を引き払うことが出来るのだと思う。
「どう、新作のアイデアは浮かんだ?」
琴子さんの前では素直になれず、聞き分けのいい余裕ある男でいたがる自分が嫌になる。
「んー……何にも浮かびません!」
振り返った琴子さんに変に思われないように、僕はいつも通りの年上の落ち着いた顔をして「そうか」と返事をした。