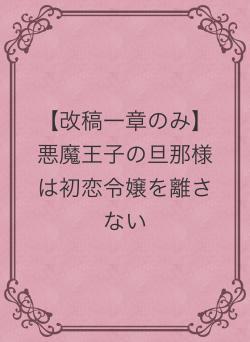ポストに入れてる合鍵で、玄関扉がガチャリと開かれて、木製階段をパタパタと駆け上がってくる音がする。
俺は慌てて、寝たフリをする。
「こらっ、春宮彰!」
部屋の扉が開いて、今日の朝も俺の大好きな声が聞こえる。少しだけ鼻にかかった聞き慣れた甘い声。
「……ん……」
俺は、ワザと瞳を開けない。砂月にして欲しいコトがあるから。
「彰!ねぇ!遅刻しちゃう」
「五分」
「昨日もそう言って起きなかった!その前もその前の前も!」
砂月の細い腕で、ゆさゆさと程よい力加減で布団ごと揺さぶられる。心地よさに身を委ねなかまら、眉を下げて少しだけ口を尖らせている砂月の顔が浮かぶ。
ゆっくり瞳を開ければ、やっぱり口を尖らせてる砂月が俺を覗き込んでいる。
「起きるって、でかい声だすなよ……響くだろ」
毎朝起こしに来てくれるを楽しみしてるけど、布団の上から、揺さぶられる度にふわふわの長い髪の毛から甘い匂いがして、毎回、思わず抱きしめたくなる。
「早く着替えてよっ」
「はいはい」
俺は精一杯、不貞腐れた顔をしながら、起き上がった。起きあがれば、ベッド脇に座っている砂月から、ふわりと甘い髪の匂いがまた鼻を掠める。
(ったく……人の気も知らないでさ。いっそ、抱きしめてやろうか)
……なんて邪な気持ちを俺は毎朝、心の隅っこに追いやる。そして、最後には、砂月に起こして貰うのが嬉しくてたまらない癖に、砂月に憎まれ口を叩いてしまう。
「てゆーか、着替えるからな!さっさと出てけよ」
言葉を言い終わる前に、スウェットの上を脱ぎ捨てると、
「わっ!彰の馬鹿!」
と顔を真っ赤にして、扉を閉める砂月が見えた。
俺は慌てて、寝たフリをする。
「こらっ、春宮彰!」
部屋の扉が開いて、今日の朝も俺の大好きな声が聞こえる。少しだけ鼻にかかった聞き慣れた甘い声。
「……ん……」
俺は、ワザと瞳を開けない。砂月にして欲しいコトがあるから。
「彰!ねぇ!遅刻しちゃう」
「五分」
「昨日もそう言って起きなかった!その前もその前の前も!」
砂月の細い腕で、ゆさゆさと程よい力加減で布団ごと揺さぶられる。心地よさに身を委ねなかまら、眉を下げて少しだけ口を尖らせている砂月の顔が浮かぶ。
ゆっくり瞳を開ければ、やっぱり口を尖らせてる砂月が俺を覗き込んでいる。
「起きるって、でかい声だすなよ……響くだろ」
毎朝起こしに来てくれるを楽しみしてるけど、布団の上から、揺さぶられる度にふわふわの長い髪の毛から甘い匂いがして、毎回、思わず抱きしめたくなる。
「早く着替えてよっ」
「はいはい」
俺は精一杯、不貞腐れた顔をしながら、起き上がった。起きあがれば、ベッド脇に座っている砂月から、ふわりと甘い髪の匂いがまた鼻を掠める。
(ったく……人の気も知らないでさ。いっそ、抱きしめてやろうか)
……なんて邪な気持ちを俺は毎朝、心の隅っこに追いやる。そして、最後には、砂月に起こして貰うのが嬉しくてたまらない癖に、砂月に憎まれ口を叩いてしまう。
「てゆーか、着替えるからな!さっさと出てけよ」
言葉を言い終わる前に、スウェットの上を脱ぎ捨てると、
「わっ!彰の馬鹿!」
と顔を真っ赤にして、扉を閉める砂月が見えた。