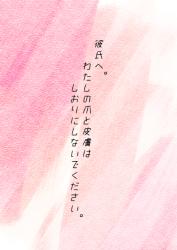1メーターごとに蝉の抜け殻がくっついているコンクリートの壁だとか、だれかがこぼしたジュースが乾き始めているアスファルトだとか。
そういうのを見ていると、田舎の夏だなあって感じがする。そんな田舎加減が、好きだった。
いまも好き。いまでも好き。前ほどではないだけで。
「あ」
ぐしゃ、とも、パキ、ともつかない音を立てながら、足元で何かが小さくなった。踏んでしまった。ペットボトルだった。コーラ、中身はもうない。
場所的に、きっと、アスファルトを濡らす原因となったのはこいつだろう。こうして、こぼされていたのはジュースだったと確信に変わった。
そういえば。
べつに、液体がジュースであるとも、飲み物であるとも、それが必然ではなかったというのに、わたしは迷いなくジュースだと思った。
それはたぶん、保科の影響だろう。
保科。
保科くん。敬称付きで呼んでいたのは最初のほんの数日だけで、気がついたら呼びすてになっていた。向こうに合わせたせいだと思う。
「あーあ、いなくなっちゃった」
保科はバイトを辞めた。田舎の中にある、いつも混んでいるコンビニのバイトを辞めた。わたしはそこの従業員だったわけではなくて、ただの客だった。
保科とわたしの関係は、ただの友達。に、なりたい。みたいな。友達だよねと言ったら間違いなく頷いてくれるけれど、たまたま会いましたね、こんにちは。そんな流れで話すことが圧倒的に多かった。
遊びに行ったことは、ない。
高校でも隣のクラスに行けば会えるし、連絡先も持ってないけれど、ちょうだいと言えばくれるはず。緊張して言い出せていなかっただけだから。
それじゃあどうして、保科がバイトを辞めたことでこんなに悲愴感を抱いているのか。
夏だからじゃない? と、わざとらしく首を傾げながら、行くべきところへの歩みを進めた。