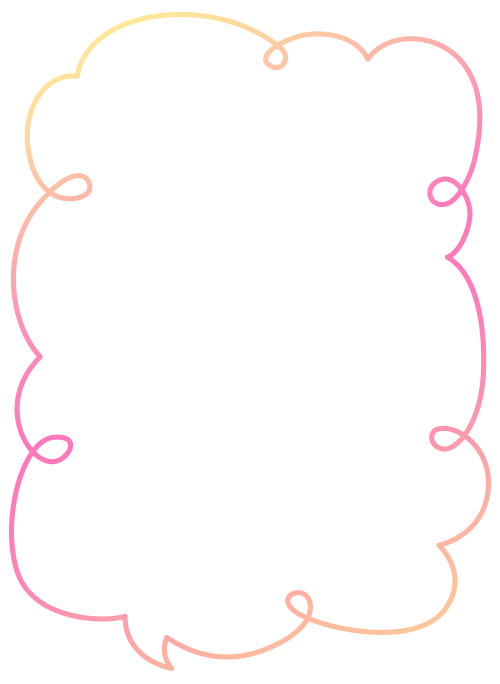「こうやってると、あったかくて眠気が増す」
そして、ぴたりと。
私たちは隙間がなくなるくらいに密着した。
くっつく直前に保健室の天井へと顔を向けたおかげで、湯本くんに顔がぶつかるのは避けられたけれども。
「あと、ちょっと甘い匂いがするのがいい」
ドキドキドキドキ。
私たちの他に誰もいない保健室の静けさの中、私の心臓は身体を突き破りそうなくらいに大きな音を鳴らしている。
このままじゃ私は死んじゃうかもしれないって、怖くなる。
でも、中和するように伝わってくる湯本くんのぬくもりとか、耳から入って心に落ちた湯本くんのくすぐったい言葉とか。
単純な私を優しく囲うから、逃げ出したいのに留まっていたい。
「ねぇ、これでも伝わんない?」
なんにも言わない私がまだ勘違いしていると思っているのか、湯本くんは腕の力を緩ませ、大きな体を縮こませて私の顔を覗き込んだ。
私の目に映ったその顔はもどかしそうで、困ったように僅かに眉が下がっていて……らしくない表情に胸が小さく跳ねたのがわかる。
初めての表情……もうなんか、いろいろと限界だ。