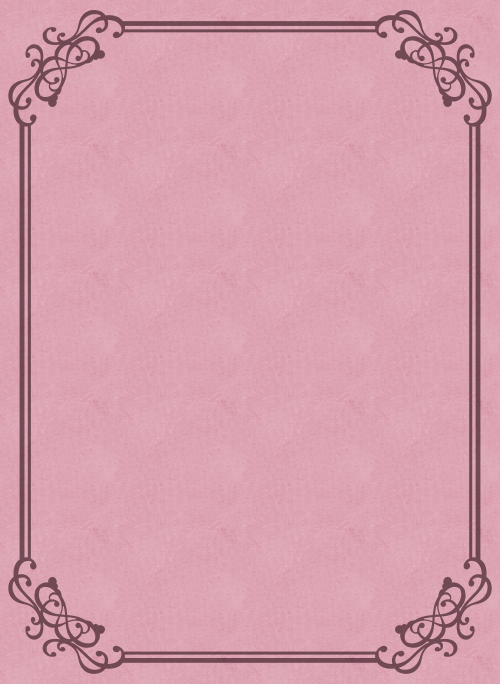その声を聞くなり令嬢が、青ざめた顔で硬直する。
さっきまで人だかりの中心で囲まれていたはずの叶兎くんが、目の前にいた。
「胡桃に触れるな。」
叶兎くんのその声に、会場の空気が一変した。
ざわめきが消え、誰もが動きを止める。
「赤羽様っ……!」
令嬢は震えた声で、伸ばしていた手を引っ込める。
叶兎くんは視線を逸らさず静かに言葉を続ける。
「自分にできないからって人に嫉妬をぶつけるの、やめた方がいいよ。」
その場のほぼ全員が息を呑んだ。
誰も言葉を返せなず、叶兎くんの瞳に射抜かれるようにして立ち尽くす。
「胡桃に手を出した者は、俺が許さない。」
静寂の中に放たれたその言葉は、刃のように鋭かった。
令嬢たちは顔を見合わせ恐る恐る後ずさり、周囲にいた人々も居心地悪そうに目を逸らしていく。
早くこの場を去りたいのか令嬢達が背を向けた時、もう1人の声が響いた。
「……発表の時名前を聞いていなかったのか?」
静けさを割って入ってきたのは──私の父。
また人々がざわめき、自然と道が開かれていく。
まっすぐこちらへ歩いてくるその一歩ごとに、空気が張りつめていった。
「赤羽叶兎の“婚約者”、朝宮胡桃───私の娘だ。」
その一言で、さらに空気が凍りつく。
会場何の人達の顔色がみるみるうちに変わっていく。
父はゆっくりと会場内を見渡し、唇の端をほんの少しだけ上げて言った。
「これ以上無礼な真似をする者がいれば……赤羽家ではなく、“私”が出ることになる。意味、分かるよな?」
静かで、けれど絶対に逆らえない声だった。
その威圧に誰もが息を詰める。
令嬢たちは蒼ざめたまま小さく会釈し、音も立てずにその場を離れていった。
周囲に集まっていた人たちも次第に散り始め、会場には再びざわめきと音楽が戻っていく。
それでも私は落ち着かないまま、その場に立ち尽くしていた。
そんな私の手を、叶兎くんがそっと取る。
「……行こ。」
『え、行くってどこに…』
「いいから。」
短くそう言って、叶兎くんはふっと笑った。
まだ背中に視線が刺さるような気がしていたけれど、彼の背中を見ているうちに不思議と怖くなくなった。