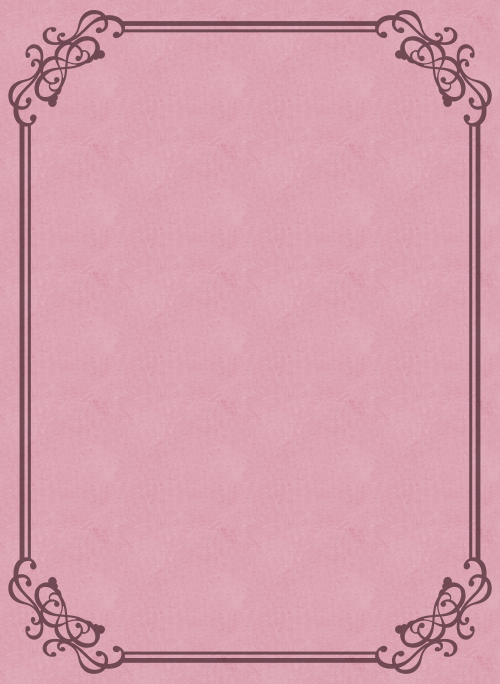「叶兎、胡桃ちゃんにこんな顔させるなんて見過ごせないな〜」
そう言われ、思わず自分の頬に手を当てる。
『……そんなに顔に出てる?!』
「うん。“悩んでます”って顔に書いてある」
軽い口調。だけど、それはちゃんと私を見てくれている証拠だった。
『……叶兎くん、あれからずっと忙しそうで。話しかけたいけど、すごく頑張ってるから……邪魔したくなくて』
「まぁ、トップの肩書を受け継ぐってことはそう簡単な事じゃないからねぇ」
天音くんの声は柔らかかった。
まるで、その苦しさも孤独も全部わかってるみたいな響き方。
『……こんなこと叶兎くんには言えないけど……なんか、叶兎くんが遠い存在になっちゃうみたいで、複雑で……』
自分でも驚くほど、素直に言葉がぽつりと零れた。
天音くんは、そういうふうに、自然と相手の心の扉を開けてしまう。
誰にも言えず押し殺していた感情がいつの間にかあふれ出していた。
「……叶兎、不器用だから。多分胡桃ちゃんの事、考えすぎてるんだよ」
『……考え、すぎ?』
「守らなきゃ、ちゃんと支えなきゃって。そのためには、まず立派なトップにならないとって。あいつ、そういう奴だから」
夕陽が沈むオレンジと群青の境界線に風が吹いて、前髪を揺らす。
天音くんが、ふいに一歩近づいてきた。
伸ばされた指先が私の頬にそっと触れる。
その手の温度は、夕暮れよりも優しくて。
「……でも、俺ならこんな顔させないのにな」
軽く言ったはずなのに、その瞳の奥は真剣で。
冗談じゃないって…見ればすぐに分かった。
「……ごめん。諦めたつもりだったけど、まだ整理ついてないみたい」
私に触れた指先が小さく震えている。
その温度が、切なくて、どうしようもなく真っすぐだった。